













 |
| 外観 |
 |
| 内部 |
 |
| 地下 |
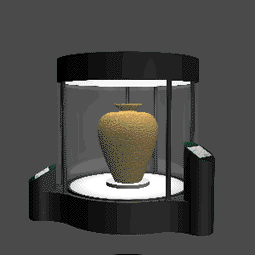 |
| カプセル1 |
 |
| カプセル2 |
 |
| カプセル3 |
建築家はコンピュータの発達の初期から、その建築に対する影響について考察してきた。
そこには、影響を恐れる心と、むしろそれ以上に新しい技術が建築に強いてくる新しい「制限」を期待する心があったのではないだろうか。環境条件の変化が生物進化を促すように、新しい制限こそが新しい建築への突破口となると…。
もしそうだったとしたら、その期待は裏切られる。
確かに設備の中でも、電灯や空調機の出現は建築に多大な影響を与えた。それは過去に有った制限をなくし、そして新しく制限を生むことで建築に変化への「理由」を与えたのである。
しかし、情報設備のコンピュータは、コンピュータが社会に与えた影響からすれば、驚くほど建築的には小さな影響しか与えていない。せいぜいがより大きなEPS(電気系の設備スペース)とフローティングフロアと反射防止照明しか要求していないようだ。しかも、これらの要求も技術未成熟の過渡的段階であるためともいえる。コンピュータは年々小さくなっている。無線LANや反射型カラー液晶などの技術とあわせ、大きなEPSもフローティングフロアも反射防止照明もやがては必要なくなる可能性が高い。実際、一昔前の空調完備のコンピュータ・センターのようなものの必要はどんどん減ってきている。さらにはコンピュータが可能にしたPHSが、ビル内の固定電話をなくす可能性すら言われており、ますます建築に対する要求は小さくなっていくだろうことが予想される。
もちろんコンピュータがCADや工法、構造計算といったサポート面で建築に与えたものは非常に大きい。しかし、それらはすべて可能性の拡大であり、要求ではなかった。 建築家とコンピュータのことを議論していても——また自分でデジタルミュージアムの「建築」を考えていても、同様に感じるのは、一種のもどかしさである。それは、コンピュータはもう少し建築に要求してくれてもいいのではないかということである。「コンピュータの要求により、このような形になった」「コンピュータをより良く使うためにこうした」と言えるような何らかの要求があるはずなのに、それが見つからない——というもどかしい思いである。
結果として、建築は「情報の流れを形にした」とか「デジタルとアナログの両面性の表現」といった、コンピュータにインスパイアされたフォルムにコンピュータと建築表現の接点を見いだそうとしているようだ。
しかし、実はコンピュータが直接与えた影響が少ないとしても、それが社会に与えた影響は確実に建築に要求仕様として投げかけられている。それは、つまりは「変化への対応力」とでもいえるようなものである。実はフローティングフロアも、コンピュータの直接の要求ではない。それはむしろ、頻繁に変わるテナントや組織に対応するための要求なのである。
シリコンバレーの企業の多くが、倉庫を利用して会社をはじめ、現在でははじめからオフィス向けでありながら、倉庫のような建築が建てられている。それは、シンプルな大空間をパーティションでいかようにも変えられるようにという要求である。あるときまでは、研究室が大きく、技術が完成したとなるとすぐ製造にかかり、すぐに大人数のサポートデスクが必要になり、次の週には技術を売って会社は解散——といったことが、一年ぐらいの間に起こるのがコンピュータの世界である。そして、いまやその変化のスピードはインターネットにより、一層加速されている。
それは、展示物についてのほとんどの情報がネットワーク経由で入手できる状況を自ら作りながら、なおかつ物理的にわざわざ足を運んでもらえるために、デジタルミュージアムが提供できるもの——それはなんだろうという考え方である。つまり、コンピュータにより博物館という建物が持っていた機能の多くが、建物という物理的拘束から切り放される方向にあるという視点から、逆に「それでも残るもの」は何かと考えたのである。
まず考えられるのは、いわゆる本物だけが与えられる感動である。手で触れるとかいった体感的なものもあるだろう。しかし、そのときに建築が提供できるものは何だろうか。個々の資料を保存し展示するということが博物館の機能なら、例えばコンピュータを組み込んだ耐候性の展示カプセルを街中に分散させ、その間を携帯端末を持った見学者が歩いて回る。場所によってはコンピュータ組み込みの自動車などで、それらを回ってもいい。史跡の多い街などはそのようにして、分散博物館にすることができる。そこでは、もはや「博物館」という名の建物は必要なくなる。
では、博物館建築だけが提供できるもの。——それはまさに巨大カプセルとしてのその空間しかない。
多くの博物館を見た中で最も「この場に来て良かった」という感動を受けたのは、ロンドンの自然史博物館の生物のサイズ比較の展示である。ナガスクジラの実物大模型を中心に、各種のクジラの骨格標本が天井から吊るされ、床には象など陸上生物の剥製などがある。中心になるナガスクジラが模型であることからわかるように、ここで与えられた感動は、「本物だけが与えられる感動」でもなければ触感でもない。ただ「おおきいなあ…」という、最も原始的とも言える感動である。
そのような感動は、音の反響や空気の流れなど多くの体感と視覚が合成されたものであり、ヘッドマウントディスプレイを使ったバーチャルリアリティ技術では、再現に限界がある何かであると信じている。いわば「本物の空間だけが与えられる感動」なのである。
中央アクセス路は大物展示物、コワレモノ、展示カプセルの移動用であり、安全な展示については、展示カプセルごと移動して展示更新も可能である。中央アクセス路は全体の中心軸の下にあり、4ヶ所程度の展示フロアへのエレベータリフトにより、展示フロアとやりとりする。博物館では改装中も、立入禁止を最小限にとどめ、できる限り来館者に対応するという使命があり、他のエリアの来館者の動線を妨げない搬入経路の確立を、この中央アクセス路と先のライド軌道により行う。
スタジオは収蔵物のデジタル化や補修、レプリカ作りを行うエリアであり、各種のコンピュータ機器が置かれ、サーバールームも含んでいる。 管理室、研究室、オフィスは地下だが、執務環境であることを考え、外周に配置し、地面を彫り込んで自然光を取り入れている。
ミュージアムショップ、カフェテリアは来館者の動線を考え、メインのアプローチの地下に置いた。また、やはり採光のために彫り込んでおり、メインのアプローチ路の下をくぐって連結されている。特にカフェテリア側からは露天へそのまま出ることが可能で、オープンカフェも可能である。電子タグは安価であり来館シールとして使い捨て可能なので、それを使って来館者の入出館を管理し要所の自動ゲートと組み合わせることで、館内を見たあとオープンカフェからそのまま帰っても、オープンカフェから再入館可能にすることも可能にできる。
具体的なデザインコンセプトとしては、「豆の種」をイメージした。巨大恐竜の全身骨格や、サターンロケットのブースターのような巨大展示物のために博物館には、いくつかの大空間が必要であるが、それを豆の膨らみ部分で取っている。
また、この「豆の種」のイメージは、水盤に映った鏡像世界のまさにバーチャルな建築物のラインで補完されることにより、完全なものとなる。
さらに、情報世界の目で見れば、この豆を中心にネットワークというツルが世界に広がっているイメージとも重なるのである。

(本館教授/情報科学)
Ouroboros 第4号
東京大学総合研究博物館ニュース
発行日:平成9年5月12日
編者:西秋良宏/発行者:林 良博/デザイン:坂村 健