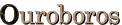







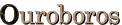







 |
| 抜歯と叉状研磨のある縄文人骨 [後期縄文時代(約4000年前)、愛知県川津貝塚] |
このような歴史的経緯を振り返るなら、資料館から博物館への移行は生物の連続した成長のようなものと考えられないこともない。子供と成人の間に明確な一線を引けないように、資料館と博物館の間にもはっきりとした区別を設けることができないと。事実、資料館のときから英語名はミュージアムを使用していたので、博物館となっても英語名にかわりはない。しかし、本当にそうなのであろうか。資料館と博物館の性格をもうすこし掘り下げて考えてみることにしよう。
設立当初、資料館は理学部、工学部、農学部、文学部などの部局、というよりもそれらに属する教室や学科で集積されていた学術標本を収納する施設としての役割を中心としていた。まさに資料館という名前にふさわしい役割である。しかし、関係者の努力で助手ポストが配分され、やがて助教授、教授ポストが設けられるようになった頃から、分類学を中核とする研究主体としての役割も担うようになる。それが資料館時代からの最終段階における活動である。大学全体から見れば小さな組織でしかないが、旺盛な研究活動によって消滅の危機に瀕していた分類学の命脈を保った功績は、将来かならず大きな評価を受けることであろう。
そのような貢献を果たしてきたとはいえ、資料館の活動には学術標本を提供した親学科のディシプリンの枠組み、つまり17部門に分散された学術標本のグルーピングが大きく作用していた。というよりも、学術標本の管理上の便法である部門の枠組みを前提とする研究活動しか公認されないという、奇妙で窮屈な状態が続いていたのである。そのような状況の中で、個々の専任教官は目を見張るような研究成果を続々と結実させていったが、学術標本のすでに分割された枠組みを取り払うような研究を資料館組織として推進することには大きな困難を伴った。
この困難への直面こそが、資料館を博物館に移行させようとする真のエネルギーとなったのである。つまり、資料館から博物館への移行は単なる名称変更ではなく、研究システム自体を改編しようとする組織変更だったのである。ディシプリンに基づくといえば聞こえはよいが、実際には学術標本の管理方策でしかない部門に拘泥することのない、真の研究を推進しうる組織への転換である。つまり、これまでの資料館における研究が学術標本に引きずられたものとするなら、博物館での研究は学術標本を先導するものと定義することができる。
そのためには、学術標本のグルーピングによってすでに付与された枠組みを前提とするのではなく、枠組みのあり方自体を構築しうる総合性と創造性が要求され、ひいては現代の学問全体を視野に入れて、学術標本と研究の相関性をシステム化することが問われているのである。その最初の一歩として、大学における教育研究活動の推移の中から引き出しうるであろうコンテクストを解明する必要があり、そのコンテクストの延長に位置づけられる新たな学問領域の創生こそが博物館に期待されている活動なのである。この活動を軌道に乗せることによって、新たに収集の必要な学術標本が何であり、どの分野の学術標本を充実させるべきかが明らかになる。そのことによって、博物館は来るべき21世紀にも重要な役割を担うことのできる組織として活動できるのである。

(大学院人文社会系研究科長/前資料館長)
Ouroboros 創刊第1号
東京大学総合研究博物館ニュース
発行日:平成8年9月9日
発行者:林 良博/デザイン:坂村 健