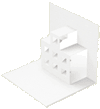
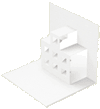
「敷地周辺は住宅地である」—この視線から、要求されている文学館や市民ホールを、施設近隣で生活する人々の「日常の中心」として位置づけ計画することが目論まれた。そこでまず敷地の大部分を、高さ23mのガラスの衝立とプリーズ・ソレイユで取り囲み、両施設の諸機能をその透明なヴォリュームの中に散在させた。
衝立に反射する光、映り込む周囲の風景は内部の諸要素と緩衝し合い、変化に富んだ複雑なファサードを作り出す。
この「ガラスの箱」によって切り取られた領域内部は基本的には室外環境でありながら、極端な悪天候の場合を除いて全天候型の広場としてある。
さらにそこは、諸室に設けられた可動間仕切などによって空間的にも、また視覚的にも敷地東側に隣接する公園を補完するものとなる。
上記のような構成は同時に、文学館と市民ホールの緊密な連携を促し、それらを物理的にも一体の建築として認識させる。また紋切り型のアトリウム空間を堕しかねないふたつの施設の間の緩衝帯を、ふんだんに設けられたテラスやデッキを連続した場所として扱うことによって、起伏に富んだ自然の地形、あるいは内部化された「公園」とでもいうような環境をつくり出す。
もちろん、様々な公演や企画が行われるとき「公園」は活況を呈するだろう。しかし特別な催しがないときの——買い物帰りの映画鑑賞や開放されたデッキでの読書、あるいはカフェでの井戸端会議といった——些細とさえいえるような賑わいの方が、地域社会を醸成していくという意味では、より必要なものである。そしてこの「公園」は地域に暮らす人々のこうした極めて日常的な賑わいを引き出す環境そのものである。
(河崎昌之)
 |
 |
 |