



















 (六朝造像
(六朝造像 )
)
中国
6〜7世紀
幅33.0cm、高さ8.0cm、厚さ4.0cm
昭和6年11月7日、江藤涛雄氏より
東洋文化研究所
 が上下に積み重ねられていたものであれば、その蓮弁がちょうど柱形の基台になるように配置されている。仏殿あるいは仏塔の荘厳のために壁面にずらりと並べて貼り付けられていたものであろう。
が上下に積み重ねられていたものであれば、その蓮弁がちょうど柱形の基台になるように配置されている。仏殿あるいは仏塔の荘厳のために壁面にずらりと並べて貼り付けられていたものであろう。
(小泉惠英)

石造
中国
山東省曲阜
東魏天平四年正月(西暦537年)銘
高さ46.5cm、(本尊のみ高さ30.3cm)
関野貞氏将来品
文学部考古学研究室・列品室
 に根拠地を据え、年号を天平と改めた。以降、隋(581〜618年)の全国統一までは新都
に根拠地を据え、年号を天平と改めた。以降、隋(581〜618年)の全国統一までは新都 が政治、文化の中心になり、仏教造像は再度東中国で栄えた。
が政治、文化の中心になり、仏教造像は再度東中国で栄えた。本像は、北魏で流行した一光三尊式像に通じる幅広の舟形光背を背負い、灰黒色の石材で作られた如来像で、光背正面には、唐草、蓮華文を挟んで、二竜、二仏、二比丘、二弟子が浮き彫り風に表され、背面には、須菩提よという語り口で始まる経文の一節が升目に正書で丹念に彫ってある。
須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人
聞此経典信心不逆其福勝(註1)何況書写受持讀誦為人解説須菩提
以要言之是経有不可思議不可稱量無邉功徳如来為發上乗者説
為發最上乗者説若有人能受持讀誦廣為人説如来悉知是人悉見是
人皆得成就可量(註2)不可稱無有邉不可思議功徳如是人等則為荷擔如
来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若楽小法者著我見人見衆
生見壽者見則於此経不能聴受讀誦為人解説須菩提在在處處
若有此経一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是
塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
大魏天平四年正月敬造
註1 『大正新修大蔵経』では、「其福勝彼」となっている。
註2 『大正新修大蔵経』では、「不可量」となっている。

五胡十六国時代(4世紀初頭〜5世紀半ば)の西域僧鳩摩羅什(343〜413年)訳金剛般若波羅蜜経の文句で、釈迦が弟子の須菩提に金剛般若波羅蜜経を信奉することの利益を説く一節である。光背正面へのやや異例の配置は恐らくこの経文の内容を意識してのものであり、両脇の僧形立像は釈迦の弟子で、同じ僧形の拝む人物は“以恒河沙等身布施”の出家者たちのことであろう。図像的には、菩薩形の脇侍を従える三尊形式が普通であるが、ガンダーラの早期作品には比丘の供養を受ける三尊像が作られていたし、中国五胡十六国時代の金銅仏にも同じ形式の三尊像が確認される。ともかく、本像を釈迦像とすることは認められよう。明治40年代頃関野貞博士によって将来され、1975年大阪市立美術館「中国美術展シリーズ(2)、六朝の美術」展に出陳されたことがある。
さて、天平4年は西暦537年に当たり、同じ天平期の作品で著名なものには、青州 (山東省)という同じ出自をもつ藤井有隣館蔵天平2年(535年)銘像(挿図1)、クリーブランド美術館蔵同四年銘像(挿図2)が知られている。本像は光背の形式、光背底辺を沿う蓮華(蓮葉)の意匠、中尊の細面で大きめの頭部、身体の形態などにおいては、特にクリーブランド美術館像との共通点をもち、時の流行を反映すると同時に、造像の盛況もほのめかしてくれる。第一、像全体を統合する対称性、中尊の裾部の、強くはないが、角張るはりなどは、クリーブランド美術館像に通じ、北魏時代に直結するこの天平期の造像に相応しく、北魏様式の継承を物語る。一方では、クリーブランド美術館像に比べても、光背のあますところのない装飾文や、中尊着衣裾部の衣紋の消失、それに、脇侍比丘の足元の蓮葉(通常は蓮華)、中尊の素髪の表現などから、本像に簡略化傾向が認められ、様式中心から一歩離れた、言い換えれば北魏離れの一面も示されているように思われる。
 |  |
| 18-1 | 18-2 |
そして、何と言っても、本像の一番の特色はその丸やかで温和な感覚にあるように思われる。裾部の北魏的なはりに対照する肩部の形態、衣紋の丸みある表現がそれである。同じような趣向は光背各モチーフの作りにおいてもっと顕著に表されているように思われる。例えば竜による荘厳は、北魏時代以来の手法だが、それも本像においては、従来のパターンを踏襲しながらも、やや太りぎみの温和なものになっている。その点、前記天平2年銘像とも違って、その軽快で鋭い感覚と一線を画すものがある。本像と近似した雰囲気の竜を同じ山東省の北魏期作品(挿図3)において見ることができることは興味深く、2年銘像と本四年銘像の継承した系譜の異なった一面も示されているように思われる。
一般に強いはりとこのはりに伴う線的鋭さを特徴にもつとされる北魏正光様式の代表的作品群を、金銅仏(挿図4)を始め、正光期(520〜525年)の河北省において見る見解があるが、河北省に地続きの山東省がその影響を受けていることは言うまでもない。一方この山東省では、正光期より2年早い神亀元年(518年)の銘記を有する作品(挿図5)と、前掲のもの(挿図3)も作られていた。その共通した点はというと、例えば強い張りのかわりに、真っすぐ垂れる裾に示された重厚温和な造形感覚にあることは明らかである。このことは、横の線での北魏正光様式の地域的限界を示すと同時に、縦の線で見た、北魏様式に対する東魏的特徴としてよく指摘される穏やかな丸みの系譜についての1つの解釈へ導くように思われる。思えば、冒頭で書いた東西魏への分裂が仏像の北魏様式からの脱皮を実現させ、東魏におけるそれには、山東省の土地柄で育まれた重厚温和な造形感が介在したように思われる。そういう意味で、本像は北魏的且つまた東魏的だと言うことができるかもしれない。
 |  |  |
| 18-3 | 18-4 | 18-5 |
ところで、本像の丸みの主張は、光背にある各モチーフの作り方においても窺えよう。形態だけでなく、決してシャープでない輪郭線、言い換えれば、立体方向の凸出のまろやかな出し方には興味深いものがあるように思われる。山東省はまた、画像石で有名な孝堂山石刻、武氏祠石刻(挿図6)を育んだ土地である。漢時代以来、造形を、線刻または鋭い輪郭線で僅かに対象を凸出させる平板型の形象に託すのに長じ、それに慣れてきたこの地方にとっては、対象を丸みのある立体に表現することが、技法と自覚の両方において、北魏代の課題であると同時に、東魏代及び続く後世の宿題でもあると思われる。本像中尊の透かし彫りの頚部、奥行きの深い頭部に一応示された立体性と、未だ半分素材(光背)に埋まっている肩部の、言ってしまえば偏平性との不釣り合いは、1つの傍注になってくれるだろう。ともかく、まだまだ検討する余地のある問題であるが、漢代画像石では、このように素材から対象を盛り上げるように作り出す浮き彫りの作品が四川省に集中して見られるし(挿図7)、北魏代の仏教彫刻では、従来南北様式の交差点とされる河南省にある竜門石窟の造像例が確認される(挿図8)。このように、本像は大きく南北様式の問題をとらえる時の価値ある材料となっているように思われる。
(漆紅)
 18-6
18-6 18-7
18-7 18-8
18-8

石造
中国
山西省天龍山石窟
8世紀初頭
高さ20.5cm
文学部考古学研究室・列品室
天龍山は彼の有名な雲岡石窟と同じ山西省に位置し、北斉(550〜578年)の代から造寺造窟が始まったことは文献によって知られる。通称の天龍山石窟は東峯と西峯とに分けられ、初期の造営としては、北斉皇建元年(560年)の聖壽寺(一説には天龍寺)や、仙嚴寺などが著名である。東魏に続く北斉代の造像の中心と見なされるこの地には、以降、隋、唐を経て、多くの造営が重ねられ、時の仏教造形の流れを把握する上で、豊富な資料を残してくれた。しかし、この天龍山石窟も、時の移り変わりと共に、長年荒涼のままに眠っていた。大正7年に関野貞氏の踏査を契機に、再び人目に触れることになった。以来、度重なる人的破壊によって、支離破砕して、今日では、もはやその全容を仰ぐことができない。眼前のこの美しい菩薩頭が過去の破壊につながっているとはなんと痛々しいことであろう。あるいは、舎利八分の思いでもって接するのがその痛みに対する些かな慰めかも知れない。
 本像はもと繭山順吉氏の収集品で、頭飾に丹、髪際に青、唇に朱が残り、顔面のところどころに白土の跡が認められる。彩色像だったであろう。髻部が欠損し、頭部の宝珠形頭飾、鼻先、左耳下部が黒ずんで見え、後補時に使われた接着剤の変色と思われる。後頭部には、上に、
本像はもと繭山順吉氏の収集品で、頭飾に丹、髪際に青、唇に朱が残り、顔面のところどころに白土の跡が認められる。彩色像だったであろう。髻部が欠損し、頭部の宝珠形頭飾、鼻先、左耳下部が黒ずんで見え、後補時に使われた接着剤の変色と思われる。後頭部には、上に、
「百」
その下には、
「十八窟
左協」
の墨書がある。「協」は「脇」の誤写であると推察されるが、「百」が何の数字なのかは分からない。根津美術館所蔵の天龍山仏頭、菩薩頭にも、同じ位置にそれぞれ「上」と「深」の墨書をもつものがあり、もとは共通した事情を有することを想像させる。
さて、十八窟は、西、北、東の3面の壁に、それぞれ一仏二半跏菩薩、一仏二立形菩薩二半跏菩薩、一仏二半跏菩薩二立形菩薩がある。左脇侍と考えられるのは、西壁1、北壁2、東壁2の計5躯があるが、『天龍山石窟の現状』によれば、北壁の2つの内、1つは根津美術館所蔵で、1つは旧山中蔵と言われ、作風から見ればそれでいいようである。
東壁の2つについては、同論文では、ハリー論文「天龍山彫刻—復元及び年代推定」の掲載写真の69番、菩薩頭部(旧山中蔵)(挿図1)を半跏像の方に当て、立像の方は明らかにされていないが、もと北壁にあった脇侍の頭部に接合されているその上半身(ともに根津美術館所蔵)の法量からみて、本頭像より一回り小さいことが分かり、本件と無関係と見てよかろう。
西壁の左脇侍の頭部も所在不明。ただ、その破損状況からみて、これも本件との関係が薄いように思われる。むしろ、東壁本尊頭部(根津美術館蔵)(挿図2)との作風上の近似などから、本頭像はもとは東壁にあったと推定するほうが妥当かもしれない。そして、本頭像が前掲ハリー論文写真69番菩薩頭部とほとんど差が認められないほど似ていることもこの推定を裏付けるように思われる。
 |  |
| 19-1 | 19-2 |
ところで、『中国文化史跡』では、破壊前の十八窟東壁の写真(挿図3)が紹介されている。それによると、半跏像頭上の髻が既に欠損しており、ハリー論文に上げられた写真69番菩薩頭部の現存状態とは論理上の矛盾がおり、その点、本頭像のほうがうまく当てはまるように思われる。つまり、本頭像の帰属について2通りの考えができる。1つは、今述べたように、東壁の左脇侍半跏像に本頭像を、右脇侍にハリー写真69番頭部を比定することである。もう1つは、ハリー写真69番頭部と本頭像とを同一のものとする見方であるが、その際には、ハリー写真69番頭部に対する確認の作業が残る。いずれにしても、過去の写真を含む資料の再確認、再検討の必要があり、今後の進展を待たなければならない。因に、本像の鑑賞に当たっては、現在の真っすぐの状態ではなく、身体部にある動きの方向に沿ってやや傾いた感じでみられるのが本来の姿にふさわしいということを付言しておきたい。
天龍山には、唐代石窟が14あり、そのもっとも優れたものに四窟、十四窟とこの十八窟などが上げられる。十八窟は、玄宗帝開元期(712〜742年)前後の造営と言われ、そのすばらしい出来栄えは、たとえ断片残頭と言えども、一世を魅了する。よく絶賛されるところのゆったりとした、静かな趣は、本像を通してもその一斑を窺うことができる。人体に対する的確な把握は、例えば本展の東魏天平四年銘像と比べても、著しい進歩が見られ、これはまた、北魏様式と違う唐様式の本質でもあると考えられる。東魏像は、全身が着衣に覆われ、身体部の肉体表現が見えないどころか、部分的には歪曲された関係にある感じさえする、それほど肉体の存在が無視されていた。顔面も理想像的な細面で、表現のポイントはより正面に集中される。それに対して、この天龍山頭像は、膨よかな顔面形態の中で、弾力性に満ちた肌の感触を出し、唇の優美な曲線にも豊かな肉体感が示されている。ここでは見られないが、身体の比例、動きから肉体の起伏まで写実性に富み、唐代を通じての造形精神を我々の目に訴えてくる(挿図4)。
 |  |
| 19-3 | 19-4 |
唐代に至るまでの300年間の造像事情はもちろん、唐様式に即しても、尚多くの問題が残り、一言で言い切れないことはいうまでもない。全体として、石材による人体の立体表現に恵まれなかった北中国の土地にこれだけの出来栄えの作品が作れたことは、東西南北の広範囲にわたる交流なしでは到底考えられないことである。前掲写真(挿図4)の菩薩像に見られた崩した半跏形式は、時代の隔たりがあるが、インド古来の在家信者、または国王、竜王の形象によく見られるポーズであることは興味深い。ともかく、この交流の結晶は、龍門の唐代石窟であり、天龍山石窟であるが、中でも、天龍山からは石に思えないぐらいの柔らかさや、菩薩の姿勢をさらに自由にさせる、人体を素材からさらに解放させる、そういった独特なとらえかたが感じられる。そういう意味でも、本像を、前にお勧めした傾いた状態で鑑賞できないのは無限の遺憾と言わねばならぬ。
(漆紅)
 en Lung Shan: Reconstruction and Dating," Artibus Asiae, Vol.XXVII, 3.1965
en Lung Shan: Reconstruction and Dating," Artibus Asiae, Vol.XXVII, 3.1965

金銅造
朝鮮
平壌(?)
11世紀初頭
高さ(中尊)67.5cm、高さ(両脇侍)37.6cm
福井武次郎氏旧蔵
文学部考古学研究室・列品室
水瓶を左手に、未開敷蓮華を右手に持し、頭上に化仏を頂く金銅観音像は中国北魏の代に先行作例が確認でき、太和8年(484年)銘をもつものは図像的先駆として知られている。古代朝鮮でも、三国時代7世紀の同形式のものが伝えられ、この種の造形の広範囲の流布が推測される。中国宋代では、各宗派とも観音造形を好んだことが指摘され、この形式の造形も時代とともに生きていたことが想定される。
 本像は福井武次郎氏が平壌に住んでいた頃に蒐集したもので、もともと三尊一具で見つかったと伝えられるが、中尊、両脇侍(ともに仮称)とも同形同様式の観音三尊像は類例を見ず、同じ工房の量産の可能性を示唆する。格狭間付き八角の台脚に、
本像は福井武次郎氏が平壌に住んでいた頃に蒐集したもので、もともと三尊一具で見つかったと伝えられるが、中尊、両脇侍(ともに仮称)とも同形同様式の観音三尊像は類例を見ず、同じ工房の量産の可能性を示唆する。格狭間付き八角の台脚に、
聖居山天聖寺統和二十八年
の銘がある。天聖寺という名の寺は複数存在し、平壌(高麗の西京)と同じ平安道にある殷県のそれに相当すると考えられるが、俄に特定できない。山号の聖居山もまた、同じ高麗の属地だった黄海道・金川や他の地域に複数に認められるものの、銘記に示されたような寺名との結び付きは、現在の調べでは確認されていない。しかし、山号、寺名とも高麗のものと見てよかろう。
「統和」は中国遼代(916〜1125年)聖宗(在位983〜1031年)の年号で、「二十八年」(1010年)は、宋真宗(在位998〜1022年)大中祥符三年、高麗顕宗(在位1010〜1032年)元年、日本一条天皇(在位986〜1011年)寛弘7年に、それぞれ当たる。『遼史』に徴すれば、高麗朝の中でも、統和期に当たるこの時期は、学童を遼に派遣して遼の言葉を勉強させるなど、遼との交流が急速に多くなったようだが、一方では、『宋史』によると、高麗朝が遼の年号を用い、その正朔を奉じるようになったのは、恐らく文宗朝の1030年代以降のことらしい。本像の「統和二十八年」の1010年代には、遼との往来は多くなったが、宋王朝を正統と仰ぐ意識が依然として強かったように思われる。この時期で遼の年号を仏像に使ったということは、本像の製作地を暗示するように思われ、可能性としては、遼の工房が高麗の注文を受けて作ったことが考えられる。
ところで、統和期の年銘をもつ本像はしかし、様式の観点から見ると、完全に朝鮮化した高麗仏像の系統と違い、必ずしも当代の様風そのものでないことが指摘でき、そして、一見大陸的ではあるが、宋風彫刻の自由平明さとも違い、言ってしまえば、かなりの古様を伝えているように思われる。
三像とも頭部から足まで一鋳で、蓮肉、八角台脚を含む台座は別鋳である。いずれも光背をつけた痕跡が見られず、部分的に錆が甚だしいほか、鍍金がよく残り、特に両脇侍が保存良好である。三像通じて、背面肩部に掛けた天衣がU字型に腰辺まで垂れ、韓国公州博物館蔵7世紀の百済観音像(挿図1)、日本では、新潟関山神社に現存する百済7世紀の菩薩像(挿図2)と同じ意匠をもつ。また、半跏像ではあるが、両肘後部衣端の鋭角的なはりも含めて、近似する表現を有する古新羅の作品があり、MOA美術館蔵隋代金銅菩薩像(挿図3)にも先駆的な様式が確認される。因に、日本の仏像の中で、那智山経塚出土十一面観音(挿図4)を始め、7世紀白鳳時代の菩薩像に集中してそれが見られるのは興味深いことである。
 | 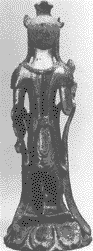 |  |  |
| 20-1 | 20-2 | 20-3 | |
それらに加えて、三面頭飾をつけた頭部が大きめ、腹を前方に突き出して、反りぎみに直立する、殊に両脇侍が長身に表現されているなどの点も、朝鮮三国時代後半の百済の観音像の基準作と見なされるもの(挿図5)や、前掲公州博物館蔵百済観音像に共通して、中国北斉隋代様式の吸収を窺わせる。 一方、天衣の作りに乱れが認められ、背面肩にあった天衣が正面から見ると、消えてしまっている。その結果、膝下でX字型に交差する天衣が2本となり、それぞれの一端が両腰側で鋲で止められ、形式的なものとなってしまった。宋風のものと見なされる台座の反花の細長い蓮弁と共に時代の下るのを物語り、銘記の示す時代の認定に証拠を与えるように思われる。
遼代在銘の作品が少なく、様式的比較を行い難い現状の中で、幸いにも、「統和二十六年」(1008年)銘の金銅菩薩像(挿図6)が伝存する。座像であるため、全容の比較は適当ではな<
 |  |  |
| 20-4 | 20-5 | 20-6 |
いかもしれないが、上半身のモデリング、例えば端正でやや硬直した姿勢、細めの首に大きめの頭部、はりながら丸みをもつ両肩などには類似性をみて取ることができるように思われる。そして、細部表現をもたず、大まかに把握される淡泊な肉身感覚は、両像通じての特徴であり、前代の唐とも、当代ないしその後のものとも違い、前記斉隋代の名残を偲ばせる。そういう意味では、本像はまた、遼代造像の守旧性の一面も示してくれると言えるかも知れない。
時間、資料等の制限で、詳細な検討ができないが、中尊と両脇侍の顔面形態、表情における著しい相違が第一の問題として残り、同じスタイルの中での作風の違いも見逃せない。特に中尊の顔の異常なほどの膨らみや、女性的な優しい笑顔は、朝鮮三国時代の中でも、古新羅の独自な展開と見なされる童顔を彷彿とさせるところがあり、中尊と両脇侍との間に再模倣、再創造の関係があることも考えられないでもない。今後の材質等に対する精査を待たねばならぬ。
(漆紅)

銅造
タイ
チェンマイ
15世紀頃
高さ37.3cm
三木栄氏寄贈
文学部考古学研究室・列品室
幾度の民族的、文化的交流・融合を経て、多様な展開をしてきたタイの仏教彫刻美術は、13世紀後半になると、スコタイ(Sukho-thai, 1250〜1438年)とランナタイ(Lan Na Thai, 1296〜1558年)のタイ族文化をベースに新しい造形を始めた。ランナタイはチェンマイ(Chiang Mai)に首都を置き、隣国スコタイとの交流から造形の栄養を吸収した。その典型的な造像の1つには、未開敷蓮華(または火焔)状の飾りを頭部につけ、触地印をした偏袒右肩の如来像(挿図1)が挙げられる。顔面の表情や、肉体の表現などには、インド作品ほどの官能性がないが、形式的には、パーラ朝(8〜12世紀)期の仏像(挿図2)を彷彿させるところがあるように思われる。
 |  |
| 21-1 | 21-2 |
本像は、破損のため全容を拝することができないが、衣紋の表現されない衣服が体に密着し、左肩から垂れてきた衣端が乳首僅か上方に終わるなど、前記ランナタイ仏像の特徴を示す。肉髻の上部には円孔が空き、火焔状の飾りがつけられていたとみなされる。大粒の螺髪が緊密に配列され、ところどころに鍍金の痕跡が認められ、往昔の荘厳ぶりを偲ばせる。弓状に波打つ髪際線、眉、目瞼、口唇部、そして円満な両肩など、随所に見られる曲線は、像全体を支配する造形感覚であり、抑揚のある優雅な美的情緒を醸し出す。顔には静かな雰囲気が漂い、タイ独自の形態感覚が展開される。逆三角形の胸部は分厚くて、弾力性に富み、解剖学的には苦しい感を免れないが、幅の広い両肩、太めの両手と呼応して、豊かな量感を主張すると同時に、人体の「日常」を超越した理想像の世界へ、我々を誘うのである。それが顔貌の禁欲的とでもいうべき清楚な肉体感覚とうまくマッチできたのは、造形に込められた高い精神性の賜物であろう。
制作期は、15世紀でも、早い時期のものであろう。
(漆紅)