





















金貨
中国
戦国楚時代(紀元前4〜3世紀)
昭和6年6月、小川浩氏より購入。
東洋文化研究所
 は中国の戦国時代に楚国で使用された金貨である。秤量貨幣であり、重量をはかって価値を定めた。チョコレートを食する時よろしくちぎって使用したものであろう。
は中国の戦国時代に楚国で使用された金貨である。秤量貨幣であり、重量をはかって価値を定めた。チョコレートを食する時よろしくちぎって使用したものであろう。中国における貨幣の出現については、殷・周の宝貝が議論される。殷や西周の金文には、この宝貝の賜與が記されており、貴重品であったことがわかる。この種の貴重品が物を交換する仲立ちとして機能し、やがて貨幣を発生させたと考えられている。
中国において、いわゆる貨幣の形態を有するものは、戦国時代になって出現する。部族制国家の衰退、領域国家による直接的交易網の広域化に平行するものであろう。この戦国時代の貨幣を検討すると、貨幣出現の経緯の一端を推測することができる。以下にこれを略述し、金貨郢 を歴史的に意味づけておくことにしたい。本稿を草するについては、以下の研究を参照し、音楽理論等について私見を補った。本稿の範囲内では、それぞれに引かれた諸研究には逐一言及しないことにした。
を歴史的に意味づけておくことにしたい。本稿を草するについては、以下の研究を参照し、音楽理論等について私見を補った。本稿の範囲内では、それぞれに引かれた諸研究には逐一言及しないことにした。
加藤繁『中国貨幣史研究』(東京帝国大学文学部における講義稿案を整理したもので、先秦貨幣については昭和初年。1993・12、東洋文庫論叢56)。先秦貨幣の大要を知るための基本資料。ただし下記の林・松丸両氏の見解等を補う必要がある。
林巳奈夫「戦国時代の重要単位」(『史林』51、1986・8)。遺物ならびに銘文史料による検討から、戦国時代各国の重量単位が一定の換算率をもっていたことを明らかにしている。戦国貨幣に鋳込まれた文字中に重量単位を指摘。
稲葉一郎「秦始皇帝の貨幣統一について」(『東洋史研究』37−1、1986、8)。統一貨幣としての秦の円銭の出土状況が、この貨幣の全国流通という通念には矛盾し一部の地域に限られる点を問題にし、始皇帝37年(二世皇帝立年)における「行銭」が、貨幣統一を意味すると推論。筆者平 は、この推論と始皇帝の「貨幣統一」は矛盾しないと考えている。下記のごとく戦国貨幣が秤量貨幣の性格をもつことから、統一を宣言した後も、現実に流通する貨幣には手を加えず、統一後の単位で重量を判断した(公にはそういうことにした)ものではないか。
は、この推論と始皇帝の「貨幣統一」は矛盾しないと考えている。下記のごとく戦国貨幣が秤量貨幣の性格をもつことから、統一を宣言した後も、現実に流通する貨幣には手を加えず、統一後の単位で重量を判断した(公にはそういうことにした)ものではないか。
江村治樹「戦国新出土文字資料概述」(林巳奈夫編『戦国時代出土文物の研究』、京都大学人文科学研究所、1985、3、30)。李学勤「戦国題銘概述」(『文物』1959、7〜9)の続編ともいうべきもの。新出文字史料や研究をまとめ、一部に貨幣を使う。
松丸道雄「西周時代の重量単位」(『東洋文化研究所紀要』117、1992、3)。西周時代の青銅インゴットが当時の重量単位によって作られていると結論。この結論によれば、西周の重量単位は10進法により上級単位に繰り上がる。その単位重量にも注目したい。 戦国時代に主に流通したのは銅貨である。燕(河北)・斉(山東)地域で作られた刀銭(形態が刀子に似る)、黄河中流域の中原地域で作られた布銭(形態が農具の鍬に似る)、秦で作られた円銭、楚で作られた蟻鼻銭(形態が蟻の顔に似る)が知られる。
これらのうち、西周時代との関連から注目されるのは、布銭である。そこに示された重量単位尚が、青銅インゴットによって想定される西周時代の重量単位1鈞(=十 〈西周の
〈西周の 〉)の1/8を1
〉)の1/8を1 〈戦国の
〈戦国の 〉=百尚とするものらしい。ちなみに戦国貨幣では、布銭のうち大型の空首布がまず出現し、以後小型化して平首布や斉・燕の刀銭、秦の円銭が現れたと考えられている。
〉=百尚とするものらしい。ちなみに戦国貨幣では、布銭のうち大型の空首布がまず出現し、以後小型化して平首布や斉・燕の刀銭、秦の円銭が現れたと考えられている。
遺物ならびに銘文史料による検討から、戦国各国内の重量単位の上級単位への繰り上げ方、および各国間の重量単位の換算率の大要がわかるが、注目されるのは、各国とも上級単位への繰り上げに当たって、音楽理論で重視されている9・6・8およびその倍数が使用され(例えば秦国では1両=24銖)、かつ各国間の換算率にも、これらの数値が介在している点である(例えば中原の1釿は秦の18銖)。上記の1鈞=1/8 もこれらに含まれる。こうした事実は、換算率が後で計算されたのではなく、換算の理念が先行し、それに合わせて単位の整理が進んだことを示す。本来10進法で整理されていたはずの重量単位が再整理される過程で、9・6・8が関与してきているのである。
もこれらに含まれる。こうした事実は、換算率が後で計算されたのではなく、換算の理念が先行し、それに合わせて単位の整理が進んだことを示す。本来10進法で整理されていたはずの重量単位が再整理される過程で、9・6・8が関与してきているのである。
このことはまた、音楽理論と度量衡が結びついたことを具体的に示す。その理論はより整理された形で後代の『漢書』律暦志に見える。度・量・衡いずれも9・6・8およびその倍数で説明され、整然とした宇宙秩序を語る。皇帝はこの秩序を熟知していなければならない。上級単位への繰り上げについては、重量単位のみがこれらの数値を介在させる。度・量ともに10進法であるのと一線を画す。音楽理論を度量衡秩序に組み入れた際、重量単位の繰り上げにこだわったことがわかる。
戦国貨幣個々の重量にはばらつきが目立つ。しかし、想定される各国の重量の目安に近いところにおおよそおさまる。各国貨幣とも、孔があいているのを1つの特徴とするのは、こうしたばらつきを解消するのに、最終的にまとめて貨幣の総重量をはかったためと見られる。 重さにばらつきがでるのは、貨幣鋳造のあり方にもよるらしい。大量に作るため、個々の貨幣重量の正確な調整には気をつかっていない。重量を正確にすることに手間をかけるよりは、孔をあけて最後に確認する現実的方法の方を選んだらしい。始皇帝が度量衡統一を宣言し、秦国とは異なる宇宙の説明を否定した際も、「換算」を前面に出すことで、貨幣の統一は実現されたであろう。公の宣言として、最後に統一の単位で重量を評価すればよいのである。現実に流通する貨幣に対する対応は、かなり寛容であったらしい。
秤量貨幣であることを形態からも示すのが、金貨「郢 」である。郢
」である。郢 の重量をはかり、その価値を判断したことは明らかで、スタンプは目安を示すに過ぎない。なお、一般に流通していた青銅貨幣と金貨との交換比率については、当時の史料が残されていない。ただし、後には、『漢書』東方朔伝・『漢書』食貨志下王莽や『公羊伝』隠公5年の後漢の何休注により金百斤が銭百万に当たることがわかる。黄金1斤が銭1万になる。銭の末端重量の変更などがあるのでこれを単純にさかのぼるわけにはいかないが、重量としての1斤は16両(384銖)、秦時の末端貨幣は半両銭(十二銖)である。前漢の武帝の時八銖銭や四銖銭・三銖銭が発行され、五銖銭で落ちつく。これらから単純比較しても、金の相対的貴重度が推し量れる。
「郢
の重量をはかり、その価値を判断したことは明らかで、スタンプは目安を示すに過ぎない。なお、一般に流通していた青銅貨幣と金貨との交換比率については、当時の史料が残されていない。ただし、後には、『漢書』東方朔伝・『漢書』食貨志下王莽や『公羊伝』隠公5年の後漢の何休注により金百斤が銭百万に当たることがわかる。黄金1斤が銭1万になる。銭の末端重量の変更などがあるのでこれを単純にさかのぼるわけにはいかないが、重量としての1斤は16両(384銖)、秦時の末端貨幣は半両銭(十二銖)である。前漢の武帝の時八銖銭や四銖銭・三銖銭が発行され、五銖銭で落ちつく。これらから単純比較しても、金の相対的貴重度が推し量れる。
「郢 」の名はスタンプの文字による。ながらく「郢爰」と字釈されてきたが、わが国の林巳奈夫氏により「爰」は、重量単位としての「
」の名はスタンプの文字による。ながらく「郢爰」と字釈されてきたが、わが国の林巳奈夫氏により「爰」は、重量単位としての「 」と釈すべきであるとされ、一般に支持されるようになった。この種の金貨は、秦統一以後も引き続き使用された。
」と釈すべきであるとされ、一般に支持されるようになった。この種の金貨は、秦統一以後も引き続き使用された。
(平 隆郎)
隆郎)


インゴット
(鋳貨と見る見方もあり、その役割も担ったものの、本来はインゴットとして作られたとする見解を採る)
中国
制作地は銘中の「上郡」であろう。後漢の上郡は、現在のほぼ陜西省北郡ならびにそれ以北の地。
郡治は、今の楡林県南の定河と楡林河の合流点近くにあった。この地で鋳造されたと考えられる。
後漢時代、建和2年(西暦148年)
制作者は後漢の銀匠、王升・王□・呉□
縦5.95cm、横4.0cm、高さ1.66cm
重さ174g
昭和6年10月20日、東京の古美術商より購入。学院閉鎖に伴い東洋文化研究所に移管。
東洋文化研究所
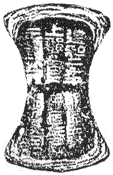
中国古代において、銀が一般的に用いられるようになったのは、春秋戦国期であろうと考えられている。戦国式青銅器にみえる金銀錯(金銀象嵌)がこれである。西アジアにおいては金属技術発展の初期段階から金銀の知識・利用が見られるのに対し、中国では、殷代以降、青銅技術が一般化したにも拘らず、金銀は殆ど知られなかった。銀について言うと、春秋戦国期を溯るほとんど唯一の例外として甘粛省玉門火焼溝遺址より銀器が発見された(未報告。文物編集委員会編『中国考古学三十年』、平凡社、1981年、142〜3頁参照)とされるが、これは新石器時代の中国でのこれまでに知られる孤例である。したがって、この時期にすでに、中国に銀の冶金技術が存在したと見るには無理があり、この遺例は西アジアからの製品の流入であったと見るべき可能性がある。戦国時代以降、中国では急速に銀の使用が増大した。
当 には、銘文があり、
には、銘文があり、
建和二年 銀匠王升
上郡亭長 銀匠王□
□造公行 銀匠呉□
と読みうる。この読み方に異説がないわけではないが、それについては、後引の松丸、李論文を参照されたい。「建和二年に、上郡の亭長たる□(人名)が造り、公行せしむ。〔鋳造者は〕銀匠王升、銀匠王某、銀匠呉某である」の意であろう。「亭長」は、『漢書』百官志に、「亭有亭長、以禁盗賊」とある亭長か。「公行」は、かならずしも判然としないが、公(ひろ)く発行する、の意かと思われる。
同類の遺物は、あまり数多くないが、奥平昌洪『東亜銭志』巻8に、器形、銘文等が基本的に同一のものが1個、収載されている。但し、重量は95匁(即ち、356g)とあるので、当 のほぼ正確に2倍の重さがあることがわかる。
のほぼ正確に2倍の重さがあることがわかる。
この重量は、後漢時代の何を意味したかを考えてみる。当時の重量単位は、
1斤=16両 (1両=13.92g)
である。したがって、当 は、
は、
174(g)÷13.92(g)=12.500(両)
また『東亜銭志』所載の銀 は、
は、
356(g)÷13.92(g)=25.574(両)
となる。このことは、おそらく、当時は百両が基本単位で、その半(=50両)、又その半(25両)、さらに又その半(12.5両)……といったきざみ方で銀 が作製されていたことを推測させる。銅のインゴットの場合にも、同様のことが推測され(松丸『西周時代の重量単位』東洋文化研究所紀要117冊、1992年参照)、鋳造の便宜のための配慮と考えられ、貨幣の刻み方とはシステムの異なっていたことが考えられる。
が作製されていたことを推測させる。銅のインゴットの場合にも、同様のことが推測され(松丸『西周時代の重量単位』東洋文化研究所紀要117冊、1992年参照)、鋳造の便宜のための配慮と考えられ、貨幣の刻み方とはシステムの異なっていたことが考えられる。
当時の銀はどの程度の価値をもっていたであろうか。後漢時代の銀相場についての文献は見当たらないが、『漢書』食貨志下に王莽の幣制として、
朱提銀重八両爲一流、直一千五百八十。它銀一流、直千。
(朱提銀は重さ8両を1流とし、その値は1580〔文〕である。それ以外の銀は1流あたり、値1000〔文〕である)
とされている。つまり、
8両=1,000文
15571両=125文……(a)
に相当する。一方、比較すべき金は、同様の王莽の幣制において、
黄金重一斤、値銭萬。
(黄金の重さ1斤は、銭1万〔文〕に値する)
とあるので、
1斤=16両=10,000文
15571両=625文……(b)
となる。したがって、(a)、(b)より、
金:銀=625(文):125(文)
=5:1
となって、王莽時の銀は、金の1/5の価値をもっていたことが判明する。この割合は、後漢時代でも、それほど大きく変化してはいるまいと思われる。
(松丸道雄)
 ”釈文」『上海銭幣通訊』第20期、1990年8月
”釈文」『上海銭幣通訊』第20期、1990年8月