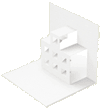
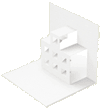
建築史家の間では、ルネッサンス初期の建築家、フィリッポ・ブルネルスキが15世紀初頭にパースペクティブを再発見したということになっている。パースペクティブというのは、遠くのものほど小さくみえ、箱型の物体の輪郭線が焦点に集まるように描く作図のやり方で、遠近透視画法とかパース画法などともよばれているものだ。フロレンスにおけるその披露の逸話は次のようなものである。ブルネルスキは、ドゥオーモ広場の一角を占める大聖堂の入り口にたち、中心に小さなノゾキ穴のあいた板を片手で取り出す。そしてまず、このノゾキ穴を通して、広場の中心にある八角洗礼堂を見る。つぎに、そのままの姿勢を保ちながら、もう片方の手で、当時ベニスで生産が始まったばかりの高品質の鏡を取り出し、ノゾキ穴のあいた板の前に掲げる。当然、鏡が八角洗礼堂への視線をさえぎることになり、ノゾキ穴のあいた板の裏側が鏡に写しだされてみえることになる。ところが、実はこの板の裏側には、はじめから、八角洗礼堂の絵が逆さまに描かれており、本物の八角洗礼堂のかわりに、鏡の中に八角洗礼堂の絵がノゾキ穴を通して見えるという仕組になっていた。目、ノゾキ穴のあいた板(裏側に絵)、鏡、八角洗礼堂という順の位置関係を想像していただきたい(fig. 1)。
fig. 1 ブルネルスキは、パースペクティブを完全にマスターしており、この八角洗礼堂の絵を正確な作図的計算に基づいて描くことができた。したがって、鏡を板の前に出し入れした際、ノゾキ穴を覗いていた人は、本物の八角洗礼堂の姿と、鏡の中の八角洗礼堂の絵の区別を言い当てることができないほどであったという。この後、ブルネルスキは、セニョーリア広場でも同様の実験を行っている。今日では、ブルネルスキが絵を描いたこの穴のあいた板は喪失し、大聖堂入り口部分の増築にともないドゥオーモ広場の形状も変わってしまが、この逸話は、パースペクティブがいかに人間の目に映る三次元空間のイメージを忠実に再現することに成功したかを示している。
実は、パースペクティブは、15世紀以前の絵画から使われており、その起源は、古代ギリシャで街並の絵を描いたステージ・セット(シノグラフィー)に遡るとされる。紀元前5世紀の哲学者アナクシゴラスは、「シノグラフィーは、光学の問題であり、建物が絵の中にどのように描かれるべきかの理論である」とのべた。デモクリトス、ユークリッドなどもパースペクティブを研究している。しかしながら、その後長きにわたって、パースペクティブは建築や絵画の中で使われる機会は少なく、その原理も伝承されずに失われつつあった。この失われた技術を復活させ、さらに正確な科学的画法として確立させたのが、ブルネルスキであり、したがって、冒頭の逸話が発見ではなく再発見とされるゆえんである。
ブルネルスキの後、数学者、建築家、画家たち(ルネッサンスでは、これらの職能区分は元からあいまいであった)によってパースペクティブが再び脚光を浴び、研究され、数多くの美しいドローイングをともなった教科書が出版される。レオナルド・ダ・ビンチは、著書「絵画の理論」の中でパースペクティブをとりあげ、1498年にはミラノの教会で、自ら一焦点のパースペクティブを正確に用いて「最後の晩餐」を描く。建築家レオン・バチスタ・アルベルティによる1511年の出版の「絵画について」では、固定された目と物体を結ぶ視線が画面にぶつかる交点をもとにパースペクティブを描く原理や、絵の中の物体の遠近の割合を計算するための作図法が説明されている。また、1525年のアルブレヒト・デューラーの著書、「画家のためのマニュアル」は、特に興味深い。ここには、デューラーの考案したパースペクティブを描き出すための装置がいくつか紹介されているのである。fig. Aは、その中の一つで、三本の糸と、額縁およびキャンバスよりなる。最初の糸は、一端が、壁のフックを通して鉛の重りにつながれている。画家の助手は、もう一端についた針の先でギターの輪郭上の点を差し示す。画家は、さらに額縁に縦と横の二本の糸を張り、その交点が、最初の糸が額縁を通過する点に合うように調節する。それから、最初の糸をゆるませておいて、キャンバスを額縁の中に収め、この縦糸と横糸の交点に鉛筆で印をつける。デューラーは、この作業を繰り返すことでギターの「輪郭上の点をすべてキャンバスの上に転写」し、その点をつなげることで正しいパースペクティブを描き出すことができると説明する。パースペクティブの原理を説明する上で、何と明快な装置ではなかろうか。
fig. A
実際のところ、ルネッサンスに確立されたのは、デューラーのいう「転写」、つまり、三次元の物体から二次元の画面への投影を、このような装置の助けを借りずに作図で求める方法であり、たとえば、1537年から1547年にかけて出版された建築五書でしられるセバスチアノ・セルリオも、その第二書のなかで、「パースペクティブについて」という節を設けて、多焦点のパースペクティブの原理を図解している(fig. 2)。以後、クライアントへの説明や、設計途中の建物の空間の感じを確かめる上で、パースペクティブが建築という職能において重要な役割を果たすようになったのは、新聞にはさまれた新築マンションのチラシ広告を見るまでもなく明らかだ。
fig. 2 ルネッサンスのパースペクティブは、平面の描画面に三次元空間の物体を投影するわけであるが、後に、円柱面や、球面に投影する方法も開発され、芸術表現では、エッシャーの作品でお馴染みの方も多いことと思う。今日では、各種のパースペクティブを、コンピューターが三次元の幾何学データから瞬時に作図することができ、そこで作成した構図に、グローバル・イルミネーション法といった最新の光学計算のアルゴリズムを使えば、ブルネルスキでなくても、現実の写真と見分けのつかないイメージを作り出すことが可能である。
話は変わるが、1993年に私がハーバード大学で講師をしていたときに、同僚のホルヘ・シルベッティー教授、当時修士課程にいたサンガ・キム博士と三人で、ハギア・ソフィア寺院に関するプロジェクトをやったことがある。ハギア・ソフィアは、トルコのイスタンブールの中心的な建物であり、現在は、イスラム教のモスクとして使用されているのだが、もともとは、東ローマ帝国のユスティニアヌス帝が式典を行うためのキリスト教教会として537年に建立された。ユスティニアヌス帝の圧倒的な権力のもとに、中心に、直径約30メートルという壮大なドームを配し、そのスケールを支えた高度な組石技術、および、空間的な効果は、後の近代建築の登場までは比肩する建物がほとんどなかった。さらに、東西文化の接続点のイスタンブール(旧称コンスタンチノープル)という要礁に位置するハギア・ソフィアは、後世の建築家に大きな影響を与えることとなる。建築史家は、平面や空間構成があきらかにハギア・ソフィアのものを踏襲した寺院、教会建築を数多く指摘し、この建物が、ドーム建築の完成された一プロトタイプとなったことを証明している。また、同時代の建築家に影響力の大きかった、19世紀の建築理論家シュワジーや、近代建築の巨匠、ル・コルビジェもその代表的著書のなかでハギア・ソフィアをとりあげている(fig. 3、4)。ル・コルビジェの「建築をめざして」では、建築家への三つの教えのひとつ、平面図に関する例としてシュワジーの本からとったハギア・ソフィアの挿絵を載せ、「平面は、構造全体に影響する。全ての元となる幾何学的法則、および、そのさまざまな変形が、建物の隅々で展開する。」というキャプションを付けている。
fig. 3 fig. 4 fig. 5 このプロジェクトにおけるわれわれ3人の目論見は、ユスティニアヌス帝による537年の建立の後、557年の大地震による破壊、および、オットーマン帝国征服後のイスラム化で幾多の改修、変更を受けてきたこの建物を、コンピューターの幾何学模型として、建立当時の姿で復元し、分析しようというものであった。たとえば、現在、外部の四隅にそびえたつ四本の塔は、ミネラットと呼ばれるイスラム寺院特有のものであり、内部の幾多のアラビア装飾と共に、イスラム化後の変更部分である(fig. 5)。
幾何学模型の制作は、シルベッティ教授の集めてきた資料とロランド・メインストーンの著書「ハギア・ソフィア」をもとに主にキム博士の努力で進められ、当時主流となりつつあったレイ・トレーシング法のソフトウェアを使って私がレンダリングを行った。作成したイメージは、コンピューター・グラフィックスという道具の特製を生かして、紙の上での作画や木の模型では表現することの難しい内容を伝えるものだ(fig. C, D, E)。
ハギア・ソフィア中央の大ドームは、ユスティニアヌス帝の400年ほど前、ハドリアヌス帝が117年にローマに造ったパンテオン(fig. 6)の円柱上の大ドームとほぼ同規模のものであるが、ハギア・ソフィアでは、この大ドームを正方形平面の基部の上にのせ、さらに高さ約40メートルまで持ち上げる計画を鉄やコンクリートのない時代に石積みで実現するため、きわめて巧妙な構造的な配慮が施されている。ペンデンティブと呼ばれるこのシステムは、ハギア・ソフィアにおいてほぼ完成されたとされる技術で、ハギア・ソフィアの建築を担当した建築家、アンテミウスとイシドロスが幾何学や機械工学に精通した学者でもあり、その卓抜した計算力と構法の知識によりはじめて可能であった。ペンデンティブ・ドームの巨大な荷重は、組石造の大アーチを経て、両サイドの四対のバットレスとよばれる塊によってバランスよく支え止められる。コンピューター・グラフィックスは、一つの幾何学模型を部分的に見せ隠しすることで、その構造体のイメージを浮かび出す(fig. D左)。
空間構成は、この中央の大ドームの一次システムのまわりに各種のドームやボールトからなる二次システムを二層に組み合わせて回廊状をなし、四隅にその上下二層をつなげるランプを配置、前面にアトリウムを持つ(fig. D右)。ドームやボールトといった内部の空間単位が連なる関係は、建築の物質と空間を図と地のように反転させることではっきりと見て取ることができるだろう(fig. C右)。実は、われわれの幾何学模型の制作は、逆にまずこれらの空間単位の形を入力し、ソリッド・モデラーとよばれるアルゴリズムをつかって図と地を反転させることにより内部空間のある建築の模型としたものだ(fig. E左)。このアルゴリズムをつかうと、完成した幾何学模型を自由に切り取って断面模型とすることもできる(fig. D右)。図と地の反転の過程では、複雑な建築のカラを肉薄の石積みの構造をつかって造り出したアンテミウスとイシドロスの天才がまざまざと見て取れるだろう(fig. C右)。
fig. C fig. D fig. E 余談だが、寸法とプロポーションの異なる様々なドームを効率よく入力するため、私とキム博士は小さなプログラムを組んだ。個々のドームの幅や高さといった基本寸法を与えるだけでドームの形状を自動生成するようにするのが目的であったのだが、プログラムを作るためにドームの一般的な幾何学原理の分析を行う過程で、面白い事実を学習することができた。たとえば、ハギア・ソフィアの両サイドの二階のドームは、球面状のペンデンティブ・ドームが連続しているが、その真下の一階では、球面ではなく、対角線に稜線を持つ変形ドームがつかわれている(fig. 7)。これは、真上に何もない二階のドームとは異なり、二階の床により階高を制限された一階の天井面をつくるためのデザイン配慮であろう(fig. 8)。この一階の変形ドームは、幾何学的には、樽状の回転体を二つ直交させてできる一種の交差ボールトなのであるが、この樽の半径をすこしずつ拡大していくと、あるところで二階のドームと同じ球面状のペンデンティブ・ドームになるのである。言い方を換えれば、二階のペンデンティブ・ドームは、一階の樽状の変形ドームの特殊形であるということになる。この原理をそのままアルゴリズムとして組み込んだわれわれのプログラムは、通常は稜線を持つ樽状の変形ドームを生成するのだが、ある特定の変数値を入れてやると、完全な球面状のペンデンティブ・ドームを生成する(fig. 9)。
三次元の幾何学模型ができてしまえば、コンピューター・グラフィックスを使って、視点を回してみる、下から見上げたり、中に入って見る、断面を切ってみるなどということが容易にできる(fig. F, G)。さらに、材料の質感や光源の強さと位置を決めて光の入り方もシュミレーションすることもできる。かくして、このプロジェクトから、ハギア・ソフィアの空間構成、構造システム、採光などを示す数百枚のスライドと、短編のアニメーションが生まれたのであった。
fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10
さて、このたびの展覧会では、このプロジェクトの成果を見せるための最も適した展示方法は何かと考え、特別なプロジェクション装置を考案することにした(fig. H)。「デジタラマ」と名付けたこの装置の目的は、建物に関する情報をインテラクティブに提示すること、操作の方法が直観的で体の動きに基づいたものであること、装置の作動原理が見た目に明らかであること、の三つである。
fig. F fig. G 大量の情報を展示する上で、コンピューターを使ったインテラクティブな方法が便利であることは明らかである。この装置も、コンピューターの助けを借りて、アームの両端に取り付けられた二つの画面の中に、ハギア・ソフィアに関する各種の映像が映し出されるようになっている。
アームの中央には小さな模型がおかれており、アームは、この模型の周りを上下左右に回転することができる。アームを回転させると、画面と模型の位置関係が変わり、画面の中の映像は、この位置関係に基づいて検索される。すなわち、手前の小さなフラット・パネルの画面には、模型を画面の手前から見た時の視点で各種の幾何学模型の外観のパースペクティブが映し出され、奥の大きなプロジェクション・スクリーンには、模型の中に入った時にスクリーンの方向を見る視点で、幾何学模型の内観のパースペクティブが映し出される。ギリシャのシノグラフィーは実物大にみえる街並みをステージ・セットの後ろに描き出し、ブルネルスキの再発見の逸話は実際の八角洗礼堂を肴にして行われた。そこには、投影物と体の間に、スケールと位置関係の一目瞭然で密接な関係があり、そのことが見る人を一層感激させたに違いない。この装置制作の原点には、パースペクティブの作画という、コンピューターにより完全に自動化されてしまったプロセスに、人間の体感で直接知覚できる姿を与えたいという欲求があった。
装置の作動原理は、アームの回転をペン・タブレットのセンサーにより計測し、そこから割り出した視点にもとづいてコンピューターでイメージを検索、そしてそのイメージをフラットパネル・ディスプレイとLCDプロジェクターでディスプレイするというシンプルなものである。一つ苦労した点は、アームの軽量化のためにLCDプロジェクターからの投光を鏡を使って反射させてからスクリーンにとどかせている部分である。アームの上下方向の回転でスクリーン自体が移動するため、それに合わせて常に鏡をアームの回転角の半分だけ回転させないと、鏡の部分での入射角と反射角がスクリーンへの投光方向にあわないのである。この部分は、ギア比が1対2になる4枚のギアをつかって解決した(fig. 10)。この装置では、デューラーの挿絵のパースペクティブ装置のように、回転角の入力部分からイメージの出力部分まですべてできる限り明快に露出するようにデザインしたつもりであるが、その成否は、実物を見てご判断いただきたい。
現在、展覧会の2ヵ月前にこの原稿を書いている時点で、デジタラマは、二つの試作デザイン(A型、B型)を経て、アルミ製のプロトタイプC型を制作中である(fig. B)。幾何学模型の内観のパースペクティブについては、当研究室助手のハルデン・リウ君が、最新のグローバル・イルミネーション法のソフトウェアを使ってイメージを作り直している。また、アームの中央におかれる小さな模型は、MITで開発された三次元プリンターとよばれるCAD/CAM機械で作られる予定である。同一位置から見回す内観のパースペクティブと、同一位置を見回す外観のパースペクティブを操るこの装置が、ハギア・ソフィアのように、単一の大空間を内部に、複雑な形態を外部にもつ教会などの建物に、カスタムメイドの表現方法となるのではないかと期待している。
fig. H
MITの私の研究室で進行中のプロジェクトの一つに、「未構築」と題したシリーズがある。古典建築を再現したり、実現しなかったにもかかわらず歴史上重要な役割を果たした建築空間を、最先端のコンピューター・グラフィックスを使って分析、構築する試みで、このハギア・ソフィア以外にもいくつか行っている。たとえば、ルネッサンスの建築家パラディオの残した20個のスケッチから彼のパラッツォ(イタリア都市住宅)の計画を完成予想したり、ムッソリーニがイタリア文化の殿堂として計画していたが敗戦により未完に終わったジュゼッペ・テラーニの「ダンテウム」の構築などを手がけており、来年のロサンジェルス近代美術館による「世紀末建築展」の巡回展でその一部を公開する予定である。現場からの報告として、コンピューター・グラフィックスという道具には、建築や空間表現に使えるオープンエンドの可能性が秘められているという実感がする。その可能性を、今度は自分の設計活動に役立ててみたいとも考えているが、その話は別の機会に譲ろう。
fig. B 尚、本論中でとりあげた参考文献に興味の有る方は、英文版のほうの末尾をご参照いただきたい。最後に、この装置の制作に当たり数多くの貴重な助言を頂いたピーター・モーリー氏と田甫律子氏、ディスプレイ機器の供与を頂いた日本電気株式会社に厚くお礼申し上げる。
 |
 |
 |