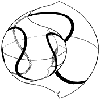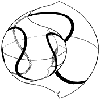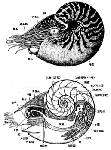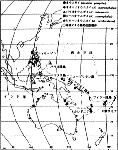現生頭足類はすべて海生で約730種が知られ、その大部分は一対の鰓と退化した内殻性の殻を持つ鞘形亜綱(イカ・タコの類で二鰓類とか内殻類とも呼ぶ)に属する。オウムガイ類は2対の鰓と外殻性の殻を持つことから鞘形類と区別されて、オウムガイ亜綱(四鰓類または外殻類とも呼ぶ)に分類されている(挿図1および口絵参照)。その分布は南西太平洋からインド洋西部(オーストラリア南西岸)にわたる珊瑚礁海域のやや深い海に限られていて、わずかに1属4ないし5形態種が確認されているにすぎない(挿図2、3、Saunders, 1987)。オウムガイ類は鞘形類に比べて神経系や脳の発達が悪く、吸盤を欠く多数の触手や水晶体や角膜のないピンホール型の単純な眼を持つなど、より未分化な体制を有している(挿図1)。このほかの解剖学・発生学的特徴をみても、オウムガイ類は鞘形類やアンモノイド類(化石頭足類)と比べて原始的な形質状態を保有していることがわかる(表1)。
現生オウムガイ類は系統分類学的にはオウムガイ目のオウムガイ科に属し、目としての歴史はデボン紀前期(約4億年前)に、また科としては三畳紀末(約2億年前)に遡る(Teichert and Matsumoto, 1987、挿図4)。オウムガイ類はアンモノイド類や恐竜類を絶滅させた白亜紀末(約6500万年前)の大事変の際にも大きな影響を受けずに、古第三紀から新第三紀にかけての世界中の浅海域に繁栄を遂げた。しかし、中新世の終わり(約500万年前)以降は化石記録がなく、現生種の起源についてはよくわかっていない。
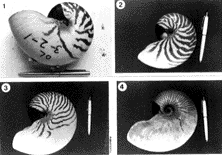 |  |
| 24-3 現生オウムガイ類。1)オウムガイ(NautiluspompiliusLinnaeus)、フィジー産。2)オオベソオウムガイ(N.macromphalusSowerby)、ニューカレドニア産。3)パラオオウムガイ(N.belauensisSaunders)、パラオ産。4)ヒロベソオウムガイ(N.scrobiculatus [Lightfoot])、ソロモン諸島産。写真中のボールペンの長さは約12cm。 | 24-4 オウムガイ科の諸属の系統進化図(TeichertandMatsumoto, 1987)。 |
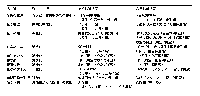 | 表1 オウムガイ類と他の頭足類との解剖学w的形質の比較。 |
殻の機能形態
オウムガイ類の殻は、多数の隔壁に仕切られた多室性の気房部とそれに続く軟体部主部を収容する住房部に分けられる(挿図1)。気房部には細い管状の連室細管(体管)が隔壁を貫いて伸びていて住房部に開口し、その中には軟体部の一部(血管、神経束、結合組織など)が収納されている。このような複雑な内部構造の殻はどのような役割(機能)を持っているのだろうか? この問題を明らかにするため、英国の生物学者デントン、ギルピン・ブラウン両博士は捕獲直後の個体を用いて、殻および軟体部の機能形態学的検討を行った (Denton and Gilpin-Brown, 1966)。その結果、オウムガイの殻の気房内部には窒素を主体とする低圧の気体と少量の液体(カメラル液)が充填されていて、そのため生体の比重は常に海水の比重 (1.03) に近い状態に保たれていることが明らかになった。さらに、後の研究者によるレントゲンを用いた成長解析から、(1) オウムガイは30〜60日の周期で新しい隔壁と部屋を作ること、(2) カメラル液は隔壁の形成に使われた外套膜外液が気室内にトラップされたものであること、(3) 新隔壁形成後、カメラル液は浸透圧によって連室細管内の上皮細胞を経由して血管へと徐々に排出されること、などが明らかにされた (Ward et al., 1981)。このような多室性の殻は、地質時代に栄えた化石オウムガイ類、アンモノイド類、ベレムノイド類などに普遍的に認められることから、進化史のごく初期から頭足類には浮力維持器官としての殻が発達していたことがわかる。
生息環境と生態
すでに述べたようにオウムガイ類は欧米から遠隔の亜深海に分布するため、長い間分布・生態・生活史などが不明であった。1970年代に入ってからようやく、日・米の研究者によって本格的なフィールド調査と室内実験が並行して行われるようになり、これらの問題が次第に明らかになってきた。
著者が参加したフィリピン、フィジー、パラオ、パプア・ニューギニアでの生態調査(Hayasaka et al., 1987ほか)によると、オウムガイ類は珊瑚礁の外側の急斜面の水深120〜650メートルの範囲の海底付近に多く生息し、現地の漁民は鶏肉や魚肉の餌を付けたトラップを用いて捕獲する。捕獲された個体の胃の内容物の調査から、オウムガイ類はエビ・カニ・多毛類・小魚などを捕食していることがわかった。また、米国の研究者による標識を付けた個体の長期にわたる成長追跡調査によると、自然環境下でのオウムガイ類の寿命は20年以上と頭足類としては例外的に長いことがわかった(Saunders, 1984)。水族館での飼育記録によると、オウムガイ類は長径4センチに達する大きな卵をサンゴ塊などに一度に1ないし2個生みつける。そして、卵は水温摂氏22度で約1年かかって孵化することが、ワイキキ水族館や鳥羽水族館で確認された。野外ではまだ産卵場所が確認されていないが、酸素同位体を用いた隔壁の形成水温の解析から、水深100メートル前後の比較的高水温の浅場で産卵・孵化し、その後すぐに低水温の深場へと移動すると考えられている (Landman et al., 1994)。
オウムガイ類の垂直分布の上限は水温によって規制されていて、摂氏25度以上(水深100〜150メートル以浅)の水塊にはほとんど生息できない(挿図5)。すでに述べたようにオウムガイ類の気室は低密度(0.6気圧以下)の窒素ガスで充填され、そのガス圧は生息深度によって大きく変化しない。そのため、約80気圧(水深810メートルに相当)の水圧を受けると殻は物理的に破壊される。オウムガイ類は連室細管内部にある神経束によって水圧を感知できるらしく、捕獲記録から推定される実際の生息深度限界(約650メートル)は、この値より小さい。いずれにしても、生息深度の上・下限は物理・化学的環境要因により厳しく規定されているといえる。テレメーターを付けた行動実験から、オウムガイ類は昼間は350〜500メートル深の深場にいて夜間に120メートル深の浅場に浮上する日周期レベルの垂直移動をしていることがわかった(Ward et al., 1984)。
 | 24-5 パラオおよびフィジー海域でのオウムガイ類の捕獲深度と生息環境(Hayasakaet.al., 1987に新しい資料を加える)。 |
集団の形態的・遺伝的変異
従来、現生オウムガイ類は比較的少数の標本の殻形態の特徴から、数多くの種が提唱されてきた。最近、サウンダー博士はこれらを再検討して、オウムガイ(Nautilus pompilius Linnaeus)、オオベソオウムガイ(N. macromphalus Sowerby)・ヒロベソオウムガイ(N. scrobiculatus [Lightfoot])・コベソオウムガイ(N. stenomphalus Sowerby)・パラオオウムガイ(N. belauensis Saunders) の5種に整理している(Saunders, 1987)。これらのうち、オウムガイは北西縁はフィリピン近海から南東縁は米国領サモアにおよぶもっとも広い地理的分布を持ち、殻側面の中心部(「臍」とよぶ)がカルスとよばれる石灰質層で閉塞されていることで特徴づけられる(挿図3および口絵参照)。本種は成体殻のサイズ・プロポーション・色帯などで大きな地理的変異を示す。ヒロベソオウムガイはパプア・ニューギニア北方のマヌス島周辺およびソロモン諸島に分布し、オウムガイと同所的に採集される。生きているときは殻の表面全体が厚い有機質の膜で被われていて、しかも螺環の断面が四角形の特異な形態を持つことで、オウムガイとは形態的に容易に識別できる。オオベソオウムガイおよびコベソオウムガイは、それぞれニューカレドニア近海およびオーストラリア北東岸(グレートバリアーリーフ)に分布し、ともにオウムガイによく似た外形の殻を持つが、殻側面の中心部が多少開口した臍があることで形態的に区別できる。パラオオウムガイはパラオ周辺にのみ分布し、表面に波目模様のある大型の殻とカラストンビの間にある歯舌の特徴などから、サウンダー博士により1981年に新種として提唱された。しかし、これらの特徴はオウムガイの集団にも認められるので、筆者ら(Tanabe et al., 1990) はオウムガイの地方集団と考えている。
それでは、オウムガイ類各「種」に認められた形態学的差異は、どの程度遺伝的変異と対応しているのだろうか? この問題を明らかにするため、鹿児島大学の増田育司・四宮明彦両博士およびカリフォルニア大学ロサンジェルス校のウッドルフ博士らのグループは各地から採集された集団標本を用いて電気泳動法によるイソ酵素の分析を行った(Masuda & Shinomiya, 1983; Woodruff et al., 1987)。その結果、多数の遺伝子座について遺伝子型が識別され、それぞれの遺伝子座ごとの対立遺伝子頻度の解析から集団内および集団間の遺伝的分化の程度を解析することに成功した。従来、「生きた化石」の形態の進化的停滞の理由を低い遺伝的変異量に求める考えがあった。しかし、分析結果はこの予想に反して、オウムガイ類集団の遺伝的変異量を表す指標である多型遺伝子座の割合や平均ヘテロザイゴシティはそれぞれ0.20〜0.22、 0.08〜0.09と他の通常の生物と同じ高いレベルあることがわかった。さらに、最近、アメリカ自然史博物館のグループ(Wary et al., 1995) が、ミトコンドリアDNAおよび核DNAを用いた分子生物学的研究を行い、集団間の系統関係を分岐分析法によって解析した(挿図6)。その結果、ソロモン諸島のヒロベソオウムガイに比較される集団は他のどの集団とも遺伝的に遠い関係にあることや、ヒロベソオウムガイ以外の集団では形態型の違いと関係なく地理的に近い集団間で遺伝的距離が高いことなどが明らかになった。この結果に基づき、彼らはオオベソオウムガイやパラオオウムガイは大きな遺伝的変異を保つ生物学的種(オウムガイ)の地方集団としてまとめられ、結局現生オウムガイ類はオウムガイとヒロベソオウムガイの2種に整理できると結論づけている。
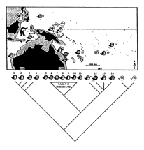 | 24-6 ミトコンドリアDNA(16SrDNA)および核DNA(28SrDNA)の塩基配列解析から推定されるオウムガイ類集団間の系統関係(分岐図)(Wray et al., 1995)。記号は集団の属する形態種のタイプを示す。P)オウムガイ、M)オオベソオウムガイ、B)パラオオウムガイ、H)コベソオウムガイ、So)ヒロベソオウムガイ。 |
あとがき
オウムガイ類にみられる高い遺伝的変異性と地方集団間での大きな遺伝的分化の割合は、ともに前述の幼生段階を欠く特殊な初期生活史や物理化学的に制約された生息環境と深い関わりがあるものと思われる。残念ながら、オウムガイ類の形態の原始性がなぜ長期間維持されたのかはまだ解明されていない。ともあれ、オウムガイ類以外の目立たない生物を含めて「生きている化石」にはまだ解明されていない多くの謎が残されている。その研究は、生物の進化と地球環境との歴史的相互作用を考察する上で基本的な資料をもたらすと考えられる。それはまた、とりもなおさず人間が周囲の自然環境といかに調和して生きていくべきかという問題にも結び付くものと考えられる。
(棚部一成)
参考文献
Denton, E.G. and Gilipin-Brown, J.B., 1966, On the buoyancy of the pearly Nautilus. Jour. Marine Biol. Assoc. U.K., Vol.46, pp.723-759.
Hayasaka, S., Oki, K., Tanabe, K., Saisho, T. and Shinomiya, A., 1987, On the habitat of Nautilus pompilius in Ta on Strait (Philippines) and Fiji Islands. In Saunders, W.B. and Landman, N.H. (eds.) Nautilus, pp.179-200. Plenum, NewYork.
on Strait (Philippines) and Fiji Islands. In Saunders, W.B. and Landman, N.H. (eds.) Nautilus, pp.179-200. Plenum, NewYork.
Landman, N.H., Cochran, J.K., Rye, D.M., Tanabe, K. and Arnold, J.M., 1994, Early life history of Nautilus: evidence from isotopic analyses of aquarium-reared specimens. Paleobiology, Vol.20, pp.40-51.
Masuda, Y. and Shinomiya, A., 1983, Genetic variation in Nautilus pompilius. Kagoshima Univ. Res. Center for S. Pacific, Occas. Pap., No.1, pp.22-25.
Saunders, W.B., 1984, Nautilus belauesnsis growth and longivity: Evidence from marked and recaptured animals. Science, Vol.224, pp.990-992.
Saunders, W.B., 1987, The species of Nautilus. In Saunders, W.B. and Landman, N.H. (eds.) Nautilus, pp.35-52. Plenum, NewYork.
Tanabe, K., Tsukahara, J. and Hayasaka, S., 1990, Comparative morphology of living Nautilus (Cephalopoda) from the Philippines, Fiji and Palau. Malacologia, Vol.31, pp.297-312.
Teichert, C. and Matsumoto, T., 1987, The ancestry of the Genus Nautilus. In Saunders, W.B. and Landman, N.H. (eds.) Nautilus, pp.25-32. Plenum, NewYork.
Ward, P.D., Greenwald, L. and Magnier, Y., 1981, The chamber formation cycle in Nautilus macromphalus. Paleobiology, Vol.7, pp.481-493.
Ward, P.D., Carlson, B., Weekley, M. and Brumbaugh, B., 1984, Remote telemetry of daily vertical and horizontal movement by Nautilus in Palau. Nature (London), Vol.309, pp.248-250.
Woodruff, D.S., Carpenter, M.P., Saunders, W.B. and Ward, P.D., 1987, genetic variation and phylogeny in Nautilus. In Saunders, W.B. and Landman, N.H. (eds.) Nautilus, pp.65-83. Plenum, NewYork.
Wray, C.G., Landman, N.H., Saunders, W.B. and Bonacum, J., 1995, Genetic divergence and geographic diver sification in Nautilus. Paleobiology, Vol.21 (inpress).
Copyright 1996 the University Museum, the University of Tokyo
web-master@um.u-tokyo.ac.jp