








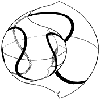









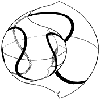
 |  |
| -25Kbyte image- | -32Kbyte image- |
昆虫標本を作ろうとする者が身をもって知らされることは、昆虫の標本が湿気と害虫とカビに極端に弱いということである。中でも虫による食害は、丁寧に保管しておいたつもりでもやられてしまうことが多い。私なども少年時代に何度も大切な標本を台無しにされて泣かされた口だから、何十年か前、学生時代に初めてこの標本を見せられたときに一番びっくりしたのは、1世紀半を経過してなお良好な保存状態を保っていたことだった。今もってこれは奇跡的としか思えないのである。
一般に、昆虫標本の保存条件は、乾燥、密封、遮光に気を配ったうえに防虫剤を絶やさず、振動や衝撃を避けることである。石寿の標本は独自の方法によってこれらの条件を極めて巧みに達成している(防虫剤については不明)のに感嘆させられる。
 | (右)外箱表書き (中)外箱中書き (左)内箱表書き |
綿にのせた1〜数匹の昆虫などに饅頭型の透明ガラス容器をかぶせ、下面を丈夫な厚手和紙を糊付けして密封してある。ガラス容器には大小2種類あって、大型は径8×10センチの略楕円形で6個、小型は径6センチの円形で87個(欠失が3個)ある。これらは桐製で中仕切りのある浅箱に大型は6個、小型は15個ずつ並べられ、重箱式に計7段が重ねられて、やはり桐製で蓋付きの木箱にすっぽり収められている。
標本に用いられたガラスの質は今からみれば決して良いものではないが、当時としては最新の素材を選び、形についても種々検討の末に加工させた苦心の作だったに違いない。死後も、はかない虫の姿を何とかして永く留め、しかも容易に観賞できるようにしたいという、虫への強い愛着と願望とが感じられる。とはいえ、石寿もこの標本がまさか1世紀半以上も良好に保存されるとは思ってもみなかったにちがいない。
当時すでにヨーロッパでは昆虫を針で刺して標本箱に保存する方法が確立されていたという。石寿の活躍したころはシーボルトが来日してかなりの年月が経過していたから、ヨーロッパの手法を知る機会が全くなかったわけではないと思われる。その間の事情は不明であるが、石寿の標本はヨーロッパの影響を全く受けていない独創的なものである。
(2)昆虫などの種類
標本の種の詳しい調査がセミ博士として名高い故加藤正世氏によってなされている。それによると昆虫の種類はじつに多くの分類群にわたって集められていることがわかる。最も多いのは甲虫目(コガネムシ類、ゴミムシ類、ハンミョウ類、ハムシ類など)で、次いで鱗翅目(チョウ類、ガ類)と直翅目(バッタ類、コオロギ類、スズムシ、マツムシ、ケラなど)が多く、その他では半翅目(セミ類、カメムシ類、タガメなど)、トンボ目、膜翅目(ハチ類)など、計9目にわたり約70種である。これらをみて感じることは、決して大型で美麗な昆虫や珍種を集めたものではないということである。チョウ、コガネムシ、トンボなどは目に触れやすい種が多いし、また目立たない小型で、地味なものも多い。カイコ、ヤママユのような産業上有益な種や、イラガ、ウリハムシ、ウシアブのような害虫として名高い種も含まれている。しかし、大半は益虫でも害虫でもない「普通の」虫である。この辺りに後にのべる石寿の博物学に対する姿勢が見て取れるように思う。
「昆虫など」と書いたのは、昆虫類のほかに、クモ類、多足類(ゲジ)、甲殻類(カニ、フナムシ、など)、軟体類(カタツムリ、ナメクジ(模型!))、環形動物(ミミズ)などの無脊椎動物と魚類(タツノオトシゴ)、爬虫類(トカゲ、ヤモリ)から哺乳類(コウモリ)など脊椎動物の一部や昆虫寄生菌である「冬虫夏草」類までが含まれているためである。「虫」が小動物全般を指していた当時の状況を考えればむしろ自然なのであろう。
(田付貞洋)
本学名誉教授、松本義明博士からは文献に関することなど種々の貴重な助言をいただいた。ここに厚くお礼申しあげる。