








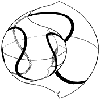









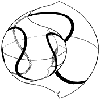

Canis lupus hodophylax Temminck
脊椎動物門哺乳類綱食肉目イヌ科
岩手県
1881年購入
農学部森林動物学教室
混乱の第2はオオカミを誤ってヤマイヌと呼ぶことがあるために生じたものである。これはまさに呼び名の違いであって、同じ動物に対する別称、つまりサメとフカのような関係にある。オオカミは「大神」、すなわち大いなる神様という意味である。日本では犬という言葉はしばしば侮蔑的な意味を含み、例えば「犬死」、「夫婦喧嘩は犬も食わない」、「官憲の犬」などの表現があるし、ピリッと辛いタデに似ているのにその味のしないものには「イヌタデ」と名付けられていることを考えると、犬にそっくりなこの獣に「大神」という、畏敬の極みと呼べるような名前がついているのは不釣り合いな気がする。
ちなみに「ヤマイヌ」にはさらに複雑な問題がある、あるいは、あった。それはわが国の動植物に関する知識が中国の本草学の影響を受けていたことに関係する。中国大陸には豺(さい)というオオカミに似た、しかし体ははるかに小さい獣がいる(大陸のオオカミは体重が30キログラム以上あるが豺は10キログラムほど)(註2)。日本の本草学研究者は豺が日本にもいるに違いないと考え、これを「ヤマイヌ」としたらしい。これは実体のない、ゴースト・ネームであった。それにもかかわらず、書物によってはもっともらしくオオカミとの区別法まで書いてあるという。いもしない動物の区別法を書くなどというのは過去の愚かな話のように思えるが、先進国の文献を鵜呑みにして実際の自然を自分の目でしっかり見ない研究者が今の日本にいないだろうかと考えると笑ってばかりはいられない。
オオカミの呼称としては東北地方の「オイヌ」がある。これはおそらく「御犬」であり、普通の犬ではないという敬意を含むものであったと思われる。字としては狼があてられ、例えば狼久保(おいぬくぼ)(岩手県滝沢村)、狼河原(おいぬがわら)(宮城県登米郡東和町)などの地名に残っている。東北地方は自然が豊かに残っていたからオオカミが広範に生息していたものと考えられる。ことに北上山地は馬(南部駒)の山地であったため、オオカミは農作物を荒らすシカを懲らしめてくれるありがたい、しかし恐るべき動物であると同時に、馬を襲う憎むべき害獣でもあった。北上山地の森林は早くから開発されたが、その主な目的はオオカミを駆除しやすくするためであったといわれている。
オオカミは北半球の北部に広く分布し、ことに北緯50度から60度に多いが、一部ではインドやメキシコなどかなり南にも及んでいる(挿図2、Fox, 1970)。というよりも本来は北緯20度以北に広く分布していたものが、人間による迫害によって現在の範囲に追いやられているというのが事実である (Fuller, 1995)。
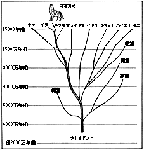 | 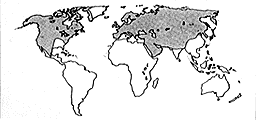 |
| 32-1 オオカミの進化(Mech, 1970) | 32-2 オオカミの分布(Fox, 1975) |
肩高は雄で80センチほど、雌で70センチほどあり、体重は雄で40キログラム、雌で30キログラムあるいはそれ以上になる。この大きさを犬と比較すると、シェパードやグレートデンよりもさらに大きく、人間にとって恐れるに十分な大きさの獣である。これまでの記録としては1902年にアメリカ北ダコタ州で捕獲された雄の79キログラム、1973年にアラスカ州で捕獲された雄の89キログラムなどがあり、大きいものはクマほどもあることがわかる。
ニホンオオカミ (Canis lupus hodophylax) は大陸のオオカミよりははるかに小さく、 肩高が50センチから60センチほどで、中型の日本犬ほどの大きさであった(ただし展示標本の肩高は約46センチ、ライデン博物館の標本は43センチ、平岩1992)。北海道にはエゾオオカミ (Canis lupus hattai) というニホンオオカミよりはひとまわりほど大きい亜種がいたが、これは大陸のオオカミと同じ亜種とされている。
オオカミは大きい上に走る能力にすぐれ、短距離なら100メートルを8秒で走れる上に、長距離をも得意とし、マラソン以上の距離を続けて走ることができる。中には250キロメートルを走り続けたという記録もある(ベルナール1991)。しかも聴覚、嗅覚、さらに知力にすぐれ、リーダーのもとに組織的な狩りを行う。
現在では世界のオオカミの研究が進み、変異の幅が大きいことがわかって、オオカミは一種であるとする見解が主流であるが、異論もある(今泉1965、1970a、b)。ニホンオオカミについても残された標本の数が少なく、しかも状態が良くないため見解の一致にいたっていない。しかし最近の生物学技術の発達により、少量の体毛からでもDNAを取り出して比較ができるようになったから、将来、現存する世界のオオカミとの系統関係の検討ができる日が来るかもしれない。
ニホンオオカミの剥製標本は国内に3体しか残っていないとされる。すなわち、(1) 国立科学博物館の一体、(2) 和歌山大学の一体、そして(3) 今回展示されている東京大学の本標本である。本標本は1881年に東京大学が岩手県の業者から購入したもので、農学部森林動物学教室で保管されていた。ただ、岩手県産であるという以上の情報がなく、詳細は不明である。3体の標本は残念なことにいずれも剥製の技術が稚拙で、生きたオオカミのもつ凛々しさや力強さは全く表現されていない。国外では大英博物館とライデン博物館にそれぞれ一体の剥製標本があることが知られている。なおエゾオオカミの剥製標本は北海道大学に2体がある。
剥製標本に較べると頭骨はかなり多いようで、お守りとして個人的に所蔵されたものが国内に散在しているらしい(今泉1969)。今泉(1969)はニホンオオカミとイヌの頭骨を比較して次の点で違うとした。(1) オオカミの方が列肉歯(上顎では第4前臼歯、下顎では第一臼歯)が相対的に大きい、(2) 頬弓(きょうきゅう)の最高点がオオカミでは鱗骨(りんこつ)だが、イヌでは頬骨(きょうこつ)である、(3) 側頭窩下部にオオカミは6個の孔があるが、イヌは5個、(4) 顔面のプロフィルがオオカミは直線的だが、イヌは中くぼみになる、など(挿図3、今泉1969)。頭骨による計測は剥製よりもはるかに精密な解析が可能であり、近年その解析法も著しく進歩しているので、これらが散逸しないうちに適切な保管がなされ研究されることを期待したい。
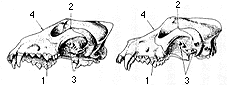 | 32-3 ニホンオオカミとイヌ(グレートデン)の頭骨。1)上顎の裂肉歯はオオカミの方が相対的に大きい。2)頬弓の最高点はオオカミでは鱗骨だが、イヌでは頬骨。3)側頭窩下部の孔がオオカミでは6個、イヌでは5個。4)顔面部がオオカミは直線的だが、イヌは中くぼみ(今泉、1969より)。 |
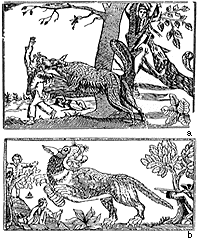 | 32-4 a)子供を襲うオオカミ、19世紀。b)巨大でグロテスクにデフォルメされたオオカミ、18世紀(ベルナール、1991)。 |
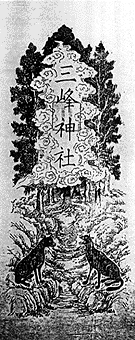 | 32-5 三峯神社所蔵の神狼図(平岩、1994) |
ところが江戸時代に事態が一変する。1732年に狂犬病が流行して、オオカミが人を襲い、しかも襲われた人が狂ったように苦しんで死んでいったので、オオカミはにわかに忌まわしい動物となってしまった。平岩 (1992) は、オオカミは集団生活をするので伝染病が流行すると個体群全体が壊滅するため減少に拍車がかかったと考えている。
そして明治時代になって徹底的な撲滅作戦がくり広げられた結果、1905(明治38)年には絶滅してしまったとされる。1904年、ロンドン動物学会と大英博物館による東アジア動物探検隊の一員として来日したイギリス人アンダーソン (Anderson, M.P. 1878-1919) は1905年に奈良県吉野郡で調査をしていた時、猟師が持ってきたオオカミの死体を買い取った。これは若い雄で毛皮と頭骨標本は大英博物館に保管されている。
記録の上ではこれが最後のニホンオオカミということになっているが、いわば物的証拠がこれであるということで、実際にはこれよりもかなりあとまで生き残っていたと思われる。奈良の奥地は関西においては山深い場所であったとはいえ、近畿地方はなんと言っても古くから開けた地方である。それに較べれば中部地方の深山や東北地方では真の自然がごく最近まで残されていた。ことに東北地方では大正時代あるいはさらに最近まで生き延びていた可能性がある。現在のように最新の情報が津々浦々まで一瞬に届くようになったのはつい最近のことであり、当時の僻地ではたいていの人はオオカミがいなくなったという情報そのものを知らなかったはずである。したがってオオカミを見ても報告したり記録したりすることもなかったであろう。
エゾオオカミは北海道開拓の中で徹底的な撲滅作戦が展開された。賞金がかけられ、またストリキニーネによる毒殺が行われたので効果はてきめんであった。捕獲され賞金を払われたエゾオオカミは合計1539頭であったと記録されている。エゾオオカミはこの作戦によって急激に減少し、1889年には絶滅してしまった。現在でも自然の残されている北海道においてニホンオオカミよりも早くエゾオオカミが絶滅したというのは意外なことだが、それだけ撲滅作戦が徹底し、効果的だったということなのだろう。
日本におけるそれまでのオオカミ信仰を考えると、この手のひらを返すような迫害は不思議な気もするが、それには日本人の自然観の変化もあずかっていると思われる。明治時代は日本人の価値観を激しく覆した時代でもあった。富国強兵という大目的のために、政治から日常生活にいたるまで徹底的な変化が求められた。民話では立身出世や親孝行が強調され、また外国の童話が紹介された。「赤ずきんちゃん」などはその代表的なもので、この中ではオオカミは欲張りで嘘つきな悪者とされる(挿図6)。「3匹の子豚」でもオオカミは飢えた狡猾な動物で、悪い大人を象徴している。こうして「男はみんなオオカミよ」といった使われ方が定着していった。この、江戸時代の「大いなる神」から現代の「いやらしい大人」への極端な失墜を考えると、明治以降の日本におけるオオカミに対する見方の変化は幼児に対する教育がいかに大きな効果を持つかを知る上で注目に値する。
 | 32-6 赤ずきんちゃんとオオカミ、19世紀(ベルナール、1991)。 |
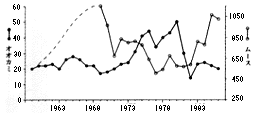 | 32-7 ミシガン州アイル鴻Cヤル島におけるオオカミとムースの頭数変化(Petersonet.al., 1988)。 |
オオカミと草食獣の関係についての研究は重要な事実を明らかにした。北アメリカでの研究によると、オオカミ1頭が1年間に必要とする肉の猟はムースで5頭から8頭、シカで15頭から18頭と言われている (Keith, 1983)。そしてこれら食料となる草食獣の多いところほどオオカミが多く(挿図8、Fuller1995)、またそのような場所では捕獲効率がよくなるためオオカミの行動圏は狭くなる(挿図9、Fuller1995)。アラスカにおける電波発信器による追跡研究によると、夏から秋にかけてムースが標高の高いところへ移動するのと同調するようにオオカミも高いところへ移動したことから、この上昇はムースを狙っての移動と考えられている(挿図10、Ballard et al.,1987)。オオカミはむやみに獲物を襲うのではなく、狙われるのは幼獣か老齢個体であり、壮齢個体が攻撃されることは少ない。例えばアメリカ、ミネソタ州のオジロジカの場合、ハンターによる射殺個体群はほぼ年齢構成を反映してピラミッド型を示すが、オオカミに捕殺された集団の年齢は仔ジカと高齢個体に多かった(挿図11、FrittsandMech1981)。またアラスカのケナイ半島とミシガン州のアイル・ロイヤル島のムースの場合もオオカミに捕殺された集団はゼロ歳と高齢個体にかたよっていた(挿図12、Ballard et al.,1987)。同様の事実はアラスカのドールシープという野生ヒツジでも知られている(ムーリー1975)。またアラスカのケナイ半島のムースの場合、オオカミの攻撃を受けた個体の蓄積脂肪を調べたところ脂肪量が少なかったことから、オオカミに攻撃されるのは栄養状態の悪い個体であることが判った(挿図13、Ballard et al.,1987)。
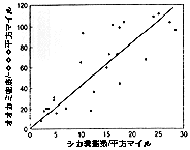 | 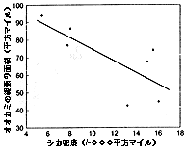 |
| 32-8 北アメリカでのシカの量とオオカミの密度の関係(Fuller, 1989)。 | 32-9 北アメリカでのシカ密度とオオカミの縄張り面積の関係(Fuller, 1989 )。 |
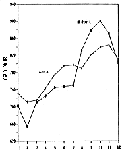 |  |
| 32-10 アラスカのムースとオオカミの季節に伴う標高移動(Ballard et al., 1987)。 | 32-11 ミネソタ州でオオカミに捕殺されたオジロジカ(上)とハンターに狩猟されたオジロジカ(下)の年齢別頭数(Fritts and Mech, 1981)。 |
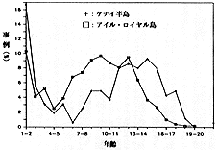 |  |
| 32-12 アラスカ、ケナイ半島とミシガン州アイル鴻Cヤル島におけるオオカミに捕殺されたムースの年齢別頭数(Ballard et al., 1987)。 | 32-13 アラスカ、ケナイ半島における死亡ムースの骨髄脂肪量と原因別死亡頭数の関係(Ballard et al., 1987)。 |
このような研究の発展により、かつて、血に飢えた残酷な獣とみなされていたオオカミは、実は老齢個体や病弱な個体を襲うことにより、個体群をむしろ健康な状態に保つというプラスの役割を持つ可能性もあるという見方が有力になっている。欧米人が未開と考えていたモンゴルやイヌイットの文化に「オオカミはヒツジの医者だ」という言葉があるのは皮肉なことである。彼らの方が自然を正しく見ていたのである。
日本列島は小さいながら極めて多様な自然に恵まれており、哺乳類相は単純とはいえ、シカ、カモシカ、クマ、キツネ、タヌキなどの中大型の哺乳類もいる。しかしクマやキツネはシカやカモシカの有力な捕食者にはなりえず、食物連鎖の頂点にいたオオカミを失ったことの意味は大きい。この意味で、私たちは、オオカミを欠いた現在の日本列島の生態系はバランスを欠いたものになりがちなのだということを心にとめておく必要がある(高槻1992)。ニホンオオカミの研究は残された数少ない標本による分類学、形態学の研究と同時に、生態系の中における捕食者の役割という視点での研究が必要であり、自然保護運動においてもそのような自然の捉え方が必要な時期に来ている(丸山1994a、b)。
(高槻成紀)
本解説を書く機会を与えられた東京大学総合資料館の大場秀章助教授に感謝します。また、オオカミについて多くの貴重な知見をご教示頂いた東京農工大学の丸山直樹助教授、東京大学保管の剥製標本についてご教示頂いた東京大学農学部林学科森林動物学講座の古田公人教授、同学部獣医学科獣医解剖学講座の林良博教授に深くお礼申し上げます。