








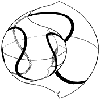









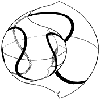

秋田県大館市花岡町、同和鉱業株式会社花岡鉱山、堤沢鉱床露天採掘場東壁産黒鉱質チムニー輪切り標本
堀越叡
1960年1月採集
総合研究資料館、岩石z床部門
このような考えを確かめるために、潜水艇を使って深海に潜り、海嶺や海溝を実際に観察しようという試みも、近年各国の研究者によって盛んに行われている。多くの観察事実が報告されているが、その中でもひときわ注目を集めたのが、中央海嶺における熱水噴出という現象である。海嶺では高温のマグマが絶えず地下から供給されており、玄武岩の割れ目に沿って深くまで浸入した海水はその熱によって温められて様々な成分を玄武岩から抽出する。このように地下にあって温度数百度にまで達する水を熱水とよんでいるが、温められて膨張した熱水は比重が軽くなるので一転して上昇を開始する。このようにして海嶺では冷たい海水が海底の割れ目に引き込まれ、高温になってふたたび海底面へと戻ってくるという循環系が発達すると考えられる。このような熱水の海底面での噴出が、海嶺のいたるところで観察されることが判ったのである。
この熱水噴出を最初に観察したのはアメリカの有人潜水艇アルビン号に乗り込んだ研究者である。1979年、太平洋の海底を生産している長大な海嶺の一部であるメキシコ、マサトラン沖の北緯21度西経109度付近、水深2650メートルの地点への潜水で、異様な光景が目撃されたのである。もうもうと黒煙を吹き上げるかのように熱水を噴出する煙突状のものが何本かまとまって海底の小山の上に突き出し、その脇には長さ3メートルにも達する巨大なパイプ状の生物の束が揺れ動いていたのである(挿図1)。調査の結果によれば黒煙を吹き出している煙突のようにみえるのは、350度にも達する高温の熱水が海底下から噴出しているもので、冷たい海水で急冷されるために熱水中に溶けていた重金属が硫化物などとして沈殿し、これが煙突状の構造物を作っている。また析出する硫化物などの一部は極めて細粒で、これが懸濁しているためにあたかも黒煙を出しているかのようにみえる。この煙突状の部分はチムニー、噴き出す熱水はブラック・スモーカーと名付けられた。チムニーを乗せている小山は、降り積もった硫化物や活動をやめて崩れたチムニーのかけらなどからなっている。熱水中に含まれる硫化水素を酸化する化学合成バクテリアが活動し、これを底辺とする食物連鎖により特殊な生物群集が発達していることも判った。
 | 2-1 アルビン号により目撃された光景を概念化した図。玄武岩質マグマが海底面上に流れてつくった枕状溶岩の上に、高温の熱水噴出によりブラックXモーカーとよばれる煙突ができている。パイプ状の生物や二枚貝窒Iもみられる(日本語版『サイエンス』1981年5月号より)。 |
さてこのような熱水活動の産物である硫化物を主体とする小山が地層として保存されると、どのような形で現れることになるだろうか。じつは過去の時代の硫化物の小山に相当するものが天然には存在するのである。玄武岩や流紋岩などの火山岩類に伴う塊状硫化物鉱床とよばれるものがそれである。ちなみに別子銅山の鉱床(図録番号1参照)もこの仲間である。このタイプの鉱床からは銅・亜鉛・鉛・金・銀を初めとする多様な金属が採掘されており、我々人類は非常な恩恵を被っているのであるが、その生成機構は周辺の地質状況から推定しているにすぎなかった。アルビン号に乗って最初にこの熱水噴出を観察したカナダ国トロント大学のスチーヴン・スコット教授が、観察結果を発表した学会講演の最後に、私が塊状硫化物鉱床の形成の現場をみた初めての人間だ、と誇らしげに胸を張ったのももっともなのである。
このタイプの鉱床の典型的なものの一つが、わが国によく発達している黒鉱鉱床である。亜鉛や鉛の硫化物に富む部分の色が黒いために、古くから黒鉱とよばれてきた。黒鉱鉱床は今から約1500万年ほど前に海底火山活動に伴って形成されたと考えられているが、玄武岩からなっている中央海嶺のような場所ではなく、日本海のような場所で流紋岩などのかなりシリカ分に富む火山岩に伴って生成している。海嶺と同様にマグマの活動があるので、それに伴って海水起源の熱水循環が流紋岩の中で起こっていたであろうことは、多くの研究者により認められている。それでは黒鉱が形成されていた時にもチムニーが林立し熱水が黒煙状に噴き上がっていたのであろうか。
本展示に出品されている黒鉱質チムニーの輪切り標本がその答えを与えている。この標本は、秋田県花岡鉱山の堤沢という黒鉱鉱床の露天採掘場の東壁から、1960年に堀越叡氏(現富山大学教授)により採取されたものである。採取時は粘土の中に横倒しになった長さ数10センチの楕円柱の鉱石で、象の足のような皺がよっていたという。特異な形状をしていたが、その当時これがどういう意味をもつものか判らず、ひとまず厚さ1センチほどの輪切り標本にして何枚かを主要大学の鉱床研究室へ送ったものである。本館では渡辺武男教授(故人、本資料館初代館長)が登録番号を付してこれを保管していた。
この標本は肉眼ではなかなか見分けがたいが、いくつかの層が重なった構造をもっている(挿図2)。まず最外殻には厚さ1ミリほどの灰白色の緻密な部分があり、細粒の重晶石(BaSO4)の結晶からなっている。この殻の内側には厚さ0〜2センチほどの黒色緻密な部分があり、重晶石・方鉛鉱(PbS)・閃亜鉛鉱(ZnS)を主としている。これより内側の部分は含まれる鉱物は同じだがいく分多孔質である。中心部へ近づくとにわかにガサガサとなり幅数10ミクロンの重晶石の結晶の集合体となる。そして中央部には1センチほどの空孔がある。この構造は現世の熱水噴出によるチムニーと酷似しており、全体の産状から判断しても、これが黒鉱鉱床形成時の海底に生成したチムニーであることは疑いない。挿図にも明らかなように、このチムニーには脇に小さなチムニーがもう1本付着して生成している。硫化物の小山で生成していたチムニーの1つが倒れて斜面を転がり落ち、引き続いて降り積もった火山灰の中に紛れ込み、この火山灰がのちに凝灰岩となり粘土化したものだろう。
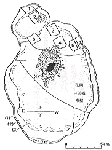 | 2-2 黒鉱質チムニー輪切り標本の裏面のスケッチ。(1)-(4)の各ゾーンは、それぞれ細粒重晶石帯、緻密重晶石剥zM亜鉛鉱帯、多孔質重晶石剥zM亜鉛鉱帯、粗粒重晶石帯に対応している。1-7の番号は切り出して検討された部分を示す。 |
現在まで日本各地で数多くの黒鉱鉱床が稼行されたが、残念ながらこれまでにこのようなチムニーと考えられる構造をもった鉱石の例はほとんど報告されていない。黒鉱の形成時にはチムニーを作るようなメカニズムが卓越しなかったのかもしれないが、見落としているということも充分に考えられる。堤沢の場合は幸いにして露天掘りであったが、暗い坑内掘りの現場ではそのつもりになって見なければ、見えるものも見えないのかもしれない。地質学には、現在は過去を解く鍵、という言葉がある。アルビン号の発見があって初めて堤沢の標本の意味も明らかになった。たとえ現在あまり意味のよく判らない標本であっても、将来重要な解釈を生み出すものもあるかもしれない。長い間埃をかぶっていた標本が、ある日突然意味をもってくることがあり得る。まして鉱床学の場合には研究対象である鉱床を、人間が破壊し消費し尽くしてしまうのだから始末が悪い。標本を大事にするゆとりもないような文化国家では情けない。本館の使命とは、一見無価値にみえる標本でも、自らの生い立ちを語る日がくるまで静かに眠らせておくことのできるゆとりにあると思うのだが。
(島崎英彦)