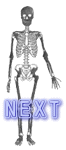「骨しかない」展示、研究博物館としての展示
東京大学総合研究博物館客員教授 洪 恒夫
多くの方々にとっての博物館は、展示をみるために訪れるところと考えられる。そのような「展示」に関わるようになって二十年が経った。2002年、総合研究博物館にミュージアム・テクノロジー寄付研究部門が設立され、それを機に客員教員として招かれ、現在に至るまで当館における6本の展覧会の企画・デザインに関わることとなった。
当館は博物館であるが故に、資料が収蔵され、研究者が所属している。また、研究博物館であるが故に、それまでも館の研究者による展示は常に行われていた。そこに、一人の展示デザイナーとして私が加わるということで何がおきるのだろうか。
総合研究博物館は、大学の施設であり、「研究」博物館である。ここで行われていることは研究である。そして展示においても、論文によらないかたち-「研究の成果を展示する」ことを行ってきた。日頃からテーマやコンセプトの見えない展示はしないという信念でやってきたつもりだが、研究博物館での展示の回を重ねるうちに、学術とデザインのコラボレーション、そして、モノ・研究の翻訳としての展示の意味、効果を考えるようになった。それによって生まれる、何か新しい効果や成果を具体化させることが、私が関わった結果であり、私が関わる理由であるように思うようになってきた。
そして、本展覧会「アフリカの骨、縄文の骨」である。学術の企画者は諏訪助教授。人類進化において、大きな発見も成し遂げている人類学者である。ディスカッションを始めた頃、「自分が展示をやるのであれば、通常実践している研究そのものを展示としてみせることだ」と何度も語られていた。これの意味は、「展示会のための展示を講じるのではなく、日常行っている研究の延長として展示も行いたい。」ということだった。そこには博物館という場において、研究することへの誇りと自信がうかがえた。
さて、研究そのものを展示にして伝えるにはどうしたらよいか。現場を再現して見せるのか。綺麗な箱を作って入れて見せるのか。翻訳としての展示と考えれば、ただそれをかたちだけで考え、処理してしまうのでは済まないことは分かっている。「結構難しい…。」わからない状態で、このプロジェクトはスタートした。
本展をご覧いただいた方はお解りだろうが、さすが人類学だけあって展示物には骨しか見当たらない。そしてそれぞれの骨にある、内容を見ていただけただろうか。これら確固たる裏づけによって、お互いの考えをかたちに進化させて作り上げたものである。目指したのは「骨のある展示」だ。
博物館は、資料を収集・保管し、展示、それに付随する事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をするところとされている。近年、「博物館=展示」の部分が話題にのぼることが多い。モノの存在感、「研究」の持つ大きな力を再確認しつつ、筆者は展示を考え続ける。