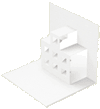
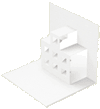
分節者の家 「奥」のない家 「奥」のない家(外壁をはずした状態) これら3つの住宅は、一つは敷地も施主もない完全に架空のものであるが、2つは具体的な施主や敷地を前提にしたが実現しなかったものである。しかし私たちはそこに区別を設ける必要はないと考える。これら3つの住宅には、空間構成によってどこまで住宅を定義することができるか、という私たちが探求を続けている概念的なプロジェクトが貫かれているからである。
住宅を空間構成によって定義するということは、単に要求された機能諸室を連結することではない。それは、空間構成という建築の物的な形式性の一つによって、現実の住宅を、あるいは住宅らしさを構成している目に見えない質を明確に分析し、再定義するということである。それは単に機能的体系の優位に対して建築の構成形式の優位を対峙させるいわゆる形式主義とは異なる。それは建築の物的な形式性の中から、まさにその住宅を定義する上で効果的な事物だけを注意深く選び出して、それらの相関を制御することである。このような相関を理解し制御すること、つまり建築の修辞は、少ない事柄でより多くを定義することを可能にするだろう。それは結果的には、単純な空間構成の原理によって住宅に要求される複雑さに対応しうる差異の網の目を建築的につくりだすことといえる。
分節者の家(1993)
あらゆる建築は、空間を分節することによって成立しているが、この分節することの初元的な力を住宅の空間で示すことを考えた。そのために、住宅の空間を構成する2つの典型的な方法—廊下を中心にそれに個室や居間を接続する構成形式と、大きな空間に風呂やキッチンや個室などの小さなヴォリームを入れ子状に包含する構成形式—を解体し、それらの特徴を併せもつ方法へと組立て直す。廊下は一般に個室をつなぐだけでなく、同時にそれぞれの室を分節しているが、廊下を外側から一つの外形を伴うヴォリュームとして眺めることはできないので、こうした働きは現実の空間において現象することはない。また入れ子状の包含によって、包含されるヴォリュームの周囲に残部のような空間が分節されるとき、動線はこの残部のような領域に対応している。しかし廊下をツリー状のヴォリュームとして規定し、これを包含するより大きな箱状のヴォリュームを設定すると、廊下のヴォリュームによって動線的に隔てられてはいるが、上部では連続する個室のような空間が分節されることになる。この構成では<包含される空間=個室、残部=動線>とい一般的な入れ子の構成における関係が、<包含される空間=動線、残部=個室>という関係に反転させられ、動線の空間を分節する働きが可視化される。包含という形式と動線による接続という形式、それぞれによる空間の相対的な定義が分離され、その関係が組み替えられているのである。このツリー状のヴォリューム内部、及び上部を歩く時、人は自らの動きが空間を分節していることに気づくだろう。
「奥」のない家(1994)
たいていの住宅には「奥」といえる場所がある。「奥」は住宅内部での人間関係や機能配列などの因習的な価値が投影されて語られやすいから、「奥」を解体することは現代の住宅の空間に対して有効な方法たりうると考えた。そのために物的な形式性のレベルにおいて「奥」を成立させる要因を分析し、それを再構成することで「奥」を解体する方法を考えた。「奥」を成立させる建築的な要因として、動線によって生じる空間の順列、室の包含関係、開口による外部との接続、インフラストラクチュアとの接続、などを挙げることができる。これら各水準で、手前/奥の対比や内/外の対比に基く相対的な室の性格が形成されている。一般に包含される室は、包含する空間より内でかつ動線的にも奥であり、外部への接続も弱い。このように「奥」は住宅の外部との関係によって相対的に定義される性格が互いに重なり合うことによって形成される。しかし、各要因による性格を明確に分離することができれば、ある要因で成立した内/外や手前/奥の対比を他の系で打ち消すことによって、全体としてはどこにも「奥」がないような住宅を作ることができるはずである。
10m角の立方体の内側に、6.8m角の立方体を入れ子状に設置し、両者をチューブでつなぐ。このチューブよって外部に直接接続された内側の立方体内部は、住人が必ず一度は入ることになるので「皆の室」と呼ばれる。壁の2m角と3m角のチューブは、2つの立方体の間に生じた空隙に設けられた階段動線の終点にあたり、個人で使用するので個室ならぬ「個窓」と呼ばれる。内側の立方体内部にはさらに水回りの直方体があり、床のチューブによって地中のインフラストラクチュアに接続される。2つの立方体の間に生じた空隙は直径200ミリの丸窓によって一様に覆われ、内側の立方体の下部と上部では1.5m、側部では9.6mの天井高を持つ。ここは一般的な住宅では壁や床の中に相当する空間であるため、「誰のものでもない室」と呼ばれる。ここから「皆の室」から「個窓」が突き出し外部に接続する構成を、外側から超越的に観察できる。
4象限の家 4象限の家(東側立面を見る) 「皆の室」は<室の包含>では内となるが<動線>ではもっとも手前になる。
「個窓」は<動線>ではもっとも奥になるが<開口>ではもっとも外に近くなる。
「誰のものでもない室」はZ<動線>では「皆の室」よりも奥になるが<室の包含>では外になる。
「水回り」は<室の包含>ではもっとも内となるが<インフラストラクチュア>ではもっとも手前になる。このように、それぞれの場所の性格が要因間で互いにバランスしあうことによって、特定のヒエラルキーのもとに「奥」が発生することが打ち消されるのである。
4象限の家(1995)
一般に、2階建ての住宅の内部空間は、壁と床によって分割されているといえるが、分割された空間どうしは互いに隔てられているので、全体の中でその空間がどのように位置づいているか認識することはできない。そこで、分割という単純な操作によって住宅の空間を定義し、しかもその操作自体が視覚化されるような構成を考えた。これは国道沿いに建つ外車ディーラーの事務所兼住宅として計画されたものである。
GLレベルを全て駐車スペースにあて、住宅はその上に持ち上げられている。建物は、準耐火建築物を満たすために鉄骨のフレームをセメント成形板で覆ったチューブと、その内部を水平・垂直の4象限に分割する3つの十字型の棚(木製、奥行300)によって構成されている。このチューブの短辺方向の断面を、床と壁による十字型が断続的に比率を変えながら4象限に分割している。チューブ状の空間のもつ明確な方向性に対して、空間を分割する3つの十字型が異なる比率を伴って重層して現われる。十字の分割による4象限が維持されることによって、その比率の違いだけが浮上し、分割された空間のプロポーションの差異と、動線のシステムによる差異の重なりが、住宅の機能諸室に対応する差異のネットワークを形成する。このことによって、分割された空間の内側としての内部空間ではなく、分割という操作自体が現象する内部空間が獲得される。
 |
 |
 |