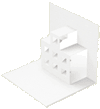
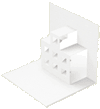
「建築はあらかじめバーチャル」
プロジェクトを前にしたとき初めにやろうとするのは、そのプロジェクトが関わってくるありとあらゆる条件をひたすら拾い集めることだ。この事だけはどんなプロジェクトでも共通している。建てようとする場所、生み出そうとしている機能、関わってくる人々、周辺の街への関わり方、利用できる技術力、建築の歴史的な背景、関係しているように思われる文化、気候、法律、風景、コストなど、あらゆる方向に開いて条件を拾い集めてくる。集められた全ての条件を部品として、部品間に矛盾の生じない仮説を立てることが、建築を構想することになるわけだ。いってみれば、物語をつくりあげる作業みたいなものだ。部品としての条件に、あらかじめ優先順位を設定することはしない。取りこぼしなく部品がそろえられたと思えたときはじめて、全ての部品を眺めながら組み立てをスタートするわけだ。大抵の場合、いくつもの物語がパラレルに進行していて、互いに他の物語の伏線となるような構造になってくる。そうして、プロジェクトの全貌がひとつの大きな物語として浮かび上がってくるのだ。物語を構想することが、ひとつの建築の全体像を構想することなのだといってもいい。この、全体像が構想された段階では、この物語のつくられ方は基本的にフィクションである。アンビルトで終わる可能性が全く無いプロジェクトであっても、こうして生み出されるものが物語である以上、フィクションであることに変わりはない。だから、設計あるいはデザインとして考えれば、アンビルトなのか実際に建てられるのかといったことに関わらず、全ての建築のプロジェクトはもともとバーチャルなわけだ。実際に建てるということは、仮説としてつくられた物語をリアルな環境の中でトレースし直すということになる。仮説の甘かった部分に絶えず修正を加えながらこのトレースは進行するわけで、建物が完成すると同時に物語も一旦フィックスして現実の中に投入されることになる。(建築のデザインの快感は、条件(部品)が上手く組み立てられていくときの達成感と、新しい物語が現実の中に組み入れられる様を見るときのスリリングさにあるといえる。アンビルトの場合は後者の快感が無くなるわけだが、その分、気楽なのだとも言える。)
みかんぐみでは、現在のところ5人のイーブンパートナーを中心とした議論でものを決めることを基本としている。5人が5人同じことを考えているわけではないし、多数決で方針決定しようというのでもない。みんなで一つのことをいろんな角度から考えてみるのだ。建築のデザインを考えるときも、みんなそれぞれが勝手なこと考えながら議論を続けるわけで、何らかの結論を導くことを目的としていないため、いくら時間があってもきりがない。極めて効率の悪い方法のようだが、これが部品を集める、あるいは物語を考える上では都合がいい。それぞれ勝手に考える分、集まる部品の数やレンジは広がるし、いくつもの物語がパラレルに進行するという構造があらかじめ作られているようなものになる。大抵の場合、5人のメンバー以外に、スタッフ、設備や構造の協力事務所、一時的に手伝ってくれる学生やフリーの人達、施主までもが、部品と物語の生産メンバーとして一緒に頭をひねることになる。だから、一つのプロジェクトに複数の価値が認識されていたとしても、何も不思議なことではないのだ。
ふれあい広場 平賀茂 鳥瞰 平賀茂 外周アーケード 平賀茂 鳥瞰(屋根無し) 平賀茂 ここで紹介する平田町タウンセンタープロジェクトは、結果としては箸にも棒にもかからなかったコンペ案である。入賞という社会的な文脈にすら組み入れられなかったという意味では、我々の数多い「アンビルトもの」の内、最もアンビルトなプロジェクトのひとつである。ここでも沢山の部品が収集され、いくつもの物語が生産された。季節毎に特徴を見せる風、確実に進行する高齢化、期待されている町の機能、地域の特性の向かうべき方向、シーズン毎に演出される雰囲気、ロケーション、メンテナンス、建物の大きさ、素材、産業、構造、イメージ・・・いくつもの物語が互いにリンクしながら大きな物語として織り上げられている。従って、全体の物語が把握されてはじめて、プロジェクトが理解されることになる。特徴を一言でいいあらわすこともできなれば、キャッチーなせりふの一つも浮かび上がってはこない。なにか特別な印象のする、いかにも建築家がつくったような建築にはならないわけだ。むしろ、互いの物語がつぶし合うことの無いように、どれか一つの物語が極端化することを避けているともいえる。こういったプロセスでつくられた建築は、なかなか判断されにくい。全体の物語を把握するのが大変なのだから当たり前のことなのだが、かといって一つ一つの物語を説明しようとすればするほど嫌がられることにもなる。ともすると、形式化に陥ったコンベンショナルな建築であるとも受け取られかねないのだ。
苦言ついでに最後に一言付け加えておこう。ちょっと見渡すと、何か特別で極端な表現を手放しに求めることが、建築となるための万能の方法であると信じているかのよう建物がたくさんある。なにをいまさらと思っていても、時代遅れのジャーナリズムの庇護の元、やりすぎものの建築は、増えることはあっても姿を消すことは無さそうだ。いつまでたっても、変なことをすれば建築っぽくなると安易に思い込んでいる人達が後を絶たないわけだ。この安易さこそが問題なのだ。これこそが最も今日的な形式化であることを認識しなければならない。とりあえずは、自分だけはそんな形式化に陥らないよう努めるしかない。
(曽我部昌史)
「縮小された世界」
私達の議論は、模型を取り囲んで行われることが多い。プロジェクトが始まって、まず最初の段階には、ボリュームスタディーのためのラフな模型をそれぞれがつくってきて机の上に並べる。残念ながら、モニター内のCGを共有して会議するというような近未来的状況には至っておらず、というよりも、複数の人間の構想を理解しミックス、研磨していくには、模型を眺めるのが一番の方法であると感じる。この初段階の議論が繰り返されるうち、かなりのバリエーションのボリューム模型が積まれていく。プロジェクトによって、また進行状況によって、つくる模型のスケールは変わってくるが、最近よくコンペのプレゼンテーションのために、87分の1のものをつくる。なぜこんな半端な縮尺なのかというと、鉄道模型用に市販されている人物や車の模型がこのスケールで、実に種類が豊富なのだ。(意外と鉄道模型にはまっていたことがある人が多いということが判明したことはさておき)それらの表情豊かな人物達を建物のに登場させると、いつのまにかガリバーの眼差しから、小人の眼差しで見るようになり、主観的に実際の空間を体感して、悦に浸ってしまう。それまで作り上げてきた物語が格段とリアリティーを増してくる。模型が完成する頃は、大抵締切り間際であるから、思い入れ充分、すっかりその気で、あとは送り出すだけという感じになる。幼い頃、リカちゃん人形やトミカやプラモデルに戯れていた私達の世代と違って、3才の頃からファミコンのなかで遊び学習もする子供達が大人になる頃には、様々なバーチャル技術が安価で提供されるだろうから、空間の体感方法も変わってくるだろう。建築家にとっての模型の重要度も変わってくるかもしれない。けれども、一方でミニ4駆や、ドールハウス、フィギャーといったフィジュカルなものが、ますます精巧さをまして、よりリアリティーのあるものを追求し、根強いブームとなっている傾向をみれば、縮小されたものの世界は、今後も永遠に人を引きつける魅力を持ち続けることを予測させる。私達が模型をつくる目的は、あくまでも実際に建てられるであろう空間の縮小模型であり、リアリティーをいかに体感するかということにある。展覧会用に、雑誌発表用にと、美しく抽象的な模型をつくらなければならない様な風潮もでてきたが、マテリアルも重力も失われたような模型を前にすると、その美しいオブジェを観賞するにとどまってしまう様な気がする。これからも私達は、模型を眺めつつ、わくわくして、心踊らせながら物語をつくって行くことであろう。
(加茂紀和子)
「ヒエラルキーの組みかえ」
いま、私が建築に期待しているのは、複雑ないくつもの条件をいかにして、切り分け、解決していくかということである。そこには、実際の物事を成立させているいくつものヒエラルキーがある。これは建築をとりまく構造や設備といったフィジカルな文脈だけでなく、その建築がもつ社会的使命や要請条件などの社会的な文脈、日本の今という文脈、あるいは近い将来建築がどう変わっていくかといったような建築全体をとりまく文脈も含まれるだろう。そういった様々な水準のヒエラルキーが現状でどうあるか判断し、それをどう組み直していくかという点において、建築が位置づけられると考えている。みんなでものを決めることを前提としているので、みかんぐみの議論はそういったヒエラルキーに対して、自動的に敏感になる。議論をした前提と後から決定されることの間の矛盾をないようチェック機構が働く。(でないとせっかくしている議論の意味がなくなってしまう。)あるヒエラルキーの連続の中で最もよい状態を見つけることもあるし、矛盾しているもの方がよいと判断される場合には、その前提条件をチェックすることだってあり得る。これはみかんぐみの建築の取り組み方の特徴の一つである。このようにして、すでにいくつかのプロジェクトが進められてきた。たとえば、NHK長野放送会館のコンペ案では、広いワンルームを取り、視聴者に開かれた会館、周辺環境への配慮といったいくつかの条件をまとめて解決策する手段として、放送センターを地下にするという案を提案した。審査の段階では、要項では地下室は禁止していないものの予想していた案の範疇におさまらないといったことで、地下案を採用するかどうかあらためて再検討されたと聞いている。その結果当選した原設計に添って、地下に大空間を持っていったことの弱点をフォローしつつ設計し、その後、工事が進み現在、空間ができあがってきているところである。現場で、実際の建物をみながら、前提条件における判断が正しかったと感じている。
さてこのコンペ案も、そういった前提条件に関する議論を重ねてできたものである。特に、これからの高齢化を迎える社会や地球環境のことを考慮しながら、建物をとりまく気候、また、室内の環境に対して積極的な提案(たとえば風向にあわせて防風林となるよう植林をしたり、いつでも花が楽しめるよう4周に季節によって違う植樹とか、オンドルのシステム等々)をしてきたが、残念ながら、完全なバーチャルアーキテクチャとなってしまった。おそらく、コンペで求められていた町民全員が集まれるような広場を作らなかったからであろう。私たちは、議論の中で、そういった広場は、あまり有効に使われないのではないかと考え、積極的に要項を違反して中間領域のような広場をたくさん作った。その方がこれからのこの町の広場として、リアリティがもてたからである。結局、コンペの前提条件を変更してしまって落選はしたが、実際には、どうすればよかったか判断するのは、当選案ができてからであろう。町民の広場がどう使われるかを見てから考えたい。
(竹内昌義)
 |
 |
 |