




















中国
河南省安陽市小屯村殷代遺址(いわゆる「殷墟」)
殷王朝第22代王・武丁期(紀元前14世紀頃)
縦21.0cm、横15.7cm
昭和61年、京都の某氏より購入。旧蔵者の入手経路は不明。
東洋文化研究所
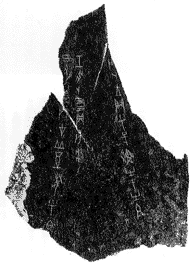
1899年以来、河南省安陽市近傍の小屯村一帯から、文字を刻した亀甲ならびに獣骨が大量に発見され、解読の結果、その刻辞は殷代後期(前14〜11世紀)に、殷王朝の卜官によって国事が占卜され、その内容と結果を記したものであることが判明した。中国考古学研究上の最大の発見とされる。今日もなお、新発見が続いており、これまでに十数万片が出土した。過去100年近くの間、多数の学者の研究により、約4千字のうち、主要な千数百字は解読され、大部分はその文意も明らかにされた。漢字のもっとも古い祖型を示すところから、漢字研究の根本資料であると同時に、中国史上、実在の確認できる最古の王朝の日常の行事についての占卜であることから、殷代史解明のための無二の史料でもあって、この大量の資料の研究上の価値は計りしれないものがある。
我国においても、その発見の初期より注目され、明治42年(1909年)に初めて舶載されて以降、多くの専門研究者が輩出した。東京大学東洋文化研究所は、日本所在の甲骨片の収蔵に努め、これまでに約2千片を収めるに至った。松丸道雄『東京大学東洋文化研究所蔵甲骨文字』図版篇(1982年)にその大部分を収録するが、本片は当書刊行後の新収品であって、拓本としては未発表である。 甲骨文は、殷の第22代武丁より末王第30代帝辛(いわゆる紂王)に至る九王の時代の所産であり、研究の成果として、これを5期に区分することが可能である。本片は、その第1期武丁期に属する最早のもので、なかでも最もスタンダードな書体である。
本片には、個別に独立した3回の占卜の内容が3行に刻されている。以下に、右行より1行ずつ簡単に解読・解説付す。
 子漁
子漁 于
于 且。
且。
 (=有)且(=祖)に
(=有)且(=祖)に (=侑)さしめんか」と)
(=侑)さしめんか」と)
 」は十二支の第1。後世の子に相当する。次の「王貞」とは王、即ち武丁自身が「貞」したことをいっているのである。殷代の骨卜においては、裏面に浅深2種の穴を製し、これを焼灼して表面にあらわれた卜兆(ひび割れ)によって、吉凶を判断した。この占いを、この場合は、王自身が担当したことを示しているのである。「子漁」は、武丁の子の名とされることが多いが、筆者は、王朝に服属した族長が、王と擬制的な父子関係を結んだもの、と考える(「殷周国家の構造」『岩波講座・世界歴史』4、1970年参照)。「
」は十二支の第1。後世の子に相当する。次の「王貞」とは王、即ち武丁自身が「貞」したことをいっているのである。殷代の骨卜においては、裏面に浅深2種の穴を製し、これを焼灼して表面にあらわれた卜兆(ひび割れ)によって、吉凶を判断した。この占いを、この場合は、王自身が担当したことを示しているのである。「子漁」は、武丁の子の名とされることが多いが、筆者は、王朝に服属した族長が、王と擬制的な父子関係を結んだもの、と考える(「殷周国家の構造」『岩波講座・世界歴史』4、1970年参照)。「 且(有祖)」は用例の多い語ではなく、必ずしも明らかではないが、合集2972、合集2973に同文例の用法があり、また、丙33、182、197の用例から判断すると、「有祖」を祭祀の対象とするのは、子某に命じて祭祀を行なわせる場合に限られているようである。このことからすれば、直系のものでなく、擬制的関係をもった者に殷の祖先神を対象とした祭祀を行なわしめる場合には、ある特定の祖先ではなく、祖先神全体を「有祖」(「有」はこの場合、「すばらしき」といった意味の美称である)として取り纒めて、合祭せしめたのか、とも考えられよう。動詞の「
且(有祖)」は用例の多い語ではなく、必ずしも明らかではないが、合集2972、合集2973に同文例の用法があり、また、丙33、182、197の用例から判断すると、「有祖」を祭祀の対象とするのは、子某に命じて祭祀を行なわせる場合に限られているようである。このことからすれば、直系のものでなく、擬制的関係をもった者に殷の祖先神を対象とした祭祀を行なわしめる場合には、ある特定の祖先ではなく、祖先神全体を「有祖」(「有」はこの場合、「すばらしき」といった意味の美称である)として取り纒めて、合祭せしめたのか、とも考えられよう。動詞の「 」は後の侑字で侑祭を行なう、の意である。
」は後の侑字で侑祭を行なう、の意である。
 白〔以下缺文〕
白〔以下缺文〕
 」は、甲骨文中に頻見の地名。所在について諸説あるが、不明とするのが正しい。「敏」は祭事の一種。「白(=伯)某」は、後の某伯に近かろう。親族称呼に起源をもつ官位のひとつで、後世の爵称の淵源である。占卜の内容は、缺文のため不明である。
」は、甲骨文中に頻見の地名。所在について諸説あるが、不明とするのが正しい。「敏」は祭事の一種。「白(=伯)某」は、後の某伯に近かろう。親族称呼に起源をもつ官位のひとつで、後世の爵称の淵源である。占卜の内容は、缺文のため不明である。当片の所見しうる部分には、裏面も含めて卜兆を行なった痕跡を缺いている。通常、牛(水牛)の肩胛骨は、縦35〜45センチほどで、1匹の牛の左右2枚の肩胛骨を組みにして占卜に用いる。当片中に卜兆や焼灼の痕跡が見られないのは、その部分が破損して残らなかったために相違ない。
(松丸道雄)


甎、陽文
中国
浙江省杭縣
三国(呉)時代、神鳳元年(西暦252年)
縦12.8cm、横9.5cm、高さ2.8cm
東洋文化研究所
 」を解説する前に、研究史をたどり問題点を整理しておこう。
」を解説する前に、研究史をたどり問題点を整理しておこう。

晋太康5年(284年)、大男楊紹買地 (
( は竹のわりふを本義とし、後に券をも意味する)が、明の万暦元年(1573年)会稽で出土し、徐渭ら文人に珍物としてもてはやされ、のち清朝金石学者銭大
は竹のわりふを本義とし、後に券をも意味する)が、明の万暦元年(1573年)会稽で出土し、徐渭ら文人に珍物としてもてはやされ、のち清朝金石学者銭大 らの攷証を経てその墓地買得証書としての性格が闡明されたのが、旧中国におけるほとんど唯一の墓券研究であった。ところが清末から民国時代にかけ、出土品の増加と金石学の進歩につれて墓券も注目の対象となり、端方(1861〜1911年)の豊富な蒐蔵をほぼ網羅著録した『
らの攷証を経てその墓地買得証書としての性格が闡明されたのが、旧中国におけるほとんど唯一の墓券研究であった。ところが清末から民国時代にかけ、出土品の増加と金石学の進歩につれて墓券も注目の対象となり、端方(1861〜1911年)の豊富な蒐蔵をほぼ網羅著録した『 斎蔵石記』(1909年10月序)には数点の収載をみ、後漢・北魏・唐・明の買墓券の実体がひろく学者に知られた。中国石刻研究の記念碑的著作と目される葉昌熾『語石』(1901年序、09年又記)には買地
斎蔵石記』(1909年10月序)には数点の収載をみ、後漢・北魏・唐・明の買墓券の実体がひろく学者に知られた。中国石刻研究の記念碑的著作と目される葉昌熾『語石』(1901年序、09年又記)には買地 (巻5)が含まれ、買墓券の概念と典型的事例がここに簡潔に示され、他方孫詒譲(1848〜1908年)の南宋地券に加えた跋には民間信仰の側面に対しても相当の注意を払っている。
(巻5)が含まれ、買墓券の概念と典型的事例がここに簡潔に示され、他方孫詒譲(1848〜1908年)の南宋地券に加えた跋には民間信仰の側面に対しても相当の注意を払っている。
以上の背景をふまえ、墓券の理解を確立しその事例蒐集、製拓、録文刊行等に最も貢献したのが貞松老人羅振玉(1866〜1940年)であった。かれは『蒿里遺珍』(1914年9月序)に自ら所蔵する拓本の逸品を考証を付して影印したのに続いて、『地券徴存』(1918年10月序)を著わし、後漢から明に至る歴代地券18種に高麗の1点を加え精確鮮明な録文を公刊した。また墓券中金属に刻された数例を苦心模録して『貞松堂集古遺文』及び『貞松堂吉金図』に収め公刊した。今日に至るまで他の墓券に関する専書は未だ出ていないので、『地券徴存』と『貞松堂集古遺文』中の関係諸例を見ることが、今でも墓券認識の第1歩である。羅氏の鑑識と見通しの基本的正しさは、羅書中に偽物の疑いのあるものが1点も含まれていない点、および同書所収諸例を各時代の典型的なものと認めてほぼ大過ないことに明らかといえよう。かれは更に知見を拡め『蒿里遺文目録』10巻・補遺1巻(1924年5月編、26年7月序)を編し、後『続編』(1929年9月跋)を加え、碑誌以下塚墓にかかわる金石文2千数百点の目録を完成した。墓券の類はその中で1/100程を占めるにすぎぬけれども、他の諸類と区別して「地券徴存目録」(蒿里遺文四)を立てている所に、かれの地券に対する立場を認めることができる。
中華人民共和国成立以後、考古学の飛躍的発展普及を通じ、墳墓から墓券の発掘される事例は数を増し、公表され管見に入ったものだけでも後掲録文に明らかなように『地券徴存』の数倍の点数に達しており、未公表のものは更に夥しいであろうと想像される。ただ目下の所中国でもそれらを集録した書は出来ていないようである。
墓券の内容的研究は、大きく2つの流れに分けて考えるのが適当であろう。その第1は墓券の土地売買証書としての性格に着目し、法制史、社会経済史の貴重な資料としてこれを取り上げるものであり、わが国の仁井田陞先生の『唐宋法律文書の研究』第2編第1章第2節、土地売買文書(東方文化学院東京研究所、1937年)・「漢魏六朝の土地売買文書」(『東方学報東京』第8冊、1938年、同著『中国法制史研究土地法取引法』、東大出版会、1960年所収、補訂版1980年)はその代表的成果と目され、買墓券の法的性格が解明されると同時に、漢六朝の墓券原文の難解な表現もその担保文言にかかる点などがみごとに説き明かされ、羅氏らの釈読を数等進めた功績も忘れられない。中国においても土地売買の実例は土地私有制の実態を示す史料として重視され、地券の紹介・研究に朱江「四件没有発表過的地券」(『文物』1964−12)、方詩銘「从徐勝買地券論漢代“地券”的鑒別」(『文物』1973−5)「再論“地券”的鑒別」(『文物』1979−8)等の諸論考が貢献する所少なくない。
他方墓券を喪葬習俗の一環として、漢民族の葬制、死生観、死後生活信仰等をうかがう屈強の資料として注目する研究者も少なからず、「民俗資料としての墓券——上代中国人の死霊観の一面」(『フィロソフィア』5、1963)、「墓券文に見られる冥界の神とその祭祀」(『東方宗教』29、1967)、「魯迅の死生観の片影」(『東方宗教』33、34、1969年)、「中国人の土地信仰についての一考察」(『洪淳旭博士還暦記念論文集』、1977年)等一連の研究で思想・習俗を追求されている原田正己氏を日本の代表的研究者にあげることができる。中国においても考古学者の宿白・徐苹芳氏が、『白沙宋墓』(文物出版社、1957年)や「唐宋墓葬中的“明器神 ”与“墓儀”制度」(『考古』1963−2)で、北宋官撰の『地理新書』や『永楽大典』所引の『大漢原陵秘葬経』といった稀覯文献を活用し、実際の発掘諸例と綜合検討の上宋代の葬俗における墓券とその背景を闡明されたものをはじめ、臺静農「記四川江津県地契」(『大陸雑誌』1−3、1950年)、方豪「金門出土宋墓買地券考釈」(中国歴史学会史学集刊三、1971)・陳槃「於民俗与歴史的間看所謂‘
”与“墓儀”制度」(『考古』1963−2)で、北宋官撰の『地理新書』や『永楽大典』所引の『大漢原陵秘葬経』といった稀覯文献を活用し、実際の発掘諸例と綜合検討の上宋代の葬俗における墓券とその背景を闡明されたものをはじめ、臺静農「記四川江津県地契」(『大陸雑誌』1−3、1950年)、方豪「金門出土宋墓買地券考釈」(中国歴史学会史学集刊三、1971)・陳槃「於民俗与歴史的間看所謂‘ 銭’与‘買地券’」(『国際漢学会議歴史与考古組報告』、1980年)等、著名な歴史家達により様々の角度から地券は取り上げられている。また後漢の鎮墓文に対し適確な見通しを与えた呉栄曾「鎮墓文中所見到的東漢道巫関係」(『文物』1981−3)も墓券を扱う者にとり最良の手引きとなる。
銭’与‘買地券’」(『国際漢学会議歴史与考古組報告』、1980年)等、著名な歴史家達により様々の角度から地券は取り上げられている。また後漢の鎮墓文に対し適確な見通しを与えた呉栄曾「鎮墓文中所見到的東漢道巫関係」(『文物』1981−3)も墓券を扱う者にとり最良の手引きとなる。
なお買地券に関しまとまった論考として、湯浅幸孫「地券徴存考釈」(『湯浅教授退官記念中国思想史論集』、1981年)、呉天穎「漢代買地券考」(『考古学報』1982−1)、冨谷至「黄泉の国の土地売買——漢魏六朝買地券考」(『大阪大学教養部研究収録 人文社会科学』36、1987年)を参照されたい。
以上を通じ墓券が古墳考古学や葬制史、墓葬習俗の基本史料であることはいうまでもないが、更に法制史、社会経済史、民俗史、思想史等の各方面からも注目に値する貴重史料たる点が認められよう。1980年ごろまでに知られた墓券については、拙稿「中国歴代墓券略考」(『東洋文化研究所紀要』第86冊、1981年12月)に概観を試みたので、御参照願いたい。
以下に「孫鼎買冢 」について簡単に説明しておきたい。
」について簡単に説明しておきたい。
 壬申三月、破
壬申三月、破 大吉。
大吉。
 壬申三月六日、孫鼎作
壬申三月六日、孫鼎作 。
。
 壬申三月、
壬申三月、 を破し大吉。
を破し大吉。
 壬申三月六日、孫鼎
壬申三月六日、孫鼎 を作る。
を作る。
 は、後漢建寧元年(168年)正月〜8月5風里番延寿の墓5個(浙江省蕭山県出土、「循園金石文字跋尾」上收)、晋太康五年(284年)九月大男楊紹買地
は、後漢建寧元年(168年)正月〜8月5風里番延寿の墓5個(浙江省蕭山県出土、「循園金石文字跋尾」上收)、晋太康五年(284年)九月大男楊紹買地 (浙江省会稽出土、葉昌熾『語石』5・羅振玉『蒿里遺珍』等收)などが知られており、当該地方にひろく行なわれていたことが窺われる。
(浙江省会稽出土、葉昌熾『語石』5・羅振玉『蒿里遺珍』等收)などが知られており、当該地方にひろく行なわれていたことが窺われる。
「日月爲證、四時爲任」の句は楊紹 にも見え、両者は文言に類似が多い。又「有私約者當律令」の句は番延寿
にも見え、両者は文言に類似が多い。又「有私約者當律令」の句は番延寿 と合致する。
と合致する。
黄立猷、『石刻名彙』14
仁井田陞「漢魏六朝の土地売買文書」『東方学報東京』9冊、1938(仁井田陞、『中國法制史研究土地法取引法』、1960年、422頁)

青銅製
中国
後漢〜呉時代(3世紀頃)
直径12.1cm、重さ269.7g
文学部考古学研究室・列品室
同向式神獣鏡である本鏡は、各単位図像が同一方向からみるように配置されている。鈕の上下および左右に神像5体が配列され、神像間に獣形4体が置かれる。
神像については、鈕の左側の一体のみ正面を向く坐像であり、他は体を右あるいは左に向ける坐像である。いずれも二重線で表現されるV字形の衿から羽状のものが左右から上方に伸び、下半身の袂には輪郭線の内側に弧線が充填される。上段左側の神像および下段の神像は三山冠を被っている。上段の神像は弾琴の伯牙、鈕の左右の神像は東王父と西王母、下段の神像は黄帝を表現しているとされるが、細部の表現は斉一的であり、神仙の個性を際立たせようとする意図はみられない。また、上段の獣形は外側を向き、下段の獣形は内側を向いており、定型的である。
主紋様の外周には半円方形帯をもつ。半円形の内側には変形した渦紋がみられる。方格内の銘は判読できない。内区外周の斜面には外行鋸歯紋帯を配す。外区には時計回りに銘帯をめぐらせるが、いずれも本来の字形から変形しており文章としての判読は困難である。また、鏡縁の外周に「将軍□□司□□□□□」の文字が線刻されているが、線刻の時期は不明である。
なお、鏡背面の一部に、鋳上がりの不鮮明な部分や、鋳型の亀裂の痕跡が認められる。鈕孔は下(鏡背面を上にして水平に置いた場合)の平らな半円形状を呈している。
(犬木 努)

灰陶
朝鮮
忠清北道公州市
百済(6〜7世紀)
直径14.4cm
昭和2年12月5日、木村京蔵氏寄贈。
資料館建築史部門(K2879)
素弁(無子葉単弁)八弁の蓮華紋瓦当で、弁端および間弁が鋭く立ち上がるのが特徴である。中房径は3.5センチ。
(谷豊信)


灰陶
中国
漢時代(紀元前2〜紀元後2世紀)
縦45.5cm、横33.3cm
厚さ5.0〜5.7cm
大正9年11月17日、工学部建築史講座受け入れ。
資料館建築史部門(K1004)
 として紹介されたものである(関野1938、134頁第42図)。
として紹介されたものである(関野1938、134頁第42図)。 は煉瓦、画像
は煉瓦、画像 は紋様を施した煉瓦である。
は紋様を施した煉瓦である。
胎土は灰色でやや粗く、焼成は良好である。日本の須恵器に比べれば、軟質であるが、土器としては硬質の部類に属する。紋様は の広い面の片側にのみ施され、他の面は無紋である。
の広い面の片側にのみ施され、他の面は無紋である。
紋様はすべて型押しによっている。面の中央部に、図像を刻んだ2種類の横長のスタンプを縦方向に隙間なく6列押しつけ、その周囲を、平行に刻みを入れた棒状の施紋具を押しつけた紋様で満たしている。
スタンプによる図像の1つは横22.2センチ、縦6.2センチ。異なった冠を被った3名の人物が、長剣を脇に置いて座っている。左の人物は左手に笏のようなものを持って話しかけ、中央の人物はコップ形の盃を持って話に聞き入っているようである。右側の人物は話に加わらず、別の方向を向いて左手を持ち上げている。図の両端には、酒を入れた壺や、料理を盛った皿が表わされ、また人物の間には耳杯(酒の盃や肴の小皿として用いる把手付の楕円形の皿)や、尊(酒を宴席に供する筒形の容器)、杓などが表わされている。全体として宴席の様子を表わしているようであるが、中央上部には鳥が飛んでいるさまも表わされている。この紋様が上から5回繰り返されている。
この図像の下に配されたもう1つの図像は、横23.2センチ、縦4.5センチで、4つの頂きのある不定形の起伏の間に、兎・虎・猪・犬(狼か?)など8頭の動物を表わしている。
これと法量・紋様ともほとんど同じものがいくつか知られているが、出土状況が知られるものはない。近年、中国の学術雑誌で2例が紹介された。1つは伝陝西省鳳翔県出土といい(北京1976)、1つは1907年にやはり陝西省鳳翔県から出土したものという(賈麦明1986)。日本では天理参考館に同様のものが2点所蔵されている(天理1986)。いずれも出土状況は不明である。
この は、図像の表現や内容が、漢時代の画像
は、図像の表現や内容が、漢時代の画像 ・画像石、その他の器物に表わされた図像と通ずるところから、漢代に作られたとみるのが普通であろう。中国では戦国秦ないし統一秦の時期とみる見解がある(北京1976、賈麦明1987)が、論拠は示されていない。従来発表された資料による限り、これが漢代前に溯るとみるのは無理ではないかと思われる。
・画像石、その他の器物に表わされた図像と通ずるところから、漢代に作られたとみるのが普通であろう。中国では戦国秦ないし統一秦の時期とみる見解がある(北京1976、賈麦明1987)が、論拠は示されていない。従来発表された資料による限り、これが漢代前に溯るとみるのは無理ではないかと思われる。
この の図像は漢代の図像の知識から解釈を進めることが可能である。まず
の図像は漢代の図像の知識から解釈を進めることが可能である。まず 下段の図像であるが、これは漢代の青銅製あるいは陶製の博山炉(香炉)などに表わされた山岳紋と通ずるもので、漢時代人があこがれた不老不死の神や仙人の住む世界を表わしたものであろう。また漢代の図像では、死後の世界の情景にしばしば鳥を登場させており、ここに表わされた宴席の図もあるいは死後の世界での快楽を祈る意味が込められているのかもしれない。
下段の図像であるが、これは漢代の青銅製あるいは陶製の博山炉(香炉)などに表わされた山岳紋と通ずるもので、漢時代人があこがれた不老不死の神や仙人の住む世界を表わしたものであろう。また漢代の図像では、死後の世界の情景にしばしば鳥を登場させており、ここに表わされた宴席の図もあるいは死後の世界での快楽を祈る意味が込められているのかもしれない。
この画像 の本来の用途は不明であるが、漢代の画像
の本来の用途は不明であるが、漢代の画像 の通例からして、建物や墓室の床に敷かれたり、壁にはめ込まれたりしたものであろう。
の通例からして、建物や墓室の床に敷かれたり、壁にはめ込まれたりしたものであろう。
(谷豊信)
 』、天理教道友社、天理
』、天理教道友社、天理