- 総合研究博物館データベース >
- 昆虫 >
- はじめに >
- 加藤正世昆虫タイプ標本目録1
加藤正世 昆虫タイプ標本目録1
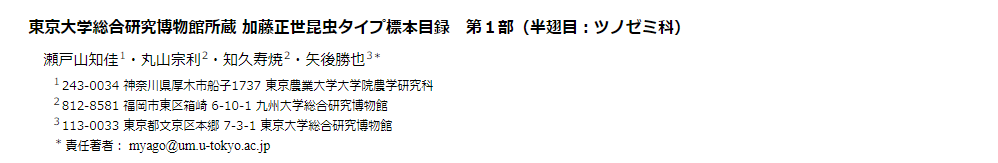
緒言
大正から昭和初期にかけて活躍した加藤正世博士(1898–1967)は、主にセミやツノゼミ類などの半翅目昆虫を専門とする在野の研究者であり、「セミ博士」の愛称で親しまれていた。1930年に『趣味の昆虫採集』を著し、重版を重ねて1945年には26版に達する名著となった。1932年には『分類原色日本昆虫図鑑』や『蝉の研究』を発表するとともに、『昆虫趣味の会』を主催し、翌1933年には専門誌『昆蟲界』を創刊するなど、日本の昆虫学において重要な役割を果たした。生涯で約700点に及ぶ昆虫関連の著作(著書、論文、報文、解説等)を出版し、その他に昆虫以外の動植物や航空機関連の著書等も加えると、計1,044点の著作を残している(矢後, 2015)。1935年には自宅に『加藤昆虫研究所』を設立し、1938年にはその敷地内に『蝉類博物館』を開館するなど、昆虫学の研究活動に加え、教育普及活動にも尽力した。このような長年のセミ類に関する生態研究および博物館等での社会教育への貢献により、1962年には藍綬褒章が授与された。加藤博士の貴重な標本や資料は、博士の没後、家族によって長年保管されていたが、2010年に東京大学総合研究博物館に寄贈されている。
本報告は、加藤博士が記載した約400点の昆虫類のうち、ツノゼミ科のホロタイプ標本をデータベース化したものである。ホロタイプ標本とは、種、亜種、または変種等を新名記載する際に、基準として唯一1個体だけ定められる、極めて重要な標本である。橋本ほか(1981)によると、加藤博士は、自身が記載した昆虫の中で、セミ科に次いで多い91点をツノゼミ科から記載した。本館に寄贈されたコレクション内からは、そのうち88点のホロタイプ標本が発見された。加藤博士が記載したツノゼミの6割は台湾産であり、これらの多くは加藤博士が1923年から1928年にかけて台湾滞在中に自ら採集したものである。今回発見されたホロタイプ標本には、破損、カビの付着、昆虫針の錆などの劣化が多少見られたが、幸いにも標本の主要部分は損なわれることなく保存されていた。台湾および日本のツノゼミ類は、依然として分類学的に解決すべき課題が多く残されている(矢後,2015)。今回発見されたホロタイプ標本が、ツノゼミ類の分類学的研究の進展に大きく寄与することを期待したい。
謝辞
加藤正世博士の五女・鈴木薗子氏ならびに女孫・鈴木真理子氏には、貴重な標本・資料等のコレクションを東京大学総合研究博物館にご寄贈頂いた。各氏に心よりお礼を申し上げる。本データベースは日本学術振興会からの研究成果公開促進費(No. JP21HP8022)により一部助成されている。
参考文献
- 橋本洽二・林 正美・大野正男,1981.復刻蝉の生物学・別冊資料篇. サイエンティスト社,東京.
- 矢後勝也(監修),2015.蟬類博物館 -昆虫黄金期を築いた天才・加藤正世博士の世界.練馬区立石神井公園ふるさと文化館,東京.
