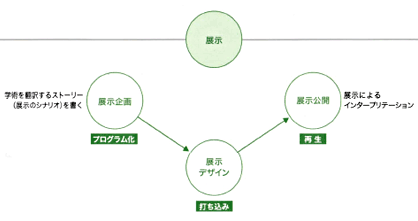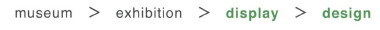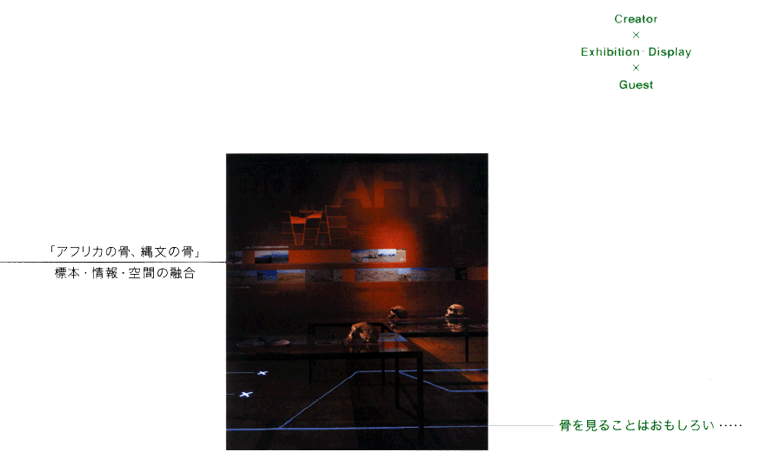いつだったか正確な日にちは忘れてしまったが、諏訪先生が人類学の展示を行うことが決まり、その企画とデザインを担当することになり、会話を続けてきた。
当初から、諏訪さんがどんな展示をやろうと考えているのか、漠然としながらも、かなり具体的な展示物、展示アイデアを語っていたことを覚えている。
ラミダスの発見。それにまつわる写真、映像、解説。自分の研究現場の様子-フィールド・ワーク。そのほか発見資料(レプリカ)の初公開。CT解析などを用いた先端的な二次的研究。
先ごろキュレーションを終え、データベース化され公開している、縄文の骨に関わる標本と内容。そこから展開されている研究。人類学の「骨をみる」観点からも楽しめるような、研究に関わる展示、等。
そして、見せ方に関してもいくつか提案があった。例えば小さいラミダスの歯を、宝石のように展示してはどうか?標本整理に不可欠な平箱を、山のように使って展示をしたらどうか。
人類の系譜をその時間、空間の広がりがわかるように展示してはどうか。研究者として、日ごろ接しているものから出るアイデアは豊富だった。その話のなかで常に言うことが、「自分が展示で紹介したいのは研究の現場であり、
通常実践している研究そのもの」ということだった。これは諏訪さんの性格だろうが、われわれに何かを提示する約束をするときには、「このときなら準備ができている」
「中途半端なものをお見せしてもしょうがない」と言われることが幾度かあった。そして、多くのものを並べ、小さいものを並べ、個々の見方、多くのものの見方を教えてくれた。
また、研究室のメンバーの標本への接し方、骨の見方、判断の仕方、これを見ているうちに次第にわかってきた。というよりも、教えられてしまった。
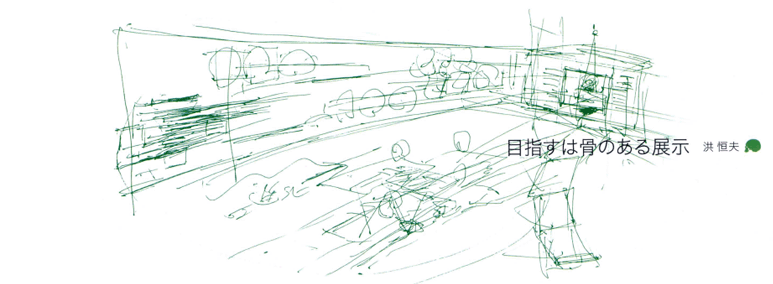
モノ、情報、空間が組み合わさり、訴えかけてくる-
展示は特異なメディアである。
ミュージアムはモノを見せる。そして、情報を伝える。いたってシンプルな要素からなる。
それが三次元の空間におかれると、可能性は無限にひろがる。
展示をつくる側、伝える側は展示に思いを吹き込む。
観覧者-受け手は、その空間に身をおく。
表現方法は無限。五感のどこに訴えてもよい。
受け手は自らの歩調で空間を進み、そして展示と対話する。
モノ、文字、画、色、光…向き合うものも様々。
この中でおもい思いの発見をし、収穫を得る。
そこには受け手の感性も介在したできごとが起こる。
その効果を最大に引き出すことに注力する。
それが展示を創造するものにとってこの上ない楽しみなのである。
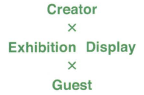
アフリカの骨、縄文の骨
おそらくこのようなことを伝えることが、「人類学の展示を実践する」「研究そのものを展示で現す」ことだろうと感じた。
フィールド・ワークの話を聞くことは面白かった。単純に、なぜあんな小さい歯を、あの大きなアフリカの大地から見つけ出すことができるのかと疑問に思い聞いてみると、やみくもに探しているわけではないこと、
研究者スコープ(見つける目)があること、それは常日頃から養い鍛えているものであり、それでもやっぱり果てしない作業であることを教えてくれた。これも研究の現場だった。
そして、その延長線上にラミダスのような大発見があるのだろうと理解した。
フィールド・ワークとキュラトリアル・ワーク。そして、骨を通して明らかにされる、人類学の研究を伝える―どうやら、これが今回の展示の目的であることがわかってきた。
学術の研究成果を展示というメディアを通して紹介(公開)する当館の展示において、まさに「研究」と「成果」を展示する展覧会。このダブルテーマをどう料理するか。
また、展示物の骨。化石人類からみる人類学の研究なのだから、当たり前といえば当たり前なのだが、骨ばかりの展示物。「僕は研究の専門家だから、デザインの方は専門家の洪さんがやりたい事を大いにやって」と、諏訪さんは言う。
ともすれば、単調に見えてしまう骨をいかに違えたかたちにするか。骨そのものをみることを楽しめるよう、どう表情をつけるか。諏訪さんの話の中からは、すでに骨の中にひそむ、とてつもない情報や内容が引き出させる予感があった。
骨の中には骨のある内容がつまっている。故に、この展覧会の企画とデザインの根本にあるものは、「骨をみることはおもしろい」を伝える―言い換えれば、骨のある展示を目指すこと。
展示は、ミュージアムの機能のひとつとして認知されているが、
そもそもミュージアムにとっての展示とは何なのであろうか?
展示は、ミュージアムと社会との接点の場であり、展示物であるモノとモノの有する情報を伝えるための舞台だ。そしてそれを実行するのが展覧会である。ミュージアムの主役であるモノに、収集・整理・保全(キュラトリアル・ワーク)がなされ、さらなる調査・研究が進められ、そこで見出された情報が展示となる。これらは全て学術研究の成果でもあるので、ミュージアムにおける展示は「学術の翻訳者」であり、「学術のメッセンジャー」とも言える。このような流れの中に展示があってこそ、意味合いや訴求力を強く持つことができるのではないだろうか?
本展「アフリカの骨、縄文の骨」は、研究を展示化するという課題に取り組んだ展覧会だ。このテーマは、展覧会ではあまり日の当たらないところである。そこにスポットを当て、そのプロセスも展示化するということは、ミュージアムの存在そのものにも踏み込むものになるのかもしれない。そして、舞台を支える舞台裏をしっかりと位置づけること。同時に、ミュージアムの活動の流れそのものに触れる。これをかたちにしていくことで、筋の通った「骨のある」展示になるのではないか。骨によってつくる骨のある展示なのだ。
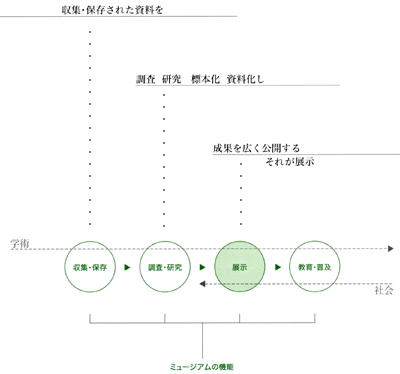
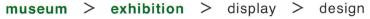
コンセプトが曖昧だと展示に力が生まれない
ミュージアムにおける展示の作業は、コンセプトメイキングから始まる。標本の持つ意味をしっかりと理解し、編集をしながら、展示のコンセプトや意味合いを確固たるものに固めていく。そして、展示空間という舞台で繰り広げられるストーリー―展示シナリオを作り上げる。
展示を表現するうえで大切なことは、明確な「展示としてのコンセプト」を存在させること、テーマ・メッセージをもたせることだ。展示は、強制力の弱い三次元空間でおこなわれるため、注意をしていないとばらばらに広がってしまう。そのうえ展示との接し方は、観覧者の興味や意識に委ねられている。そんな特異なメディアだからこそ、わかりやすく、伝わりやすいコンセプトが必要なのである。
資源の再資源化――新たな価値を生み出すこと
調査研究によってその価値が見出された個々の標本は、あるコンセプトやテーマを組合わせることによって、別の意味やメッセージを持たせることができる。これが展示における「資源の再資源化」である。ミュージアムの醍醐味は、調査・研究により生まれた資源を展示という形態に仕立て、展示としてのさらなる資源を創出させることにある。それをかたちづくるのがコンセプトメイキングだ。これは展示の特徴を作るということでもある。モノと情報の持つそれぞれの価値を展示というメディアに組み込み、展覧会の企図として伝える。これが展覧会の価値となり、ミュージアムに新たな価値を生み出すことにつながるのである。
骨という単一の資料のみで構成される本展。そこにどれだけ力強いメッセージが込められるか、どれだけ気のきいたシナリオが書けるかが展覧会の訴求力を左右する。
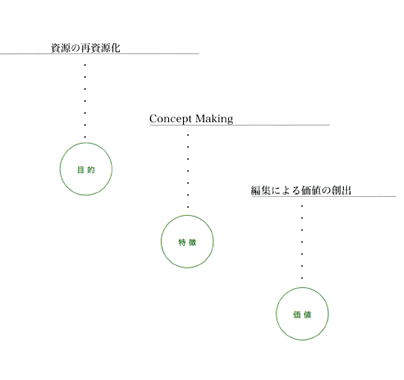
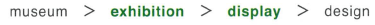
展示におけるデザインの力
展示を構成するのは標本などのモノであり、学術情報であり、デザインである。モノと情報があるだけでも最低限の展示は成立する。しかし、そこに見せようとする働きかけや工夫があれば、展示内容の訴求効果も増す。それに一役も二役も買うのがデザインだ。デザインには、伝えようとする情報・メッセージを増幅する力があるのだ。
展示はメディアのひとつである。とりわけミュージアムにおいては、コミュニケーションメディアとしての性格が強い。メディアには、提供する側と受け取る側が存在する。展示の場合、前者は展示のクリエイター、後者は観覧者である。クリエイターは、観覧者が接する展示が伝えるべき内容に、最もふさわしい手法を用い、効果的な演出を講じて実践する。だからそのデザイン一つひとつに、必ず狙いと意味があるべきなのだ。
空間メディアとしての展示デザイン
展示は、三次元の空間の中に観覧する主体(人)が移動して展開される特殊なメディアである。したがって構成を考えるときは、来観者の目線を絶えず意識する必要がある。観覧者が目にするシーンのデザイン―場面演出はもちろん、行間となる周辺の環境や観覧の際の見えがかり、移動によるシーン展開で変わる光景のひとつひとつまでも。そこにテーマ、コンセプト、世界観に気を配りながら演出をしていく。個々のデザインについては伝達効果に配慮する。さまざまな要素をミックスさせて創造できるのが展示だ。そこには、新たな効果を確かめる実験的なデザインもあって然るべきだろう。展示デザインに掟は無い。