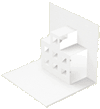
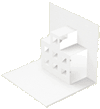
1989年〜1995年の間、浮遊する建築について考えた。浮遊という概念をダイレクトに構造や技術で表現しようとした COSMOLOGIC SPACE I、II、III(I=埼玉県平和資料館、II=文化学術研究交流施設のモニュメントを含む広場、III=岡山県操車場跡地公園に立つサッカースタジアムと公園)のシリーズ。浮遊という概念をもう少し精神的あるいはスピリチャルに捕らえた中原中也記念館や島根県立美術館のシリーズの二つの浮遊空間を考えた。COSMOLOGIC SPACE I、II、IIIはツェペリンの時代の気球や、大きなプロペラの船が少し地面を離れて行く時の、ゆっくりとした浮かぶメカニズムが感じられるような表現を目指した。そして宇宙の中を飛んでいくある種のStarshipを頭の中に描いていた。その飛行船や宇宙船は、その作られ方、飛び方、浮き方が伝わって来るような物が望ましいと考えた。またこれらの浮遊する建築はコルビジェのピロティの概念、土地から切り離して建物を持ち上げるという意味のピロティと、メカニズムとして浮遊する事や、その持ち上げ方に構造的創意工夫があり、観念的な意味を持つ私の浮遊とは異なっていると考えている。中原中也記念館、島根県立美術館においては、ダイレクトな表現や構造を避け、観念的浮遊感を、空間を作る上でのイメージとして取り扱った。ベルナール・チュミは「建築はピラミッド以来だんだん軽くなって来ている。そして20世紀にはそのスピードを加速させ、更に軽くなった。」と指摘し、Light Architectureの方向性(材料自体も軽い)を示唆している。確かに材質的にも、空間の構成もLight Architectureの方へ向かっている流れはある。しかし私は建築における軽さや浮遊感の表現は必ずしも軽い材料によるものだけではないと考えている。材料や一見軽そうな空間だけがその浮遊感の表現をしているとは思えない。軽い材料を使っても重い建物もある。それはつまりバランスによる。また物を浮かべるという事は、何を表すかということを考えれば、材料や空間の表現は様々であると考える。それらのスタディの中で、COSMOLOGIC SPACE(宇宙哲学的空間)を浮遊と考えた。CYBERSPACE(共感覚幻想空間=電脳空間)の概念を考えた。
COSMOLOGIC SPACE
建築家ブレがアイザック・ニュートンの記念碑の中で描いて見せた直径134.2mの球の中にあるSPACE=コスモスとは何であったのだろうか。何かに包み込まれた大空間というコンセプトをH・G・ウェルズもフラーも、また20世紀のSF作家も取りつかれたように表現してきた。コンピューターのICチップを拡大していくとだんだん都市の拡大写真に見えてくる。その爪の先までマイクロチップ化された空間は我々の頭脳に直接パルスを送る。サイバースペース(電脳空間)は、我々のmindの中にある共感覚幻想空間である。キューブリックの「2001年宇宙の旅」の中でボーマン船長がHALと対話した事は何だったのか。ブレートランナーが冒頭の2019年のロサンゼルスを俯瞰するシーンで描かれている光や、光の象徴機能、そしてその向こう側にある空間、それをCOSMOLOGIC SPACEと呼ぶ。それは重力に逆らう形を持ち、20世紀のテクノロジーの表現があり、終わりのないサイバースペース(共感覚幻想空間)なのだ。
COSMOLOGIC SPACE I 1989〜1990 COSMOLOGIC SPACE II 1990〜1991 COSMOLOGIC SPACE III 1994 Floating Space as Conceptual Space II
1994〜1995
観念的空間としての浮遊空間
「林の中には世にも不思議な公園があって、不気味な程にもにこやかな女や子供、男たちが散歩していて、僕には分からぬ言葉を話し、僕には分からぬ感情を表現していた。さてその空には銀色に、蜘蛛の巣が光輝いていた。」・・・中原中也は若くして死んだ詩人である。彼の精神はいつも不安定であった。彼の作品の多くに夏の暑い日、地の果てに立つ蒸気、ギラギラする太陽、影、竹林、そして空に浮かぶ雲、不気味な蜘蛛の巣(これも浮かんでいる)そして孤独な中也がいるという設定が多く見られる。彼の心の中にあった浮かぶ物とは何だったろうか。そんなことを考えてこれらの建築=空間を考えた。詩的に浮かぶということは何かと考えた。島根県立美術館の場合も、宍道湖に沈む夕日を眺められる位置にある建物を考えた時、その夕日の沈む直前の姿は、やはり浮遊というイメージとオーバーラップしていた。またその余韻を残して夜、鳥の羽ばたくように、ガラスのスロープやトップライトが折り重なって見える様は、詩的な浮遊の表現であった。また島根の伝統祭礼には鳥の舞う姿を模したものが多く、これも古来からふわりと空に浮かんで飛ぶ鳥に何らかの憧れを抱いていたのだと思った。中原中也記念館と島根県立美術館で表現した浮遊感は、一連のCOSMOLOGIC SPACEのスタディした材料、構造等によってダイレクトに表現されて浮遊感を超え、歴史的解釈や、哲学的解釈をした後のイメージを抽出した、詩的=私的浮遊感である。中でも私にとって中原中也記念館は、好きな作品であり、自分でも名作だと今でも思っている。
COSMOLOGIC SPACE I 1989年〜1990年
「埼玉県平和資料館」この平和資料館の塔は、球としての展望スペースと、斜行エレベーター、階段から成るアームの部分より成り立っている。人類は今までに色々なタワーを考えて来た。エッフェル塔等の垂直な塔、E・リシッキーのレーニンの演説台等の斜塔が思い出される。平和が極めて微妙なバランスの上に成り立つとすれば、私は垂直な塔よりむしろ斜めの塔の方が問題提起になると思った。また球を展望台の形に選んだのは、最小限の外皮によって、最大限の空間を包み込むフォルムであり、ルドゥ、ブレ等の人々によって提起されてきた宇宙や、平和や、空間のシンボルであるからである。
BODYは、それ自体でひとつの完結した状態であり、宇宙を構成している。4本のARMと4つのリングで空中に浮かび、その内部には講堂や、講座室、図書館等のミクロコスモスを内在している。この空間は建築的空間の作り方よりむしろ、スペースシャトル等と同じく、大空間をテクノロジーによって構成しようとするものである。この大空間が地上に浮遊する様やバランスは、子供たちや人々にある種の感激を与え、テクノロジーのすばらしさ、またその中に展示されている戦争の悲惨さを見ることによって、テクノロジーの正しい使い方、平和への道を考えさせるだろう。
FOOT即ちPEACE SHIPの着陸用の脚の部分には、事務室、収蔵、機械室等の空間と、エントランスホールの部分が入っている。駐車場より大キャノピーを通ってアプローチした人は、エスカレーターで2階のレベルに移動する。そこで人は前面に広がるカフェテリアや、野外展示スペース、野外劇場にもなる緑の空間を眺めることができる。図書館、講堂の階に上がると全体の展示スペースを上から見下ろせ、目の形をした空間の内部を感じることができる。エントランスホールと外部からアプローチ出来る斜行エレベーターは、人々に異質の空間体験をさせるだろう。
20世紀の戦争は、即ちテクノロジーの戦いであるとも言える。第一機械主義の人達や、未来派が描いたダイナミックでオプティミスティックな社会や、人類に夢や希望を与えてくれる機械=テクノロジーは戦争を引き起こす道具でもあった。一つの機械という概念が、平和も戦争ももたらすという歴史的事実と、人類がその使い方を誤らないようにすること等を、次の世代に伝えるために、テクノロジー自体を建築の空間や表現に取り込もうとした。
COSMOLOGIC SPACE II 1990年〜1991年
「文化学術研究交流施設のモニュメントを含む広場」
このプロジェクトは、COSMOLOGIC SPACE IIとして位置づけられる。大学の構内にあるモニュメントの設計である。この時我々は、張力抵抗を応用した偏平な逆さドームを設計した。直径33mの偏平ドームの部材構成は吊り方向である放射方向はI型ビーム、押さえ方向である円周方向は丸パイプを用い、それらによる半剛性逆さドームを考えた。この3点で支持されるドームの構造体の中に、光や雲や虹を出せる装置を組み込み、浮かぶシアターとした。シアター内より噴出させる水幕をスクリーンとして様々な映像を映し出せる。この浮かぶシアターは重力を利用した二つの曲面の内の一つを利用している。一つはアントニオ・ガウディが試みた「逆さ吊り手法」による石を用いた立体シェル構造の構成方法であり、その代表作はバルセロナに今なお建設が進んでいるサグラディファミリアである。二つ目はケーブルを用いた超大スパンの吊り橋を構成する手法であり、このモニュメントは後者の考え方によっている。
Floating Space as Conceptual Space I
1994〜1995
COSMOLOGIC SPACE III 1994年
「岡山操車場跡地公園(サッカースタジアムを含む公園の全体計画)」今までのスタジアムは回りからアイソレーションされた壁で、街や自然(風、緑)を遮断してきた。この浮遊するスタジアムの案では、根切りの土を利用して起伏に富んだ公園をつくり、その公園に彫り込まれた形で、1階スタンドをつくり、2階部分を地上から持ち上げて浮遊させるという案だ。スタジアムを浮かせることで、ランドスケープと連続して繋がり、風や緑をスタジアムの中に取り込むことができる。浮遊するスタジアムはある種の環境共生的な建物である。構造は主架構はSRC造で、スタンドはRC造で、いずれもプレキャスト工法を用いた。メインスタンド部分の片持ちの出は、3次元の面アーチで周辺部の片持ち部が小さい梁柱郡に力を効率よく分散して伝達することを考え、屋根も同じく3次元的にバランスさせる方法を考えた。
観念的空間としての浮遊空間 I 1992年
「中原中也記念館」竹林によって中也の空間を外部より切り離した。日本庭園は記念碑と記念樹を取り囲む広がりのある導入部分と、入り口からの距離をできるだけ感じさせるしつらえとした。竹林の横の徐々にせりあがる丘と石畳、駐車場を感じさせない木立。正面には軽い2本の柱の上に会議室、鏡池の上に浮かぶ中也の展示室がある内部空間では、詩の世界が持つ変化や心の動きに対応するために、シーンの変化を心掛けた。エントランスホールからは前庭や、波うつ天井の間から斜路を通して竹林が見える。動線はゆったりとした斜路とし、その途中では鏡池や緑の丘が見える。展示室の中は外壁を通して来る光を障子の様な物で受け、日々の変化は影によって感じられるようにした。
観念的空間としての浮遊空間 II 1994年〜1995年
「島根県立美術館」このプロジェクトは「浮遊」という概念をダイレクトなメカニズムで表さずに、中原中也記念館の時と同じくもう少し詩的に表現したものである。湖に並行に3つのギャラリーの大空間を設け、その間にスロープや展示室のトップライトを挟み込んだデザインになっている。その間の空間を軽いガラスによって包み込み、持ち上げることによって浮遊する空間をつくりだした。また島根県の伝統祭礼行事では、弥栄神社の鷺舞、美田八幡宮の十方拝礼、須佐神社の念仏踊り等、鳥や鳥の羽根をイメージしたものが多くあり、それらは軽く空に浮かび上がる様を模したものが多くある。それらも浮かぶということを表現している。エントランスホールを入ると、鳥の羽根が浮かび上がるように、ガラスに包まれたスロープが突出し、人々を迎え、また夜そのガラスの部分が鳥の羽ばたきのように見える様はある種の浮遊感を表現していると考えた。
 |
 |
 |