








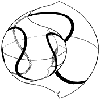









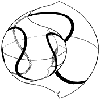

Kirengeshoma palmata Yatabe
被子植物Aジサイ科
愛媛県(伊予国)石鎚山
矢田部良吉
1888年8月9日採集
選定基準標本(レクトタイプ)
総合研究資料館、植物部門
花は五数性で、茎頂の円錐花序にまばらに着き、7〜8月に咲く。総梗は長く、三まれに1〜2花をつける。花柄は長さ約4センチで、はじめ斜上するが、果実時には下方を向く。萼筒は半球形で、径7〜13ミリあり、子房と完全に合着する。萼裂片は三角形で、長さ約2ミリくらいになる。花冠は黄色、ラッパ状で、狭卵形で長さ3〜4ミリの花弁をもつ。雄蘂は長さ3〜4ミリで、10本あり、二環に配列する。雌蘂は三まれに4室の子房をもち、同数で長さ3〜4ミリの花柱をもつ。雌蘂は熟して 果となり、中に多数の微小な種子を収める。本州(紀伊半島)、四国、九州および朝鮮と中国(東部)に分布する。
果となり、中に多数の微小な種子を収める。本州(紀伊半島)、四国、九州および朝鮮と中国(東部)に分布する。
キレンゲショウマは、2つの点で興味深い。1つは日本の植物学史、他はこの植物の系統進化の点である。
植物でいえば、それまでのヨーロッパ人の知識はヨーロッパに野生する数千種の植物に限られていた。その数は、特別な分類体系(システム)など考えなくても、独りの人間が充分に記憶し操作できる数である。そのうえ、本草学者といわれた当時の植物学者は、自己完結的な方式でそれらを記述した。未知なる植物が発見されても、それを取り込み、位置付ける一種のゆとりが彼らのシステムにはなかった。
こうした自己完結性を脱して、存在し得るすべての植物に当てはまる分類体系を思考するためには、対象が人間が記憶できぬほどの数になることに意味があった。あたかも1つのファイルやフロッピーで収容できぬ多量の情報を扱う私たちが行うように、ヒエラルキー構造をつくり、グルーピングをするよりほかに整理できないほどの、種数の存在こそが、ユニヴァーサルなシステムを生む必要条件であった。
キレンゲショウマは東京大学の植物学の初代教授、矢田部良吉により、1890(明治23)年に記載公表された。これは、日本の学術出版物に日本人学者が発表した、最初の高等植物の属であった。この前年に日本で発見された新植物の記載論文を日本人研究者が自らの手で公表すると、矢田部はわざわざ英文で宣言している。なぜ、こんな宣言が必要だったのか。それについて述べるのに先立ち、日本の植物、すなわち植物相(フロラ)の研究の歴史をかいつまんで紹介しておきたい。
カール・ペーター・ツュンベルク(CarlPeter Thunberg)は、1743年11月11日、スェーデンに生まれた。彼はウプサラ大学のリネウスのもとで医学、植物学などを学び、リネウスの最後のそして最も成功した学生のひとりとなった。ツュンベルクは、3人のオランダ人植物愛好家から、希望峰と日本の植物を研究する機会を提供された。つまり、ツュンベルクがオランダ東インド会社に医者として勤務し、日本に渡ることであった。 当時のヨーロッパからの外国旅行といえばそれは船によるものだったが、日本はヨーロッパから最も遠い国であり、しかも江戸幕府は、長崎における中国人とオランダ人を除いた、他のすべての外国人に対して国を閉ざしていた。
ツュンベルクの訪日に先だって日本の植物をかなり詳しく記述した学者がいた。それは、同じくオランダの東インド会社に医者として雇われたドイツ人のエンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer)である。彼は1690年から1692年に来日し、「廻国奇観」と親称される、Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarumの第5部(1712年)に日本植物を記述した。ただ、ケンペルはリネウス以前の学者であり、本草学に拠っていた。ケンペル以外にも日本の植物を記述した文献は若干あった。したがって、正確にはリネウスやツュンベルクにとって、日本は完全な植物学的空白地ではなかったが、植物学の発展のうえに充分に魅力ある国だった。
ツュンベルクは1775年8月に長崎に到着し、1776年10月にアムステルダムに帰着した。万難を辞さずの来日であったが、滞在中に訪ねることができたのは、長崎を中心とした九州と江戸に至る本州南部だけだった。少しでも数多くの植物を得るために、居留地、出島で飼育する家畜用に毎朝運ばれてくる飼葉を検分して、標本用に採集したと、旅行記に書いている。
ツュンベルクは、日本の植物とケープの植物を同時並行的に研究し、多数の本と論文を発表した。『フロラ・ヤポニカ』(Flora Japonica、日本植物誌、1784年刊)は、彼の最高の研究成果であり、日本の植物を集大成した最初の著作でもある。その中で812種の植物が日本に産することを報告している。その数は屋久島以北の日本に産する全種の22パーセントに当たる。
日本の温帯植物は、ツュンベルクも若干記載したが、その本格的研究は、幕府が下田(本州中部太平洋側)と函館(北海道)の港を開港した後からである。ここを足場に日本の温帯植物相を精力的に研究したのは、ハーバード大学のアーサー・グレイ(Asa Gray)とロシア科学アカデミーのマキシモヴィッチ(C. J. Maximowicz)であった。
温帯植物の研究が開始された直後、日本は明治維新を迎え、日本の植物の研究はやがて日本人研究者へと引き継がれ、ここで矢田部良吉にたどり着くわけだが、その前にツュンベルクと同様、東インド会社に医官として来日したシーボルトにふれておきたい。
しかし、ケンペルもツュンベルグも、生きた植物をヨーロッパに多数持ち帰ることができなかった。熱帯圏を通る長い航海が植物を枯死させてしまったのである。
フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(Philipp Franz vonSiebold)は日本の植物をヨーロッパの庭園に導入するという目的を合わせもち来日した。
1796年にミュンヘン近郊のヴュルツブルグの名門に生まれたシーボルトは26歳でオランダの東インド会社に勤務する外科軍医小佐になった。1823年8月11日に長崎港に着き、1829年12月30日に離日するまで、日本のあらゆる事物に関心を寄せ、集めた。
ツュンベルクよりもかなり自由に長崎に滞在し、医学上の日本人弟子を通じ植物等を手にした。滞在四年目に巡ってきた江戸参府の旅行で水谷豊文など多くの学者と出会い、貴重な資料を入手した。バタヴィア政府の指示により帰国の準備中にシーボルト事件が起こり、永久国外追放の判決を受け帰国した。彼のバタヴィア政府宛の報告によれば、生きた植物2000点と押し葉標本1万2000点、その他多数の動物標本を収集し持ち帰ったとある。
帰国後のシーボルトの半生は日本でのコレクションの研究と日本についての専門家、ロビーイストとして活躍し、1866年10月18日にミュンヘンで亡くなった。70歳であった。
シーボルトは日本の植物の研究のために標本、生きた植物、図譜、民俗資料等の文献を集めた。生きた植物はその多くを航海中に失うが、それでも2000株近い日本植物の移出に成功した。それらはボイテンゾルフの植物園で馴化され、その後オランダに送られた。いまヨーロッパの庭園に普通に見る日本の植物にはシーボルトが移入に関与したものが多い。シーボルトはミュンヘン大学の教授ヨゼフ・ゲルハルト・ツッカリーニ(Joseph Gerhard Zuccarini, 1797-1848)を共同研究者に迎え、彼らの『フロラ・ヤポニカ』(Flora Japo�nica、日本植物誌、1835〜1870年)を刊行する。
これは、上述の事実を率直に述べた後、「日本植物の研究は以後欧米植物家を煩わさずして日本の植物学者の手によって解決せん」ということを述べた一種の檄文である。
矢田部はこの宣言を踏まえて、シチョウゲ、ヒナザクラの2新種を公表し、次いで新属新種キレンゲショウマを公表した。しかし、日本人として新種を最初に公表したのは矢田部ではない。英国在学中の明治20(1887)年にトガクシショウマを記載した伊藤篤太郎である。彼はトガクシショウマをサンカクレン属の一新種とする論文をロンドンのリネアン・ソサェティ発行の学術雑誌に発表し、続いて翌年にはトガクシショウマを単型の新属とする論文をロンドンの植物学雑誌26巻に発表した。この論文を書いた伊藤篤太郎は、シーボルトの指導を受け日本にリネウスの分類体系を最初に紹介した東京大学員外教授伊藤圭介の孫である。また、日本の出版物に最初に新種発表を行ったのも矢田部ではない。これは、「矢田部宣言」の前年に当たる明治22年で、ヤマトグサを新種として発表した大久保三郎と牧野富太郎である。
このように「矢田部宣言」の後に日本人の植物学研究が開始されたわけではない。むしろ、この宣言は、東京大学における研究水準がようやく植物学といえる状態になったという自己評価であるといえる。この宣言をして後、新属として発表されたキレンゲショウマの論文には、矢田部の意気込みが読み取れる。属名は和名のキレンゲショウマをそのまま用い、日本を世界の植物学にアピールしようとする意識が感じられる。
「矢田部宣言」直後、当時助教授であった三好学もコウシンソウを新種として公表し、さらに翌明治24年には牧野富太郎がコオロギランを新属として記載した。以降、矢田部良吉、松村任三、牧野富太郎らの植物分類学者により日本からの新植物の記載が盛んに行われ、全国規模で日本の植物相の全貌がようやく判明し始めたのである。このような状況を受け、「小石川植物園草木目録」(伊藤圭介編、明治10年)、「東京大学小石川植物園草本図説」(伊藤圭介、賀来飛霞編、同14年)、「帝国大学植物標品目録」(松村任三編、同19年)、「帝国大学植物目録」(大久保三郎編、同20年)、牧野富太郎編「日本植物誌図編」(同22年)、矢田部良吉編「日本植物図解」(同24年)などの目録や図譜が相次いで発行された。 ここに挙げた文献に引用された標本のほとんどすべてが東京大学に保管され、その後に収集された標本とともに日本の植物の貴重な資料として、現在世界の植物学研究に活用されている。
矢田部はキレンゲショウマをユキノシタ科(広義)に分類し、アジサイ連のバイカウツギ属(Philadelphus)に、葉の配列、種子の特徴などから、類縁があるとした。
その後、その特異な外形から、類縁や分類学上の位置について、多くの学者が言及を加えてきた。また外国の専門誌に図示されもした(挿図2)。
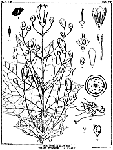 |  | |
| 15-1 矢田部良吉の論文に掲載されたキレンゲショウマの図。植物学雑誌4巻(1890年)。左下の署名はこの図を描いた、東京大学小石川植物園に雇われていた画工渡辺太郎である。 | 15-2 カーチス{タニカル}ガジンに載ったキレンゲショウマ。署名はウイリアムgレヴィティック(WilliamEdwardTrevithick)。 |
これは日本から中国中部を経てヒマラヤ東部に至る地域で、固有の科と属が地球上でここに最も多いことが注目される。
第三紀以降、地球は寒暖を周期的に繰り返した。最後の氷河期が去ったのがいまから1万年ほど前で、私たちはその後の温暖期(後氷期)に生きている。寒冷化が進むと、氷河が発達し、低緯度地方にも広がっていく。氷河の拡大と南下は植物の分布域も変化させた。より温暖な地域に移動し避難したが、ヨーロッパではアルプスに前進を阻まれ、最終間氷期に栄えた植物は最終氷期に絶滅を余儀なくされた。氷河はアジアでも発達したが、アルプスのような高山はなく、南方へ逃避し、絶滅の危機から救われたと推定される。日華区系の固有植物にはこのようにして絶滅から救われた遺存固有が多いと推測されている。
ズダヤクシュ(ユキノシタ科)では、日本とヒマラヤの個体間に生殖的隔離がなく、種子が形成される。ツバメオモト(ユリ科)では日本とヒマラヤの個体に若干の形態差があり、変種として区別される。ドクダミ、ハンゲショウ(ドクダミ科)、ゲンノショウコ(フウロソウ科)のような日本では人家周辺に生える種もある。
日華区系の全域に分布する種のほか、その東半分や西半分にのみ分布する種もある。固有で、特異な形態をもち、しかも単型的かわずか数種からなる属が多い。ヤマグルマ属、フサザクラ属、カツラ属などはいずれもそれぞれ一属で科と見なされる。キレンゲショウマ属の分布もこのパターンをとる。
キレンゲショウマのほかにアジサイ科にはソハヤキ地域に分布を限定された種が他にもある。アジサイ属ではヤハズアジサイがあり、さらに別属としては、中国浙江にも分布するバイカアマチャ、近似種が中国中部にあるギンバイソウ(関東南部に及ぶ)がそれに当たる。バイカアマチャとギンバイソウは特異でそれぞれが属として区別されている。キレンゲショウマと合わせ、日華区系およびソハヤキ地域における、こうした単型または少数種からなる属の存在は、どのように理解したらよいであろうか。この問いはまだ解かれていない。
この問いを解くため、DNA分子を用いたこれらの分類群の系統解析の結果が注目される。アメリカ合衆国のソルティスら(1995)は、キレンゲショウマがウツギ属と単系統群で、しかもそれよりは派生的という結果を発表している(挿図3)。系統の解析と並行して、形態の分化が検討されねばならない。この研究は端緒についたばかりであるが、近い将来アジサイ科の、そして日華区系、ソハヤキ地域の成立過程を解く鍵が得られる可能性が高い。それこそがキレンゲショウマの植物学的な魅力といえるであろう。
(大場秀章)
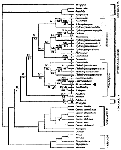 | 15-3 ソルティスら(1995年)により発表された葉緑体DNAのrbcL配列データに基づくアジサイ科の分岐図。学名の右に三角形を付したのがキレンゲショウマ属。 |