- 総合研究博物館データベース >
- 昆虫 >
- はじめに >
- 佐々木忠次郎関連コレクション14
佐々木忠次郎関連コレクション・昆虫目録14(蜻蛉目)
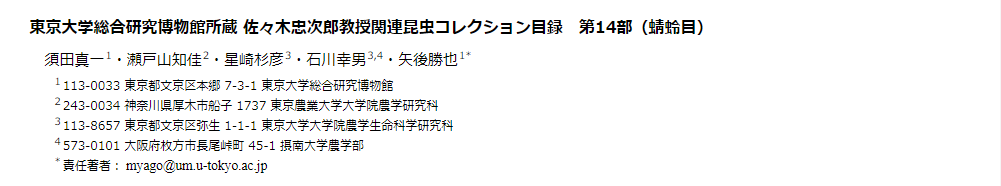
緒言
佐々木忠次郎(忠二郎)(1857〜1938年)は、明治〜昭和初期に活躍した昆虫学者で、帝国大学(のちの東京帝国大学)農科大学養蚕学初代教授の一人である。日本の近代養蚕学や農業害虫学の開祖であり、応用昆虫学の礎を築いた。国蝶オオムラサキの属名Sasakiaが献名されていることでも知られる。その経歴や業績はYago et al.(2019)に詳しい。
この佐々木忠次郎教授由来の昆虫コレクションが本学農学部から2012年に総合研究博物館へ移管されたが、その中の昆虫標本は明治〜昭和初期に採集された個体で構成されており、特に明治期のものは欧米式の針刺し標本としては国内最古級となる(Yago et al., 2019)。現在、本博物館では、収蔵されている昆虫コレクションのデータベースを作成して、出版物やウェブ上に公開発信する計画(UMDBプロジェクト)が進められている。この佐々木教授関連昆虫コレクション目録も本プロジェクトの一環として進められたもので、その第14部としてトンボ目のコレクション目録を完成するに至った。
この目録にリスト化されているトンボ目の標本群は中型ドイツ箱様の引き出し式標本箱39箱に収められており、計1,130点からなる。収集時期から大きく二期に分けられ、ひとつは佐々木忠次郎、内田清之助らにより1890〜1910年代を中心として日本や台湾、中国(清国)などから収集されたものである。内田は鳥類学者として著名であるが、学生時代は昆虫の研究に没頭しており、1932年刊行の日本昆虫図鑑の著者の一人でもある。この時代のコレクションの中で特に注目されるものとしては、旧市内周辺と推測される東京産ベッコウトンボ、オオキトンボ、サラサヤンマ、東京渋谷、赤羽産ニホンカワトンボ、東京青山産モートンイトトンボ、東京赤羽産コシボソヤンマ、北海道札幌産アオヤンマ、小笠原諸島固有種、などが挙げられる。加えて国内最古の記録と推定される千葉印旛沼産1904年採集のオオモノサシトンボも見出された。グンバイトンボは佐々木によって1882年に東京井の頭(現在の都立井の頭恩賜公園)で発見され、1899年に採集した標本を基に「グンバイトンバウ」の和名のみで報告されたのが最初となる。その際に使用された標本は含まれていなかったが、1902年から1905年にかけて採集された標本が残されている。
もうひとつは1930年代を中心としておもに石倉秀次によって収集されたものである。この時代のコレクションの中で特に注目されるものとしては、現在の東京区部および隣接する多摩地域産のグンバイトンボ、ニホンカワトンボ、モートンイトトンボ、ホンサナエ、アオサナエ、トラフトンボ、エゾトンボ、オオキトンボなどであり、東京衾(現在の目黒区八雲:目黒区, 2017)産のベッコウトンボやキイロサナエなど、文献上の記録を見出せないものも複数種含まれている。その他、千葉市川産のベッコウトンボ、コサナエ、エゾトンボ、尾瀬ヶ原のトンボなど、当時、石倉も会員であった加藤正世主宰の昆虫趣味の会会誌「昆虫界」掲載報文の根拠となった標本が残されていることも特筆される(石倉, 1935a, 1935b; 石倉・前田, 1936)。オオモノサシトンボは1936年に東京金町小合(現在の水元小合溜)で石倉により発見され朝比奈正二郎によって1948年に新種記載(現在は新参異名)されたものであるが、コレクションには1934年と1935年に石倉によって同地で採集されたものが含まれていることから、実際にはより以前に発見されていたことが明らかとなった。従来、朝比奈の記録で知られていた東京関戸のベッコウトンボも含まれていることから、当時から朝比奈は石倉と交友関係にあったことが伺われる。宮城県産メガネサナエは朝比奈による原記載で指定されたホロタイプと同一データの標本が含まれている。小笠原諸島固有種の標本も含まれているが、そのほとんどが現在無人島となっている弟島産であることも興味深い。
目録内の種の同定および学名の表記は、尾園ほか (2021)に準拠し、国外の種を中心として補足的に津田(2000)、汪(2000)、Corbetほか(2007)、Jung(2012)、Lasley(2018)、曹(2020)、Ka(2021)、Slater Museum of Natural History(2021)も用いた。また、過去のトンボ類の記録や旧地名・現在地名の検索に関しては、東京府土木部(1938)、大野(2011)、柳田(2017)、地名好きさん(2019)、喜多・須田(2021)、Higashide(2021)等を参考にした。
このコレクション目録のようなデータベースには、分類学や体系学、形態学のような分野への貢献が見込まれる。また分布情報を活用することで、生物地理学の他、生物多様性保全の基礎となるインベントリー作成、各種での地域絶滅過程の究明のような保全生物学の分野にも寄与する。ひいては森林伐採、土地利用変化、地球温暖化のような環境分野への基礎的情報も多く提供されうる。本データベースの公開発信により、国内外における様々な分野の研究に役立ち、学術標本やミュージアムコレクションの重要性を公の場に広く啓発することができれば幸いである。
謝辞
本目録の作成にあたり、喜多英人氏には既存記録の有無等でご助言を賜った。また、本目録は東京大学デジタルアーカイブズ構築事業および2022年度科学研究費助成事業(研究成果公開促進費:22HP7005)の補助を受けて作成されたものである。各氏、各機関・団体に心よりお礼を申し上げる。
引用文献
- 地名好きさん, 2019. 行政区画変遷一覧表.閲覧サイト: http://divisions.jp/(最終閲覧日:2021年12月25日)
- Corbet, P. S.(著)・椿 宜高・生方秀紀・上田哲行・東 和敬(監訳), 2007. トンボ博物学-行動と生態の多様性-.858 pp. 海游舎,東京.
- Higashide, M., 2021. 市区町村変遷情報.市町村制施行,合併等の履歴と予定.閲覧サイト: https://uub.jp/upd/(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 石倉秀次, 1935a. 井の頭池, 善福寺池, 三宝寺池の蜻蛉. 昆虫界, 3 (20): 412–419.
- 石倉秀次, 1935b. 市川市国府台付近の蜻蛉. 昆虫界, 3 (20): 420–423.
- 石倉秀次・前田一郎, 1936. 尾瀬の蜻蛉. 昆虫界, 4 (27): 329–334.
- Jung, K.-S., 2012. The Dragonflies and Damselflies of Korea.272 pp. Nature and Ecology, Seoul.
- Ka, M., 2021. 香港蜻蜓名錄 A Checklist of Dragonflies (Odonata) of Hong Kong. 香港香港自然探索學會.Available from: https://hkdragonflies.blogspot.com/(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 喜多英人(編著)・須田真一(監修), 2021. 東京都のトンボ.257 pp. いかだ社,東京.
- Lasley, G., 2018. North American Dragonflies and Damselflies. Available from: http://www.greglasley.com/dragonnoramerix.html(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 目黒区, 2017. 目黒の地名 衾(ふすま).閲覧サイト: https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/shokai_rekishi/konnamachi/michi/chimei/seibu/fusuma.html(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 大野正男, 2011. 東京都の絶滅昆虫(本土部). 昆虫と自然, 46 (1): 25–30.
- 尾園 暁・川島逸郎・二橋 亮, 2021. ネイチャーガイド日本のトンボ 改訂版(Kindle版).532 pp. 文一総合出版,東京.
- Slater Museum of Natural History, 2021. World Odonata List. Slater Museum of Natural History, University of Puget Sound. Available from: https://www2.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-museum/biodiversity-resources/dragonflies/world-odonata-list2/(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 東京府土木部(編), 1938. 武蔵野昆虫誌. 東京緑地計画調査彙報第11号.194+28 pp. 東京府,東京.
- 曹 美華, 2020. 台灣蜻蜓The Dragonflies of Taiwan. Available from: https://taiwandragonfly.blogspot.com/2013/02/blog-post.html?m=1(最終閲覧日:2021年12月25日)
- 津田 滋, 2000. 世界のトンボ分布目録.430 pp. 自費出版,大阪.
- 汪 良仲, 2000. 台湾的蜻蛉.349 pp. 人人月暦股份有限公司. 台北.
- Yago, M., Katsuyama, R., Ito, H., Tanio, T., Hoshizaki, S., Shimada, T. and Ishikawa, Y., 2019. Catalogue of the Insect Collection of Prof. Chujiro Sasaki and Associated Researchers, The University Museum, The University of Tokyo. Part I (Lepidoptera: Rhopalocera). The University Museum, The University of Tokyo, Material Reports, (119): 1-274.
- 柳田則明, 2017. 宮城県トンボ目録.247 pp. 自費出版,宮城.
