

















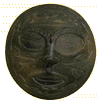
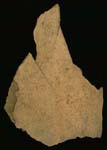
中国
河南省安陽市小屯村殷代遺址(いわゆる「殷墟」)
殷王朝第22代王・武丁期(紀元前14世紀頃)
縦21.0cm、横15.7cm
昭和61年、京都の某氏より購入。旧蔵者の入手経路は不明。
東洋文化研究所
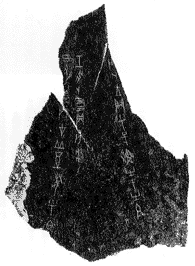
1899年以来、河南省安陽市近傍の小屯村一帯から、文字を刻した亀甲ならびに獣骨が大量に発見され、解読の結果、その刻辞は殷代後期(前14〜11世紀)に、殷王朝の卜官によって国事が占卜され、その内容と結果を記したものであることが判明した。中国考古学研究上の最大の発見とされる。今日もなお、新発見が続いており、これまでに十数万片が出土した。過去100年近くの間、多数の学者の研究により、約4千字のうち、主要な千数百字は解読され、大部分はその文意も明らかにされた。漢字のもっとも古い祖型を示すところから、漢字研究の根本資料であると同時に、中国史上、実在の確認できる最古の王朝の日常の行事についての占卜であることから、殷代史解明のための無二の史料でもあって、この大量の資料の研究上の価値は計りしれないものがある。
我国においても、その発見の初期より注目され、明治42年(1909年)に初めて舶載されて以降、多くの専門研究者が輩出した。東京大学東洋文化研究所は、日本所在の甲骨片の収蔵に努め、これまでに約2千片を収めるに至った。松丸道雄『東京大学東洋文化研究所蔵甲骨文字』図版篇(1982年)にその大部分を収録するが、本片は当書刊行後の新収品であって、拓本としては未発表である。 甲骨文は、殷の第22代武丁より末王第30代帝辛(いわゆる紂王)に至る九王の時代の所産であり、研究の成果として、これを5期に区分することが可能である。本片は、その第1期武丁期に属する最早のもので、なかでも最もスタンダードな書体である。
本片には、個別に独立した3回の占卜の内容が3行に刻されている。以下に、右行より1行ずつ簡単に解読・解説付す。
 子漁
子漁 于
于 且。
且。
 (=有)且(=祖)に
(=有)且(=祖)に (=侑)さしめんか」と)
(=侑)さしめんか」と)
 」は十二支の第1。後世の子に相当する。次の「王貞」とは王、即ち武丁自身が「貞」したことをいっているのである。殷代の骨卜においては、裏面に浅深2種の穴を製し、これを焼灼して表面にあらわれた卜兆(ひび割れ)によって、吉凶を判断した。この占いを、この場合は、王自身が担当したことを示しているのである。「子漁」は、武丁の子の名とされることが多いが、筆者は、王朝に服属した族長が、王と擬制的な父子関係を結んだもの、と考える(「殷周国家の構造」『岩波講座・世界歴史』4、1970年参照)。「
」は十二支の第1。後世の子に相当する。次の「王貞」とは王、即ち武丁自身が「貞」したことをいっているのである。殷代の骨卜においては、裏面に浅深2種の穴を製し、これを焼灼して表面にあらわれた卜兆(ひび割れ)によって、吉凶を判断した。この占いを、この場合は、王自身が担当したことを示しているのである。「子漁」は、武丁の子の名とされることが多いが、筆者は、王朝に服属した族長が、王と擬制的な父子関係を結んだもの、と考える(「殷周国家の構造」『岩波講座・世界歴史』4、1970年参照)。「 且(有祖)」は用例の多い語ではなく、必ずしも明らかではないが、合集2972、合集2973に同文例の用法があり、また、丙33、182、197の用例から判断すると、「有祖」を祭祀の対象とするのは、子某に命じて祭祀を行なわせる場合に限られているようである。このことからすれば、直系のものでなく、擬制的関係をもった者に殷の祖先神を対象とした祭祀を行なわしめる場合には、ある特定の祖先ではなく、祖先神全体を「有祖」(「有」はこの場合、「すばらしき」といった意味の美称である)として取り纒めて、合祭せしめたのか、とも考えられよう。動詞の「
且(有祖)」は用例の多い語ではなく、必ずしも明らかではないが、合集2972、合集2973に同文例の用法があり、また、丙33、182、197の用例から判断すると、「有祖」を祭祀の対象とするのは、子某に命じて祭祀を行なわせる場合に限られているようである。このことからすれば、直系のものでなく、擬制的関係をもった者に殷の祖先神を対象とした祭祀を行なわしめる場合には、ある特定の祖先ではなく、祖先神全体を「有祖」(「有」はこの場合、「すばらしき」といった意味の美称である)として取り纒めて、合祭せしめたのか、とも考えられよう。動詞の「 」は後の侑字で侑祭を行なう、の意である。
」は後の侑字で侑祭を行なう、の意である。
 白〔以下缺文〕
白〔以下缺文〕
 」は、甲骨文中に頻見の地名。所在について諸説あるが、不明とするのが正しい。「敏」は祭事の一種。「白(=伯)某」は、後の某伯に近かろう。親族称呼に起源をもつ官位のひとつで、後世の爵称の淵源である。占卜の内容は、缺文のため不明である。
」は、甲骨文中に頻見の地名。所在について諸説あるが、不明とするのが正しい。「敏」は祭事の一種。「白(=伯)某」は、後の某伯に近かろう。親族称呼に起源をもつ官位のひとつで、後世の爵称の淵源である。占卜の内容は、缺文のため不明である。当片の所見しうる部分には、裏面も含めて卜兆を行なった痕跡を缺いている。通常、牛(水牛)の肩胛骨は、縦35〜45センチほどで、1匹の牛の左右2枚の肩胛骨を組みにして占卜に用いる。当片中に卜兆や焼灼の痕跡が見られないのは、その部分が破損して残らなかったために相違ない。
(松丸道雄)