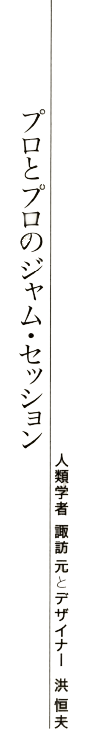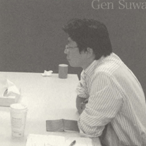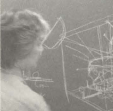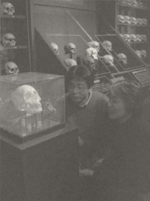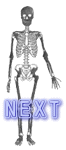端緒
今回の展示企画を初めて考えたのは数年前だった。
人類学研究のプロである諏訪元(東京大学総合研究博物館助教授)にとって、論文や学会発表といった日常的に行っている発表形式に、不満があったわけではなかった。自分の活動の場として博物館があったから、そろそろ自分も展示を企画しようと思っただけだ。そして展示をするならば、他人の研究よりも自分の研究分野で展示をしたいと考えたまでだった。
諏訪には、博物館での研究について思うところがあった。
「博物館では、通常は展示のテーマを決めた段階で、そのための調査を始めることが多い。しかし、展示のために研究するのは、元来の研究者としての営みではないのではないか。自分たちだって、そもそもの研究、つまり世界の東大の一員として世の中を驚かすような最先端の研究をすることに、もっと貪欲であるべきではないのか」
たしかに、博物館での研究といえばキュラトリアル・ワーク(標本整理)が中心であると思われがちだ。もっとも、諏訪はこういった仕事に否定的なわけではない。自分自身も大変な思いをしてノウハウ・経験を積み重ね、努力を尽くして「ちょっとやそっとではできない」キュラトリアル・ワークを行ってきたという自負がある。
通常、分類学者の扱う標本というのは、各研究者に属することが大半である。古い標本は代々引き継がれる場合も多いが、受け継いだ者がその標本の研究者でなければ、一度も開かずに埃をかぶったまま、さらにまた次の研究者に引き継がれることもしばしばだ。だから、他の研究者が使いたいと思っても、体系的な一覧すらないことも日常的である。
人類学教室の先人たちが集めた縄文時代の骨についてのキュラトリアル・ワークは、諏訪自身が「ここまでやった」と納得のいくところまでたどり着いていた。ヘルト人などのアフリカの骨についても、展示をしてもよいと思えるまで研究の進んだものが増えてきた。研究というのはすべて現在進行形であり、研究発表も一区切りがついた途中経過の報告にすぎない。今、まさに計算途中の骨については、展示をすることはできないのである。また、最先端の人類学研究の象徴であるラミダスのレプリカについても、展示できる目処がついた。機は熟していた。
諏訪にとっては、最先端の研究も丹念なキュラトリアル・ワークも、博物館の研究者としての営みそのものだった。今までの展示では、ある研究分野の一部を切り取って題材として説明を試みることがほとんどであった。しかし、実験的な展示手法を探るミュージアム・テクノロジー部門の洪恒夫(同博物館客員教授)と話し合ううちに、人類学者の営みそのものを展示にしてしまおうと、諏訪は思い始めていた。
増幅
最先端の研究そのものを展示したい。日頃のキュラトリアル・ワークへのこだわりも見せたい。
洪にとって、これまでの展示は形にするのが目的だった。今回の依頼は「研究者の営みの展示」だ。諏訪は骨の展示ではなく、骨を使った研究のプロセスを展示したいと依頼してきたのだ。実態がつかみにくかった。
もちろん、東大総合研究博物館は大学博物館であるため、今までの展示も何らかの形で研究に絡んでいた。研究者の研究に対する姿勢や眼差しを展示にするというのが、この博物館の展示の大きな特徴の一つであったと言ってもよい。しかし、最先端の成果を解説するのではなく、その成果が生み出されてくるプロセスを見せるという点で、諏訪が申し出た展示は今までに類を見なかった。
「『研究はこういうものなのだ』ということを伝える展示と、『研究でここまでわかった』ということを伝える展示では、全く異なる。後者になってしまっては、意味がない。骨というコンテンツが同じでも、骨の研究を続けるという営みがどういう意味を持つのかを示さなければならない」
たしかに、諏訪とは一年以上前から、折に触れてこの展示の話をしていた。こんな展示品だったら、こういう風に見せたらうまくいくのではないか。その標本は単独で見たら面白いかもしれないけれど、展示空間全体で作る大きなストーリーの中に組み込むにはふさわしくないのではないか。
それらのやり取りに垣間見ることができる洪の持論は、「デザインはメッセージを増幅する力を持つ」である。
物を集めてきて飾れば、それが即、展示になるわけではない。展示品に解説パネルをつけるだけでは、二次元の本や写真でもできることを、三次元を使ってわかりやすく並べているだけだ。それでは「展示」ではなく、単なる「陳列」になってしまう。
展示に仕立てるためには、展示という良さをいかに場に吹き込むかということに尽きる。空間だからこそ、物の背景にある世界観を出せることもある。そのための工夫をどこに施すことができるのかを考えるのだ。映像や空間をうまく使えば、単品の羅列でも興味のある人なら見てくれる。けれどこの展示では、日頃の研究を一連の作業として全体の展示空間にまとめたいのだ。
標本という学術資源にデザインという資源を付加することによって、諏訪の研究の訴求ポイントをいかに増幅させ、いかに印象深くみせるか。
それが洪にとっての最大の課題であった。
構築
この展示で、諏訪がもっとも示したいことは「研究者としてのこだわり」だった。物を扱う研究ならではのこだわり――展示する標本の質の高さ――はもちろんのこと、研究者はプロという自負のもと、思いのすべてを込めて研究活動をしているというところを表現したかったのだ。
キュラトリアル・ワークは、パッと現場へ行ってサンプルをすんなりと採ってきて、帰ってきたらすぐに標本整理が終わって、データベース化が整然とできる、というものではない。大変な思いをしてノウハウ・経験を積んで、それを活かしながら一歩ずつ進むものだ。学術研究にしても、誰もがアフリカにさえ行けば簡単に重大な発見ができて、新聞に載ってもてはやされるというものではない。発見するには、訓練と、常にアンテナを張り巡らしているという感度が必要だ。人類学というとロマンといった文脈で語られることが多いが、延々と過去に起こった人類の進化を、プロの技術で少しずつ解き明かしていく作業なのだ。
人類学に興味を持ってくれる人であるならば、背景となる研究とその準備段階の深みとともに、その結果として手にすることができる成果を鑑賞してもらえるのではないか。成功したという研究のストーリーの中の、ほんの一部の結末のみを提示するのではなく、実際に現在進行形でやっているところから散発的に結果が出てくるプロセスを見せることによって、より面白がってもらえるのではないか。この展示によって、成果を得るまでの楽しみを来館者と共に分かち合えるかもしれない。
また、プロセスを垣間見てもらおうという展示は、物を展示するのと性質が異なる「新しい展示」である。このような展示は、東大ならではの展示バリエーションの一つになりうるのではないか。というのも、専門性を第一線で追求しているのが、東大の東大たるところであり、研究プロセスの展示というのは正にその流れにそった展示であるからだ。
「新しい展示」を提案されたとき、洪はその肝は見せ方の情報計画であると受け止めた。
特にキュラトリアル・ワークの成果を見せる場合、ものが同じならば、情報の流れをいかに作るかによって、見え方は左右される。一つ一つの展示品に当たり前の言葉をつけて展示解説してしまうと、従来の展示と同じになってしまう。
「情報計画を立てることというのは、小説を書くことに似ている。うまい人は全体の流れを作ることができるし、メリハリがつけられて面白いものを作ることができる」
洪が情報計画を立てる際に端緒としたのは、一見、骨以外の共通項が見つけ難いアフリカの骨と縄文の骨の双方を貫くテーマだった。
「諏訪さんが両者を貫く軸は『発見』であると話されたとき、やっと糸口が見つかって、オリジナルの新しい展示が作れるという自信がわいてきた。先人たちのキュラトリアル・ワーク、データベースは博物館の資源であり、現在の研究者の発見も先人たちの発見も、研究成果という意味では同じだ。昔の発見に今の発見が積み重なること――それが常に動いている研究現場そのものなのだと感じた」
洪いわく、展示空間を串刺しするのも、すなわち展示の屋台骨ができれば、あとはどのように情報でつないでいくかという仕上げの問題であるという。もしも最終的にわかりづらいものができたときは、コンセプトが悪かったのではなく、仕上げの作りこみ方が悪かったということらしい。展示の編集作業の段階では、どのような視点をもって同じ素材を見せるのか、あるコンテンツの隣にいかなるコンテンツを置くのかなどを考えていく。たとえば、隣に同色を置くのか補色を置くのかで、見え方が全く異なってしまうからだ。この時点では、展示デザイナーはシェフの心境になるという。コース料理のここで季節ものを入れようとか、油ものの次に箸休めを置こうなどと考えるのと同じであるからだ。
「全く違う分野の人と一つの物を作るとき、想像したこともなかった何かができるのを実体験する。クリエーターとしては、こんなに面白いことはない。さらに、展示計画を練る中で、全く違う分野にも共感する部分が見つかる。今回は、研究の世界では見極める力がすべてだ、ということを知った。同定する力を持っていなければ、出てきたものが何であるのか、大事なものなのか、自分が求めているものなのかさえもわからない。知識を持って、はじめて研究ができる。その部分に非常に共感を覚えた。」
もっとも、プロの研究者として展示する題材にこだわりを持つ諏訪と、空間を使った見せ方のプロを自負する洪との間では、常に意見が一致するわけではない。諏訪が題材という直球を投げると、洪が自分なりの解釈を加えて変化球で戻ってくることも少なくなかった。諏訪はそれを受けて、さらにひねりを加えて投げ返したり、洪の受け止め方を参考にしながら別の題材を投げてみたりしたという。研究とデザインの綱引きが常に繰り広げられたようだ。
彼らは自負をどのような部分に持っているのだろうか。また、コラボレーションをしている時の綱引きについて、どのような印象を持ったのだろうか。
綱引き
研究者のプロであるとは、どのような境地であるのか。
諏訪は、「仮にも研究者と名乗るならば、どうせやるのであるならば、並大抵ではそこまでいかないというところまでたどり着くべきだ。そのためには、ノウハウ・工夫・努力・積み重ねが必要だ。自分はそのようなプロの研究者を目指して精進している」と語る。中途半端なことを、わざわざやっても仕方がない。やるならばよいものを目指すべきである。同じ題材の研究論文を作るときも、同じ目的で同じ実験をする時も、研究者としての姿勢の違いはデータにも表れる。また、たとえ同じデータから出発しても、解釈は変わってくる。その違いはすべて、どこで自分は納得するのかというこだわりの違いから生まれるというのだ。
自分の専門領域である人類学のこういうコンテンツを展示して、研究へのこだわりを感じとってもらいたいと提案した場合、デザイナー側から想像以上に整理されて投げ返される場合も多かったという。そのような場合は、「整理されちゃっているな、デザイン側としてわからなかったから、こうしたのだな」と思い、むしろ「それならば、こういうコンテンツに変えて投げかけよう。その方が、研究者がどんなプロセスにこだわっているのかを感じ取ってもらえるのかな」などと考えたという。
一方、デザイナーのプロという境地については、洪は「常にアンテナを張り巡らして、感度を落とさないことが重要だ」と語る。また、キャッチする周波数の合わせ方は場合によって違うのかもしれないが、それは苦労してやる話ではないし、どこを磨けばいいというものでないとも話す。
「何かと何かを合わせると、今までにないものができる。プロとプロがぶつかりあうときはセッションが生まれるから、面白いと感じる。セッションをしないと、いつも自分のカラーのものしか作ることができない。クリエーターというのは、同じ状態で満足してはいけないと思う」
ただし、セッションでは、相手のスタイルに影響を受けて自分のスタイルが変わる、というわけではないという。誰とぶつかりあっても変わらぬ自分のスタイルを持っていることこそが、プロたる所以だと洪は考える。
「諏訪さんは、こうしたほうが展示としてわかりやすい、成り立ちやすいという、デザイン側の立場からの説明や展示コンセプトに苦労したと思う。プロとプロがぶつかるときには、理解しあっても仕方がない。反発しあったとしても、結果として何かが生み出されたね、というところが一番面白いのだから」
異なる専門家がぶつかり合うといっても、博物館で展示をする以上は、それぞれの主張のさじ加減を見極めて、きちんと融合させて最適な一つのものを作るのが究極の目的である。そのためには、プロの感性から一歩離れた場所から全体を見通すコーディネーターの存在が不可欠だ。また、コーディネーターの視点こそが、そのまま来館者の視点や期待に寄り添うことになる。
ミュージアム・テクノロジー部門には、最強の“素人”である石田裕美がいた。彼女は、最初から展示コーディネーターとして雇われていたわけではない。博物館の展示に関わっていくうちに、最適な人材配置や各教員の視点や考え方、来館者の反応というものに長けていき、展示に関わる専門家たちも彼女の意見に一目おくようになったのだ。
彼女の特技は茶々を入れることである。形が先行しすぎていると思うと、諏訪が違和感を口に出す前に、洪に対して茶々を入れる。見せ方のアイディアに対して、もっと違う中身も考えられると思えば、この見せ方にはより相応しい中身があるはずだと諏訪に率直に話す。
石田から見ても、今回のセッションは非常にうまく機能していたという。これまでに数々の受賞経験を持ち、日本でも有数の展示デザイナーである洪の織りなす空間に対して、諏訪の研究実績に裏付けられた研究哲学と研究者としての普段の真摯な姿の迫力は不足がなく、双方が同じ力量で真剣勝負をすることができたからであろう。
さらに、彼女は成功の秘訣として、諏訪と洪とが似ていることを指摘する。
「二人とも、好きなことを一所懸命やっていると、賞をとったり大発見をしたりして、さらに好きな仕事がしやすい状況になる。結果を求めているわけでないのに、たまたま結果に巡りあってしまう」
洪も、その見解には同意する。
「次にこういう面白いものができるかなと思うと、ものを作ることには終わりがない。山を登るときに、○○山を登ることに意義を感じている人は、登った後は満足して隠居してしまう。自分は、登りたくなる山が出てきたら登ればいいと思っている。ここまでできたら納得して終わりにするという目標はない」
諏訪もこのように語る。
「人類学の研究をするうえで、ラミダスの発見はなくてもよかった。たまたま見つかっただけだった。プロとしてのこだわりをもって研究をすることが、一番重要だ」
現場
今回の展示は、人類学とは何かということを体感できる展示である。
また、研究者というのはこういう仕事なのだとわかる展示でもある。
「教科書的にパネルの上に文字で説明する形ではなく、研究と研究者の営みを表現したかった」と諏訪は語る。
人類学だけにとどまらず、研究者の営みを具現化した展示をHP上でデジタルツアーができるようにして世界に発信すれば、論文などとは別の形の発表媒体を研究者は手に入れられるのではないか。
しかし、このアイディアに洪は否定をする。展示とデジタルは根本的に違う。デジタルミュージアム的なものは、あくまで疑似体験であり、情報のみを伝えるものである。実物の持つ臨場感や訴える力は、実物を見ることでしか得られないというのだ。
「アートディレクターたる自分の仕事は、与えられた大きさや形状の空間の中で人が動くとき、その中に何をどのように配置して、来館者に何をつかんでもらうのが最も有効なのかを考えることにある。その場に来ないとつかむことができないことを提示することこそが、空間メディアの役割だと思っている」
ミュージアム・テクノロジー部門も3年間の区切りを終えるときに、研究そのものの展示という題材を得て、レベルアップを図った。情報計画を丁寧にやって、いかに今までと違うものを作り上げたのか。成功の原動力は、諏訪が提供する魅力的な素材であった。
「ラミダスはひとつの題材であったが、わかりやすさの象徴だ。この展示は人類の系統樹から始まるが、ラミダスがあったからこそ今の系統樹の形になったというしっかりした裏づけがある。人類学のトピックスを拾うといった表面的な状況ではなく、展示会場の動線に沿って研究のありようを深く掘り下げていき、現状はこうで、これらの研究がないと系統樹はかけなかったと、最後に立ち戻ってもらいたい」
研究の営みを展示する試みは、ライブで体験しなければ魅力を存分に受け取ることができない。プロとプロがぶつかりあったコラボレーション展示は、やはり期間限定の奇跡のジャム・セッションであったのだ。