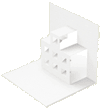
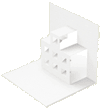
無重力と非物質的物質性
建てることが原理的に不可能な建築はありうるだろうか。—このような問いはその形式からして矛盾をはらんでいるのであって、われわれはそんな対象をそもそも思考し、イメージできるだろうか。建築の可能性と不可能性が、その時代の技術的、経済的な限界によって規定されるものならば話はたやすい。エティエンヌ=ルイ・ブレーがドローイングに描いたメガロマニアックな建築物は、その巨大さゆえに18世紀末という時代には実現不可能であったし、1920年代のロシア・アヴァンギャルドの建築家たちが夢想した、空中を浮遊する建物は、当時としてはいまだ夢物語だっただろう。しかし、巨大さへの志向をブレーと同じくするとはいっても、これがバックミンスター・フラーのジオデシック・ドームになると、テクノロジカルな合理性を徹底させて、技術的には十分実現可能な存在になっている。また、浮遊建築物がもはや虚構の問題でないことはいうまでもない。ちなみにフラーには、ジオデシックの巨大な球体が空中をいくつも漂っているドローイングがある。重力が建築を根源的に限界づける条件であった限りでこそ、〈大地〉との緊張関係のうちに屹立するギリシア神殿を例に引いてハイデガーが〈芸術作品の起源〉について語ることもできた。また逆に、建築家はこの条件からの解放を求めて、建築物を飛翔させる夢を繰り返し描き出してきた。フランス革命とロシア革命の時代には、その志向が特に際だって認められる。そして、いまや〈サイバーアーキテクチャー〉のデザイナーを自称する建築家たちは、重力による束縛のないデジタル空間内におけるデザインの自由度を喧伝している。現実空間からサイバースペースへと資本投下の場所が移動するのに応じて、建築はコンピュータ・ディスプレイの仮想の内部空間の構成を意味する言葉へと領域を広げつつあるように見える。
だが、そのような発想それ自体は何ら目新しくはなく、原理的にはすでに建築家たちの想像の中で繰り返し予感されていたものであったことは確かなのだ。情報という〈見えない足場〉の上に築かれる〈トランスアーキテクチャー〉の建築家マーコス・ノヴァクは、マレーヴィチをはじめとする初期モダニズムの抽象芸術のうちにサイバースペースの萌芽を見ている。磁力や引力、電波、宇宙感覚といった不可視の力やパルスを無対象絵画の世界に認め、その延長線上に基礎を持たない浮遊する建築、無の上に築かれる建築を構想したマレーヴィチとともに、エル・リシツキーは想像的=虚の空間の構築を、残像現象をはじめとする〈見ることの仕掛け〉によって追求した。もとより物理的空間の3次元性を変えることも、空間の曲率を任意に変えることもできない以上、そこで追い求められたのは、現実には決して表象できない対象でありながら、物体の運動や残像、ステレオスコープ的な効果を通じてつかの間現出する仮想の空間にほかならない。
「プロウンは絵画から建築への乗換駅である」というリシツキーの言葉は、2次元と3次元の狭間のあるかなきかの不確かな亜次元的、間−次元的な〈乗換駅〉の領域にこそ、彼が執着し続けたことを示している。リシツキーはそれを〈非物質的な物質性〉と呼ぶ。光と物体の運動によって生み出されるこの〈非物質的な物質性〉とは、ノヴァクが次のように叙述する、電子メディア空間へと通じていたといえるかもしれない。「サイバースペース内の流体的建築は明らかに非物質的建築である。それはもはや空間や形や光やその他すべての実世界の側面に満足できない建築である。それは抽象的要素間のさまざまな変動する関係からなる建築である。」1)
メディアを横断する建築
だが、いずれにせよ、可能な建築と不可能な建築が、かつては虚構でしかありえなかったものからその実現への発展と進化の物語に回収されてしまう限り、可能性と不可能性とを分け隔てているこの〈現実〉という基盤は微塵も揺るがない。しかし、ここでパースペクティヴを逆転するならば、あれこれの実在する建築をめぐる営為の全ては、常にすでに不可能で実在しない、虚構の建築という余白に取り囲まれてきたともいえるのだ。いまやピラネージの『牢獄』に触れずに、19世紀以降の西欧の建築文化について論じることができるだろうか。すでに名前をあげたような幻視的建築家たちの夢想は建築史的記憶の不可欠な一部なのである。そして、写真をはじめとする複製技術、マスメディアの出現とともに、建築が依拠する〈現実〉そのものが変容している。ル・コルビュジエは、建築のコンセプトを明確化するために、自ら編集する雑誌『エスプリ・ヌーヴォー』に掲載する自作の写真に多くの修正を加えた。建築物の建造はもちろん建築家が行う活動の重要なモメントだが、ル・コルビュジエにとって決してその最終結果ではない。『エスプリ・ヌーヴォー』中の写真とそのレイアウトは誌面上に別の建築を建造する。建物の構想と建物それ自体、そしてその複製はそこにおいて、建造物という現実を最高位とした階層秩序を失って交錯しあう。そして、この階層秩序の転覆とともに、ル・コルビュジエの建築そのものが写真的空間に似てしまうという事態もまた生じる。ある一つの建築をめぐる経験がこのように写真や言説、その他、雑多なメディアによる媒介を経て構成されるものとなっている時、それが不可能か可能かという判定はどのレベルでなされうるのか。『エスプリ・ヌーヴォー』時代のル・コルビュジエのように、実作をほとんど行わなくとも、ドローイングや言説のみによって〈建築家〉であることがこの時代には困難ではない。建てられて実在する〈もの〉だけが建築であるという立場からは、実証主義的な歴史は叙述できても、〈もの〉化されることを拒んで建築家の妄想の中にとどまり続ける何かを語ることはできない。ル・コルビュジエが様々なメディアを横断したのは、近代建築のプロパガンダのためばかりではなく、彼にとってその〈何か〉であった〈建築〉という理念が、メディアの差異においてしか表現しえないものだったからだろう。それはすなわち、個々の表現形態内部では〈建築〉が実現しえない対象であったということである。建築ドローイングに描かれた対象は建てられてももちろんよいが、必ずしも建てられることを必要とはしない。では、それはアート作品なのだろうか。違う。建築ドローイングはアートという領域内部には自足できない、はるかに不安定で曖昧なオブジェだ。重要なのは建築ドローイングや建築写真が建築と取り結ぶ表象関係、とりわけその相互の差異であり、言葉を換えれば、ドローイングから建築物へ、建築物から建築写真へという翻訳の過程にこそ、ル・コルビュジエの〈建築〉は存在したのである。まさに〈建築〉は建造物としてもドローイングとしても自己充足不可能であるからこそ、それらを媒介する曖昧な場所(インターメディア)において実現可能性を見いだすのだ。
建築における潜在的なもの
われわれはここでジル・ドゥルーズにならって〈可能的なもの〉と〈潜在的なもの〉を区別したはうがよいかもしれない。実在的なものに対立するのは〈可能的なもの〉であり、可能的なものは実在化=実現へと向かうプロセスをたどる。それに対して潜在的なものは実在的なものと対立せず、それ自体として完全な実在性をもつ。潜在的なもののプロセスは実在化ではなく、現実化であるとドゥルーズはいう。可能的なものの実在化と潜在的なものの現実化の差異とは、では何なのか。「可能的なものとは、実は後から生産されたものであり、またその可能的なものに類似している[実在的な]ものに似せて、あたかも以前から存在するかのように捏造されたものである。・・・それとは反対に、潜在的なものの現実化は、差異によって、発散によって、あるいは異化=分化によって遂行される。そのような現実化は、原理としての同一性とは無縁であり、またそれに劣らず、プロセスとしての類似とも無縁である。アクチュアルな諸項は、その諸項が現実化することになる潜在性とは、まったく類似していない。」2)〈理念〉とはさまざまな異化=分化によって現実化される純粋な潜在性であり、差異として展開される多様性である。ル・コルビュジエの〈建築〉という理念はちょうどそんな〈潜在的なもの〉だった。そして、それは建築を一つの〈問い〉と化すことである。問いという多様体、この潜在的なものからは、その問いを条件づけているものとは似ても似つかない解が発散する、とドゥルーズはいう。とするならば、潜在的建築、すなわちバーチャルアーキチクチャーの実在性とは、解かれるべき問題の実在性であることになろう。もちろんここではあらかじめ存在する解を目指して問いが立てられるのではない。問題は前もって与えられたものではないし、解のなかで消失してしまうものでもない。バーチャルアーキテクチャーを構想するとは、あれこれの変数(例えばさまざまな機能や経費、規模など)からなる所与の問題の解としての建築という発想とは逆に、問題そのものとしての建築へと向かうことにほかならない。ル・コルビュジエにとって〈建築〉はそのような過酷な〈問い〉であり、だからこそ彼の活動は多様なメディアにおける異なる解の産出へと強いられ続けていたのである。
このような問いであった限りで、ピラネージや幻視的建築家たちのドローイングはすでに優れたバーチャルアーキテクチャーだった。従ってそれは実現の可能性とは本来無縁と考えたほうがよい。つまりそれらは〈可能的なもの〉ではない。むしろ彼らのドローイングは逆に通常の建築的思考を阻み、その建築の可能性を枯渇させてしまう〈暴力〉にほかならず、しかし、建築をめぐる思考はこの異質な(差異としての)〈問い〉によって強制されてはじめて、類似と同一性によって囲い込まれた閉域の外へと脱出するのである。
モダニズム建築は歴史の重圧を抱えた19世紀の建築文化からの離脱を試みるために、ル・コルビュジエについて見たように、自らをそんな〈問い=拷問〉に晒した。それは建築がすでに所有していたあらゆる〈可能性〉をことごとく滅衰させることを意味した。豊かな伝統の象徴性や装飾的語彙は消尽され、空っぽにされ、モダニズム建築はその代わりに素材の物質性そのものへと集中する。語彙が限定され枯渇しているからこそ、鉄、ガラス、コンクリートなどの素材はそこに内包された強度において裸形の物質性を表現する。
例えばミース・ファン・デル・ローエのガラスの摩天楼(それはフォトモンタージュなどが残されているばかりで、実際に建造されてはいない)とはまさにそんな、フォルムをもたない強度そのものの物質的表現だった。〈消尽したもの〉(ドゥルーズ)としてのこのガラスの摩天楼は、ガラス建築に内在する可能性のすべてを網羅的に尽くしきってしまった結果、その消尽の運動の終わりにやってくる何かであり、ドゥルーズによれば、それこそが〈イメージ〉である。「そこでむしろ終わりによって、あらゆる可能性の終わりによってこそ、われわれはイメージを作ったと、イメージを作り出したところだと気づくのだ。」3)凝集した潜在的エネルギーの自己散逸の過程がここでいう〈イメージ〉であり、それは散逸し、枯渇していくプロセスそのものである。ミースにとって建築の根源にあった経験とは、こうした〈イメージとしての建築〉の経験であり、その消尽過程はこのイメージへと向かっていた。彼は建築を、何ものも表象しない強度のみのイメージへと枯渇させるのである。ミースが反復的に建てた建築物とは、このイメージという〈問い〉に対する解のヴァリエーションであった。そしてガラスの摩天楼は、そこで産出されたもろもろの解の中においても執拗に持続し、それらの解とは本質的に異なったものにとどまりながら、潜在的に実在し続けている。
バーチャルアーキテクチャーの触覚的リアリティ
いわゆるバーチャルアーキテクチャーが、現実空間の建築に対する仮想空間の建築として、前者へといわば翻案可能な—その意味で類似した—ものでしかないとすれば、それはこのような潜在性とは無縁な〈可能的なもの〉にとどまる。そこにおいて、ナヴィゲーション・システムをはじめとするインターフェースのデザインが問題ならば、それは現実空間に近いわかりやすいもので十分であり、一つの解で足りる。その場合、ディスプレイ上における多次元空間のシミュレーションは、スクリーンへの3次元空間の遠近法的投影に頼ることにならざるをえない。一方、現実空間に対するサイバースペースの自由度を強調したところで、そのような自由度はデザインの形態的な豊かさを増すだけであり、そこで生み出されている画像の多くは結果的に、ノヴァクが用いる〈流体的建築〉という比喩を文字どおりに形象化したような、奇妙に表現主義的なフォルマリズムに陥ってしまっている。バーチャルアーキテクチャーが、このように任意にデザイン可能な対象であるならば、そのデザインはすでに実在的なものに似せて「あたかも以前から存在するかのように捏造された」予測可能な範囲内のものでしかなかろう。
バーチャルアーキテクチヤーが真に〈潜在的なもの〉となるための条件は、このような自由度と恣意的に戯れることではなく、むしろそれを消尽して、枯渇し、そこに所属する〈可能性〉を減衰させることであるのかもしれない。自由度ではなく不自由度を求めることといってもよい。コンピュータとそのネットワークをあたかも現実空間と同種の、類似した世界であるかのように見せかけることが、バーチャルアーキテクチャーの課題なのではない。写真が建築を変容させたように、バーチャルアーキテクチャーは建築を変容させる。それは現実空間に対する異化=分化によって、現実空間への差異においてこそ建築に暴力を加えるだろう。なじみやすく、使いやすいインターフェースではなく、人間身体に対するコンピュータの異質性、その異物としての存在の抵抗こそがそんな異化=分化の手がかりとなるのではないだろうか。
デヴィッド・クローネンバーグ監督の映画『ビデオドローム』における主人公を呑み込んでしまうテレビ画像や、自分の体のいたるところにインターネットと接続されたセンサーやスティミュレーターをとりつけて、テクノロジーと身体の文字どおりの融合を実現するアーティスト、ステラークのパフォーマンスのように、コンピュータをはじめとする電子メディアは触覚性を持ち、われわれの身体へと皮膚感覚的に接触してくる。コンピュータにはいわば肉体的な実在性がある。それはクリーンでクールな機械であるどころか、人間に取り付いて寄生する、おぞましくも魅惑的な生命体だ。ノートパソコンを肌身離さず持ち歩くわれわれは、この寄生体的他者との接触からかつてない快楽を得ている。われわれの日常生活のリアリティはもはやサイバースペースによって構造化されており、われわれの身体はすでに現実の建築空間、都市空間よりも、サイバースペースこそを身近に(つまり皮膚感覚的に)感じているのかもしれず、バーチャルアーキテクチャーはいつの間にかわれわれをとっくに囲繞して、その子宮的な空間内に閉じ込めているのかもしれない。
サイバーパンク小説において、大都市内の無秩序で周縁化された場所とサイバースペースが好んで対になって描かれることにも表れているように、バーチャルアーキテクチャーのリアリテイの増大と現実の都市・建築の荒廃や腐敗はリンクしている。バーチャルアーキテクチャーに〈現実〉の装いを与えようとサイバーアーキテクトたちが無邪気なフォルマリズムを繰り広げているかたわらで、われわれの身体にとってのいわゆる〈現実〉はすでに崩壊し始めている。バーチャルアーキテクチャーをめぐる論議の多くは、この崩壊、そして電子メディア環境との接触によってわれわれの身体が被る変容を見ない。その結果がフォルマリスティックな視覚的イメージの探求なのではないだろうか。
バーチャルアーキテクチャーは建築(家)があれこれ好き勝手な解答を与えられるようなデザインの課題ではない。それはコンピュータとの徹底して即物的・官能的な出会いによって20世紀末のわれわれが直面している現実的条件であり、おそらくは建築(家)にとってきわめて脅威的な問い=拷問なのだ。そのような存在としてのみ、それはまさしく〈潜在的なもの〉として、この時代の建築をめぐる思考を変容させる〈暴力〉となりうるように思われる。
註
1)マーコス・ノヴァク(NTTヒューマンインターフェース研究所ほか訳)「サイバースペースにおける流体的建築」、マイケル・ベネディクト編『サイバースペース』(NTT出版、1994年)所収、262頁。
2)ジル・ドゥルーズ(財津理訳)『差異と反復』(河出書房新社、1992年)、319〜320頁。
3)ジル・ドゥルーズ+サミュエル・ペケット(宇野邦一・高橋康也訳)『消尽したもの』(白水社、1994年)、22〜23頁。