LOMAX社植物化石薄片標本大場秀章(東京大学総合研究博物館) |
|
教材と聞いて思い出すのは、小学校入学のときに使った算数用の教材だろう。使った世代ではなくともそれを買い与えなくてはならなかった中高年世代にとっても、恐らくこれが最初にかかわる教材だったのではないだろうか。だが教材は高等教育でも使われる。否、専門家として必要な知識を我がものとするためにかかせない教材も多々ある。しかし、そのことは一般には存外知られていない。 
LOMAX社が1900年代初頭に制作して販売した化石植物の顕微鏡薄片試料は、専門家にとってもまさに欠かせない教材といえるものである。現存しない絶滅した化石植物は、植物の進化や構造の発達、多様性を明らかにするうえでも欠かすことのできないものである。またかつては石炭などの有用資源を含む地層を特定する上でもこうした化石は重要な手がかりを与えてくれたのである。石炭がとくに重要な資源であったドイツでは、化石植物を研究する古植物学は地質学の一分科に含められていた。日本は、明治の学術体制確立期にドイツ流の学術体制を輸入した。こうして、化石の研究は生物学ではなく地質学の領域に置かれることになった。が東京大学では化石植物は植物学の分野でも研究されたのである。それは明治39年にイギリスのマリア・ストープスが来日したことに端を発している。マリア・ストープス(Marie [Charlotter Carmichael] Stopes)は、1880年に生れた。彼女は初めは植物学に進み1904年にミュンヘンで化石植物の研究学位を取得したのち、マンチェスター大学やロンドン大学で講師を務めたが、1920年からは産児制限や性教育や女性解放の研究や推進者として活躍し、その分野で有名になった。1907年に来日し、植物学教室の当時助教授であった藤井健次郎と共同で北海道の炭坑で採集した白亜紀の植物化石を研究した。その成果は1910年に英国学士院紀要に論文として発表された。この論文のもとになった標本(顕微鏡薄片)はロンドンの大英博物館自然史部門(現、ロンドン自然史博物館)に保管されているが、残念ながら本学には関連する標本は残っていない。藤井・ストープスによって始められた化石研究は継承されることなく終わるが、藤井教授に師事して植物形態学を学んだ小倉謙によって新たに研究が進められることになった。化石というと、一般には「木の葉石」のように、植物そのものというよりも石に刻印された植物の押し型(これを印象化石という)が話題になるが、植物体の骨格をつくる細胞壁の炭素が、長い時間を経て珪酸に置き換わった珪化化石や炭酸カルシウムに置き換わったいわば植物体そのものの化石を用いて研究を行ったのである。 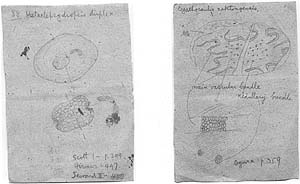
木本植物の材の部分や、球果や果実にこうした化石が多数見出されていて、保存状態がよい化石では、細胞壁が完璧に残るために、化石となった植物の器官や組織についての解剖学的な研究が可能である。これは現に生きている植物の解剖学的な研究と大差なく、また遜色なく分析ができるため、こうした化石にもとづく研究は印象化石とは異なる情報を植物学にもたらしてくれる。 1895年に仙台に生れた小倉謙は、1916年に東京帝国大学に入学して藤井教授につき植物形態学を学び、1919年(大正8)の新帝国大学令により理科大学が理学部と代わって最初の卒業生となった。彼は大学卒業と同時に講師に任命され、1927年には理学博士となり、助教授に昇任た。さらに1938年には教授となった。1928年に文部省から植物形態学の研究のためイギリスに在留を命ぜられ、ロンドンの大英博物館自然史部門とケンブリッジ大学に数ヶ月滞在して、スコット博士(D.H. Scott)やセワード教授(A. C. Seward)のもとで化石植物の研究を行った後、ドイツのミュンヘンに赴き、そこの植物学研究所長であったゲーベル教授(Karl von Goebel)のもとで植物形態学や器官学を学び、米国を経由して1930年に帰国した。 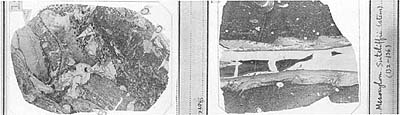
小倉教授は1920年に処女論文として、スギその他の樹木の肥大生長についての研究を発表したが、その後は研究をシダ植物の形態にシフトさせた。シダ植物の構造一般に関心があったが、とくに木生シダの構造に焦点を当た。こうした研究は1938年にベルリンで刊行された、“Anatomie der Vegetationsorgane derPteridophyten”(シダ植物の栄養器官の解剖)に集大成された。本書は世界的にも高い評価を受け、1972年にはその改訂版が”Comparative anatomy ofvegetative organs of the Pteridophytes”と題して英文で出版されている。小倉教授はその他にも多くの植物についての形態について行った研究の成果を発表するとともに、後進の教育にも力を注ぎ、日本での植物形態学の水準を国際的なものに高めた。 小倉の師である、藤井教授がストープスとともに行った化石植物についての研究の発展も当初から小倉の研究目標の中に含まれていたのだと思われる。実際にストープスと藤井によって行われた植物学教室での化石植物研究からはかなりの空白があったが、1927年以降小倉は化石植物についての研究を発表する。 初めは日本と朝鮮の三畳紀の木生シダに関するものであり、小倉の化石植物への関心は木生シダの形態学研究から広がっていったものと推測できよう。一方、1928年に大英博物館を訪問した際に、小倉は藤井教授により北海道で採集された白亜紀植物の顕微鏡切片に多くの時間を費やしている。帰国後、彼はヘゴに似た木生シダの茎の化石にたいしてYezopterisという新属名を提唱するなど、その成果を論文にまとめ発表した。その論文ではストープスと藤井が行った裸子植物化石を補足する研究も含まれている。 小倉の化石植物はこうしてシダ植物から裸子植物さらには被子植物と広がっていき、時代も中生代から新生代にまで及ぶものとなった。ところで、植物の構造、器官や組織の進化を研究するうえで化石植物の研究は欠かせない。重要な変化の多くが過去に起きたことであり、化石にのみ見い出されるためである。 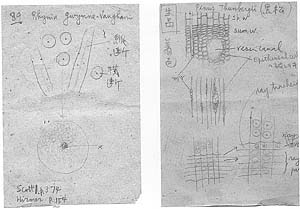
しかし、そのすべてが化石として残っているわけではない。化石化するのはかなり偶然のことといわねばならない。しかも化石は世界中のどこでも万遍なく見い出されるわけでもない。古生代・中生代・新生代を通じて重要な化石をひととおり研究するといっても、それはきわめて困難なことなのである。世界の各所から見い出された、幅広い地質年代にまたがる珪化化石から、顕微鏡用の薄片を作成したのが、このローマックスの植物化石薄片標本である。 これを克明に観察した小倉教授のスケッチが残されている。その中には、デヴォン紀に陸上が存在することに確証を与えたライニー植物群を代表するRhynia gwynne-vaughanii、石炭紀を代表する鱗木の1種、Lepidodendron selaginoidesなどの材化石が含まれている。材化石だけでなく、種子の進化や多様化を明らかにするうえで重要なLagenostoma ovoidesなどもあって、小倉教授のスケッチが残っている。
薄片には仙台の埋れ木であるTaxodioxylon sequioanumと同じ構造をもつものもあり、小倉教授のスケッチは「仙台の埋れ木と同じもの」という書き込みが残る。 また、木生シダの葉柄の化石もあり、それはCyathorachis fujianaと同定されている。この種小名は恩師でもある藤井健次郎教授に献名されたものである。 ローマックスの化石薄片標本は小倉教授の後継者らによっても利用され、日本の化石植物研究者の育成に重要な役割をはたした。この標本が本博物館の前身である総合研究資料館に創設とともに保存されるようになってからも、植物形態学や化石植物学(古植物学)の研究者による利用が続いた。なかでも本学で小倉謙教授の薫陶を受け、千葉大学教授となり、化石植物の研究に大きな業績を残した故西田誠教授はその熱心な利用者のひとりであった。 |
| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

