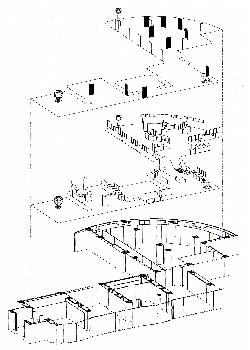
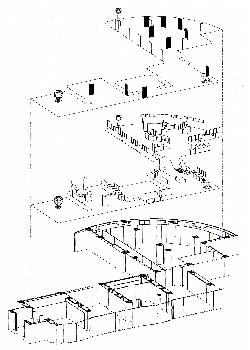 |
| 図1 『学位記展II』の展示構成概念図(上段から下段へ、扉とランドマークの配置/展示物の配置/展示室 の構成を示す) |
私が専攻する建築・都市デザインの分野で、いっときよく議論された概念に都市の<レジビリティ(legibility)>というのがあった。1960年代に出版されたケヴィン・リンチの著書『都市のイメージ』で提唱された概念で、ふつう<わかりやすさ>と訳される。
同書からこの語の定義を引けば、「レジビリティとは人々が都市の各部分を認識し、さらにそれらをひとつの筋の通ったパターンに構成するのがたやすいということである。この本のこの頁が読みやすいということは、見分けのつく記号の組み合わせからなるパターンとして、それを視覚的に把握できるということである。」この定義から言っても<わかりやすさ>という訳語でよいのだが、単に平明というのとは少し違うと私は思う。この語を硬く訳せば判読可能性だ。
それは、すべてがフラットに並べられていて一目で見て取れる故にわかりやすい、というのとはニュアンスが違う。むしろある空間環境の中にそれを理解するための手がかりが随所にあって、観者はその手がかりに導かれて環境の構造を<読む>ことができるようになっているということであろう。リンチも述べる。「外界を知覚するに際し観察者自身が積極的な役割を演じなければならないし、そのイメージを発展させるのにも創造的役目を受け持たなければならない。」
ところで、この展覧会には企画の初期段階から<博物館工学ゼミナール>に参加する学生が協力してくれている。研究を展示していただく研究者のところへ出向いていって展示内容についてのリサーチを行い、最終的に展覧会を作るところまで皆が協働する。私が初めてこのゼミに立ち会って、学生がリサーチしてきた二十点弱の展示の概要を順番に聞かせてもらったとき、すぐさますべての展示に一貫した統一性の印象を与えることは無理だと感じた。法、医、工、人文社会、理、農、薬学など各分野のいわば最先端を行く研究を一同に会するのであるから当然なのだが、なにしろ<平明>な展示にはとてもなるまい。
そこで展示構成者側がやることは先ず共通した印象を与えるタイトル・パネルを作ることだと考えた。パネルには各展示のタイトルと最短のリード文、アイコンとしての画像を含める。色彩は東大カラーのライト・ブルー。先の章扉や建物戸口のたとえを直截に採り入れ、その大きさや形を実際の扉と同じ紋切り型にしてしまう。どこからどこまでが一つの展示項目なのかということを示す最低限のしるしである。その意味では文章を区切る句読点のような、あるいは文頭の大文字なり字下げに相当する役割を果たさせる。
社会学者のゲオルク・ジンメルは、1909年のエッセイ『橋と扉』において人為(学術研究もそれに含まれるだろう)というものを無限の自然から一定の部分を切り取って閉ざされた領域を作ることであると見なし、自然と人為との間を一方で隔てつつ他方でつなぐ役割を果たすという機能を<扉>の中に見た。そして扉が道具として機能や目的を支えているというだけでなく、「扉の形には、そうした機能や目的が、いわば直接私たちを説得する造形性として凝固している」と述べている。
また展示の配置構成を行なうにあたって、上述のリンチの著書でキーワードの一つになっている<ランドマーク>(景観構成上の目印)という概念も意識した。入口ホールの大地球儀、旧館部突き当りの鹿の骨格標本、そして旧館側から新館展示室を見たときまっすぐ奥の天井吊りの金星模型などを展示空間のランドマークとして配し、来館者の動きを誘う軸を形成する。リンチが言うように、「明瞭な形状をもち、背景との対照が著しく、またその空間的配置が傑出したものであれば、ランドマークは一層見分けれられやすいものとなり」、展示空間のレジビリティを向上させるだろう。
さらに、学術研究の宇宙を象徴する地球のイメージとライトブルーの扉の形象をポスターや図録表紙のデザインにも応用することで、昨今企業イメージなどに関してよく唱えられるヴィジュアル・アイデンティティを多少なりとも展覧会に与えるように試みた。
末筆になるが、本展覧会の空間・視覚構成にあたっては高槻成紀氏をはじめとするワーキング・グループのメンバー各氏から多くの貴重な示唆をいただいた。特に実務面において、博物館の洪恒夫、石田裕美、玉川万里子の各氏、セキオカヒロユキデザインの関岡裕之氏から多大な協力をいただいた。また展示はチームワークであるということを博物館工学ゼミナールの学生諸氏から私の方が学ばせてもらったように思う。
参考文献
ケヴィン・リンチ、『都市のイメージ』(丹下健三・富田玲子訳、岩波書店、1968年)。(Kevin Lynch, The Image of the City, M.I.T. Press, 1960)
ゲオルク・ジンメル、『橋と扉』、『ジンメル・コレクション』(北川東子・鈴木直訳、ちくま学芸文庫、1999年)所収。(Georg Simmel, Br![]() ke und T
ke und T![]() r, 1909.)
r, 1909.)
![]()
(本館客員教授/建築設計)
Ouroboros 第22号
東京大学総合研究博物館ニュース
発行日:平成15年10月1日
編集人:高槻成紀/発行人:高橋 進/発行所:東京大学総合研究博物館