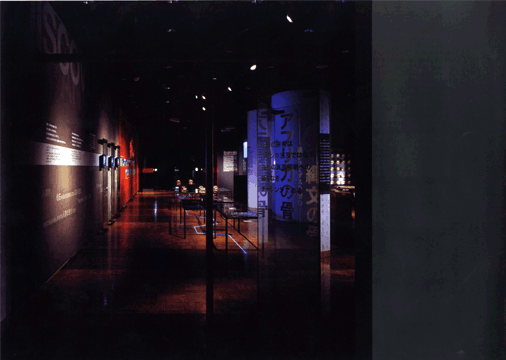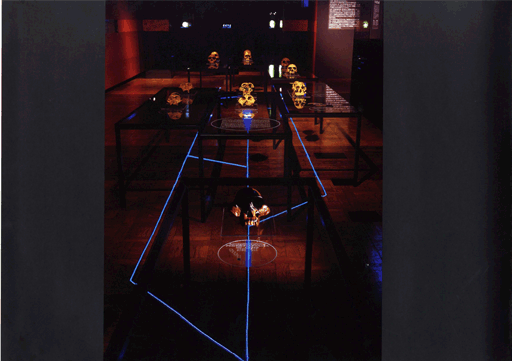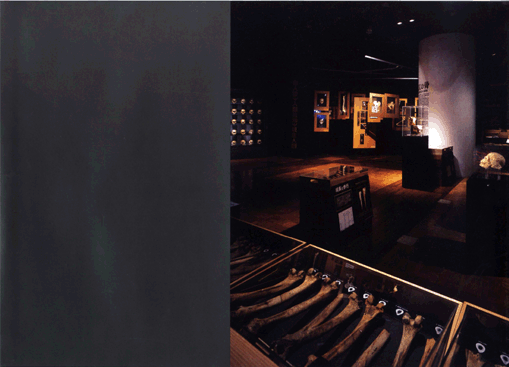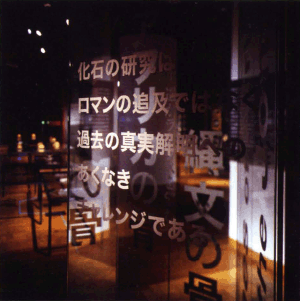▼BRAINSTORMING
▽CONCEPT
▼ZONING
▽PERSPECTIVE
▼学術研究の成果を立体表現
▽展示だからもたせられる付加価値
▼学術とデザイン、双方のポイントを押さえた展示
▽研究室の標本を運びだし、学習する
▼単純にわかりやすいオリジナルの見せ方
▽プロセスが展示のおもしろさを、密度を決める

私はテーマを形にするのが仕事だ。「研究博物館だから研究そのものを展示してもいいのでは」と、企画者はさらりと言うが、これは形にするにはむずかしいテーマだ。
諏訪さんが取り組み、実践している人類学の研究とはどんなものか?初めの頃に、自らが行っている研究の内容、こだわりについて語ってもらった。それを引き金に頭の中に浮かんだものを無責任に落書きしてみた。空間や展示を考える者の性で、どうしても空間的なスケッチになる。
ここからどうしようかという悩みと、取り組み甲斐があるという嬉しさの入り混じる混沌とした中でのスタートだった。
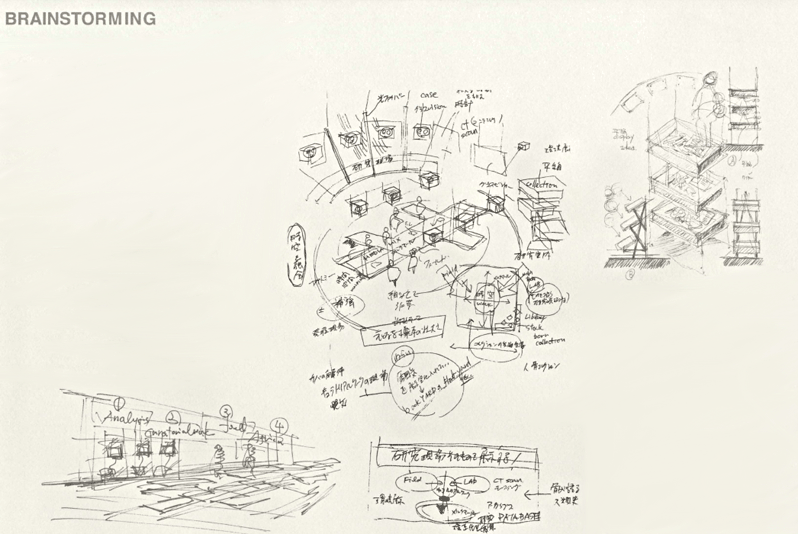
展示物として提示されたもの――アフリカで行っているフィールド・ワーク、発見された化石人骨のレプリカ。当館に収蔵されている、先人の研究者によって収集されてきた膨大な古人骨コレクション。
縄文人骨だけでも相当数ある。これらに対して現在行われているキュラトリアル・ワーク。そこから生まれた成果、等々。大まかではあったが、デザイナーのイメージを広げる具体的なモチーフとしては、有効な素材ばかりだった。
構成もさりながら、骨をどう見せたらおもしろいか。そこからも考えてみる。量があるとは言え、全て骨である。見せ方のバリエーションも勝負どころとなる。今度は何かしらをこちらが返す番だ。投げかけられたモノや情報、イメージから受けたものをかたちにしてみる。
これから、このやり取りを何度か繰り返していく。人類学と展示デザイン。活動する分野の異なる者がひとつのものを創る。これはもしかしたら、ボクシングの試合みたいなものではないかと感じはじめた。
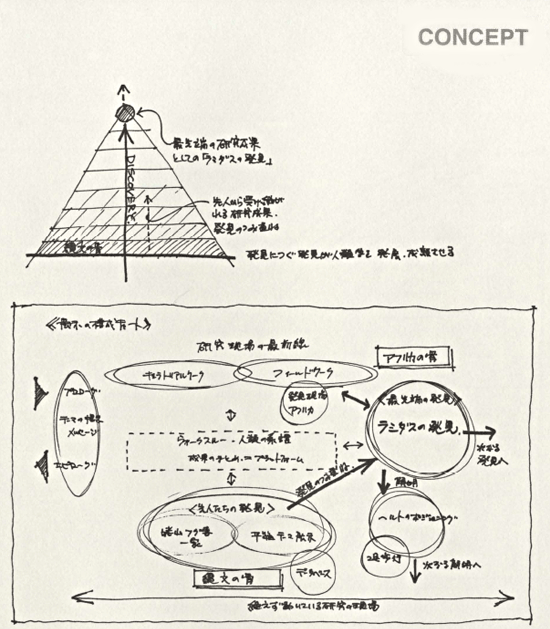
展覧会の仮タイトル「縄文の骨、アフリカの骨」は、諏訪さんから提案された。「骨」で韻を踏んでいるが、一見するとつながりがあるようには思えないタイトルだった。
研究は絶えず動いているものだ。その中で様々な成果が生まれる。人類学における「ラミダスの発見」はその最先端だろう。またその一方で、どんどん成果は積み重ねられる。それを整理し、研究に活かすためにデータベースを構築することも重要なことだという。今回の展覧会は、研究室で縄文人骨のデータベース化が終了したことも展示を実践する要因のひとつだった。ラミダスの発見と縄文データベース。仮タイトルはここに由来するのだ。
この2つは正に研究の成果そのものなので、そのリアリティを伝えることが展示の柱となるし、それにも十分耐えうるものと感じていた。
しかし、まだしっくりとこない。展示は三次元の空間で繰り広げられる。自由度が高い分、その中で何かをしっかりと訴えようとするならば、その「何か」確固たる構成が必要である。そのためにはこの二つを貫く骨太なコンセプトが要ると思った。そう伝えたところ諏訪さんは、石田さんと議論を交わし、「発見―Discovery」をキーワードにしたいと伝えてきた。
これがタイトルの二つの要素を繋ぐものであり、研究をアピールするのにふさわしいという、テンションの高いメールが届いた。たしかに、これならば展示としてのコンセプトが通る。そして、私が描いたコンセプトストーリーはこうだ。「発見に次ぐ発見が人類学を発展、成熟させる。
ラミダスの発見は最先端の研究の成果であり、これも先人から受け継がれてきた発見と研究成果の積み重ねの上に成り立つ。」展示のコンセプトとしてはうまくいく。
だが、展示のインパクトを強めるなら、やはり最先端の「ラミダスの発見」が前面に出るべきだろう。ここが半分くらいのウェイトを占めていいくらいだと思い、伝えた。いつの間にかタイトルが、「アフリカの骨、縄文の骨」に変わっていった。ここまでくると具体的な構成を描くのはたやすい。かねてから聞いていた要素、展示物は、うまく構成の中にはまってくれる。
これまで数本の展示を実行してきた、独特のかたちの、馴染みのある展示室を意識しながら展示構成をチャート化する。
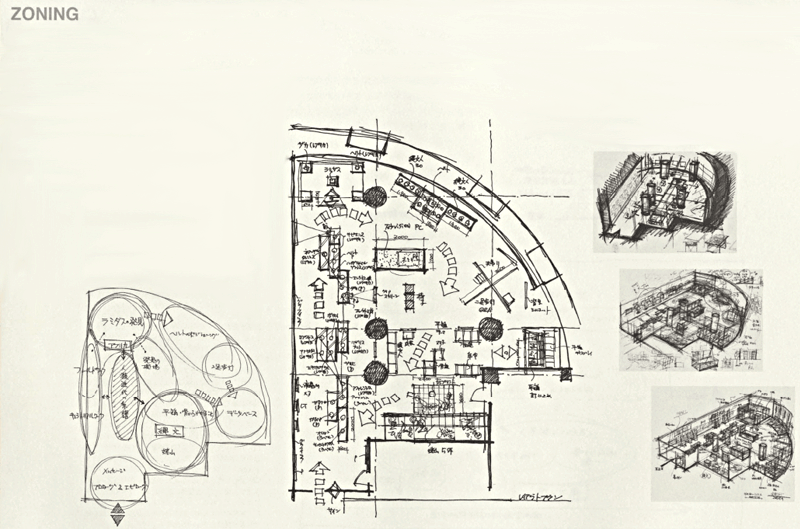
展示は観る人のためにある。観覧者は、おもい思いの興味と行動の仕方で展示と接していく。展示空間に足を踏み入れるその時から、もてなしが始まる。
展示で何かを伝えるためには、観る人を惹きつけるアテンションと興味が高まる練られた内容、そして自分の歩調で接することのできる流れが必要となる。
これらがうまく組み合わさることで、つくり手が伝えたい内容を訴求することができるのだ。その成否はかなり初期に決まるといっていい。
いかに観覧者の立場に立った出来上がりをイメージできるか。それをシミュレートしながら計画を立てられるかだ。その鍵は、ゾーニングと導線計画が握っている。
観覧者の目線、歩調を意識しながら組み立てる、云わば、空間の青図のことだ。コンセプトに裏付けられた本展の展示構成を、三次元の空間にプロットする意識でゾーニングと導線計画を立てていく。
展示物のボリュームとともに、観覧者が目にするであろう光景を意識しながら、展示空間のイメージを固めていく。
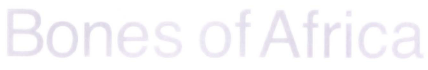
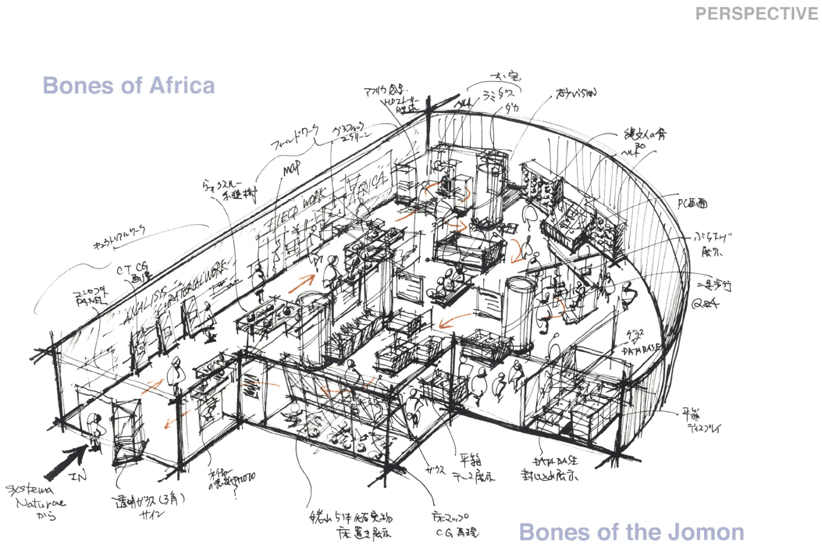
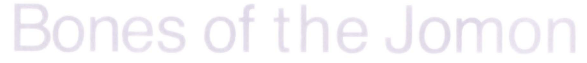
打ち合わせ中に頭の中で描いたイメージをスケッチパースとして形にする。これを見て、こういう形で展示室が展示物で埋まるのかと驚かれた。
今回のテーマ・内容で、はたして展示としカタチになるのか、展示室を埋めることができるのかが心配だったらしい。逆に私は、研究を語る上で必要な標本・素材を見せようとした時、空間に収まりきるかのほうが心配だった。
絵に描いて見せることで具体的なイメージがつかめ、意識のすり合わせもしやすくなる。これでほぼ合意形成が成された。この先の使命は、この膨大でちょっと見単調なモチーフをいかにコンセプチュアルに、なおかつすっきりと見せるかを考えることだった。
一つひとつの展示アイテムに対し気の利いた見せ方を考えることはそれほど難しいことではないが、ここで気を配らなくてはいけないのは、個々のテーマの雰囲気や空気観をどう表現するかにある。
展覧会は、そこに滞在するあいだに過ごす時間、体験する空間が、観覧者にとっていかに印象的なものであるかが重要だ。展示物は実物、映像、写真と様々だが、みな一級品である。これらを引き立たせながら、それに負けない空間デザインを作り上げなければいけない。
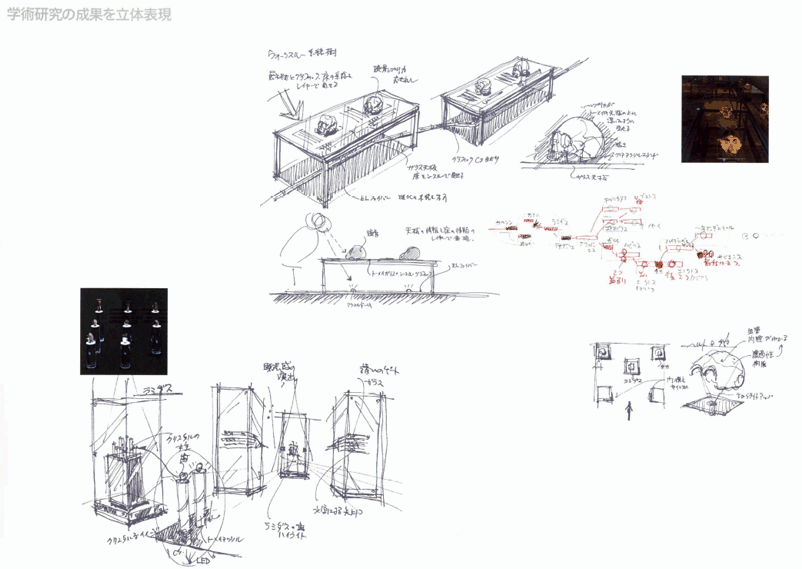
人類の進化の系譜を、標本を組み込んだ立体チャートに展開することを提案。
観覧者自身により時間の流れと進化の流れが追えるような展示を、と考えた。名付けて「人類進化の系譜ウォークスルー」。
床に系譜のライン、ガラス天板に解説、頭骨の標本をレイヤーで組み合わせ、他では見ることのできない複合情報を提供する。
ガラスという素材を活かした見せ方として考えたのだが、標本の固定方法、解説文に抜け感を出す素材選びが難問であった。
だが、このかたちを実現するためには妥協はしなかった。そして、床に施す発光ラインに向けられた諏訪さんの眼差しも、数センチの妥協も許さない。
どこで分岐させ合流させるか、そのポイントをどの位置におくか。学術発表のための図表作りと変わらないこだわり。
これこそ学術と展示デザインの融合表現。コラボレーションのなせる業と実感した。
本展の目玉展示物であるラミダスの歯と下顎骨は、宝物のように見せたいとずっと言われていた。単純な発想であるが、宝物といえば宝石だろう。だから歯を宝石店のウィンドウ展示のように見せることにした。この組み合わせ、ミスマッチかもしれないが意外性を狙ったわけではなく、じっくり観てもらう効果を果たせると判断し迷わず実践した。
人類学の仕事は実に丁寧できめが細かい。微小な標本の扱い方や標本の組み立て作業の繊細さは、我々の仕事以上かも知れない。どうやって内照のアクリル円柱に歯を立たせるか。その方法を考え実行したのは、諏訪さんだった。お願いしておきながら、こちらの描いた絵に近づけるために頑張る姿、そして作業の緻密さには脱帽する。
もうひとつのお宝であるヘルト人とダカ人のレプリカ標本は、透過性のある黄色っぽい樹脂でできていた。よく目にする白いものとは違う独特の雰囲気がある。暗い展示スペースなので、中から光を当てて、際立つように見せることにした。
遊びすぎかと思いきや、人類学的にもそのほうが良いことが判明。内照で内側から照らされることによって、頭蓋の内側の凹凸まで観察できるようになった。透過性の標本ならではの効果だ。学術とデザイン双方の狙いが一致した展示方法に一同納得した。
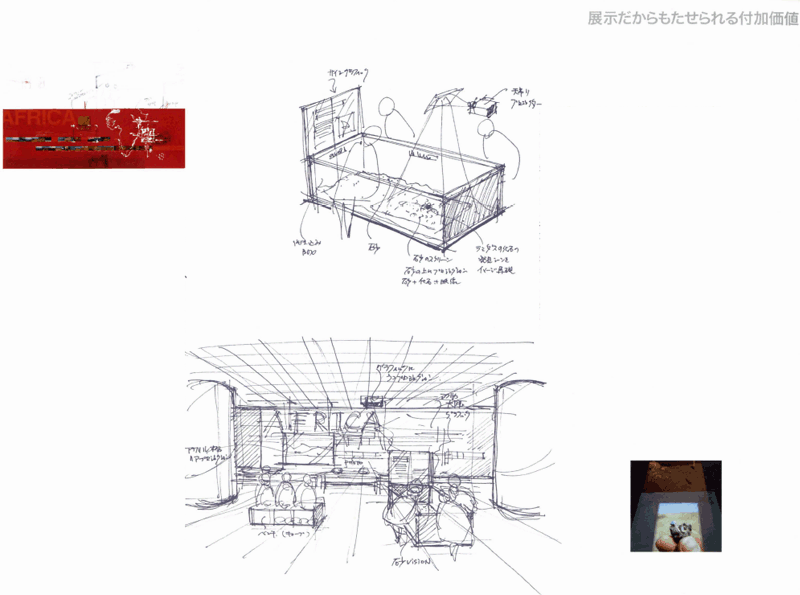
アフリカのフィールド・ワークのコーナーは、オレンジ色の壁にすることは当初から決めていた。アフリカの「暑っぽい」イメージをオレンジで強調したかったからだ。壁面は文字や写真などの情報を伝えるための、解説グラフィックの機能を持たせるのに適している。また、大きな壁は存在自体が演出にもなる。ここでは、オレンジが醸し出すイメージを感じながら、展示の情報を見る環境をつくっていった。この壁は離れたところからも見えがかりとして、空間に雰囲気を与えることができる。ミドルアワッシュの発掘現場を紹介するシアターコーナー、「発見の瞬間」を紹介する砂箱のコーナーは、それぞれの映像を観覧すると同時に、オレンジの壁面が目線に入る位置に配置している。少し距離をおいて見えるオレンジの壁の借景が、アフリカの空間としての統一感を出すことを狙ったのだ。
アフリカのコーナーからは、全てこの壁が見えることになる。この要素のレイヤーの効果は、内容には直接関係ない。空間メディアとしての展示ならではの、付加価値としての仕掛けだ。
壁に盛り込む情報にも色々仕掛けを入れた。グラフィックの壁面に、一見グラフィック情報と見間違えるぐらいに馴染ませた映像をプロジェクションした。動く挿絵のような効果を狙った。アフリカ大陸の地図を地模様に、ラミダスが発見された場所に近づいていくようなイメージのデザインも取り入れた。単に情報を見るだけではない、探っていけるようなグラフィックも展示の面白さだろう。ひとつの壁に多くのことを語らせることができるのは、展示ならではの複合演出効果だ。「なるほど展示とはそういうものか。」これは、この壁を見て発した諏訪さんの一言である。
エチオピアでのフィールド・ワークの話はとても面白い。普通の状況でそれを体験することはできない。あの広大な大地で小さいかけらを探し出す。とてつもない疲労感と絶望感(その根底にあるのはもちろん期待感)の中、作業を続ける。大変である。
このイメージの一端を展示できないかと考えた。ずっと下を向いて探しているのだから、それと同じ下を向いた状態で「発見」してもらいたい。そこで床に映像を映すことにした。なおかつ、現場再現風に表現するために観賞物も素材とし、アフリカの土を運んでくる――のは無理なので、砂に映像を映し出すことにした。
ちょうど大地を切り取ってきたような環境を作りたいと思ったのだ。これはうまくいくかどうか不安があったので、原寸での映写実験を行った。覗き込む箱の高さ、砂への映写状況などを確認する中で諏訪さんが、「目的がやっとわかった。」と言った。スケッチで説明した時点では、これにどんな意味があるのかわからなかったようだ。そこから「箱庭」のリアリティづくりに走ったのは諏訪さんだった。
エチオピアの土や石に似た雰囲気の石を調達してきて自ら砕く。ハンマーも新品だと合わないのでわざと汚し、雰囲気をつける。ここまでくると、もう立派な演出家である。
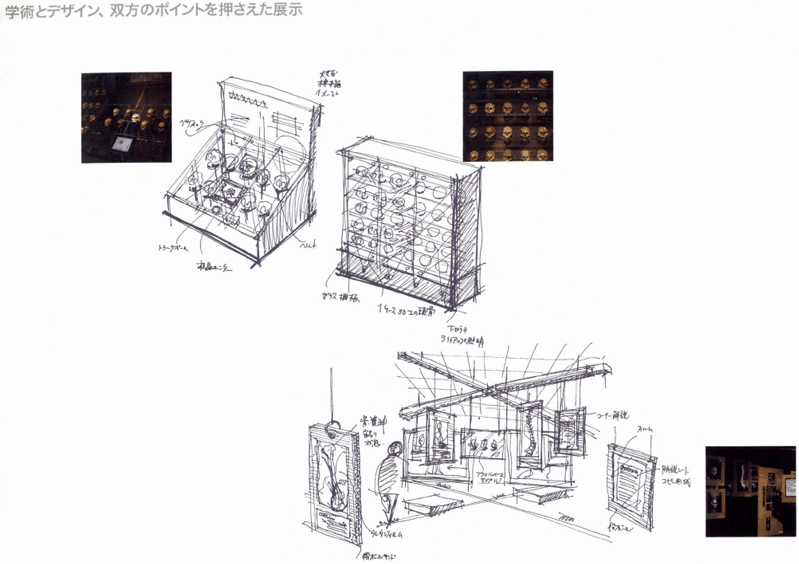
研究のアプローチの一端を展示で紹介する。いよいよ研究現場の営みそのものを扱うコーナーにさしかかった。発見される資料、標本は数が限られている。現場から持ち帰った数少ない手がかりから最大の情報を引き出す。それには比較が大切らしい。私がうんちくを語る立場ではないが、簡単に言うと、既存の標本と比較することで、共通点・相違点を探り、その標本の特性に迫っていくのだ。本展では、ヘルト人を題材にその一端を紹介した。縄文人との比較、現代人との比較などを通して、そのポジショニングを導きだす過程を展示。簡単にするなら、その概念を情報パネルで見せればよいが、館のもつコレクションを公開し、観賞に供しながら情報を伝える必要があるので、ここではやらない。展示するのは縄文人の頭骨。数があればあるほど驚きも迫力も増すだろう。展示の効果が上がるという訳だ。研究においてもこの量は鍵となるらしい。沢山の標本と比較することで、その精度が増すからだ。そういった実態を、展示演出においても実感させる方法を探った。結果、ヘルト人を挟んで可能な限り多くの縄文人の頭骨を並べることとした。
標本の骨をパッキングして、宙吊りにして見せたいと考えた。標本に注目し、見てもらうためのアテンションの加え方を考えて出したアイデアだった。透明の素材で骨を挟み、フレームをまわし、それを目線で見せる。イメージは出来上がっていたが、何を使ってやれるだろうか。標本が痛むようなことはあってはならない。なかなか適当なものが思い当たらない。そんなときに、石田さんが京都でまさにこれという商品を見つけ、買って帰ってきた。ウレタンフィルムという、伸びるうえに強度のある梱包材だった。サンプルを取り寄せ実験する。ディスプレイ素材としては使われ始めているがミュージアムでは初の試みだろう。試してみたら不思議な雰囲気の面白いものとなった。学術チームにも、「こんなの見たことない。面白い!」とかなり受けた。しかし、諏訪さんの面白いと私の面白いは、少し観点が違っていた。
この透明かつ宙吊りにされた標本は、どこの角度からでも骨を見ることができる。こんな見せ方は今までない、ということだった。だから人類学的にもすごいらしい。お互いに満足して採用となる。
ここでこだわった点に、吊ることも考慮に入れた軽い素材、なおかつ簡素な方法で展示効果を出すことだった。そこでフレームはダンボールに、回りは日曜大工的にボルトで止めた。解説文は出力した紙を挟んだものだ。アイデアと素材で効果が出せることを実践したかったのだ。効果は狙い通りだったと思う。この初の実験展示は、製造元のメーカーさんの協力によってはじめて可能となった。この場を借りてお礼申し上げたい。
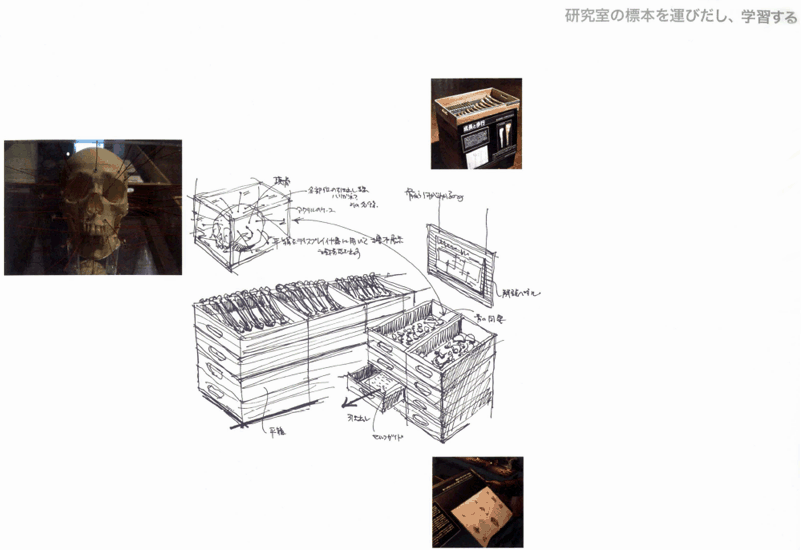
「破片の同定」を扱うコーナー展示。提示された標本は頭蓋骨をバラバラの小さな破片にしたものだった。鍛え抜かれた眼力を持って破片を見れば、頭のどの部分かがわかるのだという。むしろわからなければ、骨を発見することすらできないという。もっともである。この展示は、破片がどこの部位なのかを当てるQ&Aも兼ねていた。答えの情報を記したプリントは、異常に細かく部位が記載されていたが、紙一枚なのでかなりあっさりして見えた。しかし、この「すごさ」に敬意をはらいたい。そこから、とてつもなく変な展示物をつくることを思いついた。それは、正解を示す破片の部位を、教材用の実物の頭蓋を使って立体表現をすることだった。頭から正解に向かって突き出る針。答えとしたらわかりやすいだろうが、かたちにしたらばかばかしい姿だ。だが、「すごい」インパクトは十分に出せるだろう。しかし、これを自分で作ることになったことは計算外だった。飛び込み助っ人の吉田君の協力ももらいながら、世にも奇妙な造形物を完成させたのは、オープン前日のことだった。
ここは展示室か?研究室か?そんな環境で沢山の標本を観察し、骨から読み取れることの多さ、楽しさを紹介するコーナーを作ろうと考えた。一般の方たちは、展示されている標本を見る機会はあるが、標本自体の役割を知る人は少ないだろう。標本は研究の源であり、研究室においての主役である。そもそも、なぜこんなに集めるのか、何を調べているのか、骨が語ってくれることと、語らせ方があることを知ってもらいたいという企画だった。 平箱を展示で大量に使いたいと言ったのは諏訪さんだった。(平箱は、標本を整理・保存するのに昔から使われている木箱のこと。)それは、標本庫の空気感を伝えたいという意図があったのだと思う。ならば、研究を展示化する本展では妙な演出をかけずそのまま見せることが最適な演出方法だろう。平箱を使いながらも、什器の体をなす最低限のアレンジが必要だ。そこで平箱を積み上げ、展示台を作ってしまった。観覧者には、見下げるかたちでじっくりと観察をする姿勢をとってもらう。平箱に囲まれた空間。そこは標本庫の匂いがする。
ミュージアムの展示には少なからず解説が必要だ。解説グラフィックは壁に掛けたり、自立させたり、吊ったりと色々な見せ方をする。解説文を読む時には、それが目的となり、グラフィック自体が展示物のようにもなる。平箱のコーナーは、標本の読み解き方を目的に、骨を見せながらその見方を解説で伝えている。ここのコーナーデザインの特性を考えると解説グラフィックは、サブ的な位置づけがふさわしい。しかし、空間デザインの視点からすると、ここに何かが吊らされるのはふさわしくないように思えた。そこで編み出したのが、モノを見ながら必要に応じて手にとって読める床置きの解説パネル、名付けて「ピックアップグラフィック」である。このかたちであれば、モノと情報を見比べながら、間近に鑑賞することができる。また、展示解説の際には、掲げて見せることでフリップのような力も発揮することもできる。情報と場から生み出されたかたちだ。
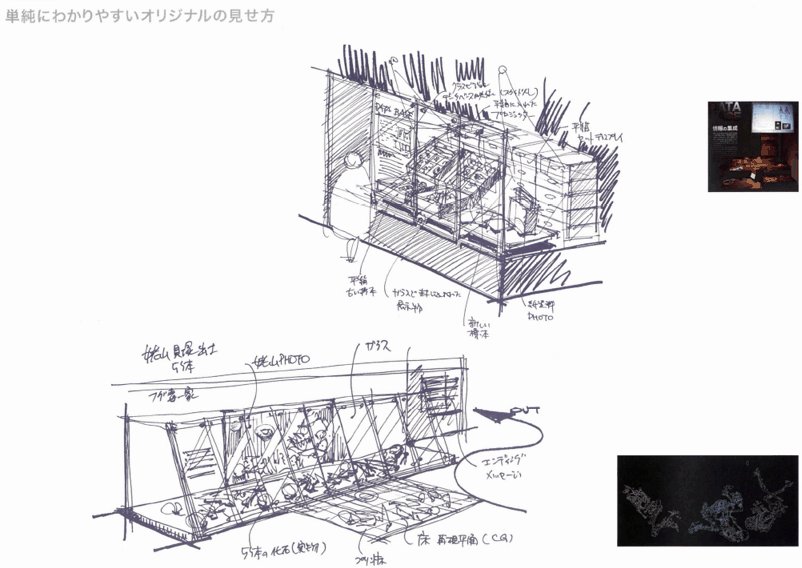
展示の手法にはグラフィック、映像、模型など、様々なものがあるが、それらを合わせて一つのことを伝える類のものは少ないように思う。やるにしても、それらがバラけてしまっているようでは意味がない。縄文データベースの成果コーナーを考える際に、データベースの取り組み方の説明を受けた。雑多な状態で平箱に詰められた標本に、修復をほどこしながら、あるフォーマットに沿って分類・整理する。その「使用前・使用後」のちがいを見せられた。わかりやすかった。そしてそれらは関連資料とともに、コンピューター上のフォーマットで整理され、データとして連動している。理想のデータベースとは何かを語るうえで、そこに必要な材料を全て用い、わかりやすくディスプレイする方法が良いと考えた。様々なメディアをミックスさせるのである。ポイントは、それらの組み合わせ演出が自然に、違和感なく見られることにある。
姥山貝塚の発掘現場の写真を見たときのインパクトは大きかった。五体の人骨が地面にバラバラと横たわった写真。これだけのインパクトがあるのだから、当時発掘した研究者たちはすごい衝撃を受けたのではないか。この人骨を、この写真の人骨とわかるように展示したい。極力現場の臨場感を表現した展示をしたいと思った。それならばその状態で展示するのが自然だろうと同じかたちで床に寝かせ、人が見下げるカタチをとることにした。しかし、現場をそのまま再現してみせるのではなく、標本を際立たせる、展示デザインとしてのひねりを加えていくことにした。
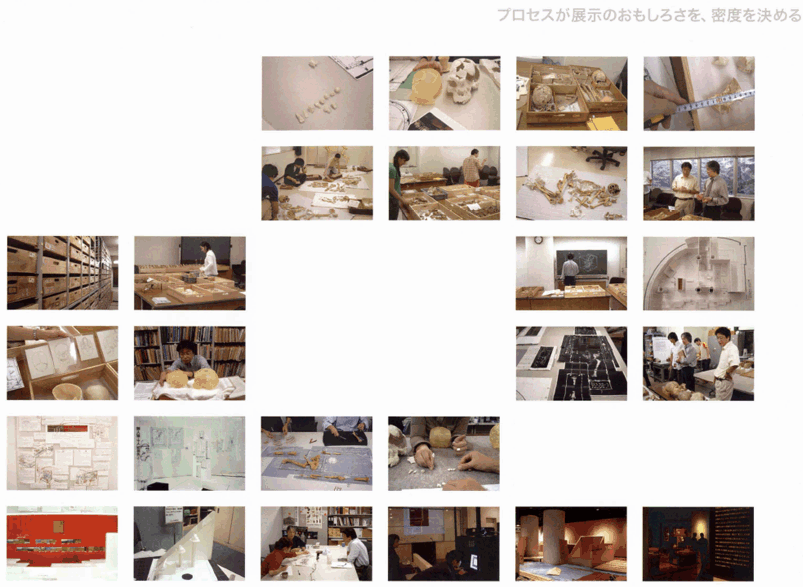
今回の展示づくりを直感的に「ボクシングの試合に似ている」と感じたが、改めてなるほどその通りだなと思った。何故なら、よい打ち合いがされてこそ試合は面白くなるからだ。諏訪さんは人類学の第一人者だ。一方、私はそれとは接点のない、企画やデザインを本業とするクリエーターだ。全く世界の異なる二人が向き合い、一つのものづくりを始めた。はじめは様子を探っていたが、少しずつジャブを打ち、少しわかり始めるとこれはどうだとパンチを打つ。するとそれに思いもよらないパンチが返ってくる。諏訪さんのパンチは強力だ。やり取りの中で、即答できない質問をされ、悔しいので次の日に納得してもらえる答えを用意して持っていったこともあった。ついにはお互いの領分を侵すこともあった。「人類学の研究はこのようなことがポイントなのではないですか」と生意気な突っ込みをしてしまったこともあるし、反対に諏訪さんからこんなデザインがいいのではないかと意見されたこともあった。
そんな、双方全く手の抜かないやり取りを繰り返すうちに、展示の密度や精度は確実に上がっていった。そして、つくり終えて感じるのは、本展は、このやり取りやプロセスが極めて楽しかったということだった。前にも述べたが、展示は一つのメディアだ。つくり手が仕込んで、見る人が自らの感性も介在させながら、何らかの発見や驚き、納得を生み出すことのできるおもしろいメディアだ。また、そういうものであるべきだと思っている。その点で本展は、ボクシングの打ち合いよろしく、作られる過程でかなりの手数が加わり、出来上がっていった。質や出来の良し悪しは観る方の評価に委ねるが、我々が楽しんだこのやり取りが、少なからず展示の中に垣間見られるであろうし、展示を通して感じていただければと思う。もちろん、見応えのある本物の骨を思う存分観賞したり、資料が沢山おかれたミュージアムの空気感を楽しんでいただくだけでもよい。
ところで、ボクシングはボクサーだけでは成り立たない。
レフリー、セコンド、支えるチームが必要だ。この試合を陰ながら仕込み、スムーズに進行するようコーディネートしてくれた石田さん、場の演出をしてくれた制作チーム、無理な要望にも真摯な姿勢で取り組み、盛り立ててくれた諏訪研究室の皆さん、そしてもちろん、よい対戦相手であった諏訪先生に感謝の意を述べたい。