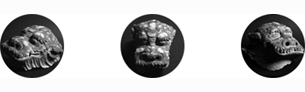
モノを活かす 〜博物館でできること・すべきこと〜 |
|
橘 由里香
東京大学大学院理学系研究科
|
|
広げられた標本は、どこまでいってもグレーとセピア色の世界だった。石、瓦、石、瓦・・・。この標本だけで特別展を行うと聞いて、来館者は退屈に感じるのではないかと危惧を覚えた。机の端から端までの一通りの標本を見た私は、何の気なしに表面がざらざらで、そのくせ光沢がある玉砂利を一つ手に取ってみた。凹凸は想像以上に滑らかで、掌に吸いつくような感触だった。もの言わぬ石。生物ですらない石。けれど、その火ぶくれした姿は、質感とともに確実に何かを訴えてくる。50年間経てなお生々しく残る、硬い岩石が受けた閃光と熱線と業火の痕は、当時の石以外のものへも思いを馳せさせる。 手のひらにすっぽりと納まる小石に底知れぬ重みを感じて、私はあわててそれを標本箱に戻した。最後に無意識に握り締めたのか、掌全体にひんやりとした感触がしばらく残っていた。 一人の科学者に拾われて、今、私たちと対面しているこれらの標本は、時代を超えて何を伝えたいのだろうか。また、新たな事実を語らせることができるのだろうか。 ——それをくみ取ることこそが、過去の試料を託された未来の科学者の使命だ。 私はもう1度、ゆっくりとその黒光りする物体に目を向けた。 LESSON1 未来の科学者に託されるモノ——ヒロシマ・ナガサキの石・瓦より——自分の研究とともに、他人の研究を伝えることに興味を持ったのは、何時の頃からだろうか。研究だけに専念できないヤツという揶揄を感じながら、私は科学が本当に好きだからこそ、自分にしか思いつかない世界でたった一つの研究も、自分ができなかった多数の素晴らしい研究も、同じように世間に紹介したいのだと胸を張れるようになった。そして、研究が生まれた背景や、調査や実験の足取り、集められた標本や研究成果は、時としてそれを成し遂げた本人の肉声よりも、雄弁に語り始めることに気づいていった。 自分の研究をする場合にも、他人の研究を語る上でも、モノ=博物標本は最も重要なものである。博物標本とは、植物、動物、鉱物といったもののサンプル(試料)のみを示すわけではない。研究のアイディアや実験結果を示したノートや研究に使った道具類、その研究者が当時おかれた状況を示す生活品や記録も含む。もっとも、見る人に第一に訴えかけ、想像を駆り立たせる博物標本の華がサンプルであることも間違いない。 大学博物館にある博物標本の利点は、通常の博物館にあるものよりも来歴、情報がしっかりした標本が意図して集められていることにある。現在の、かつての研究者らが、自分の手で採集したり、確固たる信念を持って蒐集したりしたものが大半であるだからだ。モノは、来歴がわからないほうが想像を働かせることができて面白いという見方もある。しかし、来歴や情報があるからこそ、標本そのものだけではなく、その時代や場所、背景まで思いをめぐらせることができるし、蒐集されたときには思いもつかなかったような、さらなる研究が可能となるのだ。 声を大にして言いたいのは、大学博物館の標本は、飾って愛でたり、貴重だと仕舞い込んだりしてしまうだけでは、価値の半分も活かされていないということだ。学問をするために標本がある。それが大前提のはずである。 それでは、私たちは博物館のモノを使って何ができるのか。何をすべきなのか。 まず思い浮かぶことは、現在の技術と自分の持つ手法で多角的に標本を見ることで、蒐集された当時にはできなかった研究をして、その標本に関する情報を補完していくことである。その補完方法の一つとして考えられるのは、たとえば精度があがった現在の機械を使って渡辺の石や瓦を測定し、かつては測定できなかった微量元素から、被爆被害を分析することなどであろう。しかし、それ以上に面白い補完方法は、蒐集者や現在までの科学者が思いつかなかった視点や異分野から、その標本へ学問的アプローチをすることである。たとえば、渡辺が石と瓦にこだわった状況を戦中科学史という観点から捉えたり、放射線測定に使われた土資料を被爆した微生物の研究に用いたりすることである。新たな視点を何度も導入することで、博物標本は展示という観点からも無限に活用できる魅力的な素材となる。 もっとも、収蔵品を用いての研究となると、どうしてもその標本の量は減少するし、研究に使える状態でなければ意味がない。大学博物館へ収蔵品は展示用、保存用だけではないという点を見越しての蒐集が必要であると同時に、多分野からのアプローチにふさわしい適切な保存方法の確立も重要である。たとえば、今後の研究を期待されている本博物館の標本として、全国から集められた500本のボーリングコアがある。しかし、私の持つ知識から思案しても、金属の分析は試料の多少の風化や変質には耐える場合が多いが、含有ガスの分析は試料が長年大気に晒されているだけでその影響を受ける場合もある。バクテリアの研究等の生物的な見地から分析しようとすれば、繊細で適切な保存方法をとった場合とそうでない場合とでは、得られる情報量に大差がつくかもしれない。 また、標本に対する情報の補完と適切な保存は、新たにモノを増やすことにもつながる。本博物館では、展覧会に併せて新規収蔵品展を開催している。今回は、東京帝大工科大学の採鉱冶金学科教授であった平林武のコレクションを遺族からの提供を受けて展示している。寄贈された標本を死蔵させることなく、必ず整理、分類、研究され、展示という形で広く公開されるという積み重ねは、新たな標本提供につながっていくのである。 モノとの出会いは一期一会である。そのとき蒐集しなければ二度と出会えない場合が多いし、たとえば今回の被爆試料でいえば、50年の雨風をしのいだ渡辺の試料は、今、現地に残されているものよりも保存状態がよく、高精度を必要とする研究に適している。後世で利用されることまでを考慮すると、現時点で私たちが考える貴重なもの、希少なものという観点からだけから蒐集するのでは、取りこぼしの危険であるかもしれない。博物標本の蒐集にかかわる未来の科学者は、知識と想像力を働かせることが要求されるであろう。 また、モノは力である。私たちは、通常には、科学者の業績は論文や出版物からしか触れることはできない。それらは情報のみであって質感はない。しかし、その業績を生み出したモノ--たとえば自然科学者にとっての測定したサンプルや、社会科学者にとっての知を構築するための膨大な図書や、人文科学者の感性を刺激した美術品--は、見るものに説得力を与え、新たな知的好奇心を生み出すはずである。 過去を発掘し、現在で新たな情報を付加し、展示によってその意義を広く問いかけ、未来にそのモノを再生させる。 モノを通した過去の研究者とのコラボレーション研究。それが博物館で科学者ができること、すべきことである。 LESSON2 文書のモノとしての力——渡辺のフィールドノート、被爆調査団の文書より——地球科学を専攻する私が言うのは気がひけるのであるが、今回の渡辺に関する標本の中で、もっとも心を惹かれたのは、フィールドノートや被爆調査団の背景を語る紙資料だった。サンプルからは、残念ながら研究者の生活や当時の風情までは伺え知れない。文字には科学者の思想と当時の世相が反映されており、それによって渡辺の研究の意義や世界観をよりいっそう知ることができたからである。 古い文書というのは、そのまま標本として展示されていてもそれなりの意義はある。しかし、詳細を読み解き紹介することこそが、博物館ならではのアプローチにつながるはずである。通常、研究者の業績というのは専門誌に載る論文か専門書という形で発表されるため、難易度が高いものである。また、学会誌などは同分野の人でなければ手に取る機会もないであろう。世の中には面白い研究がたくさんあるのに、ノーベル賞級の研究か、話題性があるとしてマスコミに取り上げられる研究以外は、一般には知る機会すら極端に少ない、というのは甚だもったいないことである。 ある研究を一般に紹介する場合、内容や研究者を身近に感じてもらうための最も良い方法は、自分と同じであると共感してもらうことではないか。サンプルとともに、それを蒐集した際の心情や研究するときの苦悩が書かれたノートや、「早く報告書を出してください」と再三にわたって催促され、前期とそっくり同じく書いた報告書。逆説的であるが、研究者に「人間」を感じてもらうことが、科学へ興味をもってもらう近道であると、私は信じている。 もっとも、理系である私は、文献はあくまで情報であって、それ自体が貴重な資料という感覚はなかなか持てなかった。たとえば、本博物館では昨年(2003年)、小柴昌俊・東大名誉教授が2002年度ノーベル物理学賞を受賞したことを記念して、「ニュートリノ展」という特別展を開催した。展示物の中には、ノーベル賞のきっかけとなった論文「Observation of a Neutrino Burst from the Supernova SN1987A」(Phys. Rev. Lett. 58, 1490 (1987))があったが、掲載誌について、歴史的価値があるのだから博物標本として保存するべきだ、という心境にはいたらなかった。また、他の博物館でノーベル賞を題材にした展覧会が開かれた際には、受賞者の小さい頃の写真が飾ってあったのだが、これについても学術標本とは到底思えなかった。 しかし、「ニュートリノ展」で同時に展示されていたもので、これぞ科学史を伝える学術標本だ、と私が感じたものがあった。当時、小柴研究室の大学院生であった中畑雅行・東大宇宙線研究所教授の計算ノートである。丁寧な字で読みやすく、かつ力強い筆致で書かれた計算式の数々。そのノートからは、計算している大学院生の息づかいまで聞こえるようであった。超新星爆発でできたニュートリノを捉えた機械からはきだされるデータは、それだけでは意味をなさないし、誤差の範囲であると反論されないためにも徹夜に近い状態で必死に計算した、という本人の弁を聞いていたことも理由かもしれない。けれど、これはどうしても多くの人に見てもらいたいし、後世に伝えたい。なぜならば、歴史的瞬間に立ち会った生身の科学者の姿を伝えているものであるからだ。 古文書以外の文書そのものが学術標本となる基準は、サンプル以上に難しい。大抵の文書は電子資料の形で保管して内容を照会できるようにすればこと足りるであろう。しかし、今、研究の場にいる科学者は、機器データや論文以外の部分にも、自分の研究や世界観が現れるということに留意して、それらを大切にすべきではないか。 こんなふうに考え出したきっかけは、「ニュートリノ展」のためのインタビューで小柴名誉教授と対面した際、「自分は全部、頭の中に書くから、ノートの類は一切取らない」という話を聞いて、心底がっかりしたことにある。直接、話を聞くことができた私は幸運であったが、何百年も後の人にも偉大な科学者の背景に直接触れて感じられるモノがあってほしかった。なんて惜しいのだろう、と。 よく考えればかなりおせっかいな心配だな、と我に返り、私はつい苦笑してしまった。 LESSON3 大学博物館と学外との連携——護国神社の狛犬、あるいは浦上天主堂の獅子頭より——今回の特別展「石の記憶—ヒロシマ・ナガサキ」が開かれる発端となったのは、「こま犬 原爆のツメ跡」の見出しで1996年8月6日に載った、毎日新聞の記事である。詳しくは本図録の「現代科学者の目」の稿を参照にしてほしい。要約すると、その記事を読んで覚えていた広島県護国神社の関係者が2002年、ぜひその被爆した狛犬の頭部を見学したいと連絡を取ってきたことで、本展の企画責任者が渡辺の被爆試料を発見し、その試料が今まで展示されていないことを知り、発表することになった。さらに展示のために行った、渡辺の標本に関する新たな研究調査によって、広島県護国神社の狛犬の頭と本博物館内で語り継がれていたものが、実は浦上天主堂の石柱を飾っていた獅子頭の可能性が極めて高いという新事実が発見されたのである。 私は、この一連の流れと結論に、大学博物館とマスコミ・ジャーナリズムとの間には、展示の報道を通して以上の、一歩進んだ関係を結べるのではないかという期待を感じている。それは、博物館側の利点としては、マスコミの取材から始まる企画案であり、マスコミ側の利点としては、取材で得た知識の確認場所としての博物館の存在である。 大学博物館の外部に対しての使命の一つに、大学のアカデミズムの代弁者として、大学の広報活動の一翼を担うことがある。しかし、大学内部からでないとアカデミックな視点は生まれてこないという考えは、一部に根強く残る。今の時代には全くそぐわない論理だ。市井の感覚に長けていたり、取材を通じて様々な知識と人脈を持っていたりするマスコミ関係者が「面白い」と思ったこと、つまり博物館側への取材の対象として選んだことは、その後の研究や展示企画へのヒントとして大いに参考にする価値があるはずだ。また、博物館ならではという人材の育成をすれば、その人材は実社会のみならず、学内でも必要とされるはずである。たとえば、文武両道ならぬ文理融合の博物館に相応しい、文系理系に通じていて、しかも学内でなされている研究に通じている人間や、科学者と科学ジャーナリズムの間に立てる専門家の育成を担えば、それらの人材は大学取材の窓口として、必ずや活躍するであろう。 また、外部に対しての使命をもう一つ挙げるとするならば、私は、開かれた大学の象徴として、展示や公開セミナーなどを通じて社会貢献することをあげる。その中で現在、本博物館が行っていないが、科学者が主導できる活動として、アカデミックな友の会活動と、高校生ボランティアのオーガナイズが考えられる。 博物館友の会というのは通常、年間優待券の発行や特別展の割引、公開セミナーの優先予約などを伴うもので、無料で開放している本館にはなじみにくいものかもしれない。しかし、特典として知の創造に参加する、というのはどうであろうか。たとえば企画展に意見を述べてもらったり、会員に本博物館の収蔵品を使って展示企画を立ててもらい、1部屋分のスペースで実際に展示したりするのである。このような友の会メンバーには、ワインアドバイザーのぶどう柄のバッジではないが、知の創造にかかわっているというバッジを渡したい。 また、本博物館では現在、シニアボランティアの方々が土日の展示説明などで活躍している。この役割を高校生のボランティアにも担ってもらってはどうであろうか。 ボランティアが感じるやりがいとともに、博物館側が生徒の学問離れ、理科離れを食い止めるための教育機関として社会に果たす役割も大きいのではないか。 アカデミックなものというのは、ある意味、仲間内の閉鎖性の中から生まれるものである。しかし、外部との適切なコラボレーションの中でもアカデミックさを失わないというのが、求められる未来の科学者像であろう。 LESSON4 建物展示と青空展示——旧日本銀行広島支店活用計画、護国神社の石灯籠より——旧・広島県護国神社から寄託を受けた被爆した石灯籠の台座が玄関に鎮座し、来館者を迎え入れる。今回の展示は、総合研究博物館の入口の外から始まっている。 建物そのものを標本として展示し、内部も展示会場として活用できる建物展示と、野外に説明版をつけた標本を置き、散歩しながら自由に見学してもらえる青空展示。この2種類の展示方法こそ、大学博物館にふさわしい究極の展示方法である。なぜならば、それは「全学ミュージアム化」を可能とするからだ。 建物展示については、本博物館は被爆建造物である旧日本銀行広島支店の活用方法についての研究をしており、今回の展示でも一部紹介している。 旧日銀広島支店は1936年(昭和11年)に建てられた、鉄筋コンクリート造地上3階地下1階の銀行である。所在地は中区袋町で爆心地から380mに位置するが、堅牢な造りのため、今日までその建物の姿を残している。原爆投下時は、よろい戸を閉めていた1、2階は内部の大破は免れたが、3階を開けていたために全焼し、17人が死亡した。1992年(平成4年)に広島支店が中区基町に移転するまで使用されたが、その後空き家になっており、2000年(平成12年)に広島市指定重要文化財に指定されたため、日銀から広島市に無償貸与されている。この被爆建造物をいかに有用に活用するかについては、平成8年度から大学関係者や地元経済団体、市民団体のメンバーらによる委員会が定期的に開かれている。今までにギャラリーやイベントホール、レストラン等のアイディアが出ているという。 では、本博物館ならではの活用案としては、どのようなことが考えられるだろうか。本博物館には、1876年竣工の東大最古の建物である国指定文化財の東京医学校本館を理学部附属小石川植物園内に保存しながら、それを小石川分館として一般公開しているという活用実績がある。この分館では、建物そのものを展示するだけでなく、内部では学校建築や教育研究器材を展示している。旧日銀広島支店においても、その経験を活かし、たとえば本博物館が「ニュートリノ展」から始めた学外巡回展の会場として利用や、被爆試料を扱った本展を終了後、建物の一角で常設展示することなどが期待できる。 また、身近なところでも、たとえば本郷構内は明治時代から現代までの建築家の作品の宝庫である。土日には、建築愛好家グループが見学している姿もよく見かける。建物内部に中に見学者を入れるのは難しいかもしれないが、建築物の外に説明版を置いてみたらいかがだろうか。それだけでも、立派な建物展示となるのではないか。 さらに積極的に大学構内をミュージアム化するには、構内に青空展示を充実させ、正門に建物&青空展示マップを置くことなどが考えられる。そこには、展示物の内容に応じて、歴史、科学、美術などのモデルコースマップも描いておく。そして、大学博物館には、青空展示の見学後に来れば、それらの展示のさらなる情報を得られたり、今期は大学の歴史的な背景について、来期は学内の科学者の功績についてというように、期間ごとに各コースの内容をクローズアップした説明や展示をしていたりするという機能を持たせるのだ。 もちろん、治安上の問題や研究・教育機関であるという本来の目的を損なわないために、一般に開放できる部分とできない部分の線引きは必要であろう。しかし、特別に能動的にオープンキャンパスデーなどを開催しなくても、構内に散歩にくれば知に触れられるというのは、何よりもの社会貢献になるのではないか。大学は、知のテーマパークになるべきであり、未来の科学者は知のプロデューサーでもあるべきなのである。 LESSON5 巡回展と国際協力展——特別展「石の記憶—ヒロシマ・ナガサキ」より——この展示が始まる少し前、私は大分のショッピングセンターにいた。昨年(2003年)7月から始まった「ニュートリノ展」巡回展の3ヶ所目の会場だ。オープンニングの日とその翌日を見届け、来場者に展示の説明をしたり、地元マスコミの質問に応じたりした。 ニュートリノ展の開催中、「入場無料にすることを条件に、実費だけ負担してもらえば、全国どこででも巡回展を致します」という企画責任者のコメントが新聞に載ると、全国40ヶ所から問い合わせが来た。ぜひ、との声をかけてくれたのは、地方公共団体や公営の博物館、NPO等だ。 巡回展の利点は、学内にとどまらず全国の人に、大学博物館のフィロソフィに触れてもらう機会が持てることにある。また、開館以来、特別展を1年に3-4回というペースで続けている本博物館では、特別展後に解体してしまう展示セットを活かすためにも有用である。これは、極力、学内にある博物標本のみで展示を組んでいる本博物館の特長になるのかもしれない。さらに、一度受け入れてもらえた誘致先は、この先、再び巡回展を行うときの人脈として蓄積される。 もっとも、その際に大学ブランドを過信しすぎて、巡回展に向く題材を吟味したり、巡回展だからこそやらなければならないことを論じる努力を怠ったりすれば、今後の他大学の巡回展進出の妨げにもなりかねない。学内の展示とは異なり、自分たちのやりたい展示というだけでなく、人に受け入れられる展示ということを考えざるを得なくなる。よくわからないけれど、何か高尚そうで、これぞアカデミックな展示だ、と足を運んでくれた人に感じさせるという戦略もたまにはよいのかもしれないが、そればかりでは世間には通用しない。学外に飛び出た場合は、社会貢献という観点を最優先しなければならないという意識改革が必要だろう。 たとえば、ニュートリノ展は、理系の学生でも理解しがたい最先端の素粒子物理学が題材である。子ども向けの施設で巡回展をする場合は、子どもが読んでもわかるようなパネルに作り変えたり、リーフレットを作ったりするような手直しが不可欠となる。大半の誘致先から要望を受ける、博物館関係者によるミュージアムトークや展示説明についても、学術的に正確なことを伝えるよりも、科学者の人となりを伝えるエピソードを中心において語った方がよい場合が大半だ。 また、巡回展の題材は、社会に認知されるまでは、極力、普遍性のある話題を選んだほうが良い。その上で、それを題材としたよくある展示とは違うユニークさをアピールすべきである。たとえば、「被爆試料」が題材の本展示は、人的被害という面が一切排除されていて、無機質な試料から見る人の想像力を駆りたたせるという演出と、たった一人の科学者の目を通して集められたモノから被爆調査に向き合った科学者の姿を浮き彫りにするという視点が、特筆すべき点である。 さらに、形は違うが、大学博物館のフィロソフィを広く発信する場として、国際協力展も考えられる。日本においては、理念を共にする海外の大学博物館との共同研究や展覧会の共同開催、海外においては海外巡回展や本博物館所蔵品の里帰り展示などが考えられる。本博物館では、日本における取り組みについては、オランダのライデン大学と協力して行った「シーボルトの21世紀展」(2003年10−12月)などですでに実績がある。今後はいかに海外に発信し、認知されるかが課題になるだろう。 一人の科学者として、自分の研究にフィロソフィがあり、それを語れることということは、当然のことである。しかし、共同研究が全盛の現在では、個のフィロソフィのみならず、集団のフィロソフィをいかに世界に向けて発信し、認知されるかということが重要になる。大学博物館においても、その理念は、ひいては母体である大学そのものの理念に通じる。この理念を、学外に、世界に広く伝えることができることも、未来の科学者に要求される必要不可欠の才能とされるのではないか。 LESSON6 知のテーマパークとして——東京大学総合研究博物館の様々な特別展より——4章であげた「大学の知のテーマパーク化」は、主として来訪者に向けてのアトラクション開発という観点であった。この章では、研究者に向けて大学博物館が主導する「知のテーマパーク」について考えてみたい。 私の考えるそれは、博物標本を用いた、若手研究者のワークショップとしての企画展である。 似たような試みの先例として大成功した展示として、本博物館で2001年に開催された「真贋のはざま--デュシャンから遺伝子まで」展がある。「コピー」と「オリジナル」の存在様態を世に問うた特別展で、2000年度から01年度前期にかけて行われた博物館工学ゼミの学生・大学院生ら延べ100人以上が企画の検討から展示の組み立て、図録の執筆、広報までを担当して、展覧会の企画から開催までを実際に体験したものだ。 私の考えるワークショップというのはそれとは少し違う。どちらかといえば、2年前から本博物館で開かれている、学内の各研究科で前年に受理された博士論文のうちでユニークな研究を紹介する「学位記展」や、小石川分館で2002-03年に開館一周年を記念して開かれた「MICROCOSMOGRAPHIA-マークダイオンの『驚異の部屋』展」のテイストに近いかもしれない。後者は、学内の学術標本などを、現代アートの奇才・マークダイオンが作品として再構築した展覧会である。 まず、大学博物館の収蔵品の中で、多面的な研究ができそうなモノをテーマに決める。たとえば「ボーリングコア展」でもよい。次に、そのモノの情報を多分野の研究者に提示し、研究アプローチのアイディアを募集する。呼びかける研究者は、学内に限る必要も、国内に限る必要もない。自然科学者に限る必要もなく、その展示の新たな切り口を提案する博物館工学の研究者や、実験展示を研究する美術関係者ら、学際的な分野の研究者にも呼びかけるべきであろう。そして、企画に乗った各メンバーに十分な時間を与えて、学会誌に発表できる程度に高レベルかつ新しい見地が得られるような研究を要求する。展示の組み立てや、図録の執筆も自分たちで担当するのは、「真贋のはざま展」と同様である。展示では、学会発表でも学術論文でも成し遂げられない、「自分の研究についての、3次元的な多面的なプレゼンテーション」を各自が試みる。また、研究成果は通常の学会発表や学術論文という形でも発表し、自分の研究にもっともふさわしい研究発表形態、という観点からも論じてみる。そして、最終的には各自が研究に使ったモノ——サンプルや実験ノート——を寄贈してもらい、展示そのものを標本として大学博物館に保管するのだ。 このワークショップの最も重要な目的は、展示という新しい学術発表形式を提案し、確立させることにある。 現在、研究者にとって業績としてカウントされるのは、学術論文、学会発表、著作、紀要など、2次元的な発表媒体に限られてしまっている。最近はコンピューターソフトの発達で、学会発表にもアニメーションやビデオ映像が取り入れられている。しかし、学術的な発表の場でモノを提示したり、空間を存分に使った発表をしたりというのは、ほとんど聞いたことがない。あったとしても、オープンキャンパスの際の研究室紹介等で一部見られる程度ではないか。 同業者間では、専門的な符牒が通じることや利便性からも、2次元的な発表がふさわしいかもしれない。しかし、展示といった形での研究発表は、符牒の通じない、専門的なことはよくわからない一般の人にも、工夫によっては十分に科学の面白さを伝えることができる。このような発表形態は、研究者にとっての可能性を広げるとともに、社会貢献にもつながるはずである。いやむしろ、これからは「展示」が、科学者にとっての業績のひとつと考えられるような時代にならなければ、いくら言葉だけで科学教育の啓蒙と言っても無駄であろう。 大学博物館での実験的な展示を足がかりに、「展示」という新しい形態の学術発表が生まれれば、それは大学博物館の機能-収蔵、保存、展示、研究、教育-から、博物館の枠を超えたモノが誕生したことになる。このような博物館内部に留まらない提案を、世界に発信し続けることこそが、まさに総合大学の総合研究博物館の役割として相応しいのではないか。 また、そのようなことができる人物が、博物館の未来の科学者として相応しいであろう。 |
| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |