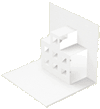
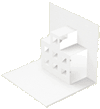
「電子の襞」はモニュメントである。だから、建物を考えるときとはいろいろと違ったモードがある。しかし、決して別の世界の出来事ではない。モニュメントを考えているときに役立つことが建築を考えるときのアイディアを引き出したり、その逆のこともある。「形」という目で見ればわかるというモードばかりではない。そして、この「電子の襞」はこの展覧会の趣旨になっている「幻」、この意味をどうにもはかりかねているのだが、水子の霊の供養祭という意味ならば、まだ死亡宣告はしないでほしいというものである。もっとも、失踪宣告はとうの昔になされていて、そのうちに死亡が擬制されてしまう可能性は否定しない。
モニュメントにも、やはり機能はある。モニュメントというよりはモニュメントを作る側に機能を与えたいという強い欲望がある。たとえば、何かを象徴するため。平和、愛、戦争、自然、権力の具象化、被権力となった怨霊への慰撫などなど。だが、どのみち、物をひとつつくってそれで何かを表していますとか、何か特定のメッセージを読み取ってくださいというのは傲慢にすぎる。もともと、モニュメントを作るということにそうした意味を含めることは無理なのである。
僕はこれらの議論を十分に理解し、モニュメントの無意味性を承知した上で、この「電子の襞」をモニュメントとして創作している。この展覧会の趣旨を私は理解していないが、「幻の建築」はそれが「幻」である所以をさぐってはじめて意味をもつのであろう。建築は表象であるが、建築の作業は表象となる前の政治である。最近、さかんに東大表象研系の哲学思想関係者が建築に言及しているが、その多くは、建築の図面やコンセプト・ドローイングですらその内容を読み取ろうとする基礎的な意思のない、まさに表象的な(いや表層的のまちがいであった)読解しかなしえない点、少なくとも建築家にとっては完全に無価値である。ただ、解釈は無限になしうるのであって、哲学・思想の勘違い、誇大妄想、無知は楽しく、しかも半ば軽蔑をもって評価したい。
話をもとへもどそう。「電子の襞」はしばしばモニュメントにおいてなされるような政治的意図を踏まえた中で依頼され、そして私の中では完全に形態演習となった。「電子の襞」という作品のタイトルは、今世紀の半ば、クセナキスがル・コルビュジエの名義のもとでなしたフィリップス・パビリオンというプロジェクトに付けられたニックネーム、Po塾e Electoroniqueへのオマージュかもしれない。
ところで、なぜ「襞」という言葉を用いたのかを説明しよう。これは、コンピューター・デザインの中の手法としてあらわれたバーチャル・クレイというテクニックに関係している。まちがっても、ドゥルーズのいうような「襞」の概念との関連性があるわけではない。(あるトンマな思想家がこのプロジェクトをドゥルーズの襞の解釈だと早合点して批判していたが、建築を読み取る基礎的な知識がないことを完全に露呈している。哲学・思想関係者の誤読は歓迎するが、作品批評をするときには誤読は自らの無知をさらけだすことを覚悟しておかなければならない。そして、作者に対する誤読の責任が生じる。)
バーチャル・クレイは「電子の粘土」とも言われるように、コンピュータの中に置かれた三次元の立体を、ナイフや接着剤を使うのと同じように、分割や接着をすることができるものである。コンピュータを創作の道具とするには、グラフィック・ユーザー・インターフェースという概念が具体化するまでは、三次元座標に対してその都度、図学的な操作を指示するというステップを踏まなければならなかった以上、なかなか取り付きにくいものであった。それに対して、グラフィック・ユーザー・インターフェース、略して通常GUIと呼ばれるが、GUIでは現実世界の操作を比喩的に模倣することによって作業を容易にする。コンピュータという、すべてをデジタル化することで成立した道具は、デジタルの融通のきかなさを、「もう少し大きく」とか「もうちょっとへこました方がいいかもしれない」というような、デジタルとは相反するアナログな手法によって克服した。
コンピュータを用いた設計手法のどこに真に革新的な部分があるかというと、至極当たり前に聞こえるかもしれないが、純粋に三次元でデザインができることである。これは自明のことのようだが、建築性の導入という場面では少しも当たり前ではない。上から見た時の平面を変更する場合には、その変更によって影響を受ける他の面、たとえば横から見た立面図を、幾何学的に矛盾が生じないようにいちいち修正しなければならない。こうした作業がなされていることは今も昔も少しも変わるところがない。機械設計では干渉チェックと呼ばれる作業である。二次元で見ていたときには問題がなさそうに見えるいくつかの部品の複合した物体が、三次元的に移動した時にぶつかったり、ひっかかって動かなくなるような欠陥を生じないように検討するために必要とされる作業である。干渉チェックも現実世界の三次元と、便宜的に使っている二次元世界のギャップを、人間が懸命に埋めようとする苦心の作業なのである。
ガウディがサグラダ・ファミリアを設計するときに、模型を測定することで様々な投影図を作ったことは有名だが、CADが実用化される以前の自動車設計では、実はまったくガウディの時代そのままである。何分の一かの模型からはじまって、最後は実物大のモックアップを粘土で作り、測定して、膨大な数の切断面に対応する断面図を作成していた。だが、切断面は二次元の連続だから、断面図相互の関係は三次元的には不連続のままであり、その切断面の集合から二つと同じものをつくれることは保証されない。プラモデル・メーカーで一番重要視されるのは、図面ではなくて、金型なのだが、自動車モックアップの話とその理由は共通している。
ところがコンピュータの中の世界では、この困難さは容易に解決されうる。サイコロの面のような二次元投影図を六っつの面に貼ることによってではなく、三次元立体をそのまま検討し、幾何学的に無矛盾な断面図を自在に作成できる。このことは、旧式の建築教育を受けた頭にとっては、意外にコロンブスの卵となる。もっとも、この技術は建設業界という極め付きのロー・テク産業では、実現はまずほとんど不可能といってよい。建設は通り芯、階高という、基準となる指標線から位置関係を決めていくことで全体をつくりだすという慣習の中にいる。コンピュータで成立した物体を、そのまま取り出すことができない以上(工場生産可能な規模なものについては、NC(数値制御)マシンを初めとして光硬化性樹脂など様々な手法が実用化しているが、成型可能な材料に限定され、最終的な製品としてコンピュータのデータを三次元の物体化することは無理がある)、誰にも理解できるような指標軸、つまり作り方を考えださない限り不可能である。
実は、もうひとつ面白いことに私は気がついた。ぐにゃぐにゃで、どんなに複雑な形をコンピューターで作ろうが、我々が日常生活を送っている三次元空間と同じユークリッド空間で矛盾なく成立している。ところが、奇妙なことにコンピュータ空間の中にある物体が、幾何学的には完璧に整合しているにもかかわらず、我々がテーブルの上にのったリンゴを見るような容易さで物体の全体像を頭に描くことができないのである。たしかにコンピュータ図学が採用している透視図法は便宜的な図法であり、肉眼によって得られるイメージと同じではない。だが、どうも理由はそうしたところばかりではなさそうである。
さて、コンピュータの中の物体には幾何学的な一貫性があるわけだから、視点をあちこち変えながら見ていけば、全体がどうなっているか必ず把握できるはずである。ところが、人間の形に対する認識力というのは、これまでの知識の組み合わせを主にしている部分が多くある。たとえば、サイコロといえば、だれもがすぐに三次元の形がどんなふうであるか了承できる。ボールといっても同じである。だが、見たことがないような形、そして比喩を用いてもそれに近い形を思い浮かべられない場合には、純粋な三次元空間ではないコンピューター・モニター上ではすぐに全体像を理解するのはかなり難しい作業になるのである。
「電子の襞」ではまさにこのギャップにもて遊ばれ、遊ばれることを遊んだわけである。
 |
 |
 |