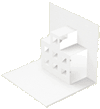
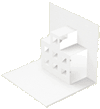
太平洋戦争開戦間近の昭和15年5月29日、陸軍京都第16師団長であった石原莞爾は「人類の前史終らんとす」と題する講演をおこなった。この講演は、今日『最終戦争論』として知られているものである。この中で石原は、古代ギリシャ・ローマ時代から「第二次欧州大戦」にいたるまでの戦争の歴史を概観し、「戦争発達の極限に達するこの次の決戦戦争」は、全国民が参加する国家の総力戦であり、この戦争の後、戦争は不可能になり、戦争は無くなる、つまりそれは最終戦争であるとした。石原の説明は次のようなものである。「戦術の変化を見ますと、密集隊形の方陣から横隊になり散兵になり戦闘群になったのであります。これを幾何学的に観察すれば、方陣は点であり横隊は実線であり散兵は点線であり、戦闘群の戦法は面の戦術であります。点、線から面に来たのです。この次の戦争は体(三次元)の戦法であると想像されます。[中略]その戦争のやり方は体の戦法即ち空中戦を中心としたものでありましょう。われわれは体以上のもの、即ち四次元以上の世界は分からないのです。そういうものがあるならば、それは恐らく霊界とか、幽霊などの世界でしょう。われわれ普通の人間には分からないことです。要するに、この次の決戦戦争は戦争発達の極限に達するのであります。」
点から線、面への戦法の歴史的変化は、傭兵と国民皆兵の違いといった社会的要因と同時に、鉄砲や機関銃の登場といった軍事テクノロジーの観点から説明されている。そして、究極の「体(三次元)の戦法」は、「無着陸で世界をぐるぐる廻れるような飛行機」と「一発あたると何万人もがペチャンコにやられるところの」破壊兵器という二つのテクノロジーによって実現するという。石原は当時すでに核兵器の可能性を認識していたようであるが、こうした最終戦争まで「余りに短いようだが」三十年内外だと予測していた。しかし、この講演からわずか五年の後、「私どもには想像もされないような大威力の」破壊兵器が人類の頭上で炸裂したのだった。
コンピュータは昔も今もただの計算機である。しかし、その計算結果をどのように人間にとって意味あるものに変換して示すか、すなわちコンピュータの出力にいかなる表現を与えるのか、という側面からみてみると、その出力表現形態の変化には目をみはるものがある。コンピュータを用いた情報表現のテクノロジーは、「体の戦法」へむかっているのである。サイバネティック・オートマトン、すなわち「ロボット」も重要な出力装置だと考えられるが、ここでは主に人間の視聴覚に対応した出力表現形態についてみていくことにしたい。
1833年、英国の発明家チャールズ・バベッジは汎用計算機の着想を得た。コンピュータの歴史を綴るすべての書物の巻頭をかざる「解析機関 (Analytical Engine)」である。この機械は今日のコンピュータの特性の多くをすでに備えていた。入力・演算・記憶・出力の4つの機構をもち、プログラムで制御するようになっていた。機械は大規模なもので、蒸気機関で駆動する。しかし、マホガニーと真鍮ではどうしても作り出すことができなかった。世界で最初の汎用電子計算機がつくられる100年以上も前のことである。解析機関は、50桁までの正確な加算が可能で、計算結果はバベッジ自ら設計した自動植字機から印刷されるはずであった。
米国国勢調査局に勤務するヘルマン・ホレリスは、膨大な統計計算のために電気作表機を発明し、1890年の国勢調査に間に合うように実用化した。特許をとったホレリスは会社を起こし、この会社は後に他の小さな会社と統合されIBMになった。この機械は穿孔カードのデータを電気的に読取って集計するのだが、その結果はずらりと並ぶ40個のダイアル式の計器に表示される。一日の終わり、係員は、針の指す数値をひとつひとつ読取って、紙に手書きで記録し、今度は指で全部の針をゼロに戻していった。計算結果が自動的に紙に印刷されるようになるには、1915年のジェイムズ・パワーズによる印刷作表機の発明を待たねばならなかった。
その後、いろいろな人がいろいろな発明をし発見をして、1946年、ついに世界で最初のデジタル・コンピュータが運転を開始した。ENIAC(Electoronic Numeric Integrator and Computer)である。開発の主な目的は、砲弾の弾道を計算することであった。完成は戦争に間に合わなかったけれども、ENIACで最初に実行されたプログラムは水素爆弾の設計のためのものであった。コンピュータは軍事テクノロジーとして産声をあげたのだ。
この後、コンピュータはどんどん性能を上げ、軍事的な目的に限らず、様々な目的のために利用されたが、その出力の表現形態はといえば、数値と文字だけであった。出力装置はラインプリンタ以外考えられなかった。それで十分だ、と皆思っていたのである。
たとえば、毎月一万人の従業員の給与支払伝票を作成する、というような仕事の場合、まず私は必要な従業員のデータと、その処理の手続を記述したプログラムを用意する。次いで、これらを穿孔カードに記録する。そのカードの束をコンピュータのシステム管理者に渡す。私には直接コンピュータを操作する資格がないからだ。そして何時間か、あるいは何日か、ともかく待つ。その間、私には何もすることがない。やがて、プリントアウトされた伝票が届く。完璧な一万人分の伝票だ。もし、この作業を人間がやっていたらどのくらい時間がかかるかわからないし(一ヶ月じゃ無理かもしれない)、ミスも多いだろう。その点、コンピュータは早いし、正確だ。コンピュータって素晴らしいなあ、と私は思う。こうしたデータの処理の方法を「バッチ処理」という。バッチとは「ひと束の」という意味である。ひと束のデータ(文字どおり穿孔カードの束)をコンピュータに入力し、プログラムどおりに処理してもらい、結果を得る。途中経過などどうでもよい、欲しいのは結果、つまり印刷された伝票だけなのだ。
こうした状況を打ち破ったのは冷戦である。核攻撃の可能性に対応するため、北米大陸の防空システムを用意する必要があった。防空司令部は、敵の爆撃機がこちらに向かってきているのかどうかを判断し、その航路を予測し、迎撃戦闘機に適切な指令をださねばならない。それは時間との闘いである。敵機は刻一刻と近付いてくる。そのためにはレーダーや無線から集められた大量のデータを一瞬で処理しなければならない。刻々と変化する状況にリアルタイムに対応する高速処理が可能なコンピュータが必要だ。そしてそれ以上の難問は、コンピュータ処理の結果を人間が理解できる形ですばやく表現しなければならないということだった。もたもた紙に印刷している場合ではないのだ。
計算結果のリアルタイムな表現、という課題に答えたのは、ブラウン管を使ったグラフィック・ディスプレイであった。この新しい防空システム“SAGE”を操作した軍人たちが、情報をディスプレイで見た最初の人々となった。1958年のことである。
穿孔カードとラインプリンタを用いた従来のバッチ処理と、キーボードとディスプレイを用いたリアルタイム処理とでは、コンピュータと人間の関係はまるで違うものになる。バッチ処理で得られた結果、たとえば給与伝票は、いかにもコンピュータが苦労してつくりあげた「アウトプット」であり、最終成果物だと感じるけれども、キーボードからの入力に対応してリアルタイムに変化しながらグラフィック・ディスプレイに表示されていく情報はずっと直接的に感じられる。この「打てば響く」感じを、SAGEの開発に関っていた実験心理学者J.C.R.リックライダーは、「インタラクティブ(対話型)・コンピューティング」と呼び、軍事利用だけでなく、もっと日常的な仕事にも使えると考えた。そして1962年ごろ、リックライダーに見いだされた若い研究者アイバン・サザランドが「スケッチパッド」と名づけられたコンピュータ・グラフィックス・システムを開発した。このスケッチパッドが本格的なコンピュータ・グラフィックスのはじまりとされている。
ブラウン管のディスプレイ装置が、リアルタイムでインタラクティブでグラフィカルな、まったく新しいコンピュータ像をもたらしたのである。コンピュータは、最終成果物を吐き出すだけのブラックボックスではなくなった。リアルタイムなフィードバックを繰返しながら処理を行い続けるインタラクティブ・コンピューティングによって、私たちはコンピュータで「体験」をするようになったのだ。その端的な事例はコンピュータ・ゲームである。徹夜でゲームにはまったとしても、なんの成果物が手元に残るわけでもない。私たちはただひたすらコンピュータからのフィードバックの連鎖を体験するばかりなのである。
さて、SAGEから30年と少しを経て、1997年の今日、私はこの原稿をコンピュータで書いている。キーボードからの入力は、まあリアルタイムと呼んでもかまわない速度で処理され、ディスプレイに文字として表示される。ディスプレイは今でもブラウン管だが、1670万色以上を表示でき、繊細な写真や、簡単なアニメーションも映し出すことができる。
計算機の出力情報の表現形態を見ると、ダイアル式の計器からラインプリンタになりグラフィック・ディスプレイになったのである。これを幾何学的に観察すれば、計器は点でありプリンタは線であり、ディスプレイは面の表現である。点、線から面に来たのである。この次の表現形態は体(三次元)の表現であると想像される…。
もちろん、これはもはや想像の話ではない。何も最先端のバーチャル・リアリティ技術についてのレポートを読むまでもなく、私たちが日常的に使っている普通のパーソナル・コンピュータも、すでに三次元空間に情報表現の枠を広げようとしはじめているのだ。
もっと大きなディスプレイを使いたい、と、ほとんどすべてのパソコン・ユーザが願っているだろう。価格や置き場所といった問題さえなければ、ディスプレイは大きければ大きいほどいいに決っている。こうした気持ちは、何もCADやCGを使う時だけでなく、文章を扱う時にも感じる。まさに今の私がそうで、執筆中の原稿(この文章)、昔書いたメモ、CD-ROMの辞書、WWWのブラウザーなどなど、たくさんのウィンドウが滅茶苦茶に重なりあっていて、何かする度にいちいちずらしたりしている。もっとたくさんの情報を一度に見渡せるようにしたい。
しかし、なかなか簡単に大きなディスプレイを用意できないのが現実であるから、そういう時は、プリントアウトして、机に広げたり、壁に貼ったりする。こうしたプリントアウトの使い方は、バッチ処理で給与伝票を印刷するというのとは、まったく異なるものだ。私たちは、パソコンのプリントアウトやコピーやファクスなどの(場合によっては雑誌や書物なども含めて)印刷された紙を、一時的なディスプレイ装置として使いはじめている。それは軽く、電力が要らず、どこへでも持運べて、用が済んだら気軽にリサイクルボックスで放り込むことができ、しかも解像度がかなり高い、非常に便利なディスプレイ装置である。論文執筆の佳境を迎えた研究者や、重要なレポートを書上げようとしているビジネスマンは、往々にしてこうしたディスプレイ装置でつつみこまれており、ほとんど繭のような状態になっている。冗談ではなく、これは情報の表現形態が三次元空間に展開し、人間をつつみこむ環境となりはじめていることの、プリミティブな事例なのだ。
三次元空間として、つまり人間を内包する環境として、コンピュータの出力情報を表現し、人間の体験を直接コントロールしようというのが、バーチャル・リアリティである。バーチャル・リアリティを実現するための出力装置には大きく2種類ある。ひとつは、体に直接装着する装置で、ヘッド・マウント・ディスプレイ(これを初めてつくったのは、スケッチパッドを開発したサザランドである)がその代表だが、この原理は19世紀半ばからある立体写真と同じで、両目の視差を利用して立体的な視覚を得ようというものである。もうひとつは、部屋のように大きな装置で、内部に直接人が入るものである。この部屋タイプの代表は、MITのメディアラボが1980年代に研究していた「メディアルーム」や、1992年にイリノイ大学のグループが発表した”CAVE (Cave Automatic Virtual Environment)”などがある。メディアルームでは正面の壁、CAVEでは前左右上の四面の壁が、それぞれ全面ディスプレイになっている。要するに、ものすごく大きなディスプレイでぐるりと人を取囲もうというものである。
そして、どちらのタイプの装置を使うにせよ、利用する人間の動作に鋭敏に反応すること、すなわちインタラクティブであることが、バーチャル・リアリティが利用者に生々しい「体験」を与えうるかどうかの要である。さらに、視覚だけでなく、音や匂いや肌触りや振動なども動員し、人間の全感覚に訴えて、「空間」を表現し「体験」をもたらそうという試みが続いているのである。
バーチャル・リアリティによる三次元空間的な情報表現形態の重要な特性は、これまでにつくられたあらゆる表現形態を内包することができるという点である。計器も作表機械もグラフィック・ディスプレイも、なにもかもひっくるめることができるのである。それはまさしく「体の戦法」であり、情報表現テクノロジー発達の極限なのだ。
バーチャル・リアリティは、これまで開発されたあらゆる情報表現形態をなにもかもひっくるめてしまうテクノロジーである。しかし、当然のことながら、バーチャル・リアリティは、単なる文字や画像の表示とは比べ物にならないコンピュータパワーを必要とする。いつでもどんな情報でも空間的に表現するのが最適とは限らない。これは単にコストの問題ではなく、過剰な表現は混乱をもたらし、理解を妨げもする。時と場合に応じて、その都度適切な表現形態が選ばれなければならない。
WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)は、限られた転送速度と課金というはっきりとした尺度をもつことによって、過剰で無駄な情報に対する違和感を顕在化させた。長い時間をかけて高い課金を払って転送されてきた画像が、無闇に精細な企業のロゴであったり、やけに凝ったイメージマップであったりして、腹立たしい思いをした経験は、WWWを一度でも使ったことがあれば誰にでもあるだろう。もちろん「今月のプレイメイト」のためには絶対にフルカラーの精細な画像が必要である。しかし、どんなにバーチャル・リアリティの技術が進んだとしても、かなりの情報は文字と簡単な画像程度で十分伝えうるのではないだろうか。
にもかかわらず、何事かを三次元空間として表現しなければならないとすれば、それは何か。コンピュータの「体の戦法」は何にむかっているのか。
この問いは、石や木や鉄を用いて物理的に三次元空間を構築し、人間を内包する建造環境を築きあげることによって何事かを表現することに営々と関ってきた建築家にも、突付けられている難問である。到底簡単に答えられるものではないが、以下に粗描を試みたい。
オペレーション・リサーチや人工知能の試みは、コンピュータを抽象的・形式的・論理的に扱う方法を突詰めようとしたものであるのに対し、バーチャル・リアリティは、より具体的・身体的・感覚的な表現を指向するものだ。それは論理的な手続を一気にジャンプして、様々な事柄を一挙に即座に把握させようとする。それは思わず身震いするような体験をもたらす。それは感動にかかわっており、人間の欲望に直接接続される。バーチャル・リアリティはまだまだ未熟な技術であるけれども、人間の想像力は、解像度の粗さや反応の鈍さなどの制限を簡単に乗越えてしまう。「たまごっち」の死を、私たちは心から悲しむことができるのである。
バーチャル・リアリティによって、まったく新しい空間のイメージに出会える可能性に胸を脹らませることもできよう。しかし、ゲームデザイナーの島田敬介が「ゲームの中では城は城に見えなければならない」と指摘しているように、陳腐で安易で貧困なイメージが拡大再生産される不毛な世界に陥る可能性も低くはない。まず、ほとんどが「クソVR」になるとみて間違いないだろう。
自然環境はつくることができない。都市や庭園や建築といった建造環境をつくるのも非常に困難である。だから、空間を表現に用いることは、ずっと権力に独占されてきた。バーチャル・リアリティは、建設の物理的困難さというタガをはずす。空間による表現を権力の独占から解放するのである。しかし、それは必ずしも薔薇色の未来ではない。空間的表現によって解放された身体的情動はゲリラ化し、暴力や差別と容易に結び付く危険を孕んでいる。これは建築や都市が抑圧と支配のための権力装置であったことの裏返しなのだ。
バーチャル・リアリティは、ダイアル式の計器やラインプリンタにはじまったコンピュータの情報表現形態の発展の極限にあるものであり、三次元空間を直接表現する。表現力の拡大を無邪気に喜んでいられた時代は終ろうとしている。問題は表現の形態ではなく内容そのものであり、それをいかにデザインするか、が問われている。私たちはすでにコンピュータの中の空間を生きはじめているのだから。
参考文献
石原莞爾『最終戦争論』石原莞爾選集3、たまいらぼ、1986
ハワード・ラインゴールド『思考のための道具』栗田昭平監訳、パーソナルメディア、1987
ハワード・ラインゴールド『バーチャル・リアリティ』沢田博監訳、ソフトバンク、1992
The Office of Charles and Ray Eames『A COMPUTER PERSPECTIVE 計算機創造の軌跡』和田英一監訳、アスキー、1994
日経アーキテクチュア、1997年3月10日号、日経BP社
 |
 |
 |