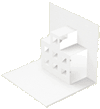
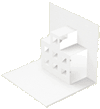
I
バーチャル・リアリティ(Virtual Reality)という概念は、すでにわれわれの身の回りにも押し寄せてきている。つぎつぎに画面を切り替えながら建築の細部にまで連続的に検討を加えられるシステムや、眼鏡と手袋をはめることによって、画面のなかの部材を自分で組み立てられるシステムなどが、すでに身の回りに現われてきつつあるからだ。建築は身体のすべてを取り込んで存在するものであるから、こうした仮想現実の提示装置によって極めて有効に検証され得る分野だと考えられる。バーチャル・リアリティのデモンストレーションに、建築的な体験装置がしばしば現われるのも、そうした理由によるのであろう。だが、バーチャル・リアリティとリアリティとのあいだの違いはどこにあるのか、そしてその違いはどれほど本質的なものなのかを考えることは、建築とは何なのかを考えることに通ずる作業になるであろう。
レンズが結ぶ像に実像と虚像とがあることは、中学校の理科で習うからよく知られているが、虚像とはバーチャル・イメージ(Virtual Image)の訳語だと知れば、バーチャル・リアリティ(Virtual Reality)という概念もそれほど新奇な概念ではないらしいという気になってくる。因みに実像とは、リアル・イメージ(Real Image)である。それならば数学でいう実数と虚数は何なのかを調べてみると、実数はリアル・ナンバー(Real Number)だが、虚数はイマジナリー・ナンバー(Imaginaly Number)というのだと気づく。イマジナリーとバーチャルの違いはよく説明できないが、バーチャル・リアリティ(Virtual Reality)の概念がイマジナリーなものではない、つまり想像力上のものではないことだけは感じられる。だが、バーチャルな世界とリアルな世界との関係はどのようなものなのだろうか。そもそも世界は何からできあがっているのだろうか。
II
権力をもった人間にとって、世界を手中に収めることは夢のひとつだった。古来、国王は国土を保持しそれを拡げたがったし、諸侯は領国を拡大したがった。そして士太夫にとって領地を安堵されることは、封建社会にあっては発言権を与えられる基本的条件だった。これはみな、さまざまに異なる位階においてであれ、不動産を保有することである。世界のすべてではなくとも、世界の切れ端を自らの意のままにすることが、いきがいとなることを意味していた。土地こそ世界の実体だからであろう。
そうして保有される土地は、何らかのかたちをもつ。つまりは実体である。何の意味もない、単なる実体としての土地を持ったときには、ひとは何とかしてそこに意味を与えたいと思う。実体は何の意味もなく実体として止まることはないものなのだ。庭園は、そうして意味を与えられる土地のありかたの典型を教えてくれる。ローマの五賢帝のひとりハドリアヌス帝が、ローマ郊外のティヴォリに営んだ広大な離宮は、この皇帝が生涯に亘って旅した世界中の思いでの土地をその庭園のなかに写したものだった。例を東京に求めれば、駒込の六義園が思い浮かぶだろう。五代将軍徳川綱吉の寵臣柳沢吉保が、和歌の名所を八十八境として構想し、それをちりばめて作り上げたのが六義園だからである。もっとも吉保自身は、この構想を練っているうちに八十八をこえる名所の写しを作り上げてしまい、後の世のひとびとは伝説の八十八境が八十八として完結していたはずだと思い込み、逆に後世の人々によって八十八境が新たに選び直されてしまうという皮肉を生むことになるのだが。これは実体としての庭が、現在の言葉でいえばフィクションを備えるに至っていることを意味するだろう。
庭園を作り上げるための技法には、いくつかの定石がある。日本庭園の場合には借景と縮景、見立て、写しなどである。借景は庭園の外部の景観を庭越しに取り込んで、庭園が境界を越えてはるか遠方にまで伸びていって、外部と一体となっているかのごとき印象をつくるものである。縮景は、庭園のなかにつくる岩や樹木を、実際のスケールより大きなものであるかのように見做す手法である。これによって小さな池の磯辺が、海辺の風情を漂わせることになったりする。見立てや写しの手法も、縮景を応用したり、部分をもって全体を暗示させたりしながら、庭園のなかに外の世界の名所や景色を取り込むものである。
したがって庭園のなかに、われわれは物理的な敷地の広さと形状を越えた世界を見るのである。庭園がこのように庭園そのもの実体を越えて拡がるのは、そうして生み出される世界がわれわれの連想を喚起するからである。こうした事情は西欧の庭園においても認められるもので、英国の風景式庭園では、敷地の境界が解かってしまわないように、境界近くには樹木を不規則に密集させて曖昧にしたものであるし、庭園とその外側にひろがる牧場を、あたかも一体のものであるかのごとくに見せるために、ハーハーとよばれる匿し垣根を考案したりしている。透視図の原理を逆に用いて、遠景を近くに見せたり、あるいは遠景を実際以上に遠くに見せたりするための工夫も、しばしば試みられた。
このようにして生みだされる庭園は、世界の写しという性格をもつことになるのだが、それではその写しは世界そのものであろうか。無論そうではない。写しとは文字通り写されたもの、「写像(mapping)」ではある。しかしながらその「写像」は、現実の世界に対して正確な比率で一対一に対応するわけではない。現実の世界が拡大されたり縮小されたりし、同時にそれが歪められたり肥大化したりして、庭園のなかに写し込まれる。そして一旦庭園のなかに写し込まれた世界の「写像」は、世界の時の流れとは異なった、庭園内の時間の流れのなかを生き始める。われわれが歴史的な庭園のなかに、江戸時代の時代精神を見いだしたり、あるいは東山文化の香りをかいだりするのは、庭園のなかに、時代から切り離されて保たれつづけた時間を感じ取るからである。庭園は現実の世界を特別の手法によって写し込み、それを現実の時間とは異なる時間の流れのなかに保ちつづけ、世界とは二重の意味で異なった「写像」を生み出すのである。それは世界のなかの世界といってよいものなのだろうか。
こうしてわれわれは、世界のなかの世界のもつ意味を、場所と時代を軸にして考ええることになる。それはバーチャル(virtual)な世界のひとつと考えられるものなのだろうか。バーチャル・リアリティを仮想現実感と翻訳して考えるかぎり、庭園のような世界のなかに封じ込められた時代と場所は、仮想現実と呼ぶにはあまりに生々しい。そこには確実に現実の断片、世界の切れ端が存在しているからである。
III
それではここで例を庭園以外の領域に求めてみよう。連想性の強い品、時代と場所を越えてある種の世界を保ちつづける品は、遺品(Relic)と呼ばれる物の世界にはしばしば見いだされる。というより、時代と場所を越えてある種の世界を保ちつづける品を、遺品と呼ぶのである。遺品には宗教的なものもあるが、そうでないものもある。たとえば茶道の世界の大名物に、「つくも茄子」という茶入れがある。この茶入れはもともとは中国伝来の茶入れであり、足利義満が戦場に行くときも持っていったというほどに愛した品だった。これが足利義政、山名政章、村田珠光、三好宗三、浅倉太郎左衛門、小袖屋某、京袋屋某、松永久秀と伝えられて、織田信長の手に入った。信長はこれを本能寺にも持っていったらしく、この茶入れを用いた茶会を催した数時間後に明智光秀に襲われる。茶入れはこの事件の渦中からどうやら運び出されたらしく、やがて豊臣秀吉の所持するところとなる。これが息子の秀頼に伝えられたところで、豊臣家は滅亡、つくも茄子の茶入れも大阪城落城の際、城の宝庫のなかで焼けてしまった。徳川家康は焼け跡を捜させ、ついにこのつくも茄子を発見する。それを発見し、修理した奈良の漆工、藤重藤元は後にこの茶入れを拝領し、「東照大権現宮拝領」の家宝として江戸時代を通じてその家中深くに秘蔵しつづけた。しかしながら明治の世になって持ちこたえられずに、明治9年に人を介して岩崎弥之助の所有となった。このとき弥之助は四百円というこの茶入れの代金を払うために、兄の弥太郎から借金をしたと伝えられる。現在この茶入れは、弥之助、小弥太父子のコレクションである静嘉堂文庫美術館に収められている。弥之助がこの茶入れに執着したのは、その伝来の重みもさることながら、「つくも茄子」という名が、九十九商会を興した岩崎家の歴史に響きあうところがあったからではなかろうか。これが真実なら、この茶入れには明治になって新しい連想性がさらに付加されたことになる。こうして「つくも茄子」は静嘉堂文庫美術館に現存するのだが、先にも述べた通り、この茶入れは大阪城落城の折り、火を被っている。大正時代にこの茶入れの実見記を書いた高橋箒庵は「灰燼中より拾ひ上げ、漆を以て継ぎ合せたる者なれば、原土を存する處極めて少き者の如し。(中略)勿論原形は過半消滅したれども、藤重父子の丹精にて、漆を以て其景色を原作と見紛ふばかりに作り上げたる其技巧は、此茶入に新に名物たるべき生命を輿へたる者と謂ふべし。」と述べる。
絢爛豪華な顔ぶれの歴代所持者たちによって、「つくも茄子伝説」ともいうべき連想性は大きく拡がっていったと言うべきであろう。小さな陶器の壷に見いだされる価値は、歴代の所持者たちへの思い抜きには語ることができない。これは「つくも茄子」の価値を貶めるものではなく、茶道具の価値観がいかに洗練されたものであるかを示す事実であろう。しかもこの「つくも茄子」は、大阪城落城の際、火を受けて壊れたものを漆で接いだので「原土を存する處極めて少き者」であり、「漆を以て其景色を原作と見紛ふばかりに作り上げたる」ものであるという。実体としての茶入れは、本来の陶器の要素を過半失い、すでにかつての茶入れそのものとは言えない組成なのである。とすればますますこの茶入れは茶入れの形見、茶入れの連想を純粋化した存在に思えてこないだろうか。こうした存在と、バーチャルなものの存在形式との間には、思う以上の近親性があるのかもしれない。
IV
たとえ例外的な存在ではあれ、「つくも茄子」のような遺品(Relic)に生じ得る「バーチャルなものの存在形式」の価値が、庭園における「連想性に基づく存在形式」の価値と異なるのは何故であり、またどこが異なるのだろうか。遺品においては、その遺品を巡る歴史が価値を生むのであり、遺品はそうした歴史の象徴となるのである。したがって遺品という一滴の触媒がもたらされれば、そこには幾重にも重なり連綿とつづく過去が、たちまちにして立ち現われるのである。キリストの顔を拭った布、真の十字架、仏舎利など、聖なる遺品はみな、こうした性質を備えている。遺品とは、それが担っている歴史的真実の方にこそ価値がある品なのであり、誤解を怖れずにいえば、その品であってその品でないような存在なのである。だから世の中には十字架がいくつも出来るほどの真の十字架の断片があったり、無数の仏舎利が存在すると言われたりするのである。庭園において、そのような存在形式はあり得るのだろうか。一番の問題になるのは庭園は時空を越えて移動はしないという事実であろう。遺品は遠く異国へも伝えられる。遺品の将来によって聖なる歴史、高貴なる伝説が遠く伝えられるのである。呂宋渡りの壷や、クレオパトラの針と呼ばれるオベリスクなどは、すでにその言葉を聞いただけで異国の歴史の香りが漂う。そうした品が日本にあり、ロンドンに立っているという事実がすでに驚異である。
だが、庭園は動かない。庭園にできることは、そこに世界を持ち込むことである。蘇鉄を植えた桃山時代の庭園は、豪快なたたずまいのなかに異国情緒を招き入れ、漂わせる。八景を写し、歌枕を見立てた庭もまた、世界を庭園のなかに招き入れて静かに蓄積させているのだといえよう。太湖石を据えた庭には支那の香気が立ちのぼる。それが日本につくられた庭であっても、大湖石をもつことによって、その庭園のなかに中国がもたらされるのである。緑の芝生は西欧の郊外住宅での生活を連想させる。庭園は土地の上に営まれるが故に、世界を移動するのではなく、世界をその上に蓄積させるのである。本来土地あるいは場所とは、文化を蓄積させる形式なのである。
V
遺品と庭園の中間に位置すると考えられる「建築」の場合は、このような問題はどう立ち現われるであろうか。建築は移動しうる。京都、東京、大磯、犬山と移動した茶室「如庵」をはじめとして、茶室には移動を重ねたものが多い。茶室以外の建築においても、われわれが「聚楽第の遺構」、「御所より拝領の建物」などという説明をしばしば耳にするのは、その大半が単なる伝説にすぎないにせよ、建物は移動しうるし、移動してきたという証しである。だが、日本の建築が移動されるとき、そこにいはつねに周囲の庭あるいは伽藍を整えるという仕事が付随するように思われる。そうした整備を待ってはじめて日本の建築は移動を終えるのである。それはかつての由緒を移す試み、言い換えればかつての場所そのものを新しい場所に移し替える試みであるように思われるのである。日本以外の建築を見ても、エジプトのアブ・シンベル神殿はダムによる水没を避けるため移動されたし、ニューヨークには、ヨーロッパの修道院建築を何棟も移築してつなぎ合わせたクロイスターズという美術館がある。また、インテリアを移築して新しい建物のなかに埋め込んだ例は、メトロポリタンやフリーアといった博物館のなかに見られるだけでなく、個人の邸宅などにおいても見られる。わたしはある会議の時に、18世紀のフランスのオテルの一室をはめこんだインテリアをもつプリンストン大学の迎賓館で、建築史を専門とするからといって一番よい部屋を寝室に割り当ててもらい、そこで一週間ほどを過ごして不思議な気分を味わったことがある。
建築は移動しうる。だが、そう考えたときに、建築とは一体どのようなものと考えられているのだろうか。茶室や木造の日本建築の場合、それはあたかも樹木を移植するように移動されるのではなかろうか。解体され、移動後に再度組み立てられる木造建築であっても、それらは周囲の庭や伽藍を整えることによって新しい土地に根付くことはできた。つまりそれは「つくも茄子」のように、由緒を伝えるものとして移植され根付くのであろう。
それに対して西欧の建築は、空間として完結しているがゆえに、移動可能と考えられているのではないか。歴史的なインテリアを、完結した箱として新しい建物に移し込む行為は、もっとも西欧的な建築の移動法である。それは彼らの建築に対する意識が、完結した空間を基礎とするものであるがゆえに、可能であることることを示している。そこでは建築やその内部空間が即物的に移動される。西欧の建築の本質がそこに現われている。バーチャル・リアリティという概念とその実現は、こうした西欧的な空間意識の延長上に発展したものなのだ。すでに今世紀初頭にユイスマンスの小説やスクリアービンの音楽のなかで試みられていた人工的な空間は、まさしく完結した空間性を基礎としたバーチャル・リアリティ実現の先駆である。だが、世界は空間から成り立っているのか、それとも場所から成り立っているのかと問うとき、バーチャル・リアリティの文化的背景が、改めて浮かび上がってくるように思う。バーチャル・リアリティの試みは、世界を空間として把握することを前提としているのではないか。つまりそれは極めて西欧的な世界把握の伝統をその背景にもつ方法なのではないか。世界を包み込むドームを構想したバックミンスター・フラーの思想が、技術至上主義的に見えながら、その実極めて西欧的な世界把握の哲学に立脚していたように、バーチャル・リアリティという技術も極めて西欧的な思想の上に立脚しているのではなかろうか。建築の体験を空間化することによって、はじめてバーチャル・リアリティという概念は意味をもつ。だが、建築は空間をつくる技術なのだろうか。それは場所をつくりあげる芸術なのではないのだろうか。場所なき建築は、はたしてどこまで可能なのだろうか。
 |
 |
 |