




















日本
富山県朝日貝塚
縄文時代中期
高さ37.2cm、直径26.5cm
資料館人類・先史部門(EA. 2228)
非常に繁縟な文様で器面を埋めつくすが、上部のふくらむ部分に文様のアクセントを置き、円筒形の下半分を同じ文様のリズミカルな繰り返しに統一することにより過度の煩雑さを抑え、バランスを確保している。非対称に位置する大小2個の把手もしゃれた感じに見えるが、実はもともと大1個、小3個、都合4個の把手と4個(?)の小波状突起が点対称の位置に配されていたことが破損部から知られ、これらを復元すると、相当にうるさい口縁装飾になり、全体のイメージも一変するであろう。
次いで全体のプロフィルに注目すると、器体は、内折する口縁部、外反する頚部、円筒形の胴部の3部分に分けられる。この形は上山田式土器において一般的な器形のひとつである。この3部分に対応する3つの文様帯配置は上山田式には少ないものであるが、後述するように、よく見ると、中段の文様と下段の文様はつながっているので、この土器の文様帯は、正確には口縁部の狭い文様帯と以下の胴部文様帯の2つになり、上山田式一般の文様帯配置の規則に外れない。この器形と文様帯に加え、細い刻み線を加えた、隆起線の間を半截竹管による半隆起線で埋めること、交互の深い刻みなどはみなこの型式の特徴的手法である。しかしこの土器を特徴づける、下段を同じ隆起線の繰り返しで埋めつくす装飾はほとんど類例が知られていない。この隆起線は大把手の下の渦巻きに発するもので、この渦巻きの上端から発する隆起線は横に伸びて1周したのち別の渦巻きに入って終わる。下端に発する隆起線は右方向に延びて約10周らせん状に胴部を回って隆起線を篭様に重ねた後、底部に達する。底部を欠損しているため正確な巻数は不明。
上山田式の隆起線は普通、渦巻きに発し少し水平に延びた後、第2の渦巻きを形成して終わる。つまり全体として大きなS字状をなすものが多いが、この土器の場合、延びた隆起線が胴部をらせん状に回って底部にまで達しているのである。
内面を観察すると、この隆起線と隆起線の間の谷に相当する位置にかすかな膨らみが認められ、これもらせん状に回っているが、これは器壁を作る際の巻き上げ成形の痕跡ではなく、文様としての隆起線貼付の際に外側から内側に押されてできた膨らみとみられる。なぜなら、この隆起線は上記のように渦巻きに発し、上から下に向かって巻き付けられ、内面の隆起もこれに対応しているが、それは一般に土器を作る場合の粘土の積上げの方向が下から上であるのと逆である。
この土器の胴部の隆起線の繰り返しは、篭の形象、あるいは器体をつくりあげるときの粘土の輪積みとの関係を思わせるが、上記のような観察から、そのような関係はなく、あくまで装飾として加えられたものと言わなければならない。
この土器を出土した富山県朝日貝塚は北陸地方の代表的な貝塚として知られ、1918年以来6回の発掘調査が行われている。縄文前期と中期の土器を主体とし、縄文後期の土器、弥生土器、古墳時代の土師器も出土している。地点によっては4枚の貝層が認められているが、発掘が古く、記録が不十分で、各貝層に含まれる土器型式や各貝層を構成する貝類など十分明確ではないが、上記4枚の貝層が認められた地点では第3の貝層から縄文前期末の朝日下層式が出土している。今回展示された深鉢形土器は大正13年、柴田常惠らの調査で出土したものらしい。
北陸の縄文土器編年の大網は、九学会連合「能登」の調査の後に山内清男によって示され、石川県の中期中葉に上山田の土器が、富山県の中期中葉に朝日貝塚上層の土器が置かれたが、その後は北陸の中期中葉を「上山田式」で代表させることが多く、とくに富山県については「天神山式」の型式名も用いられた。最近では小島俊彰が北陸の土器を「上山田・天神山式土器様式」の名でまとめた上で5段階に細分している。関東・中部高地の勝坂式に並行する形式である。
(今村啓爾)

日本
茨城県稲敷郡東村福田貝塚
縄文時代後期
高さ13.5cm、底径6.8cm、口径6.6cm
資料館人類・先史部門(CW. 2155)
遺跡は明治26年に坪井正五郎らが椎塚とともに確認した学史上名高い貝塚であり、佐藤の報文によると調査地点は字神明前にあたる。地表から貝層が確認できる部分を貝層下まで発掘したということであるが、この土器がどの層から出土したのかは記録にはない。ともに堀之内一式から加曾利B3式までの土器が出土しているようである。幾多の土器が出土した中で佐藤はこの土器をそれまで出土例のない第一に注目すべき遺物として報文でとりあげたが、100年経った現在でも同類の完形品の出土は希である。
器面は丁寧な平滑化がなされており、器表には砂粒はほとんど認められない。頚部と胴部を別に作り装着したのか、内面の接合部分には鋭利な触感がある。注口の接合部分は通常の方法では観察ができず、どのような装着方法を用いているかはわからない。注口部側の把手表面の調整がやや粗いのは注口部が邪魔になったためと考えられる。器面調整の丁寧さにくらべると、文様施文や把手の接合にはやや粗雑さが見られる。細い粘土紐を貼り付けた区画の中に長円形の区画を削りだし、そこに点列を充填しているが、点列は直線とはならず、また区画からはみ出している部分もある。把手の左右にも沈線区画文と列点が施されるが、左右対称とはなっておらず、いずれも把手の左側が逆コの字形の区画であるのに対し、右側は不完全な区画となっている。また胴部の沈線文はほぼ対称に配置されているものの、注口部と逆側の把手はそれには沿わず時計方向にずれた位置につけられている。底面にはけずり痕があるのみで、網代痕などはない。また器面には特に用途を示すような使用痕跡は認められない。
いつの発掘かは判らないが、ほぼ同工異曲の注口土器が同じ福田貝塚から出土しており、かつて滋賀県長浜市の下郷コレクション中に納められていた。その写真が『日本原始工芸』に掲載されている。しかしコレクション散逸後の考古遺物類の所蔵先である辰馬考古資料館、天理参考館、大阪市立博物館にはその土器は見あたらず、残念ながら現在の所在は確認できないでいる。現在でもこのタイプの土器の出土数が少なく、一遺跡から二個体も完形に近い土器が出土していたのは珍しい。
この注口土器の編年的位置は縄文時代後期中葉の加曾利B1式とされている(山内他1964)。しかし同時期の他の器種と文様の共通性が乏しいため、変化を追うことが難しく、土壙内、住居址一括出土など他の土器との良好な伴出例が殆ど知られていない。そのような意味ではやや特殊なタイプである。底部が張り出すこの特徴的な器形の注口土器には列点文が組み合うのが一般的であり、この基本的な文様と器形の組み合わせは前段階の堀之内二式で成立しており、さらに頚部が筒状に発達した器形も前段階で祖形が認められる。注口土器には独自の文様が用いられる傾向があり、この土器に見られるような区画内に列点を充填する手法の文様もまた注口土器特有のもので同時期の他の器種で用いられることはほとんどない。この種の文様が施されたほかの器種としては堀之内二式の浅鉢形土器があり、その他には堀之内二式から加曾利B1式の深鉢形土器の突起の内面に希に用いられるのみである。堀之内二式が層位的に出土した東京都荒川区延命院貝塚の調査では上層の2つの層から同種の注口土器の口縁破片が出土しており、また茨城県土浦市上高津貝塚でも堀之内二式終末期の土器を主体とし加曾利B1式の土器が若干混じる層から把手部分が出土している。これらのことからこのタイプの土器の製作開始の時期を堀之内二式末期まで遡らせることができる可能性がある。
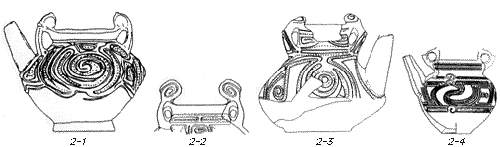
推測される変化としては、胴部に渦巻き文を持つ群馬県赤城村三原田出土例(挿図1)のようなタイプが堀之内二式にあり、渦巻き文様の把手を持ちながら頚部に区画文のある神奈川県伊勢原市下北原出土例(挿図2)や茨城県高萩市小場出土例(挿図3)を次の段階におくことができるであろう。そして把手の位置が口縁部より下につけられるようになった段階が福田出土例であると考えられる。 地域的広がりとしては北は福島県、西は滋賀県まで確実に分布しており、器種は判然とはしないが大阪府淡輪遺跡でもこの注口土器の流れを汲むと考えられる土器口縁部破片が出土している。 なぜかこの特異な形態の注口土器は後継器種を残さないまま姿を消したと見られ、密接細線文を特徴とする注口土器(鎌倉市東正院遺跡)(挿図4)がこのタイプにとって替わり、さらに広範囲に分布を広げることとなった。
(西田泰民)

日本
秋田県山本郡二ツ井町麻生遺跡
縄文時代晩期
直径14.5〜13.9cm
資料館人類・先史部門(BE. A4117)
麻生遺跡は東西2地点からなるが、ここで紹介する仮面は明治20年頃、大洞C1期を主体とする東地点から掘り出され、地元の蒐集家小笠原為吉氏に所蔵されていたものである(——1898)。東京帝国大学人類学教室の画工大野延太郎(雲外)が明治30年(1987年)12月初旬に麻生遺跡の調査をおこなったさいに、この仮面を小笠原氏から預かり、人類学教室に持ち帰ったのである(——1897、同上1990)。それはすぐさま当時の主任教授坪井正五郎の古典的論文「石器時代の仮面」のなかで中央学界に紹介されている(坪井1987)。なお、そこには大野延太郎の手になる模写図が載せられているが(挿図2-I)、大野の図には明治33年(1990年)に発表された別のものもある(——1990)。一方、この仮面のまとまった説明としては、明治38年(1905年)の『人類学写真集 日本石器時代土偶ノ部』における柴田常惠のものがある(坪井・柴田1905)。
その後、この仮面に対する言及や説明は再三おこなわれ、その資料的・美術的価値はひろく知られるところとなり、昭和32年(1957年)には重要文化財に指定される(野口1957)。そして、昭和41年(1966年)に東京大学総合研究資料館が設立されるのにともない、同館の人類・先史部門に保管され、現在にいたる。
椀形の形状を呈するこの仮面は、縦幅14.5センチ、横幅13.9センチの、大人の手のひらに収まるものである。内湾の深さは中心部で最大値4.1センチを測る。眼・口は塞がっており、外部を覗くことはできない。額部左右下端に開けられた直径0.5センチの耳孔の存在は、この仮面が、人間が直接着装する「被り仮面」よりも、壁や木柱などに掛ける非着装の「飾り仮面」、あるいは着装するにしても間接的なかたちでの「当て仮面」として用いられたことを示している(坪井1987、磯前1994)。 製作法は内湾する円盤を基盤とし、その表面全体に薄い化粧土を貼りつけている。外縁部には幅0.4センチ前後の沈線が二条めぐらされ、沈線部から外縁部にかけては無文、沈線部より中心寄りのところには縄文帯が設けられている。外縁部の厚さは0.6センチ前後である。裏面はヘラ削りをしたうえで、ナデが施されている。ヘラ痕がかなり残っているものの、表面同様に光沢をもったものに仕上げられている。色調は右頬の茶褐色を除くと、表裏両面とも全般に黒褐色を呈する。焼成は堅固な状態を示す。
額・眼・頬・口・顎部には、周囲の無文帯より一段盛り上がった浮き彫り状の縄文帯が設けられ、そこにLR縄文が充填される。額部縄文帯には大洞C1式土器の文様と共通する雲形文が三単位施文される。但し、額部を無文帯にする資料も珍しくはない。
遮光器状の眼部の上下辺にめぐらされた眼帯は縄文帯にされ、両眼帯上辺には半裁竹管が外に向って開いたかたちで施される。そして、左右両眼帯のあいだには縦位のB突起が付されている。なお、左眼部は眼帯上辺を除き欠損しているが、偶然の剥離が想定しにくい部位のため、意図的な破壊のおこなわれた可能性もある。もしそうであれば、鼻梁を斜めに走るヒビも、そのさいの衝撃で生じたのかもしれない。
無文の鼻部には鼻梁がまっすぐに走り、鼻先にいたって急激な隆起を示す。鼻孔は陰刻によって深く開けられている。鼻の下には二条の縄文帯によって人中が表現されているが、その縄文帯はさらに下垂して楕円形の口の周りをめぐる。この口部の中央には横位の沈線が引かれている。そして、頬部には陰刻の三叉文を抱えた縄文帯が、中央に向かって二等辺三角形状に張り出し、その両底辺部には円形の突き出しが付されている。顎部にもB突起状の縄文帯が三単位施されている。
仮面はその数の少なさから、族長あるいは特定集団に保管され、彼らの指揮下のもと共同体の儀礼がとりおこなわれていたと考えられる。そこから、族長による共同体成員に対する共同体の価値規範の付与、例えばイニシエーションなどの具体的な儀礼を推察することも可能であろう。それは、土偶がその量の多さから共同体成員のあいだに広汎に保有されていたと考えられるのとは対照をなす。また、土偶はその破損率の高さから儀礼のさいに故意破壊がおこなわれていたと思われるが、それに比べて仮面の破損率は低く、仮面自体の破壊が儀礼の必須過程であったとは考えにくい。
仮面と土偶の違いは儀礼過程にとどまらず、型式特徴にも指摘することができる。遮光器型土面第一類に属する麻生の資料は、小型で内湾する形態、額部の文様帯、ふさがれた遮光器状の眼部、人中、写実的な鼻部、頬部の三叉文などの型式特徴を示すが、それらは遮光器状の眼部を除くと、遮光器形土偶にはみられないものである。総じて、遮光器形土偶は抽象的な表現傾向をもつが、それに対し、遮光器形土面は現実の人間の顔の造作に近い写実的傾向をもつ(磯前1994)。
遮光器型土面第一類はおよそ大洞C1期に北上川中流域以北の東北北半部に分布するが、このことは東北北半部がその他の地域に対して仮面儀礼を共有するひとまとまりの地域であったことを表している。但し、同じ遮光器型土面第一類といっても、東北北半部のなかでいくつかの地域的な特色を示す(挿図1)。資料数が少ないため強引な推測にならざるを得ないが、米代川流域では耳部を欠くのに対し、北上川中流域では耳部をもち、岩木川・雄物川・馬渕川流域では両方の折衷様式をもつ。しかも、馬渕川では遮光器型土面の外に鼻曲り型土面を併せもつ。鼻曲り型土面は、遮光器型土面が直接の着装を不可能とするのに対し、眼孔・耳孔を穿った人面大のものであり、直接的な着装を可能とする。仮面の表情の違いや異型式の併存は、東北北半部の各河川流域で仮面に込められた精霊のイメージが異っていたことを示す。このような東北北半部における仮面型式の共有とその内部での差異の併存は、東北北半部における緩やかな文化的同一性の存在を前提としたうえで、各河川を単位とする固有の文化的同一性が存在したことを物語っている。
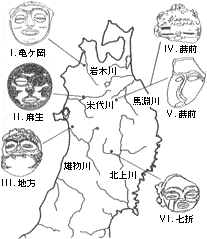 | 3-1 大洞CI期における東北北半部の仮面 I〜IV.VI.遮光期型土面第1類、V.花曲り型土面 |
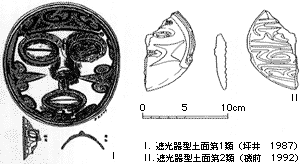 | 3-2 秋田県麻生遺跡出土の仮面 |
なお、麻生遺跡からは遮光器型土面第2類の資料も出土している(磯前1992)(挿図2-II)。これも当資料館に保管されているものであるが(標本番号546)、もはや眼部は遮光器状をとらず、鼻下の人中も消滅する。現長の縦幅9.2センチ・横幅5.9センチを示す大きさは第一類同様に手のひら大であるが、断面形は新たに平板化し、裏面にも文様が施文されるようになる。耳孔もみられなくなり、同じ飾り仮面でも何かに掛けるよりも、横に安置するか立て掛けるほうがふさわしくなる。 縄文時代の土製仮面は後期前葉の九州北部・韓国南部を皮切りに、その形態・文様を変えながら日本列島を北上していった。最後に行き着いたのが、晩期東北北半部の亀ケ岡文化であった。しかし、それも遮光器型土面を最後として、土偶よりもいち早く日本列島から姿を消す。つまり、麻生にみられる2点の資料は、縄文時代の土製仮面の最後の姿を伝えるものなのである。
(磯前順一)
明治30年の麻生調査
——、1897、「羽後来信」『東京人類学会雑誌』141
——、1898、「秋田県庁より東京帝国大学への照会」『東京人類学会雑誌』143
大野延太郎、1898、「羽後国北秋田郡七座村大字麻生上ノ山遺跡取調報告(第1回)」『東京人類学会雑誌』143
仮面総論
坪井正五郎、1897、「石器時代の仮面」『東洋学芸雑誌』197
磯前順一、1994、『土偶と仮面—縄文社会の宗教構造—』、校倉書房

石製
日本
埼玉県岩槻市真福寺遺跡
縄文時代晩期
長さ60.4cm、最大幅3.1cm
最大厚2.6cm、重さ779g
資料館人類・先史部門(136)
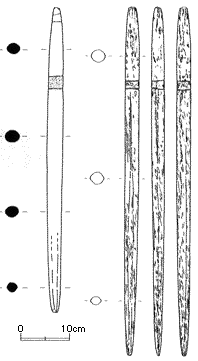 4-1 熊登型石剣(左:埼玉・新幅寺 右:秋田・虫内III)
4-1 熊登型石剣(左:埼玉・新幅寺 右:秋田・虫内III)
石材は不明だが、黒光りしているのが印象的である。さらにつぶさに観察するに、本石器がこのような光沢があるのは、全体にきれいに研磨されていることに起因するが、一部研磨が不十分な部位があって、それ以前の成形工程の痕跡である敲打痕を残している。その部位とは、棒状の本体に二条のやや稚拙な沈線に囲まれた幅2センチ程の範囲のことである(挿図1左)。二条の沈線で区画しさらに敲打痕を残すことで帯状部が強調されており、明らかに意図的なもので、ここが明瞭な区画となって把部が形成されているとみなせ、さらに、もう1カ所、これも稚拙な沈線がより端部に近いところを二条めぐっており、これによって把頭を表しているとみなせる。他方、一見棒状のこの石器のもう一端のところから10センチ程のところまでは、両側縁にそって比較的明瞭な稜を形成しており、両刃が形作られていると見るべきであろう。しかし、さらに把部にいたる間はそのようなはっきりとした稜を呈していないようであるが、その部分の身の断面形態は円形ではなく、やや不整形な楕円状となる。そして、把部や把頭の断面形態も同様に不整形な楕円状である。
要するに、一見棒状の本石器は、詳細に形態を観察することから、一端には両刃の刃部を有し、他端は把部になっていると見なすべきなのである。さらに、このような性状の石器は、特に両刃の刃部を有するという形態上の特徴を根拠に考古学上石剣と呼ばれるのを常とするのに倣い、ここでも石剣と呼称するのである。通常、身の断面形態が円形で刃部とみなせる部分がない棒状石器は石棒と呼ばれ、また、石剣と違い片刃の刃部を有する棒状石器が石刀と呼ばれるのである。
さて、実際に、把とみなせる部位を握り、この石剣を振ったり突いたりしてみると、実に具合がよく、手頃な重量感を覚え、あたかも武器である剣を手にしているかのごとき感覚に支配される。はたしてそうなのか。違うのか。本資料の性格をもう少し考えてみようと思いたくなるが、考古学では、取り扱う与件資料を分類命名する際に、現実に存在する道具や武器に似ているからということだけからその名前を採用している場合が多々あり、本当に同じ機能・用途かは保証がない場合が多い。石剣も、石を素材とした両刃の武器なのか否か、あるいは偶然そのような形を呈しているが武器としての実用の道具ではなく、非実用的な祭祀具ではなかろうかなど、存外議論が続いたままなのである。より正確には、縄紋時代の棒状の石器が形態的に「石棒」「石剣」「石刀」といった3つのカテゴリーに分けられるようになって以来(鳥居1924、八幡1933、同上1934、小林(行)1951など)、機能・用途については実に多様な議論を生んでいるのである(その学史的概要は能登1981、野村1985、山本1987参照)。つまり、いま取り上げている石剣も機能・用途がよく分からない縄紋文化の遺物の代表のようなものの1つなのである。
ところで、考古遺物を考究する場合の必須的基礎的研究領域として、型式論的研究・編年論的研究・分布論的研究がある。真福寺遺跡の石剣についても、型式論的研究・編年論的研究・分布論的研究から、まず検討されねばならない。幸いなことに、この3領域については参照に値する研究があるので(後藤1986、同上1987)、その研究を手がかりとしてみよう。後藤氏は石剣を次のように型式分類している(後藤1986)。——裏畑型石剣、熊登型石剣、東北原型石剣、高井東型石剣、西広型石剣、なすな原型石剣、貝の花型石剣、乙女不動原北浦型石剣、寺下型石剣。そして、それらは縄紋時代後期後半/晩期に発達することが詳しく論じられている(後藤1987)。
後藤氏が掲げている各型式標本資料を検討するならば、真福寺例は把部を沈線で造っている点や形態上の類似から熊登型石剣に該当しよう。氏の説く熊登型石剣は、東北地方(新潟県東部を含む)に分布する型式で、編年的には晩期前半に位置するらしい。ということは、真福寺例は縄紋時代晩期前半という編年的位置を占めることになり、しかも関東出土であるが、所属型式は東北地方のものであることになる。当然、搬入品であろうことが推定されることになるのである。
真福寺遺跡の石剣が東北地方からの搬入品の可能性があるということは実に興味深いが、まずもって後藤氏の型式設定の当否を検証しなければならない。後藤氏は事例が少ないことと完形品に恵まれていないことが熊登型石剣の設定に当たって難点とされていたが、筆者の手元にある報告書を案配してみるに、氏の説く熊登型石剣が東北地方に分布することは確実であり、編年的位置を晩期前半とすることも妥当のようである。しかもなお、熊登型石剣設定の当否を検証してく過程で、当該型式の完形品を知った。挿図1右に転載した石剣がそれである。東北地方日本海側秋田県虫内III遺跡(大野ほか1994)の縄紋時代晩期前半に形成された土壙群の1つ(SK91土壙)から出土したもので(この遺跡の近隣にも同様の石剣を出土する遺跡がある)、粘板岩製で、全長71.1センチ、最大幅2.8センチ、最大厚2.6センチ、重さ807グラムである。二条の沈線で区画された部位(しかも敲打痕を残したまま)によって把部を形成していることは、真福寺例とよく似ているのである。他方、関東地方では筆者が検索し得た文献からは熊登型石剣は見いだせなかったのである。今のところ、真福寺例が熊登型石剣の関東に於ける唯一の例といって差し支えないようである。
このように後藤氏の熊登型石剣の設定の当否に対してはその設定が有効であることが追証できたことによって、意外なことに真福寺例は関東在地の型式ではなく、縄紋時代晩期前半の東北の型式・熊登型に属する石剣であることが判明したのである。したがって、東北地方からの搬入が考えられるのである。このことは重要であろう。なぜならば、縄紋時代晩期に関東地方は様々な分野で東北地方のいわゆる亀ケ岡式文化から影響を受けることがつとに指摘されているからである(山内1939)。しかも、東北地方からの影響がさらにどのような分野に及ぶのかを例証するのが今後の課題だからである。真福寺遺跡から出土の熊登型石剣はそのような動向を示すまたあらたな例証といえるのである。
真福寺遺跡出土の石剣の由来として、縄紋時代晩期前半に東北地方から持ち込まれた可能性が高いことが分かったが、そもそもこのような石器は一体何なのであろうか。その点は従来からいろいろな意見はあるが、見解の一致を見ていない故に、ここで議論を止めるのも1つの見識であろうが、あえてどのようなことに使われるのか筆者の常々考えるところを記しておこう。もちろん、正体のよく分からない遺物故に甲論乙駁の轍を踏むのは承知である。結論を先に述べるならば、このような石器は模擬戦という祭儀の過程で使用されるのを本来とするのではなかろうかと考えている。しかも、縄紋時代後晩期に発達する石棒・石剣・石刀の3者について該当すると考えている。
ちなみに日本の古典研究から模擬戦という祭儀があったことはかなり以前に指摘され(西郷1967)、考古学では金属製武器を模した木製品が弥生時代の遺跡から出土することからそれが武器型木製品として模擬戦の祭儀でもちいられた祭祀具であることが説かれるようになっている(金関1978、中村1980)。筆者はそのような研究趨勢に鑑み、縄紋時代後晩期に発達するこれら一見武器的な石剣や石棒・石刀が手でもつのに都合いいように工夫されていることの指摘(末永1961、後藤1987)を重視し、遺跡内での出土状況の分析から、完形品ではなく破損品が圧倒的に多いということ(新津1985、藤村1985、山本1979a・b)と、ある対象物に対して例えば石刀を打ちつけたという示唆(末永1961)とを関連づけるべきで、さらには石剣や石棒や石刀はそれぞれを打ちつけあった故に破損品が多いとみるべきと思う。そして、そのような行為の場は、つまりは、模擬戦が行われる祭儀の場に結びつけるべきと考えるのである。要するに集落のどこかに据え付けるのではなく、手で持って使う石器であろうということに注視し、破損品が大多数であることの原因を手に持って打ちつける動作に求めたいのである。そして、そのようなことが執り行われる場は模擬戦という祭儀の場と考えたいのである。また、時として土壙から石棒・石剣・石刀が出土するが、このように副葬品として用いられるのは、被葬者が生前に模擬戦に関与した人物であることを顕彰しているのではなかろうかと想像する。筆者の意見は、学史的には石棒・石剣・石刀を祭祀具と考える見解の1つということになるが、武器とみる見方にも配視し、より具体的な祭儀として模擬戦と結びつけるという点では新しい解釈を示したことになる。
さらには、模擬戦と石棒・石剣・石刀とを結びつけて考えることで縄紋時代後晩期に関する時代像に関しては、緊張をはらむ時代像を描くべきではなかろうかということにもなる。例えば、土偶研究に於いて、後期後半から晩期にかけての日本列島の南・九州とより北の本州とでは土偶製作のピークが時期的に異なることに着目し、アジア大陸からの稲作の到来に帰因した「縄文世界観の存亡の危機」がこの時期にあったとする意見がすでに小林達雄氏によって出されているのは重要であろう(小林(達)1991)。何故ならば、そのような時期に石棒・石剣・石刀の発達を見るからである。これらの石器の発達を考える上で、日本列島内部の事情だけでなく、アジア大陸の動向をも視野に入れるべきであろうと考える。
したがって、真福寺遺跡に異型式の石剣が出土している社会的背景は、思いの外深刻なものとみるべきであろうことをいい添えておこう。
(大塚達朗)
註1 ちなみに、後藤氏は石棒・石刀については以下のような型式設定をおこなっている(後藤1986)。——石棒(東正院型石棒 柏子所型石棒 大沢型石棒 興野型石棒 蟇沢型石棒)/石刀(天附型石刀 新田型石刀 橿原型石刀 保土沢型石刀 萪内型石刀 山本新型石刀 寺家にしきど型石刀 小谷型石刀 亀ケ岡型石刀 九年橋型石刀 札苅型石刀)。

日本
東京市向ヶ岡(現東京都文京区弥生)、向ヶ岡貝塚
弥生時代後期
頚部径8.4cm、胴部最大径22.7cm
底部径8.5cm、高さ22.0cm
資料館人類・先史部門(DO. 6990)
農耕社会の定着発展期として縄文時代と古墳時代の間に位置づけられる、弥生時代。その名称の由来は、この1個の土器が1884年(明治17年)、帝国大学(現東京大学本郷キャンパス)の隣地、向ヶ岡弥生町(現文京区弥生)で貝や縄文土器とともに発見されたことにある。この壺が発見された地点は「向ヶ岡(弥生町)貝塚」と呼ばれているがその正確な位置はよく分かっていない。
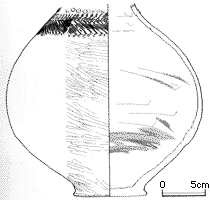 5-1 向ケ岡弥生町出土の壷型土器(最初の弥生土器)
5-1 向ケ岡弥生町出土の壷型土器(最初の弥生土器)
「弥生町の壺」を発見したのは有坂 蔵氏であるが、『東洋学芸雑誌』上に報告したのは坪井正五郎氏であり、1889年(明治22年)のことであった。当初から、この壺形土器が弥生式土器と呼ばれていたわけではないが、後に、蒔田鎗次郎氏が1896年(明治29年)自宅ゴミ穴壁面から出土した土器について、「はじめて弥生ヶ岡より発見せられたるゆえに人類学教室諸氏が弥生式と名づけられたるもの」と述べたように、次第に「弥生式」の名称は定着していった。つまり、弥生町出土の1個の壺形土器は学史的に「最初の弥生式土器」となる。昭和初期になると弥生式土器は日本の初期農耕文化の土器であると認識されるようになり、ここに「弥生」の名は日本の1つの時代を表す名称となっていったのである。
一方、弥生式土器の研究が進むと、弥生式土器を分類し、地域差や時期差を明らかにしようと試みられるようになる。1939年、日本各地の弥生式土器の編年を試みた『弥生式土器聚成図録』が小林行雄氏らによって刊行されたが、ここで再び「弥生町の壺」が注目された。つまり、南関東地方の弥生土器は4つの様式に分けられたが、「第三の様式は彌生式土器の名の基となった彌生町貝塚の土器を以て代表される様式である」、「第三様式を彌生町式と呼ぶことを提唱したい」としたのである。その後、杉原荘介氏によっても「弥生町式」の名が用いられるようになり、南関東地方の弥生時代後期に使われた「土器形式」と考えられるようになる。つまり、「弥生町の壺」は時代の名称の由来となったとともに、一地方のある時期の標式ともなってきたのである。
蔵氏であるが、『東洋学芸雑誌』上に報告したのは坪井正五郎氏であり、1889年(明治22年)のことであった。当初から、この壺形土器が弥生式土器と呼ばれていたわけではないが、後に、蒔田鎗次郎氏が1896年(明治29年)自宅ゴミ穴壁面から出土した土器について、「はじめて弥生ヶ岡より発見せられたるゆえに人類学教室諸氏が弥生式と名づけられたるもの」と述べたように、次第に「弥生式」の名称は定着していった。つまり、弥生町出土の1個の壺形土器は学史的に「最初の弥生式土器」となる。昭和初期になると弥生式土器は日本の初期農耕文化の土器であると認識されるようになり、ここに「弥生」の名は日本の1つの時代を表す名称となっていったのである。
一方、弥生式土器の研究が進むと、弥生式土器を分類し、地域差や時期差を明らかにしようと試みられるようになる。1939年、日本各地の弥生式土器の編年を試みた『弥生式土器聚成図録』が小林行雄氏らによって刊行されたが、ここで再び「弥生町の壺」が注目された。つまり、南関東地方の弥生土器は4つの様式に分けられたが、「第三の様式は彌生式土器の名の基となった彌生町貝塚の土器を以て代表される様式である」、「第三様式を彌生町式と呼ぶことを提唱したい」としたのである。その後、杉原荘介氏によっても「弥生町式」の名が用いられるようになり、南関東地方の弥生時代後期に使われた「土器形式」と考えられるようになる。つまり、「弥生町の壺」は時代の名称の由来となったとともに、一地方のある時期の標式ともなってきたのである。
1974年、東京大学浅野地区構内で弥生土器が発見され、翌年東京大学考古学研究室及び人類学教室によってこの地点の発掘調査が行われた(挿図2)。調査区内からは集落を囲む環濠と考えられる断面V字形の溝が検出され、溝内からは数カ所の貝層と一括出土品を含む土器などの遺物が検出されたのである。 この調査地点は、発見者の有坂氏が記した、「根津の町を眼下に見る丘」、「陸軍の射的場があってその西北の方」u上野の森や不忍池を望んでいる」、といった向ヶ岡貝塚の位置についての記述と合致し、しかも、「貝塚は円形や矩形の穴で一部削られていた」(佐藤1975)とされることから、この調査地点が有坂氏の「弥生町の壺」発見地点であった可能性も示唆されている。
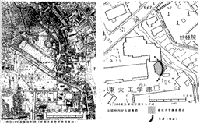 | 5-2 「弥生町の壷」発見の頃の弥生町周辺と東京大学調査地点 |
東京大学によって調査された断面V字形の溝が集落をとりまく環濠であるならば、調査地点の北西側に展開する集落をとりまいていたものと考えられる。つまり、調査地点は環濠の南東コーナー部分に相当すると考えられ、環濠はさらに崖線に沿って言問通りの方へ伸び、西へ湾曲して旧射的場の谷の方へ向かい、小台地上を南走、東走して1周していたものであろう。調査地点で環濠内への貝や土器の廃棄が見られたということは、集落をとりまく環濠の各所に、点々と同様の廃棄が行われていた可能性は高い。有坂氏の発見した壺は口縁を除いてほぼ完形であるから、弥生時代にこの壺が廃棄された後に、原位置を動いた可能性は少ない。つまり、有坂氏の発見地点は集落をとりまく環濠のどこかであり、東京大学調査地点であった可能性も高いといえよう。
東京大学調査地点の発掘報告書は『向ヶ岡貝塚』として刊行され、同遺跡は「弥生二丁目遺跡」という名称で史跡指定されている。
肩部には縄を転がしてつけた縄文装飾が施され、上側の縄文をつけた後に、それとは撚りの異なる縄を用いて下側の縄文をつけている。縄の原体は「単節縄文」と呼ばれるもので、細い割にやや長めの縄を用いている。この下段の縄の下端には、縄が解けないように縄の節の1本を解いて結んだ跡がS字状になって付いている。縄文の上には円形の貼付文が3つずつ並んで施され、一部欠けているがこれが、6単位ほぼ等間隔に頚部にめぐらされていたようである。
縄文を施した部分以外の胴部は全面にわたって丁寧にミガキ調整されるが、頚部の縄文より上はミガキ調整の痕跡は認められない。ミガキが施された部分は焼成の具合で、赤みがかった部分もあるが、もともと赤く塗られてはいなかったようである。
挿図3には東京大学の向ヶ岡貝塚の調査で、環濠内より一括出土した土器群であるが、様々な土器がみられる。1は「弥生町の壺」に似ているが、底部は突出せず、やや上げ底になる点や、胴部に縦ハケを施し胴下位の稜をなす接合部付近を横位にミガキ調整するなど、駿河湾西部から天竜川流域の特徴を持っている。2は東京湾岸に特有の広口壺であり、3は平底の甕であり口縁に布目の押圧文を施すなど東京湾岸に見られる手法を持つが、胴下位に残る接合の手法やハケ目による調整法、口縁端部の仕上げ方など、東海地方東部の特徴を有しており、南関東地方との折衷的な土器といえよう。4、5はハケ調整の台付甕であり、東海地方東部から相模湾及び武蔵野台地東部に分布するものである。 このようにみてくると、「弥生町の壺」は東海地方東部、中でも駿河湾の東部との類縁性が認められるようである。「弥生町の壺」が東京大学の調査で環濠より出土した土器と同じように廃棄されたものであったと考えれば、向ヶ岡貝塚の環濠には、南関東地方の特徴を持つ土器とともに主に東海地方東部との関連を持つ土器群が出土していると考えられよう。 向ヶ岡貝塚に近い、神田川流域や荒川中下流域は、新宿区下戸塚遺跡、板橋区四葉地区遺跡、同区根ノ上遺跡、北区赤羽台遺跡など弥生時代後期の環濠集落が集中している地域である。これらの環濠集落からも、主に東海地方東部との関連を示す土器群が出土しており、向ヶ岡の環濠集落と同様な傾向を示しているといえよう。四葉地区遺跡や神奈川県綾瀬市神崎遺跡などでは東海地方から直接人が移住してきたことも示唆されている。
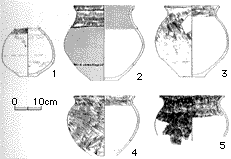
5-3 向ケ岡貝塚(東京大学調査地点)B溝(環濠)一括出土土器(報告書より転載)
向ヶ岡貝塚の環濠から出土した弥生土器には、東海地方に見られる手法が見られるほか、南関東地方との折衷的な要素や東海地方の手法には見られない特徴を持つものもある。「弥生町の壺」も多分に東海地方東部、特に駿河湾付近の土器づくりの特徴を残しており、その地から弥生時代後期にこの地へ移り住んだ人々、あるいはその後間もない後裔の手に成ったものである可能性が高いといえよう。
(鮫島和大)
 蔵、1923、「日本考古学懐旧談」『人類学雑誌』38-5
蔵、1923、「日本考古学懐旧談」『人類学雑誌』38-5 蔵、1924、「過去半世紀の土中」『中央史壇』9-4
蔵、1924、「過去半世紀の土中」『中央史壇』9-4 蔵、1929、「史前学雑誌の発行を喜ぶにつけて過去五十年の思ひ出」『史前学雑誌』1-1
蔵、1929、「史前学雑誌の発行を喜ぶにつけて過去五十年の思ひ出」『史前学雑誌』1-1 蔵、1935、「弥生式土器発見の頃の思出」『ドルメン』4-6
蔵、1935、「弥生式土器発見の頃の思出」『ドルメン』4-6 蔵、1939、「人類学会の基因」『人類学雑誌』54-1
蔵、1939、「人類学会の基因」『人類学雑誌』54-1

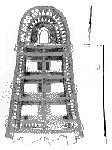
日本
静岡県引佐郡細江町岡地船渡
弥生時代後期
高さ56.6cm
資料館人類・先史部門(12268(A2578))
この銅鐸は、静岡県引佐群細江町の岡地船渡において、1877年(明治10年)頃、別々の機会に発見された2点の銅鐸のうちの1点である(註1)。その後、柴田常惠氏により出土地点は都田川の堤防沿いであったと確認されたが(註2)、新たに現地踏査を行った梅原末治氏によれば、まず2号鐸が1880年(明治13年)8月15日の昼頃に発見され、その数日後に2号鐸よりも小さい本銅鐸(1号鐸)が発見されたとのことである(註3)。1号鐸は人を介して東京帝国大学理学部人類学教室に寄贈されて本館に収蔵されるに至ったが、2号鐸は国内を転々とした後に海外に流出し、調査した時点では「伝近江出土」としてベルリンの博物館に所在することが梅原氏によって推断された。当時ベルリン在住の寺田貞次氏から梅原氏に送られた実測図(挿図2)と、流出前に撮影された写真(挿図1)から、二号鐸の特色を窺い知ることができる。
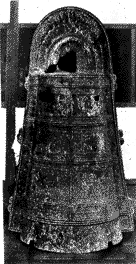 | 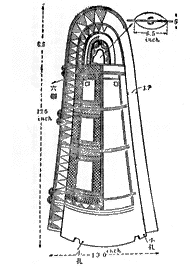 |
| 6-1 岡地船渡2号銅鐸(ベルリン博物館蔵) 梅原末治 1937年「銅鐸の研究」図録第58(2) | 6-2 岡地船渡2号銅鐸図 梅原末治 1937年「銅鐸の研究」 資料篇145頁、第41図(一部改変) |
銅鐸は、いわゆるベル形の青銅器で、その起源は大陸製の小型類品にあったと推定されているが、大きさや形状、紋様構成などに見られる多くの特色は弥生時代の日本列島で独自に醸成された。大きくみて、元来はつり下げるために必要とされた「鈕」と、裾広がりの形状を呈する「身」からなる(註4)。銅鐸の型式変化の方向性は、この「鈕」に注目して合理的に説明することができる(註5)。すなわち、全体の大型化に併せて、つり下げるのに適し装飾紋様も簡素な「鈕」から、幅広・偏平で多くの連続紋様で飾られる「鈕」へと変化していった。その過程で、装飾効果を著しく高める「鰭」(「身」から「鈕」へ連なる偏平な張り出し)や「飾耳」(2つ1組の小突起)が作り出され、さらに、「鈕」および「鰭」の外周、紋様帯の区画などに突線が用いられるようになったのである。銅鐸は祭器の一種であったと考えられており、ほとんどは往時の居住地から離れた地点に意識的に埋納された状態で発見される。記録に残された発見状況から推して、岡地船渡1号および二号銅鐸もこのような一般的傾向を示している。
岡地船渡1号銅鐸は、全体的に鋳上がりの悪さが目につく。鋳損じ孔が少なからずあり、特に、「鈕」が取り付く「身」上部の平坦面(「舞」)の型持孔(内側の鋳型を支えるためにできる穴)の一方は孔としての形状を呈するに至っていない。また、両面とも紋様の不鮮明な部分が認められ、実測図では適宜復元して示した。突線に若干の歪みやズレが生じている箇所もある。裾部はかなり欠損しているが、中軸線に近い遺存部分ができるだけ接地するように若干起こして計測すると、全体の高さは56.6センチを測る。この銅鐸には三条一組の突線が用いられており、古・中・新の3段階のうち新段階三式(突線鈕三式)に該当し(註6)、弥生時代後期の所産である。また、「鈕」に「飾耳」が付加されない、縦方向の軸突線が1組だけ「身」の中央を貫く、などの特色から、三河や遠江に分布が集中するいわゆる「三遠式」の範疇に入る。1982年の集成(註7)によると、出土地が明らかな「三遠式」は31例で、出土地不明例や以後の新例を加えると確認総数はこれより若干増える。「三遠式」は、紋様構成や突線の用い方に独自の約束ごとをもち(註8)、分布状況と併せて「近畿式」に相対する地域色を発現させているため、当該時期の集団関係を探る上で重要な考古資料とみなせる。
一方で、岡地船渡1号銅鐸は、「三遠式」の定型とは異なる特色をもつ。「三遠式」の「鈕」や「鰭」は、内側に頂点を向け斜線が充填された三角形の連続紋様、すなわち内向鋸歯紋で飾られ、定型例は頂点を上に見て右下がり斜線と左下がり斜線の三角形が交互に配される。岡地船渡1号銅鐸は両面とも、交互ではなく各々が連続的に配された箇所が多い。これが第一の特色である。また、横走する軸突線とその上下の紋様帯を1組にして捉えると4段構成(上から「第一〜四横帯」)となり、「第四横帯」の下には先の内向鋸歯紋が巡らされる(「下辺横帯」)のが一般的である。例えば、長野県塩尻市柴宮出土例(挿図3)では、内向鋸歯紋の基本的な配列原則は守られていないが、「第一横帯」と「第四横帯」には斜格子紋、「第二横帯」と「第三横帯」には左右から縦の軸突線に向かう綾杉紋が用いられ、「第四横帯」と「下辺横帯」との区分は明瞭である。これに対して岡地船渡1号銅鐸(A面)は、「第四横帯」を構成するはずの下段の斜格子紋が欠落しており、あたかも「下辺横帯」を取り込んで新たな「第四横帯」が創出されたかのようである。これが第二の特色である。このように、「横帯」区分の原則が崩れた例としては、例えば、愛知県小坂井町から出土した伊奈2号および3号銅鐸などがあり、これらが後出の突線鈕四式に属することから岡地船渡第1号銅鐸の突線鈕三式における年代的位置づけを推し量ることができる。また、この区分原則の崩れは岡地船渡1号銅鐸のもう一方の面(B面)でも認められ、そこに第三の特色を指摘することができる。すなわち、B面では「下辺横帯」を作り出す要素であったはずの内向鋸歯紋はみられず、最下段には斜格子紋が施されている。このように「第四横帯」と「下辺横帯」の区分認識に関わる形で、A・B両面の紋様構成に違いがみられるのである。ちなみに、同一個体で表裏の紋様構成を異にする例として、岡地船渡1号銅鐸と同じく細江町から出土した七曲り2号銅鐸がある(挿図4)。こちらは「鈕」の紋様構成を異にしており、また、定型「三遠式」の原則が遵守されていることから、岡地船渡1号銅鐸の場合とは別の説明が必要であろう。なお、岡地船渡2号銅鐸は、参考写真によれば基本原則が遵守されたタイプの「三遠式」である。
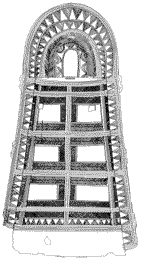 | 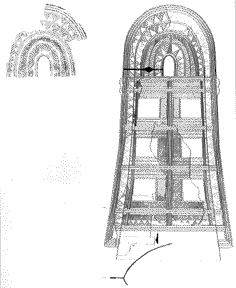 |
| 6-3 長野県塩尻市柴宮出土銅鐸 長野県市観光会 1988年「長野県史・ 公庫資料編・遺構・遺物」の 865頁、第603図(一部改変) | 6-4 静岡県引佐郡細江町滝峰七曲り2号鐸 柴田文雄 1982年「静岡県引佐郡細江町滝峰七曲り2号鐸」 『考古学雑誌』第68環第1号、 154頁、第2図および155頁、第3図(一部改変) |
「三遠式」銅鐸は、基本的な約束ごとが明瞭であるだけに、細かな差異にも目を向けやすい。これらの差異は、製作年代の違いという時間的側面、使用ないし保有した集団から工人集団、場合によっては製作者個人まで様々なレベルの集団的側面、さらに技術的側面などが複雑に絡み合って発現した可能性がある。「生きた分布」をふまえた巨視的枠組みの構築と、個別資料の綿密な観察および比較検討の中に、さらに探究されるべき重要な問題が潜んでいるように思われる。
(倉林眞砂斗)
註1 ——、1887、『東京人類学会雑誌』第18号、290頁の雑記

日本
栃木県宇都宮市雀宮町菖蒲塚(通称綾女塚)
古墳時代
高さ59.8cm
資料館人類・先史部門(AW. A864)
この人物埴輪は、1895年(明治28年)3月頃、栃木県宇都宮市雀宮町(旧下野国河内郡雀宮村)菖蒲塚の辺りから出土した、と報告されている(註1)。現在のJR東日本、東北本線雀宮駅において停車場の工事をしていた時のことであった。本館には、ほかに「栃木県宇都宮市雀宮町大人(ウシ)塚」から出土した埴輪円筒部が1点収蔵されている(登録番号A859)。菖蒲塚は一般的には綾女塚と記されており、台地上に築造された前方後円墳であったが、工事で削平されたために墳丘規模は不明である(註2)。
本資料は、1958年(昭和33年)2月8日に重要文化財の指定を受けた。その指定書「考第179号」によれば、「栃木県宇都宮市雀宮町小字十里木牛塚」から出土した「長い丈の衣を放り着た女子像」で、高さは「一尺九寸七分五厘(=約59.8センチ)」、「円筒部欠失」となっている。1959年(昭和34年)頃、本資料は不幸にして盗難に遭い、おそらく美術的価値を高めるために欠損部分に手が加えられたため、いくつかの点で出土時の様子とは異なっている。幸いにして、手が加えられる以前の写真が公表されていた(註3)ため、その旧状を知ることができる(写真1)。これによれば、主として、頭髪表現の大半、耳および頸部の装飾表現、着衣の結び紐表現および裾部に手が加えられ、円筒部分は後からまったく付け足されたものであることがわかる。また、『東京人類学会雑誌』第112号に添付された「着色埴輪土偶ノ図」(井上喜久次氏紀念図版)(挿図2)によれば、赤色塗料で彩色された部分が存在したはずであるが、現状ではそのごく一部がかろうじて認められるだけである。
 | 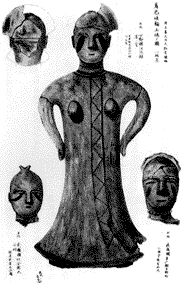 |
| 7-1 | 7-2 |
後頭部には、頭髪表現として、撥の先端部に類似する板状品が上方および下方に円弧を描くように取り付けられている。このような頭髪表現は発掘調査で出土した人物埴輪にも認められる。前髪や鬢(左右側面の髪)を張り出して髷の中ほどを元結で締めるいわゆる「島田髷」に似た髪の結い方を表現していると考えられている。額の部分には一条の突帯が巡らされており、八木奘三郎氏はこれを髪結いと一連のものとして捉え、「髪抑え」と呼んでいる。
両耳の下半には環状の耳環が、また、頸部には直径1センチ程度の小円盤を連ねて頸飾が表現されており、これも類例は少なくない。しかし、これらは周辺の器表面とは明らかに違和感がある。八木氏の報文によれば、いずれも痕跡が認められただけで、これは参考写真からも確認することができる。したがって、盗難による紛失時につけ加えられたものと考えて良いであろう。なお、両眼の周辺から両頬にかけて施されていた長楕円形状の彩色は、八木氏の観察時にはかなり鮮明であったため、類例に目を向けるきっかけになったようである。
胸部には、粘土塊を貼り付けて直径3センチほどの乳房が表現されており、本資料が女子像であることを決定づけている。着衣の丈は長く、本来の円筒部は現状に近い形で裾端内側に直接取り付けられていたと考えられる。胸部と腹部の2カ所で結び紐が表現されているが、やはり八木報告と参考写真によれば、もともと剥落欠損していたものが痕跡を手がかりにしてこのように復元されたようである。頸飾下から裾部の向かって右方まで1本の沈線が刻され、これと3センチほどの間隔をあけて段差が作り出されている。その間には、右下がり、左下がりの斜沈線が交互に連続的にひかれ、結果的に連続三角紋が帯状に表現されている。先の「着色埴輪土偶ノ図」によれば、赤色塗料でも同様の表現がなされていたらしい。2カ所の結び紐は、向かって右側の段差が作り出すラインにほぼ沿うように取り付けられていたことは間違いなく、いわゆる「左衽(ひだりまえ)」であったことがわかる。 ここで取り上げた埴輪女子像は、かなり早い段階に、思いがけず考古学の世界に飛び込んできた。したがって、同じような経緯をたどった多くの考古資料と同様に、これを取りまいていた様々な「関係」から切り離されて存在する。一方で、造作の丁寧さもさることながら、おそらく女子像が希少であったが故に珍品としての取り扱いを受け、結果として盗難に遭い、再び本学に収蔵されるという数奇な運命をたどった。その経緯に関しては、当時理学部人類学教室の主任教授で、現在は東京大学名誉教授である鈴木尚先生から直接うかがうことができた。重要文化財の指定を受けた翌年の春頃、出品依頼を受けた折に盗難に遭っていることが判明し、海外に流出する可能性も念頭におかれて写真付きの手配書がすみやかに作成され、国内およびアメリカ合衆国で配布されたらしい。その効もあってか、事件発覚から1年も経たずに都内世田谷区の古物商から該当品が持ち込まれた、との申し出がなされた。無事に回収されたために示談となり、以後は厳重な文化財管理がなされるに至っている。当時の伝聞によれば、欠損部分に手を加えたのは窃盗した当人で、その際には粘土や石膏ではなくどうやら餅が使われたらしい。細部にわたって細やかな手当がなされたさまを目の当たりにすると、十分に納得させられる話である。
現在では、人物埴輪全体は言うに及ばず、女子(巫女を含む)像に限っても資料の蓄積は著しい。したがって、これらとの比較検討を通して、また、地域的な検討が推し進められていくことにより、この埴輪の考古資料としての側面は間違いなく再生されると思われる。
(倉林眞砂斗)
註1 八木奘三郎、1895、「各地発見ノ埴輪類」『東京人類学会雑誌』第112号

日本
埼玉県行田市将軍山古墳
古墳時代後期(6〜7世紀)
高さ(全)11.8cm、高さ(本体)7.6cm
直径10.4cm
資料館人類・先史部門(KU. 2089(A906))
日本
埼玉県行田市将軍山古墳
古墳時代後期(6〜7世紀)
高さ8.6cm、直径16.4cm
資料館人類・先史部門(KU. 2090(A907))
本資料は、埼玉古墳群(埼玉県行田市)の将軍山古墳から出土した。この古墳は、1894年(明治27年)7月に地元村民によって発掘され(註1)、乳文鏡、環頭太刀・銀装太刀・鉄鉾などの武器類、金銅製および水晶製三輪玉、挂甲・衝角付冑などの武具類、杏葉・雲珠・鏡板・鐙・鈴などの各種馬具および馬冑、蛇行状鉄器、金製耳環・ガラス小玉・ガラス丸玉などの装飾品が出土し、これらは本館のほか、東京国立博物館、埼玉県立博物館、埼玉県立さきたま資料館、本庄市教育委員会などに分散して管理保管されている。銅鋺は、高台付有蓋銅鋺(以下、高台付鋺)のほかに2点が出土した。これらはいずれも高台をもたない無蓋の銅鋺(以下、無台鋺)で、1点は本館に収蔵され、もう1点は個人蔵となっている。ここでは、本館に収蔵された無台鋺を併せて紹介する。
高台付鋺は鋳造品で、身部、蓋部ともに一部破損しているが、遺存状態は良好である(挿図1)。身部の口径は10.4センチ、高さは7.6センチで、丸みを帯びた下半部からやや内湾気味に立ち上がる。若干外開きに作られた高台は他例に較べて厚く、ずっしりとした安定感をかもし出している。その内面には、鋭い稜線をもって傾斜変換部分が作り出され、ロクロ挽きによる削り痕が認められる。口唇部直下の外面には、一条の細沈線が巡らされている。頂部に宝珠形のつまみ(鈕)が付けられた蓋は、半球形に広がるなだらかなカーブを描き、下端には「返し」が巡る。鈕座は花弁状を呈しており、形状は不揃いながら8つの花弁が表現された八花形である。鈕および鈕座は半球形の蓋部とは別に作られ、中心から若干ずれて「かしめ留め」されており(註2)、蓋部内面の中央部には直径が4ミリほどのビス状突起が認められる。蓋部外面には、二条一組の沈線が4段にわたって巡らされている。蓋部のみの高さは4.4センチで、これを身部にかぶせた場合は総高は11.8センチである。製作に関わった技術や丁寧な造作から、一般的には大陸製品である可能性が高いと考えられている。ほかに、大陸系の製品としては馬冑や鞍に旗を取り付けるための蛇行状鉄器などがあり、被葬者の性格を考える上で注目される。
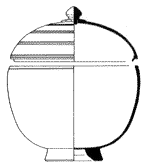 | 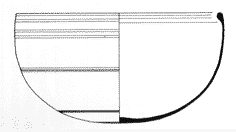 |
| 8-1 埼玉県将軍山古墳出土の高台付銅鋺 | 8-2 埼玉県将軍山古墳出土の無台鋺 |
本館に収蔵されている無台鋺は、口縁部周辺が1/4程度破損しているが全体的に遺存状態は良好で、口径16.4センチ、高さ8.6センチを測る鋳造品である(挿図2)。器壁は丸底の底部から緩やかなカーブを描いて立ち上がり始め、高さの2/3を越えたあたりから垂直に近くなり、わずかに内湾気味に口縁部に至る。口縁端部の内面は肥厚し、肥厚部下端近くには一条の細沈線が巡らされている。一方、外面の口縁下には、細沈線を用いて作り出された四条の突線が巡る。中位および底部近くにも四条の細沈線が巡らされているが、口縁下のような突線表現には至っていない。さらに二条一組および一条の細沈線が巡らされており、底面からみると、各々直径3.5センチ前後の正円と同1センチの正円を描いている。本館収蔵の無台鋺は、多くの沈線で飾られるタイプの典型例と言える。本資料は、個人蔵である別の無台鋺と較べると高さに比して口径が小さく、丸底の度合いが強いようである。 日本列島における銅鋺資料は、例えば、法隆寺蔵品や正倉院献納御物、祭祀遺跡である沖の島遺跡(福岡県宗像郡大島村)、土器溜り状遺構から2点が出土した高野谷戸遺跡(註3)(埼玉県児玉郡上里町)などの例を除けば、大半は古墳ないし横穴墓の副葬品である。副葬品としての出土例はこれまでに90基113例が知られており(註4)、資料集成の充実とともに分類規準や編年観が次第に確たるものになってきている。毛利光俊彦氏は基本器形として無台鋺・高台付鋺・高脚付鋺を弁別し、各々2類6種、4類13種、2類6種に型式分類し、一緒に出土した須恵器の編年観に基づいて概ね6世紀中頃から8世紀代に及ぶ年代を与えた(註5)。埼玉将軍山古墳から出土した高台付鋺と無台鋺は、蓋部ないし身部が多くの沈線(およびそれらによって作り出された突線)で飾られることから、墓への副葬が本格化する時期(6世紀末〜7世紀前半)に比定される。
埼玉将軍山古墳はちょうど100年前に発掘されたが、先述したように、幸いにも副葬品内容の大半は明らかにされている。それ故に、ここで紹介した銅鋺資料を通して、現在の我々に様々な問題を投げかけている。この古墳は、墳長102メートル、後円部径57メートル、同高さ5メートル、前方部長45メートル、同幅50メートル(推定)、同高さ8.2メートルをはかる前方後円墳で、その築造時期は10期編年の第10期(概ね6世紀後半〜7世紀初頭)、つまり前方後円墳が築造された時代の最終段階に相当する(註6)。朝鮮半島との関係を視野に入れて銅鋺の全土的な集成を行った小田富士雄氏は、集成から読み取れる分布上の問題点を指摘した(註7)。すなわち、畿内では希少であるのと対照的に、長門を含めた北九州地方と、下野・上野・武蔵、上総、駿河など関東および東海地方の一角に集中しており、特に東日本では複数の銅鋺が副葬された古墳が散見されるのである。複数(2〜5点)の銅鋺が副葬された前方後円墳は、埼玉将軍山古墳のほかに、八幡観音塚古墳(群馬県高崎市)、小見真観寺古墳(埼玉県行田市)、殿塚古墳(千葉県山武郡)、金鈴塚古墳(千葉県木更津市)などがあり、いずれも第10期に属する。これらの墳長は90〜110メートル前後で、同時期かつ同規模の前方後円墳が全土的にみて関東地方にきわめて多いことを勘案しても、各地において相応の評価を付与すべき前方後円墳であることは言うまでもない。無台鋺はいずれにも副葬されており、高台付鋺と高脚付鋺、あるいはこれらのいずれかが組み合わさる。一方、東日本における単数出土例の大半は無台鋺であり、小規模な円墳や横穴墓に副葬された場合が少なくない。このことは、銅鋺の有無だけではなく、器種内容が被葬者の社会的地位に相応していた可能性を示唆している。このような較差に関しては、先に述べた分布状況もふまえて、まず「畿内政権」から東日本の政治的中枢地域に銅鋺が類品とともに「威信材」として賜与され、ついで各地首長層によって地域内での「再分配」が行われた、という推定がなされている(註8)。「再分配」という概念は、同型式の製品を媒介にして質的格差が具体的に説明づけられることによって説得力をもつため、銅鋺に限らず、その導入にはいくつかの前提条件が欠かせない。銅鋺の場合は、出土点数に比べて多くの型式が設定される点を考慮すべきであろう。したがって、まず、銅鋺を取りまく諸々の情報内容が比較的豊富な事例、すなわち、確実に銅鋺が副葬された前方後円墳を通して「関係」復元の手がかりを得ていくことが重要である。
整備事業に伴う近年の調査の結果、埼玉将軍山古墳の横穴式石室の石材には、直線距離で約120キロ離れた千葉県富津市金谷付近で採取される凝灰質砂岩が用いられていることが明らかにされた(註9)。石材の遠距離運搬と言えば、西日本では石棺石材の研究を通して、広範かつ継続的な地域間交流の一端が既に明らかにされている。このような長距離輸送には甚大な労働力と多くの情報が不可欠であり、おそらく様々な形での統制がなされた結果、作業に従事した人々は帰属集団の一体性を一層強く意識させられたことであろう。さらには、地域間の協力関係が目的完遂の前提であったはずであり、また、これをますます促進させたことは想像に難くない。埼玉将軍山古墳と同型式の銅鋺が副葬されていた金鈴塚古墳は、運搬に舟が利用されたにせよ、石材採取地からの運送経路の途上に位置する。おそらく、双方に代表される集団の間では、相当に密接な連携が果たされたはずである。
さらに、埼玉将軍山古墳の墳丘形態や規模に関して、従来よりも詳細な検討が可能になった点も重要である。すなわち、前方部の形状は後円部に比して長く、かつ、幅広く復元され、このような特色は、金鈴塚古墳だけではなく、石材採取地の近くに位置する内裏塚古墳群の稲荷山古墳、三条塚古墳、古塚古墳に共通することが指摘されている(註10)。後円部径を8等分した「区」を用いて墳丘形態の特色を表示する方法(註11)によると、埼玉将軍山古墳は前方部の長さが10区分(10区型)で、その前端幅は12ないし13区に復元される可能性がある。一方、内裏塚古墳群の3墳は同様に10区型で、いずれも前方部の前端幅は後円部径(8区)を大きく超える。これに対して、金鈴塚古墳と八幡観音塚古墳は、前方部の前端幅が後円部径を超えるものの、前者は8区型、後者は4区型に復元される。また、八幡観音塚古墳と同じ4区型の殿塚古墳の前方部前端幅は後円部径に等しく、殿塚古墳と後円部径が等しい小見真観寺古墳は不確実ながら7区型に復元される。このように、銅鋺が副葬された前方後円墳の墳丘形態には共通点とともに差異点も認められ、必ずしも単純な状況を呈してはいない。当該時期における墳丘企画の意味付けをふまえながら、様々な「関係」を明らかにしていくことがこれからの課題の1つである。
埼玉将軍山古墳から出土した銅鋺は、最終段階の前方後円墳に副葬された点を重視するか、あるいは長期に及ぶ銅鋺全体の推移を重視するかにより、異なった側面をあらわにするであろう。前者の場合は前方後円墳秩序がいまだ存続している中での評価であり、後者の場合は重要なイデオロギーの変化、すなわち仏教思想の浸透や政治体制の刷新を念頭においた評価と言える。
(倉林眞砂斗)
註1 柴田常惠、1905、「武蔵北埼玉郡埼玉村将軍塚」『東京人類学会雑誌』第231号